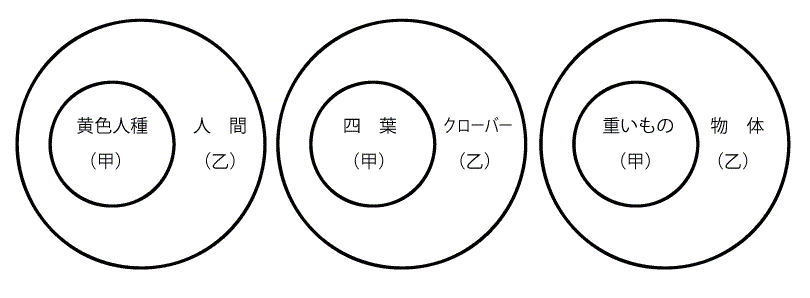偶然性(講演)
一
偶然性とは何であるかということに就いて述べるのであるが、偶然性の意味を論理的、形而上的、心理的の三つに分けて考えて見ようと思う。
先ず偶然性の論理的意味について云えば、思惟の対象相互間に存する関係について、論理的に根本的な区別を考えることが出来る。即ち思惟の対象相互間の関係が、本質的なりや否やということに基いた区別である。諸関係が本質的なる場合にそれを必然的と云い、然らざる場合に偶然的と云う。それ故に偶然性とは論理的見地にあっては本質的関係としての定立を拒否する対象相互の関係を意味する。一体、経験界に於ける本質的関係に三種ある。
(一)内属の関係(主体と属性との関係)
(二)因果関係(原因と結果との関係)
(三)目的手段の関係
又、思惟の対象相互の関係が本質的関係としての定立を拒否する仕方に三通り考えられる。
(一)
本質的関係に対して単なる附帯的関係より構成しない場合
(二) 恒存する本質的関係の破られた場合
(三)
二つあるいは二つ以上の本質的関係間に非本質的関係の存する場合
偶然性の概念を明かにするためには、本質的関係としての定立を拒否する三つの仕方の各々を内属関係と、因果関係と、目的手段関係との三様の場合に於いて考察しなければならない。
一 附帯的関係としての偶然性
先ず内属関係にあって、主体と本質的関係にある属性を本質的属性と呼ぶ。本質的属性の特徴は、それを否定する場合に、主体その物も否定されるといふ事に存する。本質的関係を示さない属性を偶然的又は偶有的属性(accident)という。偶然的属性とは主体に対して附帯的関係より有って居ないものである。本質的属性と主体との関係は、必然的であるが、附帯的関係より有たない属性は必然性を欠くために偶然的と云われるのである。
例えば、人間にとって、その本質的属性は理性を備へて居ると云うことと考えられる。それに反して人種的差異を表はす皮膚の色は偶然的属性に過ぎない。即ち皮膚の色(白い、黄色い、黒い)は人間という主体に対して単に附帯的関係より有って居ない。論理学の直接推理の中に偶然による換位(conversion per accidens)というのがある。すべての甲は乙なりと云う場合には若千の乙は甲なりと云うことが出来る。この換位法が偶然によると云われるのは、甲が乙の本質の中に含まれて居ないからである。即ち甲は乙の偶然的属性に過ぎないからである。例えばすべての黄色人種は人間であると云うことが出来る。それに対してすべての人間は黄色人種であるとは云えない。全称判断を特称判断に改めて若干の人間は黄色人種であるということが出来るだけである。人種的差別を示す皮膚の色というものは人間の偶然的属性である。人間に対して単に附帯的関係より有って居ないから偶然的と見られるのである。
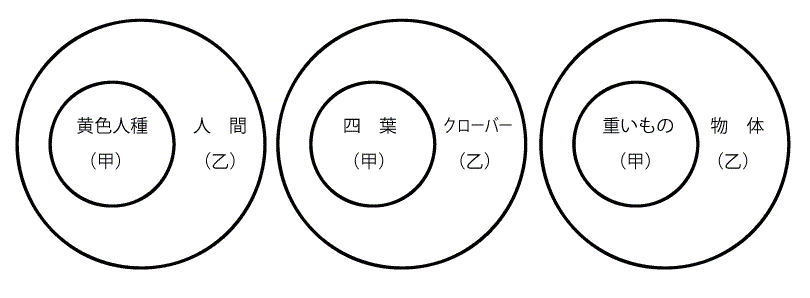
因果関係にあっては、原因と結果とは本質的関係をなすと考へられて居る。しかし、若しここに、本質的因果関係に対して単なる附帯的関係が存在するとするならば、その附帯的関係を偶然と云う。
例えば、感官の刺戟と大脳中枢との間にはエネルギー等量則によって規定される本質的の因果關係が存すると考えられる。そうしてこの生理的因果関係の外に大脳中枢の運動に意識現象が附帯して生ずるという考えがHuxleyその他によって主張された。その場合意識現象は人間という一種の自働器械に依存する"附帯現象"(Epiphenomenon)として偶然的のものと見られて居る。又、感官の刺戟という物質的事象は感覚という精神的事象を生じ得ない、意志という精神的事象は身体の運動という物質的事象を生じ得ないと考へ、感覚及び身体運動の眞の原因を神と見る場合には、感官の刺激及び意志は本質的因果関係に対して単に附帯的関係を有するのみである。この説をとったジューランクスや、マルブランシュが感官の刺激及び意志を"偶因“即ち偶然的原因と呼んだのは単に附帯的関係より有たないからである。
次に目的手段関係は因果關係、即ち原因と結果との関係を価値の上から逆に見た場合である。従って矢張り本質的関係と考えられるが、なおそこに附帯的関係に立つ現象が存する場合には、それを偶然的と考える。
例えば、電車と人を運搬するということとは手段と目的との本質的関係を成して居る。しかし、電車がやかましい音を立てるということは目的の中には含まれていない。即ち目的手段の本質的関係外に立って、単に附帯的関係より有っていない現象である。それ故に偶然的のものと考えられる。又、日本が色々の手段を尽くして日支親善を計つても容易に目的が達せられない。そこへ露支関係が紛糾を来したために排日運動が止んだとする。露支関係の紛糾ということは日支親善の意識的な目的手段関係には単に附帯的に起つたことに過ぎない。事実上は日支親善の目的を達せしめた手段の役目をしているが、単に附帯的に起ったことであるから偶然なものと考えられるのである。
Aristotelesがτ? συμβεβηκ??と云ったものは附帯的関係としての偶然性に略々当たる。
二 本質的関係の破却としての偶然性
内属関係にあって、主体とその本質的属性との間に存する本質的関係が破却せられた場合に、その新たなる関係を偶然的という。凡そ一定の主体と一定の属性との間に本質的且つ恒常的関係が存する場合に、その関係を記述的法則という。従ってその関係の破却せらるる場合とは、記述的法則の例外を云うに外ならぬ。
例えば、クローバーは三つの小葉から成る複葉を有って居る。クローバーとその属性たる三つの小葉との間には本質的関係として記述的法則が成立して居る。その関係は即ち必然的である。若しここに、四葉のクローバーがあったとするならば、その本質的関係の破却、若くは記述的法則の例外の意味に於いて、偶然的と見られる。又、ある一定の個人に就いて、その人がかりに罪を犯したときにその犯した罪科がその人の本質的属性の破却を意味する場合、換言すれば、その罪科がその人の行爲の恒常的法則の例外を示す場合、その罪科は偶然的と考えられる。ロンブローゾ等の所謂“偶発性犯罪”の概念は斯くして成立するのである。
因果関係の普遍性を言表すときに因果的法則という。因果関係に於ける本質的関係の破却とは、即ち因果的法則の例外を示す場合である。それを偶然と云う。換言すれば、法則として規定された原因を欠く場合に、それを偶然と呼ぶのである。
例えば、「生物は生物より生ず」という法則がある。即ち生物発生の原因は生物にありと考えられて居る。然るに若し無生物から生物が発生したとするならば、法則として規定された原因を欠く故に「偶然発生」と呼ばれる。又、生物は外界の影響その他を原因として漸時に変化するとされて居たが、ユーゴ・ド・ヴリー〔Vries〕の研究によってこれらの原因を欠く急激な変化の存在することが確められた。法則として規定された原因を欠くためにこの種の変化は「偶然変化」と呼ばれる。
目的と手段との間の本質的関係が破却された場合、即ち目的と手段との間に成立する法則が例外を示す場合にも、我々は偶然と云う。
例えば、個体及び種属の保存ということと、人体の諸器官の生成との間には目的と手段としての法則的関係があると考えられる。若し仮に盲腸の虫状突起が存在の目的を有っていないとすれぱ、我我はその存在を法則の例外と見て偶然的と名付ける。
Demokiritosの原子論を採用したEpikurosは原子の本来の運動を上から下に向う垂直運動と考えたが、何等の原因に規定されることなくして自ら垂直線より極めて少しくそれる原子のあることを説いた。Lucretiusはこの微小の傾きをClinamenと呼んだ。この種の本質的関係破却の意味の偶然性は又自発性と呼んでも差支ないものであるが、Aristotelesがπαρ? Φ?σιν(自然に反して)と呼んだのもこの種の例外としての偶然性である。Hegelが偶然性に無関心な(GleichgUltig)という形容詞をつけて居るのも、概念的法則の理念的必然性に対して関心を欠いて居るからである。
三 二つあるいは二つ以上の本質的関係間に存する非本質的関係としての偶然性
内属関係を構成する主体とその本質的属性との一体系と、同じく内属関係を構成する主体とその本質的属性との他の体系との間に何等か非本質的関係が成立する場合には、それを偶然という。
例えば、三日月の孤形円の弧に当たる形と、鎌の弧形と、眉の弧形との間に存する関係は単に弧形であるという関係以外に何等本質的関係が考えられない。それ故に三者の関係を偶然的と考える。
又、一つの因果関係の系列と、他の因果関係の系列との間に、何等か非本質的関係の成立するときにも偶然という。
例えば、飢餓と日蝕とが同時に起ったような場合である。天明年間には江戸の大火と浅間山の噴火との間に存するこの種の非本質的関係が注目された。
又、一つの合目的関係の系列と、これと独立した他の合目的関係の系列との間に、或る非本質的関係が存する場合にも、我々はその関係を偶然と呼ぶ。
例えば、二、三ケ月前に、粛親王の王子憲開氏を張宗昌将軍が別府でピストルで射殺した事件があったがそれは全く偶然の出来事とされて居る。何故に偶然かというに、張氏はかねて実弾をつめて置いた護身用のピストルを人が触れると危険であると思って、弾丸を抜き出そうとしたが、抜けないので、縁側から発射した。憲開氏は他の友人と談話する目的である木の蔭へ行った。張将軍の行動は一の合目的系列である。憲開氏の行動もそれとは独立の他の合目的系列である。憲開氏が木の蔭で弾丸に中って訃れたということは、一の合目的系列と他の合目的系列との交叉点、即ち二つの合目的関係間に存する非本質的関係である。それ故に偶然という。〔義貞が流矢に当たって死んだのも同様の偶然なり。〕
なお、又、一方が因果関係で、他方が合目的関係の場合もある。例えば、或る公的生活をして居る人の隠退が一般に世間から希望されていたとする。丁度その時にその人が急病で死んだというような場合がそれである。又、日本歴史上に有名な元寇と嵐との間の関係もその一例である。〔後醍醐帝の夢と楠正成〕
この意味の偶然性、即ち二つあるいは二つ以上の本質的関係間に存する非本質的関係は偶然性の最も模範的なものであると云える。この種の偶然性は特に「相対的偶然」と云われることがあるが、その実すべての偶然はみな相対的である。附帯的関係としての偶然も、何かに附帯して、そこに相対的の関係を構成するのである。本質的関係の破却としての偶然も、本質的関係に代えて、そこに何等か非本質的関係を相対的に構成するのである。偶然には二つのものが遇うということが何等かの形で存在する。偶然の偶は相並ぶ意である。人偏に書かれて居るが、之繞に書いた遇と同義で遇ふといふ意味である。偶数といえば一と一とが遇って二となることが基礎をなして居る。偶座といえば向き合って座ること即ち対座の意味である。配偶の偶も同じである。Stuart Millが『論理学』(System of Logic)の中にこう云って居る。「何等かの現象が偶然によって産み出されたと云うのは正しくない。しかし、二つあるいはそれ以上の現象が偶然によって結合された(conjoined by chance)と云うことは出来る。即ち、それらの現象は単に偶然によって同時にまたは継起的に存在するのみで、何等因果性によって関係附けられて居ないといふ意味である」。又、偶然性の研究で有名なCournotは偶然性を定義して「理性的には互に独立している事実と事実との合致」(le concours de faits rationnellement independents les uns des autres)と云って居る。
二
今迄述べたところは偶然性を与えられた現実として考えた論理的意味であったが、今、この与えられた現実を、与えられていない可能の領域の背景の中に置いて考察することが出来る。また、それによって思惟は形而上的見地に立つことが出来るのである。そうしてこの見地からして、偶然とは、可能が現実に移る必然的ならざる推移、又は必然性によって規定されないで、可能性が現実化すること、と考えられるのである。現実へ移る必然性を欠くために、偶然性を可能性その物であるとする考えもある。斯様に偶然性を、可能の現実化に於ける様相と見ることは、例えば経験的に与えられた三次元の空間を可能的なる多次元体系の具体的定立と見たり、現実の世界を可能の諸世界中の最善、又は最悪のものと見たりする様な立場である。即ち、与えられた現実の背後に立って見る意味で形而上的である。換言すれば現実を選言的立場から見ているのである。甲は乙なるか、丙なるか、丁なるかであるという様に選言的な可能性が背景をなして居る。Hegel曰く「偶然とは現実が同時に単に可能として規定されているものである。それが他のものであること又は反対のものであることが同様にあり得るものである」(Logic,Ⅱ,205)。その場合偶然という訳は、可能と現実とが必然的でない遇い方をして居るからである。即ち可能と現実との相対的関係が必然的でないからである。
斯様な立場から見た偶然の意味は、我々が可能の場合を悉く知って居る時に明かに現われるのである。我々が可能の場合を悉く知って居る時とは、例えば骰子(さいころ)、競馬、ジャンケン等、可能性を取入れて偶然の遊戯をする場合である。骰子の現はす面を偶然と云うのはその六つの可能性を背景として考えるからである。他の五つでもあり得たと考える故に、可能と現実とのある一定の遇い方を偶然というのである。その実、骰子の現わす面は、骰子の重さ、投げられる位置、投げるカと方向、投げ落される床の表面の傾斜等によって必然的に規定されている。しかしながら、他の必然性の因果的系列をも取り得たと考える点、即ち、今与えられた因果的系列が必ずしも絶対性を有っていないと考える点、DenkmOglichkeitと事実との間に齟齬が存する点に偶然性が存在するのである。世界を神の遊戯と考えた哲学に存する深い意味もその点にあるのである。この意味に於いて、すべての事実は偶然的と考え得る。与えられた事実は他の事実でもあり得たと考えることが出来る限り、可能性と現実との遇い方が必然性によって規定されたと考える必要はない。斯様にしてすべての事実は可能性その物の措定であると考え得るのである。Spinozaが「我々がその存在を必然に措定し、又は、それを必然に排除する何物をも見出さない限り、自分は個物〔res singulares〕を偶然と呼ぶ」と云って居るのはこの意味の偶然である。さうしてこの意味で、比叡山が禿げ山でなくて、木の茂った山であるということも偶然であり、豊臣秀吉が京都でも大阪でもなく、又、その他のどこでもなく尾張の中村で生れたことも偶然である。我我がアメリカ人でも印度人でもなく日本人であることも偶然である。今日、雨天でなくて晴天であることも偶然である。
斯様に可能と現実との関係に於いて偶然性を認める立場から、更に進んで現実と現実との関係に於ける偶然性の意義を一層することが出来る。即ち現実相互の関係が本質的関係としての定立を拒否する場合とは、選言的な可能性の存することによって、今現に与えられた現実相互の関係が他の関係をも取り得たのであったと云うことを意味して居る。骰子の例について云えば、同時に投げられた二個の骰子が共に同じ面を表はす場合とか、又は賭手が意志を表明して、骰子がその意志表明と符合した場合などには、与えられた現実相互の関係が、選言的可能性を背景として、偶然と考えられるのである。運動会の日に天気を願って居る。その日丁度天気であったとすれば、それは偶然である。雨天でもあり得る可能性を背景として考えるから偶然と云うのである。
然らば幾つかの選言的可能性の一つが実現される場合、即ち幾つかの選言肢の一つが措定される場合、如何なる可能性、即ち如何なる選言肢が特に偶然と考えられるかと云うに、措定に何等かの合目的性が想像される場合、即ち可能性の措定が何等かの価値と関係する場合である。換言すれば、偶然が偶然でない様な場合である。Aristotelesはこの種の偶然をτ?χη又はα?τ?ματονと呼んだが、その例としてある債権者が散歩に出て、思いがけなく債務者に出逢って金の払戻しを受けたという場合を挙げて居る。武者小路氏の小説『その妹』の中に「あの日あなたの処へ行ったのは偶然とは思えない気がします(七二頁)。という言葉があるが「偶然とは思へない」ということが偶然性の一つの持色である。
夏目漱石の『こころ』の中にも「それがまた偶然なのか、故意なのか、私には解らない」(一五一頁)と云う言葉がある。「偶然なのか、故意なのか解らない」ところに偶然性の特色がある。即ち、現実と現実との関係が、可能性の領域内で何等か本質的関係を有って居るが如く感じられる場合である。換言すれば可能性の事実的自己措定が何等か必然的なるが如き形をとる場合である。故に、偶然性の形而上的意味の中には自己否定の下に自己を肯定するということが含まれている。
三
今迄は偶然性の論理的意味と形而上的意味とであった。なお偶然性は心理的意味をも有って居る。偶然性を心理的見地にあって考察するときは、驚異を伴うということがその特色である。
例えば、数百の赤い花の中にただ一つだけ白色の斑点を帯びたものが見出された場合に、その「変わり咲き」に対して我々は驚異を感ずるのである。
安倍能成氏の「京城風物記」という文の中にこういう言葉がある。「リラの名、リラの香には私には遠いヨーロッパ殊にパリの連想があった。その花が今私の鼻先に咲いていたということが、私にとって一つの驚きであった。」この驚きというのは、リラの花によって京城とパリとの乖離性が結付けられた偶然に対する驚異でなくてはならない。
八月頃の新聞に法廷奇縁といふ題で出て居た記事がある。新聞にこう書いてある。「夫の死亡後、その遺子をめぐって未亡人の上に起ったよく似た内容の二訴訟事件の弁論が、奇しくも同じ日に同じ法廷―――大阪控訴院二号法廷―――で開かれた。」これは二つの独立した本質的関係間に存する非本質的関係としての偶然であるが、「奇しくも同じ日に同じ法廷で」と云って居るように奇しいという驚異が伴って居る。法廷奇縁という奇もそのためである。
もう一つ新聞から例をとれば、ある政治家が一度脱党して新党を組織して居た。その政治家が再びもとの政党へ帰って来た。その折りに、両党合同の懇親会が催されたその席上の演説(今年の六月頃)の中でこう云って居る。「昨日合同を決議した後に於いて一の辻占が出た。「人は人、早く帰れと親爺いい」いうことであるが、実に妙なことである」と云って居る。又その人の先輩でその人を呼んで家出息子と云って居た某が「右のような妙な辻占で妙な感激をしていた」ことを語って居る。この種の偶然性と、又偶然性に伴うこの妙なという驚異の中に見出す一種の快感とが存在しないとすれば誰一人として辻占を買う者はなくなる筈である。
夏目漱石の『行人』の終りに「私がこの手紙を書き始めた時、兄さんはぐうぐう寝ていました。この手紙を書き終わる今も亦ぐうぐう寝ています。私は偶然兄さんの寝ている時に書き出して、偶然兄さんの寝ている時に書き終わる私を妙に考えます。兄さんがこの眠りから永久覚めなかったら幸福だろうという気が何処かでします。同時にもしこの眠りから永久覚めなかったら嘸悲しいだろうという気も何処かでします」。この偶然とは『行人』の主人公の睡眠と永眠との間に価値の上から見て交叉点を示している。その交叉点が偶然と考えられたので、そうしてそれが偶然である故に「妙に考えます」と云って居るのである。
一体、偶然に当たる純粋な日本語はたまたまという言葉であるが、たまたまはたまを繰返してたまたまと云ったのであれあれとかあかあかとか云う場合のように繰返して云うことがそれ自身、一種の驚異を表わして居るものであらう。
それならば、どうして偶然性に驚異が伴うのであるかと云えば、第一に附帯的関係としての偶然性に伴う驚異は、普通はその附帯的関係が本質的関係の例外と見られる様な場合に起って来る。内属関係について云えば、偶然的属性が本質的属性の例外の様に考えられる場合である。日本人が西洋へ行って自分が黄色人種であることに対して一種の驚異を感ずるのは、周囲がすべて白人であるために、白色人種ということが人間の本質的属性ででもあるかの様に感じられて、黄色人種という偶然的属性がその本質的属性の例外の如くに感じられるためである。
第二に本質的関係の破却としての偶然性に対する驚異は恒常的法則が例外を示すために感ずる驚異である。驚異を伴うのは自然のことである。さうして、今述べたように、第一の附帯的関係の場合も、結局この第二の場合に還元されて驚異を伴うのである。要するに有る筈のものが無いから驚くのである。
第三に本質的関係間の非本質的関係としての偶然性に対する驚異は第一、第二の場合と反対に無い筈のものが有るから不思議に感ずるのである。二つの全く独立した系列間に、有りそうもない何等かの関係が有るから、そのために驚くのである。
この有る筈のものが無いということと無い筈のものが有るということとはなお押しつめて考えれば畢竟同一のことである。有る筈のものが無いとは何も無いのではない。有る筈のものこそ無いが、その代りに無い筈のものが有るのである。それ故に偶然性に対する驚異は畢竟、何等か無い筈のものが有ることに基いている。本質的関係としての定立を拒否する対象相互間になお何等か思い掛けない非本質的な関係が存するから驚異の情を禁じ得ないのである。一言にして云えば、偶然性の驚異は邂逅、めぐりあいの驚異である。Platoが『宴会篇』の中で「彼等は不思議に驚かされる」(θαυμαστ? ??πλ?ττονται)と云って居るその驚異に外ならない(Symposion,192b)。
凡そ、我々の概念的理解は経験内容として与えられた特殊を普遍者によって包摂することに存するのであるが、事実の事実性その物は普遍者に包摂され得ないもの、普遍的思惟に反撥するものである。その意味に於いて事実は常に非合理的で、常に問題として残るものである。そうして問題の存するところに驚異(θαυμ??ειν)がある。それ故に、事実には常に驚異が伴わなければならない筈である。そうして邂逅の驚異としてのθαυμαστ? ?κπλ?ττονταιは事実の事実性に対する驚異としてθαυμ??εινの一様相に過ぎないのである。
四
これで偶然性の意味を論理的、形而上的、心理的の三つに分けて大体明かにしたと思う(即ち何等かのものが逢う。逢わないでもあり得たものが逢う。それで驚異を伴う。偶然性はこういう構造をもったものである)が、なお偶然性と精紳生活との関係に就いて少し考えて置き度い。
偶然性と科学とは如何なる関係に立って居るか。すべて学的認識は経験の形式としての普遍者によって、経験内容の本質的相互関係の体系を組織することである。偶然とは該内容を形成する対象相互間にあって本質的関係の定立が拒否される場合である。それ故に科学、否一般に学問の目的が出来得る限り偶然を除去するにあることは云う迄もない。Spinozaは「物は吾々の認識の不完全なるが為にのみ偶然と呼ばれるのであって、如何なる他の原因からでもない」(Res aliqua nulla alia de causa contingent diciter、nisi respectu defectusnostrae cognitionis)(Ⅰ,33,Anm.1)と云って居るが宇宙の組織が数学的自然科学の要請する如き必然性を示していることを独断的に仮定している哲学の見地からは当然のことである。要するに、学的認識の立場からは、偶然を出来得る限り除去することがその任務である。換言すれば驚異を絶滅して、一切のことが自明となることが科学の、恐らく一般に学問の理想である。
科学は偶然の除去に関して二様の方法を講ずる。一は偶然と考えられることの因果的必然性を指摘して、偶然に非ざることを闡明することである。他は偶然の起り得るべき場合を数量的に規定して、偶然の生起に関して必然的法則を立てようとすることである。この、科学と偶然との関係を積極的に云表わせば偶然は科学に対して二様の役目をする。第一に偶然性は科学に対してある特殊な研究の具体的動機を与える。第二に偶然性はある一定の学問の構成原理となる。
第一の場合の好例はDarwinの事業であるが、その著書の名Origin of Speciesが既にその意味をよく表わしている。種とは類に対して偶然性を表わして居る。「種の起原」とは偶然性を因果的説明によって除去することを意味して居る。Darwinの子のFrancis Darwinは父に関して「彼に発見を為すに特に甚だ適当と思われた精紳的特質が一つあつた。それは例外を決してその儘看過しないというカである。・・・・・彼は正にそれを捕へて出発点とした」(Life & Letters of Charles Darwin,Vol.Ⅰ,p.125)と云って居る。即ち偶然性の因果的説明をDarwinは怠らなかったのである。〔vg1.Windelband,Lehren vom Zufall,S.21,Trendelenburg:,,das Zuf?llige ist in der Wissenschaft immer nur ein Ubergang und der Impuls zu einer weiteren Forschung.''〕
第二の場合、即ち偶然性が学問の構成原理をなして、学的認識が偶然の起こり得べき場合を数量的に規定しようとする場合とは確率論又は公算論として蓋然量の計算をするときである。例えば六個の貨幣を投上げる場合、その六個とも表、又は六個とも裏の出た場合を我々は偶然と考える。その組合せには七つの場合がある。即ち六個共表、五個は表一個は裏、四個は表二個は裏、三個は表三個は裏、二個は表四個は裏、一個は表五個は裏、六個共裏、の七つの場合。然るに幾千回も投げて見るとこの七つの場合は1,6,15,20,15,6,1の割合を以て現はれる。六個共表及び六個共裏の場合の起り得る確実の度合、則ち確卒(又は蓋然量)は1/64である。全体の1/64より起らないことであるから、それを偶然と我々が考えたのである。
学的認識はこういう様に二様の方法によって、偶然の非合理性の合理化をつとめるのであるが、それには越えることの出来ない限界がある。種の起原を類によって説明することが出来ても、何故に正にある種がある類と斯様な因果的生成関係をとったのか、何故に正にこの種であって他の考え得るべき極めて類似した種でなかつたか。与えられたその種と全く同価値の他の組合せでなかったか。そこには依然として偶然性が存する。又、確率論によって、非常に多い事実の全体に於いて偶然の起り得る比例を数量的に規定することが出来たとしても、ある一定の場合に必然的にある一定の組合せが起ることは何等予知することは出来ない。そこには偶然性が依然として残されて居る。それ故にHegelも「偶然を理解することを概念に要求するのは最も不適切なことである」と云って、偶然が認識に対して限界を成すことを認めている(Encyklopadie,250)。〔Windelband,ibid.,S.21, ,,Zufall ist Grenzbegriff der menschlichen Erkenntnis“〕
五
次に偶然性と宗教との関係に就いて考えて見るのに、今述べた偶然性に関する学的認識の限界がやがて宗教の起始となる。宗教の本質は不可知に対する帰依である。そうして偶然に対する驚異はやがて不可知に対する絶対的帰依の形を取るのである。
旧約聖書「約百記」第一章で四人の使者が殆んど同時にヨブの処へ来て、各々独立して起った不幸な事実を告げる。一人は牛と驢馬と若者とをシバ人が襲ったことを告げて「我ただ一人のがれて汝に告げんとて来れり」と云う。他の二人は落雷のために羊と若者とが即死したことを告げて「我ただ一人のがれて汝に告げんとて来れり」と云う。又、他の一人は三隊に分れたカルデア人が駱駝と若者と虐殺したことを告げて「我ただ一人のがれて汝に告げんとて来れり」と云う。第四の使者はヨブの息子息女(子女)が酒宴を開いていた際に大風が起って家を破壊し、ヨブの子女が悉くその下敷きになって死んだことを告げて「我ただ一人のがれて汝に告げんとて来れり」と云う。この四つの事象が同時に起ったという偶然性に面接したヨブは「起ちあがり、外衣を裂き、髪を斬り、地に伏して拝し、言う。われ裸にて母の胎を出たり。又裸にて彼処に帰らん。エホバ与え、エホバ取り給うなり。エホバの御名は讃むべきかな」(「約百記」第一章二〇-二一)という。即ち偶然に対する驚異が直ちに宗教的情緒の発露に移つて居る。
又、「羅馬書」第九章でパウロは事実の有する偶然性を神の意志によって説明して居る。「レベカ(も)我等の先祖イサク一人によりて双子を孕みしとき、その子いまだ生れず、善も悪もなさぬ間に神の御旨は動かず、行為によらで召によるを表はさんとて「兄は弟に事うべし」とレベカに宣給えり。「われ、ヤコブを愛し、エサウを憎めり」と録されたる如し。……されば神はその憐れまんと欲する者を憐れみ、その頑固にせんと欲する者を頑固にし給うなり」。
Bossuetが「人間にとって偶然のものは、神にとって意図である」(Ce qui est hazard a l'egard des homes est dessein a l'egard de Dieu.)と云って居るのは有名な言葉であるが、その他物質的事象と精紳的事象との乖離的独立性を物心平行論の立場から主張して、両者の一致を偶然と見、そうして偶然の根拠を神の意志に帰せしめようとするLeibnizの予定調和説も、偶然性を出発点として宗教に行くものである。
仏教が事実の有する偶然性を業又は輪廻の考によって説明しょうとするのも全く同様の行き方である。ミリンダ王がナーガセーナに問ふて言わく〔問う言葉に〕「尊者よ、何故に一切の人々は等しくないか。何故に或者は短命、或者は長命、或者は病身、或者は健全、或者は醜く、或者は美しく、或者は無力、或者は有力、或者は貧乏、或者は富貴、或者は生れ下賎に、或者は生れ高貴に、或者は愚、或者は賢であるか」。ナーガセーナは仏陀の言葉をひいて「衆生には各々彼等自らの業がある。彼等の位置の高下等を区別するものは業である」と答へて居る。業及び輪廻の説は「一切生法皆属業因」とか「萬物從業因生」とか云って、一見、偶然性に因果的説明を与えて居るようであるが、その実、偶然性を過去に向って無限に延長して居るに過ぎない。ナーガセーナが、ミリンダ〔Milinda〕に反問して「何故に一切の果物は等しくないか。何故に或者は酸く、或者は塩からく、或者は辛く、或者は渋く、或者は甘いか」と云ったのに対してミリンダは「尊者よ、何故なれば彼等は、異った種子から生じたからである」と答えている。果物の相異の偶然性が、種子の相異の偶然性に移されただけのことである。種子の相異は依然として偶然性として残されている。そうして幾度この種の論法を繰返しても偶然性はその非合理性を失わない。そうして又、偶然性がその非合理的本質に於いて、絶対的自己措定をして居るところに、宗教的情緒が起り得る筈である。
なほ「偶然か運命か」ということが問題とされることがあるが、それは恐らく問題を誤っている。可能性の事実的自己措定の可能性ということを強調して考えた場合が偶然性であり、事実的措定ということを強調して考えた時が運命である。偶然と運命とは二つの者ではない。同一のものである。そうして運命に対する驚異は偶然に対する驚異に外ならない。
宮津の刑務所にいる舜海尼の歌ということであるが、
不思議のえにしを思ひ刑務所に独り眠つて虫の声きく
無礙光のひかりまばゆき仏前に青葉さえざえしらふじの花
宗教の本質は畢竟、不可知に対する帰依である。そうして運命、即ち偶然に対する驚異、不思議のえにしに対する驚異がやがて不可知に対する絶対的帰依の形を取るのである。偶然性の存在する限りに於いて、宗教はその存在の哲学的理由を有っている。しかしながらこの哲学的理由は同時にまた宗教が一切の概念的思弁を断念して単に不可知に対する帰依の形で存在すべきことを要求するのである。〔哲学は単に合理的認識に立脚して認識の限界を限界として示せばよいのである。〕
六
次に芸術は内容としても、また形式としても偶然性を重要な契機として有っている。即ち、宗教が絶対的帰依を示した偶然性を芸術は自己の対等者として観賞しようとする。芸術の内容に就いて云えば、例えば文学では偶然性に伴う驚異が劇的効果を有って居るために、非常に重要なものになって来る。戯曲や小説で偶然性を全然取入れて居ないものはないと云っていい位であらう。謡曲『蝉丸』では、蝉丸と姉とが逢坂の関で偶然逢う。その場面だけで十分の劇的効果があればこそ謡曲として生かされて居る。又、『朝顔日記』の駒沢と深雪とは先ず宇治の蛍狩りで偶然に知合になる。次で明石の浦の舟出の時に偶然に出逢う。最後に島田の宿の宿屋で客と門附として偶然に逢う。この三つの偶然性が『朝顔日記』の骨子を成している。又、里見弴の短編小説に「不幸な偶然」という題のものがある。ある神経質な女が汽車の窓から硝子瓶を投げた時、丁度汽車が町の往来の上の鉄橋を通って居た。その後、その女が銭湯へ行って居た時に、天井の明りとりの硝子窓が壊れて直ぐ自分の側へ硝子板の破片が落ちて来た。それでもう少しで大怪我をするところであつた。そうしてそれ以来自分が汽車の窓から投げた硝子瓶が人を負傷させはしなかったかという心配がもとになってその女は狂人になるという筋である。この小説には二重の不幸な偶然がある。第一に硝子瓶を汽車の窓から投げた時に、汽車が丁度雑踏した往来の上の鉄橋を通過して居たということは同時性としての不幸な偶然である。第二に斯様な経験をした女がその後間もなく銭湯へ行った時にそれに類似した事件が時間的に偶然に継起して起った。それがひどい刺激を与えて遂に狂人にしてしまった。即ちその不幸な結果から考えてこの継起的の偶然も不幸な偶然であった。二重の偶然性がこの小説の内容の全部である。〔夏目氏のもの。Novalis 曰く,,Alles Poetische ist marchenhaft;der Dichter betet den Zufall an"〕
芸術の形式としては、例えば“絵画にあって、描かるべき事物その物を描写の目的とせず、事物の有する色彩相互の偶然的関係のみを考慮する。フランス現代のHenri Matisseの絵はその一例である。又、詩にあっては音韻上の偶然の一致、即ち同音異義の語を利用して芸術の形式を構成する所謂、韻がそれである。例えば松という言葉の内容、即ち松杉科の植物と、も一つの待つという言葉の内容、即ち一種の緊張した心理状態とは、本質的には何等の関係をも有って居ない。両者の発音が同じく「まつ」であるという偶然の関係に過ぎない。詩はその偶然性を生かす。又、掛詞の妙味は一つの音を異った二つの意義に分解して二つの意義の有する音韻上の偶然的一致、即ちその偶然性を観賞するのである。又、西洋の詩にとって頭韻及ぴ脚韻の持つ芸術的価値は論ずる迄もない。Paul Valeryは詩を定義して「言語の運〔偶然〕の純粋なる体系」(Systeme pur des chaces du langage)(Variete,p.159)と云っている。
七
最後に道徳と偶然性との関係に就いて考えて見たい。偶然を道徳から除去しようとする試みは道徳を科学と同様に普遍齊一的立場からのみ取り扱おうとするためである。Kantの道徳論に若し弱点があるとするならば、正にこの点にある。Kantの倫理学上の不朽の功績として何人も認めて疑はないことは善なる意志を以て道徳の原則となす自律的道徳を建設したことである。しかしながら、又Kantは「汝の意志による汝の行為の準則が普遍的なる法則となるが如くに行動せよ」と云っている。この意味は必ずしも一義的ではないが、若しそれが、意志の原則を以て、例外を許さない普遍的自然律の如くにあれという意味であるとすれば、たしかにそこに弱点が存する。実生活に生きた力を有つ道徳は、与えられた偶然の場合によって異った形式を取り得る意志の自律でなくてはならぬ。Jacobiはこの点についてkantを非難した。彼はkantの普遍的意志を「何物をも意志しない意志」(der Wille,der Nichts will)であるとして「絶対的無規定に於ける自由と独立との空虚な胡桃」と呼んだ。而して曰く「然り、自分は無神論者で、信心のない者である。自分は何物をも意志しない意志に反抗して、死に臨んで詐ったDesdemonaの様に詐わろうと思う。Orestの風を装うPyladesの様に詐り且つ欺こうと思う。Timoleonの様に人殺しをしようと思う。Epaminondasの様に、Johann de Witの様に法律を破り誓いを破ろうと思う。Othoの様に自殺しょうと思う。Davidの様に神の殿に入って盗みをしようと思う。然り、自分はただ飢えるが故に、また法律は人間のためにつくられ、人間が法律のためにつくられたのでない故に、安息日に麦の穂を摘もう思う」。そうしてJacobiは絶対的普遍的理性法則の字句に対するこの種の犯罪に関して人間は大赦の特権を有って居る。それが人間の権威であると痛論した。一体、道徳とは決して架空なものではない。与えられた偶然の事情を立脚地として高飛するものでなくてはならない。
なお曩に、偶然とは驚異を伴う現象であると云ったが、その驚異は必ずしも過去又は現在によって基礎づけられなければならないことはない。偶然性の驚異は未来によって倒逆的に基礎づけられるものであってよい。通常の意味の偶然性は瞬間、即ち現在に位置を有っている。謂わば持続の休止点に関する現象である。しかしながら、この休止点をして現勢的の休止点たらしめないで、単に潜勢的のものたるにとどめ、これを出発点として新しい道徳的生活に入るとき、瞬間としての偶然性の意義が発揮されるのである。偶然性の驚異は斯くして未来から倒逆均に基礎づけられるのである。
又、Henri Poincareは「我々の気附かないような極く小さい原因が、我々の認めないで居られないような重大な結果を惹き起す。その時に我々はこの結果は偶然によって起ったと云う」(Science et Methode,p.71)と云って居る。重大な結果とは畢竟主観的評価によることである。そこに我々の自由がある。
我々が価値を提供することが出来る。そうして、可能性の自己措定の中に含まれて居る仮想的合目的性を、我々自身の事実的目的性によって置換へることが出来る。凡そ道徳を架空な、空虚なものと考えないで実生活にあって生きた力として働くものと見るならば、道徳の意義は正に生を深めることであり、生を深めるとは、偶然性の中に働く仮想的意志を自己の事実的意志を以て置き換へること、偶然性の主観的価値を我々自身が価値として創造すること、一切の偶然性の驚異を未来によって基礎づけることより以外にあり得ない。即ち道徳とは偶然性をして眞に偶然性たらしむることである。〔Geworfenheitに基づいてEntwurfをすることが道徳なり。〕
これで大体、偶然性の意味、及び偶然性と精紳生活との関係を明かにしたつもりである。〔偶然を偶然として発揮させるには必然を必然として確乎として提立して行くべきである。Spinozaの云う様に(res aliqua...)偶然がなくなったら、またPoincareの云うように「偶然とは吾人の無知を測る尺度に他ならぬ」(吉田洋一訳『科学と方法』岩波文庫六一頁)というところに意味がある。偶然がなくなってすべてが自明になったら何等の憧憬も何等の努力もない世になってしまう。〕
(昭和四年十月二十七日大谷大学に於ける講演)