��@����
��@�_���I���R
�O�@�o���I���R
�l�@�`����I���R
�@�@�_���v�|
��@����
���R���̌��{�I�Ӗ��͕K�R���̔ے�ɑ�����B�K�R�Ƃ͕K���R���L�邱�Ƃ��Ӗ����Ă���B���Ȃ킿�A���݂��������̈Ӗ��Ŏ��Ȃ̂����ɍ��������Ă��邱�Ƃł���B���R�Ƃ͋�X�R���L��̈ӂŁA���݂����Ȃ̂����ɏ\���̍��������Ă��Ȃ����Ƃł���B���Ȃ킿�A�������Ƃ̏o���鑶�݂ł���B��������A���R���Ƃ͑��݂ɂ��Ĕ݂Ƃ̕s���̓��I�W���ڌ�����Ă���Ƃ��ɐ���������̂ł���B���R�Ƃ͗L�����ɍ������Ă����Ԃł���B�܂��͖����L��N���Ă��邩�����ł���B
���R���ɂ��āA���݂͖��ɒ��ʂ��Ă���B�������āA���݂��Ė��ɍs�����Ƃ��A�`���z���Č`����̂��̂ɍs�����Ƃ��A�`����w�̊j�S�I�Ӗ��ł���B�`����w�́E�E�E�E�E����Ƃ��Ă���ɑ���Ȃ��B�������A?�˃у�?�@?�˂̓�?�@?�˂Ƃ̊W�ɂ����Ă̂��{�I�ɖ����`������̂ł���B�`����w�̖��Ƃ��鑶�݂́A�݂��Ȃ͂����Ɉ͂܂ꂽ���݂ł���B�������Č`����w���Ȃ킿���`�ɂ�����N�w�Ƒ��̊w��Ƃ̑�����܂��ɂ��̓_�ɑ����Ă���B���̊w��͑��݂������͗L�̒f�Ђ��A�^����ꂽ���݂���җL�̒f�ЂƂ��Ė��Ƃ��邾���ŁA���ɏA�ẮA�܂��L�Ɩ��Ƃ̊W�ɏA�ẮA�����̂����m�낤�Ƃ��Ȃ��B
���R���̖��́A���ɑ����Ɨ������Ƃ��o���Ȃ��Ƃ����Ӗ��ŁA�����Ɍ`����w�̖��ł���B�܂��]���āA�`����w�Ƃ��Ă̓N�w�ȊO�̊w��͋��R���Ƃ��������Ƃ���Ƃ��Ȃ��B�ہA���Ƃ��邱�Ƃ�~���Ȃ��B���w�̂����̊m���_�����R������Ƃ���ƍl�����邩���m��Ȃ��B�m���_�͋��R�̏ꍇ���戵�Ă���ɑ���Ȃ��B���������R�����R�Ƃ��Ď戵���̂ł͂Ȃ��B���R���̈Ӗ����ꎩ�g��葖����悤�Ƃ���̂ł͂Ȃ��B�m���_�̊S�́A�ꎖ�ۂ̐��N����ѕs���N�̑��Ẳ\�I�ȏꍇ�ƁA���̎��ۂ̐��N������R�I�ȏꍇ�Ƃ̊Ԃɑ����鐔�ʓI�W�Ƃ������Ƃɐs���Ă���B���������_��̐��ʓI�W�́A�o����ɂ͊ϑ��̉��ɑ�ɂ����ꍇ�ɏ��߂đÓ�������������̂ł��邩��A�m���_�͋��R�I���ۂ̐��N����ꍇ�̑��a�̑��ΓI�P�퐫���K�肵�悤�Ƃ���ɉ߂��Ȃ��B�זڂɑ�������R�I�ω����͏������G����Ȃ��B���������R�̋��R���鏊�Ȃ͂܂��ɂ��̍זڂ̓����ɑ����Ă���B�v����ɁA�m���_�Ƃ͋��R���̂��̂̍l���ł͂Ȃ��B���R���̂��̂͌v�Z�͏o���Ȃ��B�v�Z�̏o������͉̂������̈Ӗ��ŕK�R�ł���B�m���_�̎��́u���R�v�́u�v�Z�v�ł͂Ȃ��B�u�W�R�v�́u���v���u�K�R�v�Ƃ��Č��肷�邱�Ƃɑ�����B���R�����R�Ƃ��Ă��̖{���̖ʖڂɂ����Ė��ƂȂ�������̂͌`����w�Ƃ��Ă̓N�w��[���Ăق��ɂ͂Ȃ��B
�������Ȃ���A�܂����ׂĂ̊w��́A�����̕K�R�I�W���������悤�Ƃ��闝�R���̂��̂ɂ�āA�����I�ɂ͋��R���̖��Ɨ���邱�Ƃ��o�҂Ȃ��B���悻�K�R�Ƃ������Ƃ͋��R�Ƃ������ƂƑ��ΓI�ɐ�������T�O�ł���B�]���ċ��R���l����ɕK�R�𗣂��čl���邱�Ƃ��o���Ȃ��悤�ɁA�K�R���l����ɋ��R�𗣂��čl�ւ邱�Ƃ͏o���Ȃ��B�K�R�Ƃ͖������Ƃ̏o���Ȃ����̂ł���B�������Ƃ̏o���Ȃ����̂́A�������Ƃ̏o������̂Ɗ��݂��Ă̂ݍl���邱�Ƃ��o����B�������āA�������Ƃ̏o������̂Ƃ͂��Ȃ킿���R�ł���B����̂ɁA�����̕K�R����Nj������̊w��́A���Ȃ̎d���Ɋւ��Č����I���Ȃ�����ꍇ�ɂ͕K���A�A�����̎��ɏ��߂āA���R���̖��ɑł�������̂ł���B����͂ق��ł��Ȃ��B��̊w��͂��̍���ɂ����Č`����w�ɘA�Ă��邩��ł���B
�v����ɁA���R���̖��́A���Ɋւ�����̂ł������A���Ȃ킿���̒n���ɂ����ď\�S�ɔc���������̂ł������A�����Ɍ`����w�̖��ł���B���Ƃ��A���̖��͊��S�ɉ�������������ł��邩�ۂ��A����͂��̂Â���܂��ʖ��ł���B������X�͋��R���Ƃ������Ƃ�N�w�̖��Ƃ��ĒNj����Č��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����A�ϋɓI�ȉ�����^�����Ȃ��Ƃ������ʂɓ��B���Ă��A����͒v�����Ȃ��B
���āA���R�����K�R���̔ے�ł������A���R���̈Ӗ���c�����邽�߂ɂ́A��ÕK�R���̈Ӗ���葖����邱�Ƃ���o�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�R��ΕK�R���Ƃ͉����Ƃ����ɁA���ɉ]�����悤�ɁA�K���R���L�邱�ƁA���Ȃ͂����̕s�\�Ȃ邱�Ƃ��Ӗ����Ă���B�����s�\�Ȃ�Ƃ́A���Ȃ̂����ɑ��݂̗��R��L���A�^����ꂽ���Ȃ��^����ꂽ�܂܂̎��Ȃ�ێ����邱�Ƃł���B�������āA���Ȃ��O�������Ȃ�ێ�����ꍇ�ɂ́A���ȕۑ��܂��͎��ȓ���̌`����ė���B���Ȃ킿�K�R���̊T�O�͓��ꐫ��\�z���Ă���B�]���āu�b�͍b�ł���v�Ƃ������ꗥ�̌`�����ł������Ȃ�K�R����\�킵�Ă���B�K�R�Ƃ́A�L��A����Ƃ���������̋K���l���̌��n���猾�\�������̂ɂق��Ȃ�Ȃ��B
����A�]���ĕK�R�A�Ƃ����K��́A�_���w��̊T�O�ƁA�o���E�ɉ�������ʐ��ƁA�`����I�̐�Ύ҂Ƃɂ����čł������Ɍ����Ă���B���R�����K�R���ɑΗ������Ӗ��ł������A���̎O�l�̕K�R���ɑ��ĎO�l�̋��R���������锤�ł���B�]���ċ��R���̖��͘_���I���R�A�o���I���R�A�`����I���R�̎O���ɕ��čl�@����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
��@�_���I���R
�_���w��̊T�O�̍\���͌X�̕\�ۂɉ��������ʂȕ��ՓI���ꐫ��ڌ����邱�ƂɊ�Ă���B�������ĊT�O�̍\���I���e�͓��ꐫ�Ƃ��Ē��ۂ��ꂽ�{���I���\�̑S�̂ł���A���̉\�I���e�͎̏ۂɂ�ē��ꐫ�̌��O�ɒu���ꂽ��{���I���\�ɒʘH��^���邱�Ƃɂ�Đ�������B�{���I���\�̓��F�́A�����ے肷��ꍇ�ɊT�O���̂��̂��ے肳���Ƃ������Ƃɑ�����B�T�O�̍\���I���e�ƁA�{���I���\�̑S�̂Ƃ�����̂��̂ł��邩��ł���B�܂��A�{���I���\�ƊT�O�Ƃ̊W�́A���悤�ȓ��ꐫ�ɂ�ċK�肹���Ă������A�K�R�I�ł���B����ɔ����āA��{���I���\�ƊT�O�Ƃ̊W�́A�ʘH���^�����邩�ۂ��Ƃ������ƂɈˑ�������̂Ƃ��Ă��ꎩ�g�̓��ꐫ���������߂ɁA���R�I�ł���B�{���I���\�͕K�R�I���\�ƌĂ�A��{���I���\�͋��R�I���\�ƌĂ��B�_���I���R�Ƃ͋��R�I���\�̋��R���ɂق��Ȃ�Ȃ��B
��X�̓N���[�o�[�Ƃ����T�O�����Ă���B���̊T�O�͖{���I���\�Ɣ�{���I���\�Ƃ�����Ă���B�R��N���[�o�[�ɂƂĎO�t�Ƃ������Ƃ͂��̓��̒��\�̂����̂��Â�ł��낤���B��������ΎO�t�Ƃ��������̓N���[�o�[�Ƃ����T�O�̍\���I���e�ɑ����邩�A�܂��͉\�I���e�ɑ����邩�B�����Ȃ��Ӗ��ɂ����ẮA�O�t�̓N���[�o�[�̖{���I���\�Ƃ��č\���I���e�ɑ�����Ƃ͉]���Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�N���[�o�[�ƑS�R������������������̂Ŏl�t���������̂����o���ꂽ�ꍇ�A��X�͂�����N���[�o�[�łȂ��Ƃ͉]��Ȃ��ŁA�l�t�̃N���[�o�[�Ƃ����B���Ȃ킿�N���[�o�[�Ƃ����T�O�͎O�t�Ƃ������Ƃ�K�������{���I���\�Ƃ��Ă��Ă���̂ł͂Ȃ��B�O�t�Ƃ������Ƃ̓N���[�o�[�Ƃ����T�O���ꎩ�g�̂����ɂ͕K���������܂���Ă��Ȃ��B�]���āA�N���[�o�[�ƎO�t�Ƃ̊W�͌����ɉ]�����R�I�ł���B�������Ȃ���A�O�t�Ƃ������\�̓N���[�o�[���A���Ƃ���ɂł͂Ȃ��Ƃ��w��Ǐ�ɗL���Ă�����̂ŁA�X�`���A�[�g�E�~���̂��������I���R�I����(separable�@accident)�ł���Ȃ���s�����I���R�I����(inseparable�@accident)�ɋ߂����̂ł���B�~���ɏ]���Εs�����I���R�I�����Ƃ́A�{���I�����ƊW�Ȃ����̂ŁA�]�đ��݂��Ȃ����Ƃ̏o������̂ł��邪�A������ɂ͑��݂��Ȃ��ꍇ���m���Ă��Ȃ����̂ł���B���ՓI(universal)�ł��邪�K�R�I(necessary)�łȂ����̂ł���B�����I���R�I�����Ƃ͎�����ɂ��ƁX���݂��Ȃ����Ƃ̂�����̂ł���B���Ȃ킿�K�R�I�łȂ��݂̂Ȃ炸�A���ՓI�ł��Ȃ����̂ł���(Mill,System�@of�@Logic,�T,ch.�Z,��8)�B�O�t�Ƃ��������̓N���[�o�[�̕s�����I���R�I�����ł͂Ȃ����A�������s�����I���R�I�����ɐr���ڋ߂������̂ł���B�������ĉ�X���l�t�̃N���[�o�[����ɋ��R�I�ƍl����̂́A�O�t�Ƃ���������s�����I���R�I�����Ƃ̐ڋ߂ɂ����āA�ہA���{���I���\�Ƃ��Ĕc�����邱�ƂɌ��Ă���B
��{���I���\�Ƃ��Ă̘_���I���R�͕��ՓI���ꐫ�̕�ۋ@�\�ɗ^��Ȃ����̂ł���B�������Ă��̕�ۋ@�\�́u��Ɂv�܂��́u�w��Ǐ�Ɂv�Ƃ����}�������ĉc�܂��̂ł��邩��A���̋@�\�Ɏ̏ۂ��ꂽ�_���I���R�́u��Ɂv����сu�w��Ǐ�Ɂv�̔ے�Ƃ��āu�H��Ɂv�Ƃ����\�������̂ł���B���R����ʓI�@���ɑ����O�̈Ӗ�����ė���̂͂���Ɋ�Ă���B�܂����R��\�킷�ꂪ�u�H��Ɂv�Ƃ������Ƃɍ����L����ꍇ������̂����̂��߂ł���B�u�킭��Ɂv�Ƃ������R���Ӗ�����Ìꂪ���邪�A�킭��t�Ƃ͉Ă̂���g�t�̂悤�ɐF�Â��Ă���͂ꂽ�̗t�Łu�H��Ɂv�������Ȃ����̂ł���B�u���܂��܁v�̌�����R���Ӗ�����ق��A�u���܂Ɂv�Ɠ����Ɂu�H��Ɂv�̈Ӗ������L���Ă���B�܂��u���܂����Ɂv�́u�����v�́u���i�����j��v�̈ӂł���Ƃ������A�u����v�͖@���̈�ʓI�s�ϐ���艓������䂭�����̗�O�̔w���̓����ł���B
�Ȃ��T�O�Ƌ��R�I���\�Ƃ̊W�́A�J���g�̂����镪�͓I���f�Ƒ����I���f�Ƃ̊W�ɐ[���G��Ă���B���͓I���f�͓��ꐫ�Ɋ�b�����Ă�����̂ł���B�J���g�́w���������ᔻ�x�̂����Łu���͓I���f(�m��I)�͏q��Ǝ��Ƃ̌��������ꐫ�ɂ�Ďv�҂�������̂ł���v(B.10)�Ƃ����A�܂��w�_���w�x�̂����ł��u���͓I����Ƃ͂��̊m�������T�O��(�q��Ǝ��̊ϔO�Ƃ�)���ꐫ�Ɋ����������v(��36)�Ƃ��Ă���B���Ȃ킿�A���͓I���f�Ƃ́A���ꐫ�ɂ����Ĕc������ꂽ�T�O�́A���ꐫ���ɂ����镪�͂ɂق��Ȃ�Ȃ��B�u�}�Ă̕��͉̂������Ă���v�Ƃ������Ƃ́A���̂Ȃ�T�O��a+b�Ƃ���A���̊T�O�̂����ɂ͉���b�����܂�Ă��邱�Ƃ��咣���Ă���̂ł���B�������āA���ꐫ����b���Ȃ�����A��X�͂��̎�́u���f�̕K�R�����ӎ����邱�Ƃ��o����v(B.12)�̂ł���B���͓I���f�̓����̋Ɍ��ɒB�������̂́u���͕̂��̂ł���v�Ƃ����悤�ȓ��ꔻ�f�ł��āA�u�b�͍b�ł���v�Ƃ������ꗥ�ɔ����K�R�������̘ԂɗL���Ă���B����ɔ����āA�����I���f�Ƃ͏q��Ǝ��Ƃ̌������u���ꐫ�Ȃ����Ďv�҂�������́v(B.10)�ł���B�u�}�Ă̕��̂͏d���v�Ƃ������Ƃ́A���̂Ȃ�T�Oa+b�ɁA����c���������Ă��邱�Ƃ��咣����̂ł���B��������c�Ȃ�q��͊T�Oa+b�ƑS���ʂ̂��̂ł������A�d���ƕ��̂Ƃ̌����́u�P�ɋ��R�I�v(B.12)�ł���B�@�@
���Ƃ��A��̓���Ȓm�o���f�ɂ��ĉ]���A�m�o�����ςɗ^����ꂽ�m�o�̋�̓I���e�����͂����Ĕ��f��������̂ł��邩��A�u���̃N���[�o�[�͎l�t�ł���v�Ƃ����悤�Ȕ��f�����͓I���f�Ɖ]���ׂ��ŁA�]���āu���̃N���[�o�[�v�Ɓu�l�t�v�Ƃ̌����͕K�R�I�ł���B��X�́A������ʊT�O�ƌ��J���g�̉���̉��ɁA���͓I���f�Ƒ����I���f�Ƃ̋�ʂ����e������ŁA�O�҂͕K�R�����A��҂͌o���I�����I���f���Ӗ����������R��������Ă��邱�Ƃ��w�E���悤�Ƃ���ɉ߂��Ȃ��B���Ȃ킿�u��̃N���[�o�[�͎l�t�ł���v�Ƃ����o���I�����I���f�ɂ����āA�u�N���[�o�[�v�Ƃ����T�O�Ɓu�l�t�v�Ƃ����q��Ƃ̌����͑S�����R�I�ł���B
�S�̔��f�Ɠ��̔��f�Ƃ̑Η����K�R���Ƌ��R���Ƃ̑Η��Ɉ��̊W��L���Ă���B�q�ꂪ���ɑ���W���K�R�I�ł���ꍇ�ɏ��߂đS�̔��f�������Ȃ�Ӗ��ɂ����Đ����ł���B�u�}�Ă̕��̂͏d���v�Ƃ����Ƃ��ɂ́A�����ɉ]���A�d�������̂Ȃ�T�O�̖{���I���\�ł��邱�ƁA���Ȃ͂��d���ƕ��̂Ƃ̊ԂɕK�R�I���W�̑����邱�Ƃ��\�z����Ă���ׂ��ł���B���̕K�R�����ے肳�ꂽ�ꍇ�ɂ́A���̔��f�ɂ�āu��̕��̂͏d���v���u��̕��̂͏d���Ȃ��v�Ɖ]����B�������ďd�������̂Ȃ�T�O�̋��R�I���\�ɉ߂��Ȃ����Ƃ��\�������B�܂��A�d�������ǂ̋��R�I���\�ɉ߂��Ȃ��ȏ�́A�u�}�Ă̕��̂͏d���v�Ƃ����ꍇ�̕��Ր��͌����Ȃ镁�Ր��ł͂Ȃ��āu�P�ɔ�r�I�v(Kant,Welches�@sind�@die�@wirklichcn�@fortschritte,die�@die�@metaphysic�@etc.,Beilagen�@�T,Abschnitt�@�T)�̂��̂ł���B�������āA���̋��R������w�K�m�Ɍ��\���邽�߂ɃJ���g�́w�v�����S���i�x�ɂ����Ă͑S�̔��f����̔��f�ɉ��߂āu��̕��̂͏d���v(��2,a)�Ɖ]�Ă���B�Ȃ��A���ڐ����̂����Ɂu���R�ɂ�銷�ʁv(conversio�@per�@accidens)�Ƃ����̂�����B�u�}�Ă̍b�͉��ł���v�Ƃ����ꍇ�ɂ́A�u��̉��͍b�ł���v�Ƃ������Ƃ��o����B���̊��ʖ@���u���R�ɂ��v�Ɖ]����̂́A�b�����Ȃ�T�O�̓��ꐫ�̂����Ɋ܂܂�Ă��Ȃ�����ł���B���Ȃ͂��b�͉��̋��R�I���\�ɉ߂��Ȃ�����ł���B��ւu�}�Ẳ��F�l��͐l�Ԃł���v�Ƃ������Ƃ��o����B����ɑ��āu�}�Ă̐l�Ԃ͉��F�l��ł���v�Ƃ͉]���Ȃ��B�S�̔��f����̔��f�ɉ��߂āu��̐l�Ԃ͉��F�l��ł���v�Ƃ������Ƃ��o���邾���ł���B�l��I���ʂ������畆�̐F�͐l�ԂȂ�T�O�̋��R�I���\�ł���B�������ċ��R���͓��̔��f�ɂ�Ę_���I���\�����߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�T�O�Ɏ��ݐ���t�^�������̂����̂ł���B���̂Ƃ͓��ꗥ�ɂ�Ď��ԓ��Ɏ��Ȃ�s�ϓI�ɕێ�������̂ł���B�J���g�̌��t����ĉ]���u��̂̓��ꐫ�v(�w���������ᔻ�xB.229)�Ƃ������Ƃ����̂̈Ӗ��ł���B���̂ɑ��đ������l������B�����Ƃ͎��̂̂������̋K��ŁA��̎��̂̑��ݗl�Ԃ��Ӗ�����B���Ȃ킿���̂Ƒ����Ƃ̊W�́A�T�O�ƒ��\�Ƃ̊W�ɑΉ����Ă���B�]���Ė{���I�����Ɣ�{���I�����܂��͋��R�I�����Ƃ��l������B�T�O�����݉����āA���̂̈Ӗ��m�Ɍ��\���������ȗ�͉]���܂ł��Ȃ��v���g���̃C�f�A�ł���B�C�f�A�͊T�O�Ƃ��āA�����̌��ɑ��āu���ʎҁv(��?�@�ȃ̓ǃ�?��)�]���āu��ҁv(�ʃ̓�??)�ł���B���������ꎩ�g�ɓƗ��������E���`������u���̑��݁v�ł���B���͈���ɂ̓C�f�A�Ɋ��^������̂ł��邪�A�܂������ɂ͋�ԂƉ����ꂽ�u�݁v�ɍ������Ă���B�������ċ��R���Ƃ́A�C�f�A�w�̊��^���݂ɂ�ĕs���S�ɂ���邱�Ƃ��A���Ȃ킿���^�Ɩ͎ʂƂ̊Ԃɑ�����u����Ӗ����Ă���B�A���X�g�e���X�͂��̎�̋��R�����Ѓ҃ʃ��Ã��Ń�??�ƌĂЃ҃ʃ��Ã��Ń�??�Ƃ́u������̂ɑ����A�܂����ɏq�ׂ�꓾����̂ł��邪�A�������K�R��(?�́@?��?���ȃ�?)�ł��Ȃ��A�����̏ꍇ��(?��?�@��?�@�̓�?)�ł��Ȃ��v(Met.,��.18,1022(�@a)�@�r�B�������ăA���X�g�e���X�́u���ꎩ�g�ɂ��v(�ȃ��Ɓf�@��?��?)�Ɓu���R�ɂ��v(�ȃ���?�@�Ѓ҃ʃ��Ã��Ń�??)�Ƃ̋�ʂ𖾗Ăɂ����B�㐢�L���s��ꂽper�@se�@��per�@accidens�Ƃ̋�ʂ����Ȃ킿����ł���B�u���ꎩ�g�ɂ��v�̂́u�{���v�܂��́u�{���ɑ����邷�ׂĂ̂��́v�܂��́u���ڂɎ��g�̂����ɁA�������͎��Ȃ̈ꕔ���̂����ɂ��̂����ꂽ�Ƃ��v�ł���(Met.,��.18,1022(�@��)�@)�B�Ⴆ�u�l�Ԃ͂��ꎩ�g�ɂ�Đ����Ă���B�Ȃ��Ȃ�ΐ������ڂɏh�Ă���Ƃ���̐��_�͐l�Ԃ̈ꕔ�ł��邩��ł���v(ibid.)�B���Ȃ킿�u�ނ������ł��邱�Ƃ͋��R�ɂ��̂ł͂Ȃ��v(Met,.E.2,1026(�@��).)�B�������Ȃ���u����l�Ԃ����F�ł��邱�Ƃ͋��R�ł���B�Ȃ��Ȃ�A��ɂł��Ȃ��A�����̏ꍇ�ɂł��Ȃ�����ł���v(ibid.)�B���悻�u���ՓI�̂��́i��?�@�ȃ���?�Ƀ̓ҁj�͂��ꎩ�g�ɂ�ċA�����邪�A���R�I�̂��̂͂��ꎩ�g�ɂ��̂ł͂Ȃ��B�X�̂���(��?�@�ȃ��Ɓf�@?�ȃ��Ѓу�)�Ɋւ��ĒP�Ɍ����̂ł���v(Met.,��.9,1017(�@��))�B�u����(?�Ƀ�)�����R�̌����ł���v(Met.,E.2,1027(�@a))�B�]���āu���R�Ƃ͔݂ɋ߂�����(?����??�@�уǁ@�у�?��?�@?�˃у�?)�ł���v(Met.,E.2,1026(�@��))�B
�v���g������уA���X�g�e���X�ɑk�邱�Ƃɂ�āA�_���I���R�����Ɋւ�����̂ł��邱�Ƃ����ɑN����葖����ꂽ�B���R�������Ɋւ���Ƃ���A���R�I�������ƁX�̓I�����ƌĂ�闝�R�������ɂȂ�B�܂��V�����C�G���}�b�w�������̑����I���f�̓K�p�͈͂��X�̎����Ɍ��낤�Ƃ�������킩��B�v����ɁA�_���I�n���ɂ�������R���Ƃ́A������ʊT�O�ɑ��Ă��K��ł���B��X�����F�l��ł��邱�Ƃ͋��R�ł���B�Ȃ��Ȃ�A��̓���̐l�Ԃɂ̂݉��F�Ƃ������������o����邩��ł���B�l�t�̃N���[�o�[�����R�̂��̂ł���B�Ȃ��Ȃ�A����X�̃N���[�o�[�ɂ����Ă̂ݎl�t�Ƃ������������邩��ł���B�w�ߐ��u�o�x�̂����Ŝ\�����ߐ�Ɏ��̖���Ă���B�u���Ԑl���ʖڐg�̎l�x�F����A���̗L�����җL�Z���ҁA�L���a���a�ҁA�L�n�ҕx�ҁA�L���җL�ڎҁA�L�[���җL�X���ҁA�Lਐl���M�ҁA�אl���^�ҁA�L���җL�ŎҁA���Ȍ̕s���v�B���̖�͐l�Ԃ̊�тƔY�݂Ƃ𑠂����ł���Ƌ��ɁA�N�w�̂����̓N�w�I�Ȗ�ł���B�ߐ�͂���ɓ����āu����O���ؐ��فA�L�|�җL��ҁA�L�h�җL�[�ҁv�Ɖ]���B�������āA���̓����₤�҂ɖ�����^���Ȃ��Ƃ��ɁA���͍X�ɐV���Ȃ�n���ɂ����ēW�J����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�@
�O�@�o���I���R
�u���̃N���[�o�[�͎l�t�ł���v�Ƃ�����̓���Ȓm�o���f�ɂ��āu���̃N���[�o�[�v�Ɓu�l�t�v�Ƃ̌������K�R�������Ă��邱�Ƃ͞G�ɏq�ׂ��B�u�N���[�o�[�v�Ɓu�l�t�v�Ƃ̌��������R�I�ł���̂́A��ʓI�ȊT�O���v�҂��ꂽ�ꍇ�ɂ����Ă����ł���B�u���́v�Ƃ����w���㖼���ɂ�āu�N���[�o�[�v�Ɍ�������^����Ɠ����ɁA��̓���ȃN���[�o�[�Ǝl�t�Ƃ̊W�͂��͂���R�I�ł͂Ȃ��Ȃ�̂ł���B�u���̃N���[�o�[�v���u�l�t�v�ł���̂́A�h�{�̏�Ԃ��A�C��̉e�����A�n���̎h�����A�������̌������Ȃ��Ă͂Ȃ�ʁB���l�Ɂu�l�ԁv�̊O�e�́u�[���X���v�����R�I�ƍl����̂́A�u�l�ԁv�Ƃ�����ʊT�O�𗧂ĂāA���̈�ʊT�O�Ƃ̊W�ɂ����ē����ڌ����邩��ł���B�u���̐l�v���u�[���v�ł���A�u���̐l�v���u�X���v�ł���̂́A�j�������̐��B�זE�̌����̎d�����A�D�P���̕�̂̌��N��Ԃ��A�������̌������Ȃ��Ă͂Ȃ�ʁB��X�͂��悤�ɂ��ĊT�O�̖�肩����ʐ��̖��ֈڂ�̂ł���B�_���w�̒��ۓI�͈͂��玩�R�N�w����ѐ��_�N�w�̌o���I�̈�ֈڂ�̂ł���B
���ʐ��Ƃ͔@���Ȃ�\�������Ă��邩�B���C�v�j�b�c�͖������Ə[�����R���Ƃ��u��匴���v�Ə̂���(Opera�@philosophica,d.Erdmann,pp.515,707)�B���Ė������͕L��A���ꗥ�ɂق��Ȃ�Ȃ��B�J���g�����҂̋�ʂ����Ȃ���(Logik,Einleitung�@�Z)�B�܂����C�v�j�b�c�̂�����[�����R�����A�u�F�����R�v�Ɓu���ݗ��R�v�Ƃ̓�҂��܂ނ��̂Ƃ��Ĉ��ʗ��̈Ӗ������L���Ă��邱�Ƃ́A�N���[�N�Ɉ��Ă�����̂����Łu���̌����́A��̎��������݂��A��̎������N��A��������������邽�߂ɁA�[�����R��K�v�Ƃ��錴���ł���v(Erdmann,ibid.,p.778)�Ɖ]�Ă��錾�t�ɂ�Ă������ł���B�R����̓�匴������u���ꗥ�v�Ɓu���ʗ��v�Ƃ͔@���Ȃ�W�ɗ����B���C�v�j�b�c�͒f��primae�@veritates�ɂ����Ĉ��ʐ��ꐫ�ɊҌ������ނ邱�Ƃ̉\���Î�����(Opusculcs�@et�@fragments�@indits�@de�@Leibniz,d.Couturat,pp.518-519)�B�N�[�`�����[�̊Ȗ��Ȍ����\�킵�����u�}�Ă̓��ꖽ��(���͓I)�����ł���Ɠ��ꗥ�͂����B�}�Ă����Ȃ閽��͓���I(���͓I)�ł���Ɨ��R���͍m�肷��v(Revue�@de�@Mettaphysique�@et�@de�@Moralc,t.X,1902,p.8)�B���C�G���\�����u���ʗ��́A���ԓ��̏������̑��݂ɓK�p���ꂽ���ꗥ�ɂق��Ȃ�Ȃ��v(Identit�@et�@Ralit,p.38)�Ɖ]�Ă���B��X�����鎖�ۂɊւ��Ă��̌����ƌĂԂ��̂́A���̎��ۂ̂����Ɍ��o����铯��҂ł���B���f�Ǝ_�f�Ƃ������������ʂƂ��Đ����������Ƃ������Ƃ́A���f�Ȃ�_�f�Ȃ茳�f�ƌĂ����̂��������̂����ɂ����Ȃ�ɕێ����Ă��邱�Ƃł���B����̂Ɉ��ʊW�͕����������ĕ\�킵���邱�Ƃ𗝑z�Ƃ���Bcausa�@aequat�@effectum�Ƃ͂��̈Ӗ��ł���B�G�ɊT�O�����ꐫ�Ɋ�b��L���邱�Ƃ��q�ׂ����A�����Ɉ��ʐ������ꐫ�ɋA�����ނ邱�Ƃ��\�ł��邱�Ƃ��킩���B�������Ĉ��ʊW������W�ɂق��Ȃ�Ȃ��Ƃ���Ȃ�A���ꗥ�̗L����K�R�������ʗ����L���Ă��锤�ł���B��X�͐��f�Ǝ_�f�Ƃ���������ΕK�R�I�ɐ��ɂȂ�ƍl����B���f�Ǝ_�f�̉����Ƃ������ƂƐ��Ƃ̊Ԃɂ͕K�R�I�W��������B�Ȃ��Ȃ�A���f�Ǝ_�f�Ƃ͐��̂����Ɏ��Ȃ�ɕێ����Ă���B�����ɂ͓���҂�����B�]�Ă����ɂ͕K�R��������B
�Ȃ��A�ړI��i�W���L�`�̈��ʊW�̈��ƌ��邱�Ƃ��o����B���̈Ӗ��Łu���͈��v(causa�@efficiens)�ɑ��āu�ړI���v(causa�@finalis)�̊T�O������B���Ȃ킿�A�A���X�g�e���X�́u�ω��̋N�n�v(?�σ�?�@��??�@�ʃÃу����̓�??)�Ɓu���̂��߂Ɂv(��?�@?�˃Ã˃ȃ�)�Ƃ����Ɂu���́v(��?�@��?)�̖�ɓ�����u�����v(��?��?��)�ƌ���(Phys.,�U.3;Met,��.2)�B�������ʊW�ƖړI��i�W�Ƃɂ����ẮA���̊W���t�ɂȂĂ���B���ʂƂ��Č�ɗ��邱�Ƃ��A�ړI�Ƃ��Đ�ɍl�����A�����Ƃ��Đ�ɗ��邱�Ƃ���i�Ƃ��Č�ɍl������B�ړI�������Ƃ��ē����A���̌��ʂƂ��Ď�i���邩��A���ƌ��ʂł������̂������ƂȂ�A���ƌ����ł������̂����ʂƂȂ�B���k�[���B�G�́u��i�Ƃ́A�ړI�I�ƌĂ�錴���ɓƓ��Ȉ��̌��ʂł���v(Trait�@de�@logique�@gnrale,1912,�U,p.164)�Ɖ]�Ă���B����̂ɁA�A�������̌��t����ĉ]���A�ړI���Ƃ́u�����ɂ�錈��v(Essai�@sur�@les�@lments�@principaux�@de�@la�@reprsentation,2(�@e)�@d.,p.332)�ł���B�������āA�������������Ă��锤�̖������A��������ттČ����Ƃ��ē������Ƃ��o����̂́A�ӎ��̎��ԓI���̎����ɂ��̂ق��͂Ȃ�����A�ړI���Ƃ������Ƃ͌����ɂ͈ӎ��͈̔͂Ɍ���Ó����������T�O�ł���B���̊T�O���ӎ��͈̔͂��Ď��R�E�ɂ��\���I�����Ƃ��ĔF�߂悤�Ƃ���ɂ́A���炭���ӎ��̊T�O�̒��}�ɂ��ق��͂Ȃ��ł��낤�B�ӎ��I�s�ׂ��K���ɂ�Ė��ӎ��I�Ȕ��ˉ^���ɕς��鎖���Ɋ�āA�ӎ����K���ɂ�Ė��ӎ��ɂȂ��Ɍ������R�E�ƌ���l����������B�����F�b�\�������̈�l�ł���(De�@l�fhabitude�Q��)�B�J���g�͓V�˂��u���R�Ƃ��āv(Kritik�@der�@Urteilskraft,��46,182)���Ζ��ӎ��Ɍ|�p�I������Ȃ����Ƃ�����Ă��邪�A�ނ̓V�˘_�͂܂������ނ̔��w�Ǝ��R�N�w�Ƃ������J�ł���B�J���g�͎��R�E�ɂ�����ړI���̓K�p��P�ɋK���I�����Ƃ��Ă̂��e���Ȃ���A�Ȃ��\���I�����Ƃ��ď��F���邽�߂ɉ��肷��K�v�̊T�O�A���Ȃ킿���ӎ��̊T�O���Î����Ă���B���āA�ړI��i�̊W�́u�b�̂��߂ɂ́A�����Ȃ��˂Ȃ�ʁv�Ƃ����`����āA�ړI�Ǝ�i�Ƃ̊ԂɕK�R�I�W�̂��邱�Ƃ������Ă���B���̕K�R���͌��ǂ͈��ʊW���痈�Ă���B�u�b�̂��߂ɂ́A�����Ȃ��˂Ȃ�ʁv�Ƃ����ړI��i�W�́u�����Ȃ��A�K���b��������v�Ƃ����������ʂ̊W��\�z���Ă���B�]���Ă����ɕK�R��������B���悻�ړI�̎����͈��ʊW�ɂ�邱�Ƃ�v����B�ړI�͈��鎖�ۂ̌��ʂƂ����i������j����˂Ȃ�ʁB���̂��߂ɂ͌�������i�Ƃ��Ď��Ȃ���Ȃ�ʁB�R��Ɍ����ƌ��ʂƂ̊Ԃɂ͕K�R�I�W������B����̂Ɉ��̌��ʂ�ړI�Ƃ��Ĉӎu����ꍇ�ɂ́A���̌�������i�Ƃ��Ĉӎu���邱�Ƃ��K�R�I�ɗv�������B���Ƃ��A���ʊW�̕K�R���ƖړI��i�W�̕K�R���Ƃɂ�Mu(�E�E)ssen��Sollen�Ƃɂ�ĕ\�킵���鑊�Ⴊ����Ƃ��l�����邪�A���ɕK�R������ɂ����Ă͓����ł���B
���āA���R���Ƃ͕K�R���̔ے�ł�������A���ʓI�K�R���ƖړI�I�K�R���Ƃɑ��āA���̊e�X�̔ے�Ƃ��āA���ʓI���R���ƖړI�I���R���Ƃ̓�����锤�ł���B���ʓI���R�Ƃ͈��ʐ����������Ƃɂ�Đ���������R�ł���B�ړI�I���R�Ƃ͖ړI�����������Ƃɂ�Đ���������R�ł���B�������Ă��̈Ӗ��̋��R����X�͘_���I���R�ɑ��Čo���I���R�ƌĂԂ��Ƃ��o����B�Ȃ����R��\�킷���t�̂����ŁA�ے����_�@�Ƃ��ėL����u�[�Ȃ����v�A�u�䂭��Ȃ��v�A�u�s�}�v�Ȃǂ͂�������݂Ȉ��ʐ��܂��͖ړI���̔ے�ɐ����̊�b�����Ă�����̂ł���B��?��?�ʃ��у̓˂���?��?(���ꎩ�g)��?�ууŃ�(���R�Ȃ�)���痈�Ă��āA���l�̍���̏�ɐ���������̂ł���B
���悻�@�B�ς͂��̓O�ꂵ���`�ɂ����Ă͈��ʓI�K�R���݂̂��F�߂Ȃ��B�]���Ĉ��ʓI���R���̑��݂̗]�n�͂Ȃ��B�������A�ړI�I�K�R����ے肵�A���̌��ʂƂ��āA�ړI�I���R�������F����B���R�Ȋw�I���E�ς͂��̌X�����\���Ă���B����ɔ����āA�ړI�ς��O��I�Ȍ`������ꍇ�ɂ́A�ړI�I�K�R���ɂ�Ă݈̂��������悤�Ƃ���B�]���ĖړI�I���R���͑��݂��Ȃ��B���̑��ɁA���ʓI�K�R���̔ے�̌��ʂƂ��āA���ʓI���R���͑��݂��邱�Ƃ��o����B����_�w���_�̈ӎu�ɂ�Ė}�Ă��������ꍇ�A���ʓI���R���Ӗ������ւ̑��݂�F�߂�̂͂��̊W�Ɋ�Â��Ă���B���̈Ӗ��ɂ����āA���ʓI�K�R���͖ړI�I���R���ƌ������Ղ��A�ړI�I�K�R���͈��ʓI���R���ƌ������Ղ��B�u���R�̕K�R�v�Ƃ����悤�ȋt���I�̌�͂������������̉\���Ɋ�����̂ł���B�܂������Q���w�B���_�j�x�̂����Łu���R�ƕK�R�قNJ��S�ɑ�����������̂͑��ɂȂ��B����ɂ��S��炸���҂قǎƁX�����������̂����ɂȂ��v(Geschichte�@des�@Materialismus,�T,S.13)�Ɖ]�Ă���̂��A�����錋�����e�Ղɐ������邽�߂ł���B���܂��̌����̎d��������Ɂu�َ팋���v�Ɩ��t���Ēu�����A�������A�َ팋���������\�I�Ȍ����̎d���ł����ł͂Ȃ��B���ʓI�K�R���ƖړI�I�K�R���Ƃ��������āA�K�R������������N�w�ƂȂ�A���ʓI���R���ƖړI�I���R���Ƃ��������āA���R�����J������N�w���\������ꍇ������B�X�g�A�h�͖ړI�I�K�R�����甭���Ĉ��ʓI�K�R���Ɏ���O��I�Ȍ���_������A�G�s�N���X�͈��ʓI���R������o�ĖړI�I���R���ɏI���`�I�Ȕ�_���������B�������������̎d�����u���팋���v�Ɩ��t���邱�Ƃ��o����B�����̊W����̂悤�Ȑ}���ɂ�Č��킵�Č��悤�B���̐}�ɂ��āA���팋��(���ʓI�K�R�ƖړI�I�K�R�Ƃ̌����A���ʓI���R�ƖړI�I���R�Ƃ̌���)�͐����̕����ɍs���A�َ팋��(���ʓI�K�R�ƖړI�I���R�Ƃ̌����A�ړI�I�K�R�ƈ��ʑً��R�Ƃ̌���)�͐����̕����ɍs����B
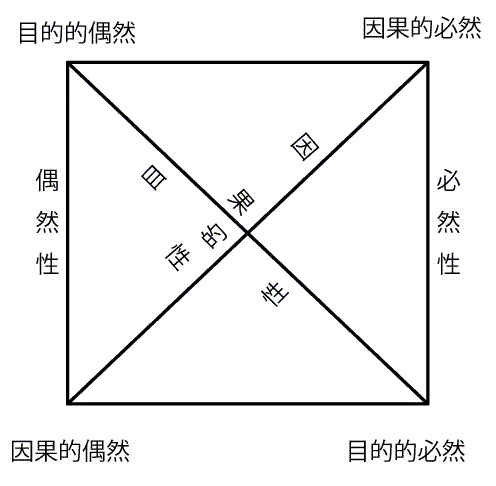
���ʓI�K�R��?��?���ȃł��Ȃ͂�necessitas�̌�ɑP���\���Ă���B���ꗥ�ɂ�đ��݂̋K����o�����p�����j�f�X�͎��ȓ����ێ����鑶�݂Ɋւ��Ă��̌��p���āu�����e����?���ȃł����݂��j�Ŋ��Ď��͂�����߂Ă���v(Diels,Die�@Fragmente�@der�@Vorsokratiker,Fr.8)�Ƃ����A�܂��u���͂���͂Ă���V���ǂ����琶���������A�܂��A�@�@�e����?���ȃł��@���ɓV��U�����ď����̍S����ێ����ׂ��������������A���͒m��悤�ɂȂ邾�炤�v(Diels,ibid.,Fr.10)�Ƃ��]�Ă���B�Ȃ��Ñ�ɂ�����@�B�ς̓T�^�ł��錴�q�_�ɂ��Ă����̌�͎ƁX�p����ꂽ�B�u�����Ȃ���������͉̂������Ȃ��B��͈��闝�R����A�܂�?��?���ȃł������Đ�����v(Diels,ibid.,Fr.2)�Ƃ̓��E�L�b�|�X�̌��t�ł���B�J���g���u�K�R���Ƃ́A�������̗͊w�I�@���ɏ]���錻�ۂ̑��݊W�Ɗۂ��̊W�Ɋ�Â��āA����^����ꂽ�C�ӂ̑���(������)���瑼�̑���(���ʂ�)��V�I�ɐ��_����\���ƁA�Ɋւ�����̂ł���v(�w���������ᔻ�xB.280)�Ɖ]�Ă���ꍇ�̕K�R�������ʓI�K�R���ł��邱�Ƃ͉]�������Ȃ��B
�ړI�I�K�R����e�Ƃ��Ă��Ă��钘������̓�?�˃̓ǃ��ł���B���ʂɁu�挩�v�܂��́u�ۗ��v�Ɩ��B���̌�̓v���g�����w�e�B�}�C�I�X�x�̂����Łu�_�X�̃�?�˃̓ǃ��ǁv�i44c�j�Ɖ]�ėp���Ă��邪�A�X�g�A�h�̓N�w�҂����ɂ�ē��ɍD��ŗp����ꂽ�B�N���V�b�|�X�́u�Ⴉ�甒�F�Ɨ₳�Ƃ������Ă��܂��牽���c�邩�A����g�����A������Â����A�썰����^�����A�_�����?�˃̓�?�˂���Ă��܂��牽���c�邩�v(Arnim,Stoicorum�@veterum�@fragmenta,�U,no.1118)�Ɖ]�Ă���B�V���ł�燎m�e���g���X�����ɒ悷��]���Ɂu���̍��͎��̃�?�˃̓ǃ��ɂ��ėǂɉ��܂�v(�u�g�k�s�`�v��\�l�͎O��)�Ɖ]�Đl�Ԃ̐挩�ɂ��̌��p���Ă��邪�A��?�˃̓ǃ����Ȃ킿providentia�̊T�O�͐_�Ɣ푢���Ƃ̊W���K�肷����̂Ƃ��Ċ���_�w�ɂ��ďd��ȈӋ`�����Ă���B�ړ���̃�?�i��j�������ɂ�錈��Ƃ��Ă̖ړI�I�K�R���������Ă���B
�A�i�N�T�S���X�̃˃�??���ގ��������e�����Ă���B�u�����ɂ����Ă���ׂ��悤�ɁE�E�E�E����˃�??���������v(Diels,ibid.,Fr.12)�Ƃ����ނ̌��t�Ŗ����ł���B�v���g�����u���̐��E�̌`���ɂ�����?��?���ȃłƃ˃�??�Ƃ������o�����B�������˃�??��?��?���ȃłɏ����B���Ȃ킿��҂�������āA�����̐����ɍۂ��đ啔�����őP�̕��֓������߂��v(Timaios,48a)�Ɖ]�Ă��邪�A?��?���ȃł��Ȃ킿���ʓI�K�R���ƁA�@�@�@�˃�??�̓��܂���ړI�I�K�R���Ƃ�Η������߂Ă���̂ł���B�������܂��A���������g�p�@�𗠐���?��?���ȃł̌�����ĖړI�I�K�R����\�킷�ꍇ������B���̐��ڂ̓A���X�g�e���X�Ɍ�����B�u?��?���ȃł���̌����Ƃ������Ƃ��]���̂́A����҂��琅���������ꂽ�̂͏����ɂ��̂Ō��N�ɂ��̂ł͂Ȃ��ƍl����̂Ƌ��炭����̂��Ƃł��낤�B�������������؊J�����̂͌��N�̂��߂ł����̂ł���v(De�@gener.Animal.,�X.8,789(�@��))�Ɖ]�Ă���ꍇ��?��?���ȃł͈��ʓI�K�R���ł��邪?��?���ȃł̈�̈Ӗ��Ƃ��āu���ꖳ�����Ă͑P���������́v(Met.,��.7,1072(��))�Ƃ������Ƃ������Ă���ꍇ�ɂ͖ړI�I�K�R�����w���Ă���B���Ȃ킿���ʓI�K�R���ƖړI�I�K�R���Ƃ̊Ԃɓ��팋�����s�͂�Ă�����̂ƌ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B?��?���ȃł��˃�??�ɂ�ĈӖ��̕ύX�����Ɖ]�����Ƃ��o����B
�w���N���C�g�X�̃�?����?�i�����j���?�ȃŁi���`�j���?�ʃ��σ�?�˃Łi�^���j�����炭���Ƃ͖ړI�I�K�R����\�킻���Ƃ������̂ł��낤�B�R��ɂ����ɂ��A�A�����x�͔��̕����ɁA���팋�����s���āA�ړI�I�K�R�������ʓI�K�R�������Ӗ�����悤�ȌX������Ă���B��Ƀ�?�ʃ��σ�?�˃ł��Ȃ킿fatum�����̌X���𑽂������Ă���B�f�B�I�Q�l�X�E���G���e�B�E�X�̓X�g�A�h�̐��Ƃ��āu��̓�?�ʃ��σ�?�˃łɂ�ċN��B�E�E�E�E�������ă�?�ʃ��σ�?�˃łƂ͑��ݎ҂̌���(��?��?��)�A�������͐��E������ɂ�ĉ^�s���闝��(��?����?)�ł���v(Diog.�Z.149)�Ɖ]�Ă���B���̏ꍇ��?�ʃ��σ�?�˂͖ړI�I�K�R���ƈ��ʓI�K�R���Ƃ̓���Ӗ�����ƌ��č��x�Ȃ��ł��낤�B���̊T�O�͍X�Ɉ��ʓI�K�R������َ팋���𐋂��ĖړI�I���R���̈Ӗ������Ƃė���B�R��ɖړI�I���R���͖ړI�I�K�R���Ɩ����Γ��̊W�ɗ����̂ł���B����̌ꂪ�������������e�����Ƃ������Ƃ͕s�v�c�̂悤�ł���B���������̂悤�ɍl������̈Ӗ��������ɂȂė���B�ړI���́A�����ɂ�Č��݂����肷����̂Ƃ��āA�G�ɂ��]���悤�Ɉӎ���\�z���Ă���B�������ӎ��Ɩ��ӎ��Ƃ̊Ԃɂ͒i�K�I�ȒʘH���J���Ă���B�ӎ��͂��̒ʘH��ʂĐ����甽�ɓ]����B�ړI�̍m��͖ړI�̔ے�ɐ��ڂ���B�ړI�I�K�R�����ړI�I���R���ɕς���\���͂����ɂ���B�w���N���C�g�X�́u�S�R��?�ʃ��σ�?�˃łɌ��肳��Ă���v(Diles,Vorsokratiker,Fr.137)�Ɖ]�Ă��邪�A�܂��u���Ƃ́A�V�т���A������������(�Ãуу�?�փ�)�A�����ł���B�����̉����v(Diels,ibid.,Fr.52)�Ƃ��u�ł����������E�́A�o�L�ڂ�(��?��?)�͐ς��ꂽ�o�H�̂����܂�ł���v(Diels,ibid.,Fr.124)�ȂǂƉ]�Ă���B�����Ƀ�?�ʃ��σ�?�˃ł͖����ɖړI�I���R���Ɉڂ�s�Ă���B�܂��A���Ƃ����ꎩ�g�ɖړI�I�K�R�����Ӗ�����Ƃ��Ă��A�l�ԂɂƂĂ͈ӎu�ƊW�̂Ȃ��ړI�I���R�ł��邱�Ƃ����̊T�O�G�Ȃ炵�߂Ă���B�E�B���w�����E�t�H���E�V�����c�����̒��w���R�x�Ɂu�^���̑O�`���v�Ƃ����ʖ���^���Ă���̂��A�^���Ƌ��R�Ƃ̊Ԃɂ����������I�W�������邩��ł���B���ؓc�Օ����w�^���_�ҁx�̂����ōb���u�l�͉^���_�҂ł͂���܂���v�Ɖ]���̂ɑ��ĉ��Ɂu����ł͋��R�_�҂ł����v�Ƌl�₳���Ă���B���̋l��͒P�Ȃ����ɉ߂��ʂ��̂ŁA�^���Ƌ��R�Ƃ��L��A����̂��̂ł��邱�Ƃ��O��Ă���B�J���g�́u�K�^(Glu(�E�E)ckO)�Ƃ��^��(Schicksal)�Ƃ������悤�Ȏ[�D���ꂽ�T�O������B����͖w��Lj�ʂɊ��e�����Ēʗp���Ă��邪�A���������Ƃ��āu�����͉����v�Ƃ�����̓���v��������B��������ƁA�l�X�͂��̉�㈂̂��߂ɏ��Ȃ��炴�鍢�f�Ɋׂ�v�i�w���������ᔻ�xB.117)�Ɖ]�Ă���B�������Ȃ���A�����u��ϓI��㈁v���Ȃ����铹������Ƃ���u�q�ϓI��㈁v�̖��͕K�������N��Ȃ��̂ł͂���܂����B�����̊T�O�̎�ϓI���ݐ����w�E��������@��������Ȃ�u���̋q�ϓI���ݐ����ؖ�����v(ibid.)�K�v�͂Ȃ��̂ł͂���܂����B
���ʓI���R�ƖړI�I���R�Ƃ́A���Ƌ��Ƀ�?�ԃłƂ�����ɂ�ĕ\�킳�ꂽ�B����̂ɁA�f���N���g�X���@�B�ς̗��ꂩ����ʓI���R���U������ꍇ�ɂ��A�v���g�����ړI�ς̗��ꂩ��ړI�I���R�ɔ�����������ꍇ�ɂ��A�o���Ƃ��Ƀ�?�ԃłƂ����������p���Ă���B�f���N���g�X���u�l�Ԃ͎����̓��f�̌����Ƃ��ċ��R(��?�ԃ�)�Ƃ����������v(Diels,Vorsokratiker,Fr.119)�Ƃ��u���R(��?�ԃ�)�͎{���D�ށB���������ɂȂ�Ȃ��B���R(��?�Ѓ�?)�͂���ɔ����Ċm���ł���v(Diels,ibid.,Fr.176)�ȂǂƉ]�Ă���ꍇ�̋��R�́A���R�ɔ��́A���Ȃ킿���ʓI�K�R�ɔ��́A���ʓI���R�ł���B����ɔ����āA�v���g�������q�_�҂��]���āu�ޓ��̌����Ƃ���ɂ��A�ł���Ȃ���̂���эł����������̂����R(��?�Ѓ�?)����ы��R(��?�ԃ�)�������炵���A��菬�Ȃ���̂��Z�p�������炵���v(Leges,X.889)�Ƃ��u���_�ɂ��̂ł͂Ȃ��B�܂������̐_�ɂ��̂ł��Ȃ��B�܂��Z�p�ɂ��̂ł��Ȃ��B���������R�i��?�Ѓ�?�j�Ƌ��R(��?�ԃ�)�̂��̂ł���v(ibid.)�ȂǂƉ]�Ă���ꍇ�̋��R�́A���R�ƌĂ����ʓI�K�R�ƈَ팋�������Ă���ړI�I���R�ł���B�v���g�������R��ړI�I���R�Ɖ����Ĉ��ʓI�K�R�Ɠ��ꎋ���Ă��邱�Ƃ́u���R(��?�Ѓ�?)�ɂ�ĕK�R(?��?���ȃ�)����v(ibid.)�Ƃ����ܒ~���錾�t�ɂ�Ă������ł���B
�Ȃ��v���g���̓�?�ԃłɂ��A���Ȃ킿��?�ԃłƂ�������?�у�?�@�у�?�@��?�у̓�?�у̓҂Ƃ������p���Ă��邪�A�����Ƃ��S�������Ӗ���\�킵�Ă���B�Ⴆ�w�v���^�S���X�x�̂����ŁA���`�Ƃ����悤�ȓ��́u���R�ɂ��̂ł��Ȃ����R�ɂ��̂ł��Ȃ��v(��?�@��?�ЃÃǁ@��?�f�@?��?�@�у�?�@��?�у̓�?�у̓�)����ɂ����̂ŁA���̏��L�҂͓w�͂ɂ�Ă��̓����l�������̂ł���B����ɔ����āA�X���Ƃ��⏬�Ƃ�����Ƃ������悤�Ȍ��_�₻�̔��̒����́u���R�ɂ�邩�܂��͋��R�ɂ��v(��?�ЃÃǁ@?�@
��?�ԃ�)���̂Ƃ��Ă���(Prot.,323d)�B�����Ŏ��R�Ƌ��R�Ƃ���g�ƂȂē��o�ė��Ă��邪�A����̏ꍇ�ɂ́u���R�ɂ��v��?��?�@�у�?�@��?�у̓�?�у̓҂Ƃ����A�����̏ꍇ�ɂ̓�?�ԃłƂ��Ă���B���Ȃ킿���҂͑S�������Ӗ��ɗp�����Ă���B�܂��w�\�N���e�X��燖��x�ɂ����āA�P�l�ɂ͐��ɂ����ɂ����Ƃ������̂͂Ȃ��B�ނɊւ��邱�Ƃ��_�X�ɓ��Ղɂ���邱�Ƃ��Ȃ��B�]���Ă������Ɋւ��邱�Ƃ����R�ɂ��̂ł͂Ȃ��B�����ʂ��Ƃ������ɂƂĔJ��P�����Ƃł���ɈႢ�Ȃ�(41d)�Ɖ]�Ă���Ƃ��ɂ��A�u���R�ɂ��v��?��?�@�у�?�@��?�у̓�?�у̓҂Ƃ������t�ŕ\�킳��Ă���B
����ɔ����ăA���X�g�e���X�́w���R�w�x�̂����Ń�?�ԃłƃ�?��?�ʃ��у̓˂Ƃ̋�ʂ𗧂Ă��B�ނ̐����Ƃ���ɂ��A���҂̋��ʓ_�́A�ړI���̗̈�ɑ����鎖�ۂ��A�������i������j���ꂽ���Ƃ�ړI�Ƃ��ċN���̂łȂ��A���Ɍ��������Ă����ꍇ�Ƃ����_�ɂ���B���Ȃ킿���҂Ƃ��ړI�I���R�ł���(Phys.,�U.5)�B���҂̍��ٓ_�́A��?�ԃłƂ͋��R�I���ۂ��A�Ӑ}(�σ̓�?�σÃЃ�?)�ɂ�čs�ׂ�������̂ɊW���Ă���ꍇ�������ɑ��āA��?��?�ʃ��у̓˂Ƃ͑R�炴��ꍇ�ɂ��Ó�����T�O�ł���B���Ȃ킿��?��?�ʃ��у̓˂͊O�����?�ԃł��ۂ����ʊT�O�ł���B��?�ԃł̓�?��?�ʃ��у̓˂ł��邪�A��?��?�ʃ��у̓˂͕K��������?�ԃłł͂Ȃ��B�]���Ă܂���?��?�ʃ��у̓˂͓����ɂ��������ɂ����邪�A��?�ԃł͖ړI�I�s�ׂ̏o����҂Ɍ����Ă���B���Ȃ킿�@��?�ԃł͍K�^�i��?�у҃�?��)�ƍK��(��?���ǃʃ̓�?��)�Ƃ̓�T�O�̔}��ɂ�čs��(��?�̃�?)�Ɍ��t�����Ď��H�I�̈�ɑ����߂���B�]���ĈӐ}�������Ȃ��������⓮���⏬���̓�?�ԃł�m��Ȃ�(Phys.,�U.6)�B�����I�̃X�R�t�N�w�̓�?�ԃł�fortuna�āA��?��?�ʃ��у̓˂�casus�Ă��B
����ɂ��Ă̓u�[�g���[�͈��ʓI���R��contingence�Ɖ]���A�ړI�I���R��hasard�Ɖ]�Ă���B
�Ⴆ�A�����ɑ��锽�Θ_�҂̗���ɗ��Ĉ��ʓI���R���ړI�I���R�֓�����͂��Ȃ����Ƃ̋^����f���Ă���ꍇ�Ɂucontingence�̌�����hasard�łȂ��Ƃ�����A��̉��ł��蓾�邩�v�iDe�@la�@contingence�@des�@lois�@de�@lanature,9(�@e)�@d.,p.140)�Ɖ]�Ă���B�܂��A����ɑ��铚燂Ƃ��āu�Ⴕ������I�����̌n��̂����Ɉ��x�܂�contingence���x�z���Ȃ��Ƃ����Ȃ�A�ړI�����̌n��̂�����hasard���x�z����ł��炤�v(p.143)�Ɖ]���Ă���B�������A�u�[�g���[�̂悤�ȗp��@�͈�ʂɂ͍s���Ă��Ȃ��B�Ⴆ�A�������͈��ʓI���R�ƖړI�I���R�Ƃ����������̂�hasard�ƌĂсA�������Ĉ��ʓI���R���u���ʐ��݂̔ɂ����R(hazard�@par�@nant�@de�@causalit)�v�Ƃ����A�ړI�I���R���u�ړI���݂̔ɂ����R(hazard�@par�@nant�@de�@finalit)�v�Ɖ]�Ă���(Essai�@sur�@lcs�@lments�@principaux�@de�@la�@reprsentation,2(�@�Q)�@d.,pp.324,329)�B�E�B���f���o���g��������������Zufall�Ƃ����A���̊e�X�ɂ�kausaler�@Zufall��teleologischer�@Zufall�̌��p���Ă���(Die�@Lehren�@vom�@Zufall,S.65)�B�������āA���҂̋�ʂ�����̏�ɕ\�킳��Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ́A���ɍאS�ɂ��̋�ʂ�F�m���邱�Ƃ��̗v�ł���B�Ⴆ�����Q���u��X�͖ړI�_�҂ɑ��āA�ړI����J��E�����߂ɂ̂ݎ��ۂ̋��R�����咣����B��������X�́A�[�����R�������ƂȂ�₢�ȂⒼ���ɁA���̓������R�����Ăѕ�������v(ibid.,�T,S.14)�Ɖ]�Ă���B�ނ́u�������R��(dieselbe�@Zufa(�E�E)lligkeit)�v�Ɖ]�Ă��邪�A���̎��A�����ł͂Ȃ��B�O�͖̂ړI�I���R�ł���A��͈̂��ʓI���R�ł���B
���悻�ړI�I���R�Ƃ͖ړI���̔ے�ɂ�Đ���������̂ł���B�������āA�ړI�݂̔����ɓI�ɖڌ�����ꍇ�ƁA�ړI�ȊO�̂��̂̑��݂�ϋɓI�ɖڌ�����ꍇ�Ƃ����邪�A���Â�̏ꍇ�ɂ��Ă��ړI���̔ے�Ƃ����_�ɂ����Ă͕ς�Ȃ��B���ɓI�ȏꍇ�Ƃ��ẮA�Ⴆ�Δ�ᗂ͖ړI�I���R�ƌ�����B�l�ԂɂƂĎv�l�����̑��݂Ƃ������Ƃ���������ׂ���̖ړI�����Ӗ����Ă���Ƃ��āA��ᗂ͂��̎v�l�����݂̔��Ӗ����邩����R�I�̂��̂ƍl������̂ł���B�Ԃ����d�ɂȂ錻�ۂ��ړI�I���R�ƌ�����B�Ԃ̋@�\���A���̂̐��B���i����̂Ƃ����ꍇ�A�Y�ǂ��A�ɕς��邱�Ƃ͖ړI�̔ے�ł��邩��A���d�̉Ԃ͐A���w��ł��b�ԁA���Ȃ킿���R�I���ۂƌ����̂ł���B���̎�̖ړI�I���R���A���X�g�e���X�́u�����R(����?�@��?�Ѓǃ�)�v(phys.,�U.6,197(�@��))�ƌĂсA�ց[�Q���́u���R�̖���(Ohnmacht�@der�@Natur)�v(Encykl.,��250)�ɋA�����B�������āA�����R�Ȃ�ƌ�������w��ɂ́u���R�͉����������R�Ȃ�(��?�уŃ�)����Ȃ��v(De�@caelo,�T,4)�Ƃ����ړI�ς�����B�܂����R�͂Ȃ�ƒf�肷�邽�߂ɂ́A�\�߉������́u���s�iAusfu(�E�E)hrung)�v(Eneykl.,��250)��ړI�Ƃ��Ď��R�ɉۂ��Ă���̂ł���B���ɐϋɓI�ȏꍇ�Ƃ́A�Ⴆ����т�H�����ۂɐ^�삪�o�ė����悤�ȏꍇ�ł���B����т�H���Ĕ����𖡂����Ƃ��ړI�ŁA�^��邱�Ƃ͖ړI�̂����Ɋ܂܂�Ă��Ȃ�������A�^������Ƃ����R�Ƃ��̂ł���B�܂��Ⴆ�ΘB���p�t�̃u�����h��������ɕς��镨���悤�Ƃ��āA�A�������������ʁA�����錳�f�����Ƃ��A�ނ��ӂ����R�ɔ��������Ƃ����B���̏ꍇ�ɋ��R�Ƃ����̂��A�ӂ邱�Ƃ��ړI�̂����Ɋ܂܂�Ă��Ȃ�������ł���B�ȏ�̓�̏ꍇ�ɂ����āA�O�҂ɂ��ẮA��ᗂƂ����d�Ƃ��������Ƃ́A�ڎw���ꂽ���̖ړI�������������Ă���Ƃ����P�Ȃ���ɐ��ɂ����ė�������Ă���B��҂ɂ��ẮA�^��܂��͗ӂ̔����Ƃ������Ƃ́A�ړI�Ƃ��Ėڎw���ꂸ���āA�������ړI���蓾�ׂ����̂����݂��Ă���Ƃ����ϋɐ��ɂ����Ĕc������Ă���B�������ăA���X�g�e���X�̃�?��?�ʃ��у̓˂ƃ�?�ԃłƂ̋�ʂ͑嗪���̓�̏ꍇ�ɊY��������̂ł���B���Ȃ킿��?��?�ʃ��у̓˂͖ړI�̌��@��P�ɏ��ɓI�ɒq����B����̂ɖړI�I�s�ׂ̏o���Ȃ��҂ɂ��K�p�����T�O�ł���B����ɔ����ă�?�ԃł͖ړI�ƌ��꓾����̂���������Ă��邱�Ƃ�ϋɓI�ɒq����B�]���ĖړI�I�s�ׂ̏o����҂ɂ݂̂��錻�ۂƌ�����B�v����ɏ��ɓI�A�ϋɓI�̓�̏ꍇ�ɋ��ʂ̓_�͖ړI�I�K�R�̔ے�Ƃ������Ƃł���B�Ȃ������̏ꍇ�́A�����I�ɖړI�I���R���ڌ�����Ă��邾���ł��邪�A�X�Ɉ�̐��E�ςƂ��đS�̓I�Ɉ�̖ړI����ے肷�闧�������B�M���V�A�̌��q�_�����߂Ƃ��ăh���o�N�́w���R�̌n�x��E���g���[�́w�l�ԑ��@�B�x�͂��̍D��ł���B���Ȃ킿�@�B�ϓI����_�̔��ʂƂ��ĉF���̑S�̂ɖړI�I���R�����咣����̂ł���B��������ΖړI�I���R�̊ϔO�����ʓI�K�R�Ƃَ̈팋���ɂ�Đ������̂ł���B
�������Ȃ���A�_���w�I�n���ɂ��ċ��R������ʊT�O�ɑ��Ă̂ݑ�����Ɠ��l�ɁA�ړI�I���R�͎v�҂��ꂽ�܂��͎v�҂��꓾��ړI�ɑ��Ă̂ݑ�������̂ł���B���悻�_���I���R�ƖړI�I���R�Ƃ͕s���̓��I�J�W�ɗ��Ă���B��ʊT�O�ƖړI�Ƃ����v���ĖړI�̎�����v������Ƃ���ɘ_���I���R��������A�ړI�I���R��������̂ł���B�v���g���̃C�f�A���P�̃C�f�A�Ƃ��āA���b�c�F�̉�����悤�Ɂu�Ó��v���邪�̂ɁA���R��������̂ł���B�_���I���R�́A�T�O�Ƃ��Ă̕��Ղ��ړI�Ƃ��Ă̑Ó���v������Ƃ��A����̌��̂����ɖړI�ȊO�̂��̂��Ŏ悹����ꍇ�ɐ�������̂ł���B�Ⴆ�A�l�Ԃɂ��ė����Ƒ̌`�Ƃ̎�������v�̂��̂ł���Ƃ���Ȃ�A�X�̐l�Ԃɂ����Č��o�����畆�̐F�͂��̖ړI�ɂƂĊS�̌��O�ɂ��邩����R�I�ƍl������̂ł���B�ړI�I���R�́A��ʂɉ������̖ړI���T�O�I���Ր��ɉ��Ďv�҂����āA���̖ړI���ے肳�ꂽ�ꍇ�Ɍ�����̂ł���B���ɖړI�̗v���ɉ����Ȃ����ɓI�K��A�܂��͗v���ƊW�Ȃ��ϋɓI�K�肪�������ꂽ�ꍇ�ɖړI�I���R�͔c�������̂ł���B�R��ɖړI�I�n���ɂ����邩�悤�ȋ��R�I�K������`�̈���萌W�̌��n���猩��A�������̌����̌��ʂƂ��Đ��������̂ň��ʓI�K�R����b���Ă���B��ᗂł��邱�Ƃ͑�]�̑g�D�A���炭�זE�̈�`���̂����ɉ������̌��������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ԃ����d�ɂȂ邱�Ƃ́A�����ۗނ܂��͒��ނ̎h����p�ƁA����ɑ���Ԃ̔�����p�ƂɈ��̌��������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����т�H���Đ^������Ƃ́A���̂���т��^��𑠂��Ă������ƂƁA��p�ɂ�Ă���т̓�����J���ꂽ���ƂƂ������Ƃ��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂��A�����������M���ėӂ�����ꂽ���Ƃ́A�����I�R�Ă̏I�ǎY���Ƃ��ėӎ_�����A�̂����ɊܗL�����Ă��邱�Ƃ������ł����̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B���悤�ɂ��ĖړI�I���R�͘_���I���R�Ƌ��Ɉ��ʓI�K�R�A���Ȃ��Ƃ����`�̈��ʐ��̖��ɊҌ�������̂ł���B
�c��͍̂��ʓI���R�̖��ł���B���ʓI�K�R�݂̔����ʓI���R�ł���B���q�_���̗p�����G�s�N���X�͌��q�̖{���̉^�����ォ�牺�Ɍ��������^���ƍl�������A�����̌����ɋK�肳��邱�ƂȂ�����(?�˃��ǃ�?��?)����(sponte)���������ɂ߂ď��������錴�q�̂��邱�Ƃ�������B���N���`�E�X�͂��̐������̂��������Ȃ�w�����u�X���v(chinamen)�ƌĂB�u���_���g�͊e�X�̍s���ɂ����ē��I�K�R���ɂ�Ċ����������ĔE�J�����邪�@���ɍS������Ă�����̂ł͂Ȃ��B����͌��̗̂L����A��ԓI�ɂ����ԓI�ɂ����肳��Ă��Ȃ�������(exguum)�X��(clinamen)�̂����ł���v(De�@rerum�@natura�@�U.289-293)�B���������G�s�N���X�h�̔�_�̓X�g�A�h�̌���_�ɑ��ď������ꂽ���̂ł��邪�A�f���N���g�X�̌��q�_�Ƃ����萫�̖��ɂ����Đ����̐����������Ă���Bchinamen�͎��Ɉ��ʓI���R�̓T�^�ł���B���̈Ӗ��̈��ʓI���R�͎������ɂق��Ȃ炸�A�܂��u��l�Ȃ�(?-��?�Ѓ̓у�?)�v(Diog.X.133)�̌�ɂ�Ď�����邪�@���A�K�R�ɑ��鎩�R���Ӗ����邱�Ƃɂ�ďd��ȈӋ`�����ė���B�u�[�g���[�����ʓI���R�̑��݂�F�߂��B�u�[�g���[��.���A���ʖ@�͒��ۓI�̂��̂Ƃ��ĉȊw�̎��ۏ�̊i�����蓾�邪�A��̓I�Ȍ����̐��E�ɂ��Ă͌����ɂ͓K�p����Ȃ��B���ׂĂ̌v�ʂ͒\�ɋߎ��I�ł���B��̐����ɓ��B���邱�Ƃ͌����I�ɕs�\�ł���B�����I���Ƃ͌��ǂ͏����ۂ̉��I�v�f�̉��l���A�o���邾���ڋ߂������E�ƌ��E�Ƃ̊ԂɈ��k���邱�ƂɋA����B��X��������͈̂���Ε�����ꂽ�e��ɉ߂��Ȃ��B�����g�ł͂Ȃ��B�������ĉ�X�̑e�G�ȕ]�����@�̌��͔͈͂��z�������x�̔����̔萫�������ۂɓ��݂�����B���ꂪ���Ȃ킿���ʓI�K�R�݂̔Ƃ��Ă�contingence�ł���B�������ău�[�g���[�̓��[�k�E�h�D�E�r�����A�����F�b�\���Ȃǂɂ�ď������ꂽ�u���R�̓N�w�v���u���R�̓N�w�v�̌`�ō��������̂ł���B�������A�G�s�N���X�̔�_�ɂ��Ă͈��ʓI���R�ƖړI�I���R�Ƃ����팋�����Ȃ��Ă���ɔ����āA�u�[�g���[�ɂ��Ă͈��ʓI���R���ړI�I�K�R�ƈَ팋�����Ȃ��Ă���B�G�s�N���X�͈���ɐ_�X�̑��݂����F�������A�����ɂ��̐_�X�͏��F����(�ʃÃу���?�Ѓʃǃ�,intermundia)�̋ɏZ���Ď����̎����Ɉ����E�Ɛl�ԂƂɉ����̊������Ȃ����̂ƍl�����B�R��Ƀu�[�g���[�́w���R�@�̋��R���x�͕L��A�F���̖ړI�I�K�R���Ɉˑ����Ă���B�u�[�g���[�́u�`���̌`�ɂ�����K�R���v(De�@la�@contingence�@des�@lois�@de�@la�@nature,9(�@e)�@d.,p.155)���Ȃ킿�u�K�R�I�ƍl������ړI�v(ibid.)�ɂ��Č��A�_�ɂ��Ắu���R�������ł���v(p.156)�ƂƂ��Ɂu���H�I�K�R���v(p.157)������Ƃ����B�܂��_�́u�s�f�̐ۗ��v(ibid.)�u����̐ۗ��v(ibid.)������u�F���̂������̌`�����ʓI�@���̒i�K�g�D���������R���́A���̐_�̎��R�̋����ɂ�Đ��������v(ibid.)�Ɖ]�Ă���B�������Ĕނ��W��Ƃ��Ċ����Ɍf�����u�����ɂ��܂��_�X������v�Ƃ����A���X�g�e���X�́w�����̕����x����̈��p��́A���ʓI���R���̔w��ɐ��ޖړI�I�K�R�����w�E������̂Ƃ��Ĕނ̗����\������Ƌ��ɁA�ނ̎v�z���Q�[�����N�X��}���u�����V���̋���_�ƕs�v�c�Ȑڋ߂�L���邱�Ƃ��Î����Ă���B�Ȃ��A���̎�̈��ʓI���R�͌����������Ƃ����O��I�ȈӖ��ł��邩��A��ΓI���ʓI���R�ƌĂԂ��Ƃ��o����B�܂���ΓI���ʓI���R�͈�U�A�����I�Ɏ咣������Ƃ��ɂ́A���ǁA�S�̓I�Ɉ�̈��ʐ��̔ے�֓����X�������Ă���B
�������Ȃ���A��ΓI���ʓI���R�̊ϔO�͋ɂ߂ē���Ȍ��������Ƃ�Ȃ��B�����̐l�X�̓|�A���J���Ƌ��Ɂu��X�͐�ΓI����_�҂ɂȂ��Ă��܂��v(Science�@et�@Mtthode,p.65)�Ɖ]���ł��낤�B�~�������̒��_�̏�ɗ��Ă�Ƃ��A����̕����ɓ|��邩�́A�Ȃ�قNj��R�ɂ��悤�Ɍ�����B���������̓|�����������肷��ɂ͕K���������̌������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Ȃ킿�A�ɂ߂ď����ł��~���̑Ώ̂Ɍ�����Ƃ��낪����Ή���̑��ɂ��͂��ɌX���B�������Ĕ@���ɋ͂��ł��Ă��A���̌X�����~���̓|�����������肷��B�܂��Ώ̂����S�ł������Ƃ��Ă��A�ɂ߂Ĕ����ȐU���ɂ����b�p���X������B�������Ă��̋͂��ȌX�����~���̓|�����������肷��̂ł���B�v����Ɂu��X�ɋC�����Ȃ��悤�Ȕ����̌������A��X�̔F�߂Ȃ��ł����Ȃ��悤�ȏd��Ȍ��ʂ����肷�邱�Ƃ�����ƁA���̂Ƃ���X�͂��̌��ʂ͋��R�ɋN���Ɖ]���v(ibid.,p.68)�B
���ʐ��Ɋւ����_�ƌ���_�Ƃ̘_�_�́A����̂����ɔ����̔萫��F�߂邩�A��̂����ɔ����̌��萫��F�߂邩�ɑ�����B���́u�����v�̈�_�ɋA������B���N���`�E�X��exiguum�̈�_�ɏW������B�������ău�[�g���[�̉��肷������̔萫���l�ԂɌv�ʂ̏o�҂Ȃ����̂ł������A�|�A���J���̌����@�����̖��́u�����ɉ�������v(La�@Valeur�@de�@la�@Science,p.248)���ł��낤�B�e���p����ΓI���ʓI���R�̊ϔO�͖��I�̂��̂ł���B
�R��Ή��������̈Ӗ��ŁA���ʐ��Ɋւ��ċ��R�����݂��Ȃ��ł��낤���B��ΓI���ʓI���R�ɑ��đ��ΓI���ʓI���R�̊ϔO������B�Ⴆ�ΐ������犢�������Č������s���ʍs�l�������߂��Ƃ��ɁA��X�͂�������R�ƍl����B�܂��ΎR�����o�����ۂɁA���I�ł����ꍇ�A��������R�Ƃ����B���͉����̋��p�����̗͂��������̌����������āA���̌��ʂƂ��Ĉ��̏ꏊ�֗��������B�ʍs�l�͋��������̏����������̎G�����������̌����ɑ�����āA���̌��ʂƂ��Č����̋߂���ʂ��B���ʌn����قɂ����̎��ۂ����̊W�ɒu���ꂽ���Ƃ����R�Ƃ����̂ł���B���l�ɁA�n���̔M�����������ɉ����钣�͂�����x�ɒB�������Ƃ������ŁA���̌��ʂƂ��ĉΎR�����o�����B���ɂ�������ꂽ�Ƃ��������ɂ��A���̌��ʂƂ��đ��z�͈Í��̌��ۂ�悵���B��̈��ʌn��Ƒ��̈��ʌn��Ƃ́A�S�R�Ɨ��ڗ����Ă���B���n��Ԃɂ͈��ʊW�͑����Ȃ��B���n��͕K�R���ɂ�Č���Ă��Ȃ��B���Ȃ킿���̏ꍇ�̋��R���́A��̈��ʌn��Ƒ��̈��ʌn��Ƃ̕K�R�I�Ȃ炴�鑊�ΓI�W�ɑ�����B�����ɑ��ΓI���ʓI���R�̊ϔO����������B�������Ă��̑��ΓI���ʓI���R�������ɋ��R���̊j�S�I�Ӗ����Ȃ��Ă���B�X�`���A�[�g�E�~�����u�������̌��ۂ����R�ɂ�ĎY�ݏo���ꂽ�Ƃ����̂͐������Ȃ��B�������A������͂���ȏ�̌��ۂ����R�ɂ�Č������ꂽ(conjoined)�Ƃ������Ƃ͏o����B���Ȃ킿�A�����̌��ۂ͒P�ɋ��R�ɂ�ē����ɂ܂��͌p�N�I�ɑ��݂���݂̂ŁA�������ʐ��ɂ���ĊW�������Ă��Ȃ��Ƃ����Ӗ��ł���v(System�@of�@Logic,�V,ch.�]�Z,��2)�Ɖ]�Ă���B�܂��N�[���m�[�����R�����`���āu�����I�ɂ݂͌ɓƗ����Ă��鎖���Ǝ����Ƃ̑���(rencontre)�v(Trait�@de�@l�fenchainement,nouvelle�@d.,1922,p.67)���Ȃ킿�u�݂ɓƗ����Ă���n��ɑ����鑼�̎����Ƃ̌���(combinaison)�܂��͑���(rencontre)�ɂ�����ꂽ��̎����v(Essai�@sur�@les�@fondements�@de�@nos�@connaissances,nouvelle�@d.,1912,p.38)�Ɖ]�Ă���B���R�́u��v�͑o�A�A���A���̈ӂł���B�l�ɏ�����Ă��邪�A�Vㅂɏ������u���v�Ɠ��`�ŋ������Ƃ��Ӗ����Ă���B�����Ƃ͈�ƈ�Ƃ����ē�ƂȂ邱�Ƃ���b�Ƃ������ł���B���R�̋�͋�H�̋�A�z��̋�ł���B���R���̊j�S�I�Ӗ��́u�b�͍b�ł���v�Ƃ�������̂̕K�R����ے肷��b�Ɖ��Ƃ��琁A���Ȃ킿�ق��̐ڐG�ł���B�Ѓ҃�-���Ã��Ń�??��con-tingens��ac-cidens��Zu-fall���݂Ȏ����ړ���ɂ�ē̐ڐG�𖾗Ăɒq���Ă���B��?�ԃł̓у҃���?�˃Ãǃ˂��Ȃ킿�u�����v���痈�Ă���BChance��caden-tia����Ahasard��casus����A���Ȃ킿���ɖ{����cadere���痈�Ă���B��������cadere(������)�́u�����ʍs�l�̓���֗�����v�Ƃ����悤��in�ccadere�i�E�E�E�֗�����j�̍\�����������̂ŁAZu-fall�Ɠ��l�ɑ��ΐ��ɂ�ď��߂ĈӖ����Ȃ����̂ł���B�u���܂��܁v�́u���܁v�́u��ԁv�̋`�ł���Ƃ����B�u���܂Ɂv�̌ꂪ�����Ă���悤�Ɂu��ԂɁE�E�E�v���Ȃ킿�u��Ԃɓ���v�u��Ԃɗ�����v�̈ӂ������Ė�葊�ΐ�����Ă���B����́u���܂��܁v�̌�ɋ�A���Ȃǂ̎������Ă��Ă���̂͋ɂ߂ēK�Ȃ��Ƃł���B���̑��u�s�������v�u��荇���v�u�܂��ꂠ����v�Ȃǂ������R�Ɋւ����͑��ΓI���ʓI���R���Î����Ă���B
�v����ɋ��R���Ƃ́A������͓�ȏ�̈��ʌn��̌����_�ɑ�������̂ŁA��ԓI�́u���|�v�܂��͎��ԓI�́u���v�ɂ�Ĉ��ʌn��̌����_���`��������܂��͌X�̎��ۂɊւ�����̂ł���B���R�Ƃ͈��haecceitas�Ƒ���haeceitas�Ƃ��A�u���̏ꏊ�v�ɍs������A�u���̏u�ԁv�ɖڂ���������̂ł���B�ց[�Q���̂�����u���S(gleichgu(�E�E)ltig)�v(Encykl.,��250)�������̊S�Ɏ~�g�����̂ł���B���R���Ƃ͖��S�Ɩ��S�Ƃ̌����_�̊S�I��[���ɂق��Ȃ�Ȃ��B���Ƃ�蕸�_�ōb�Ɖ��Ƃ���������ꍇ�A�b�͍b�f���A�b�f�͍b�h�������Ƃ��A���͉��f���A���f�͉��h�������Ƃ��A�b�h�Ɖ��h�Ƃ�O�����ʂ̌����ɂ��Ă��邩���m��ʁB�]���čb�Ɖ��Ƃ��琂͌����Ȃ�Ӗ��ŋ��R�Ƃ͉]���Ȃ������m��ʁB������O���g�͂܂�M��N�Ƃ̌����_���Ӗ����Ă���B�R��ɂ���M���܂�MM�fM�h�̈��ʌn��ƁAN���܂�NN�fN�h�̈��ʌn��Ƃ́A�X�ɋ��ʂ̌����Ƃ���P�����Ă��邩���m��ʁB������P�͂܂���̈��ʌn��Ƒ��̈��ʌn��Ƃ̌����_���Ӗ����Ă���B�R��ɂ��̓�n��ɂ͂܂����ʂ̌��������邩���m��ʁB�������ĉ�X�̓Ԃɑk��B�Ȃ��A�����_���琂�����ʌn��͎��ۏ�͌����ē�����Ɍ����Ă͂��Ȃ��B���ɖ����ɂ���B�A���X�g�e���X���̂̋��R�I�����́u���ی��i?�Ãǃσ�?�j�v(Met.,E.2,1026(�@��)�GPhys.,�U.5)�ł���Ƃ��A���R�I�����́u������(??�σǃЃу�?)�v�iMet.,��.30,1024(�@��)�GPhys.,�U.5�j�ł���Ƃ��A�܂����R�Ɋւ���w��͖���(Met.,E.2)�Ɖ]�Ă���̂́A���̌����_���t��������ʌn��̖����ł��邱�ƂƁA�����_���̂��̖̂����ł��邱�ƂƂɊ�Ă���B���C�v�j�b�c���u���R�I�����v�Ɋւ��āu�ی��Ȃ��ז�(dtail�@sans�@bornes)�v�Ƃ��u����(infinit)�v�Ƃ��]�Ă���(Monadologie,36)�̂����l�̗��R����ł���B�܂��|�A���J�����u�����̕��G�v(Science�@et�@Mthode,pp.73-76)�����R���̎�v�Ȃ�Ӗ��ł���ƍl����̂́A�t��������ʌn��ɂ�Č����_���ߖ������邱�Ƃ�M���邩��ł���B�X�s�m�U���u���͉�X�̔F���̕s���S�Ȃ邪���߂ɂ̂��R�ƌĂ��̂ŁA���̔@���Ȃ錴������ł��Ȃ��v(Ethica,�T.33.Schol.�T)�Ɖ]�Ă���̂��A�����_�Ɋւ��銮�S�Ȃ�m����\�z���Ă���̂ł���B�������Ȃ���A��X�͌����_�̊��S�Ȃ�ߖ��Ə\�S�Ȃ�F���Ƃ͒P�ɗ��O�ɉ߂��Ȃ����Ƃ��v��Ȃ���Ȃ�ʁB��X�͌o���̗̈�ɂ��ĕK�R���̓���H��A���O�Ƃ��ẴԂ��u�����v�ɒǂ��̂ق��͂Ȃ��B�ہA�P�ɂ���Ɏ~�܂�Ȃ��B��X���u�����v�̔ޕ��ɗ��O�𑨂֓����Ƃ�����A���̗��O�̓V�F�����O�̂�����u�����R�v(Urzufall)�ł��邱�Ƃ�\�ߒm��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����R�ɂ��Ă͒P�Ɂu���ꂪ�݂�Ƃ������Ɓv(dass�@es�@Ist)���]���Ȃ��B�����R�́u���`�̎������ہv�ł���A�u���j�̋N�n�v�ł���B�u�������v(Urerignis)�ł���A�u�s�O�z�I�h���v(unvordenkliches�@Verha(�E�E)ngnis)�ł���(Schelling,Werke,�U,1,S.464;�U,2,S.153)�B���̓ߐ��u�͜\���ɔ��₵�āu�������؉��̕s���v�Ɖ]���B�\���͂���ɑ��āu�s���Җ{�͊e�فv�Ɖ]�Ĕ�u�ɓ����܂�����ɓ������B�������Ȃ���A���̋��R�������ʗ��ɂ�ĕc�̋��R���Ɉڂ��ꂽ�Ɏ~�܂Ă���B�܂��w�����_�x�Ɂu�ݕ��n�ƈ����v�i�ƈ��i)�Ƃ����Ƃ����A���������R���Ɉ��ʓI������^�������̔@���ł��邪�A���̎��͋��R�������̂܂܁u�����R�v�ɂ܂Ŗ����ɉ��������ɉ߂��Ȃ��B
�l�@�`����I���R
�u�����R�v�����̉��������̂��`����I�̐�Ύ҂ł���B��Ύ҂͐�Ύ҂Ȃ邪�̂ɐ�ΓI�Ɉ�ƍl������B�܂���ΓI�Ɉ�Ȃ邪�̂ɐ�ΓI�ɕK�R�Ǝv�҂����B�m���@���X���u�K�R-���R��(das�@Notwendig=Zufa(�E�E)llige)�v(Novalis,Fragmente)�Ɖ]�Ă���̂͐�ΓI�K�R�Ƃ��Ă̌����R���Ӗ����Ă���ɑ���Ȃ��B
��ΓI�K�R���Ȃ킿�`����I�K�R�̊T�O�͊��ɃA���X�g�e���X���w�`����w�x�̂����ɏq�ׂ��B�u�s���̌����ҁv�͕s���̌̂����āu�قĐU�������Ƃ͌����ďo���Ȃ�(��?�ȁ@?�˃�?�ԃÃу��ǁ@?�ɃɃ�?�@?�ԃÃǃˁ@��?����??)�v�iMet.,��.7,1072(�@��)�j�B�]���āu�K�R�ɑ��݂�����́i?�́@?��?���ȃ�?�@?�ˁj�v(ibid.)�ł���B���́u�s���̌����ҁv�ȊO�̂��̂͂��ׂđ��ɂ�ē����������̂ł��邩��u�قĐU�������Ƃ��o����(�H�H�H�@�H�H�H�@�E�E�E)�v(ibid.)�B���Ȃ킿�`����I�K�R�̔ے�Ƃ��Č`����I���R�ł���B���̌`����I�K�R�ƌ`����I���R�Ƃ̊T�O�͒����I�Ɏ��ăA���X�g�e���X�����҂Ȃ郂�[�[�X�E�}�C���j�f�X�ɂ�č̗p����A�_�̑��݂́u�F���_�I�ؖ��v�̌_�@�Ƃ��Đ������ꂽ�B�g�[�}�X�E�A�N�B�k�X���}�C���j�f�X�ɕ�āA���E�̋��R�����u����ɂ�ĕK�R�I�Ȃ鈽���(aliquid�@quod�@est�@per�@se�@necessarium)�v(S.theol.,I,q.2)�ւ̐��_���Ȃ����B�`����I�K�R�ƌ`����I���R�Ƃ̊W�͂��悤�ɂ��āu�������v(aseitas)�Ɓu�������v(abaliettas)�Ƃ̑Η��̌`���Ƃ��B�X�r�m�U�̂�����u���ߌ���(caussui)�v(Ethica,I,def.1)���`����I��ΓI�K�R�ɂق��Ȃ�Ȃ��B�u�_�͕K�R�ɑ��݂���(Deus�@necessario�@existit)�v(ibid.,I,11)�B����ɔ����āu���̑��݂�K�R�ɑ[�肵�܂��͕K�R�ɔr�����鉽���������o���Ȃ�����A�]�͌������R(contingents)�ƌĂԁv(ibid.,�W,def.3)�B���C�v�j�b�c���w��~�_�x��w�P�q�_�x�̂����Łu�K�R�I���ݎ�(Etre�@
ncessaire)�Ƃ��Ă̐_�Ɓu���R�I���ݎ�(Etres�@contingens)�v�̑��̂Ƃ��Ă̐��E�ƂɏA�Č��(Opera�@philos.,d.Erdmann,pp.506,708)�B�܂��J���g���u���݂ɂ����Đ��ꂽ���͈̂�ʂɋ��R�Ə̂��A����Ȃ����͕̂K�R�Ə̂��v(�w���������ᔻ�xB.447)�Ƃ��u��X�͋��R�����A���鎖�ۂ����錴���̌��ʂƂ��Ă̂ݑ��݂��\���Ƃ������Ƃ���F������B����̂Ɉ�����̂����R�I�Ƒz�肹����A���ꂪ���錴�������A�Ƃ����͈̂�̕��͓I����ł���v(ibid.,B.291)�ȂǂƉ]�Ă���ꍇ�ɂ����̎�̕K�R�Ƌ��R�ƂɊւ��Ă���B
��X�͌o���I�n���ɂ�����ƌ`����I�n���ɂ�����Ƃɂ�ĕK�R����ы��R�̈Ӗ��������ɂȂĂ��邱�ƂɋC�����B�o���I�n���́u�����v�̍s�����ŁA���ʓI�K�R�̌n����ɑk�āA�����R�ɓ��B�����B�`����I�n���́u����v�̍s�����ŁA��ΓI�K�R�̔ے�Ƃ��āA���ʐ��̂����ɗ��ɂ���ꂽ���R�̊T�O���B��������A���ʐ��ɂ�ċK�肹���邱�Ƃ́A�o���I���n���͕K�R�Ɖ]���A�`����I���n���͋��R�Ɖ]����B�܂��A���ʌn��̋N�n�����O�Ƃ��Ĕc��������Ƃ��A�o���I���n���͌����R�Ɖ]���A�`����I���n���͐�ΓI�K�R�Ɖ]����B���Ȃ킿�K�R���ɂ́u��ΓI�K�R�v�Ɓu�����I�K�R�v�Ƃ̋�ʂ�����B�N���X�e�B�A���E�E�H���t�ɂ��u�K�R�I���݂Ƃ́A���̑��݂���ΓI�ɕK�R(absolute�@necessaria)�̂��̂ł���B���R�I���݂Ƃ́A���Ȃ̑��݂̗��R�����Ȃ̊O�ɗL������̂ł���v�B�]���āu���R�I���݂̑��݂͒P�ɉ��z�I�ɕK�R(hypothetice�@necessaria)�ł���v(Ontologia,��309f.,��316)�B�������āA���̒P�ɉ����I�ɕK�R�ł���Ƃ���̌`����I���R�́A���ɃA���X�g�e���X���������悤�ɁA���ȈȊO�̈��錴���ɂ�Ă̂ݑ��݂���Ƃ������R�Ɋ�āA���݂��Ȃ����Ƃ��\�ł���B����̂Ƀg�[�}�X�E�A�N�B�k�X�͋��R���u���݂��Ȃ����Ƃ̉\�̂���(possibiliaa�@non�@esse)�v(S.theol.,�T,q.2)�ƌĂ�ł���B�`����I���R�͕L��A�o���I�K�R�ɂق��Ȃ�Ȃ��̂ł��邪�A�o���I�K�R��嫂���Ύ҂̌`����I�K�R�ɑ��Ėڌ���������A���R�̐�����тт�̂ł���B
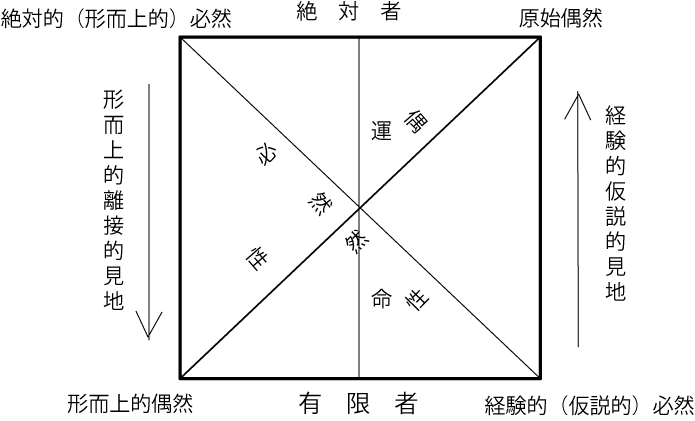 �i�Q�l�@���R���̖����j
�i�Q�l�@���R���̖����j���悻���R���̖��͉\���̖��ɐ[���G��Ă���B��X�͑��݂܂��͌����ɑ��Ĕ݂܂��͔����l����B���݂܂��͌����Ƃ͗L����́A�݂܂��͔��Ƃ͖������̂ł���B�������āA�u�L����́v�́u�������Ƃ̏o���Ȃ����́v�Ɓu�������Ƃ̏o������́v�Ƃɕ����čl������B���Ȃ킿�u���݁v�ɂ́u�K�R�v�Ɓu���R�v�Ƃ�����B�܂��u�������́v�́u�L�邱�Ƃ̏o������́v�Ɓu�L�邱�Ƃ̏o���Ȃ����́v�Ƃɕ����čl������B���Ȃ킿�u�݁v�ɂ́u�\�v�Ɓu�s�\�v�Ƃ�����B���āA���R���͑��݂̕K�R����ے肷����̂ł��邩��A�K�R�Ƌ��R�Ƃ͖����Γ��ɗ��Ă���B�s�\���͑��݂̉\����ے肷����̂ł��邩��A�\�ƕs�\�Ƃ������Γ��ɗ��Ă���B�܂��s�\���͔݂̕K�R�����咣������̂ł��邩��A�K�R�̈��ƍl������B���̕K�R�ƕs�\�Ƃɋ��ʂ̓����́u�_�ؐ��v(��)�Ɖ]����B���R���͔݂̉\�����m�肷����̂ł��邩��A�\���̈��ƍl������B���̉\�Ƌ��R�Ƃɋ��ʂ̓����́u��萫�v�Ɖ]����B�������đ��݁A�݂̒n���́A�_�ؐ�����і�萫�ɑ��āu�������v�Ɖ]����B�Ȃ��K�R�������S�Ȃ鑶�݂ƊŘ��ɑ��āA���R���Ɖ\���Ƃ͕s���S�Ȃ鑶�݂ƊŘ�邱�Ƃ�����B�Ȃ��Ȃ�A���R���͔݂̉\���Ӗ��������A���݂Ɉʒu���߂Ȃ�����݂ɍ������Ă�����̂ł���B�\���͑��݂̉\���Ӗ��������A�݂Ɉʒu���߂Ȃ�������݂ɓ���Ă�����̂ł���B����̂ɋ��R���Ɖ\���Ƃ͎ƁX�ɂ߂ċߐڂ������̂Ƃ��Ėڌ������B�g�[�}�X�E�A�N�B�k�X�͐_�́u�F���_�I�ؖ��v���u���R�����v(e�@contingentia)�Ƃ͉]�킸�Ɂu�\���v(ex�@possibili)�B�ƌĂ�(S.theol.,�T,q.2)�B�A�x�����h�́u�\�Ƌ��R�Ƃ͑S������̂��̂��Ӗ�����(possibile�@et�@contingens�@idem�@prorsus�@sonant)�v(Ouvrages�@indits,publ.par�@Cousin,Dialect.,p.265)�Ɖ]���B�X�s�m�U���u���R�������͉\(vel�@contingens�@vel�@possibilis)�v(Ethica,�T,33,Schol.�T)�ɏA�ďq�ׁA�ց[�Q���́u���R�Ƃ͌����������ɒP�ɉ\�Ƃ��ċK�肳��Ă�����̂ł���v(wissenschaft�@der�@Logik,hrsg,v,Lasson,�U,S.173)�Ɖ]�Ă���B�����̊W���E�̔@���}���ɕ\�킷���Ƃ��o����B
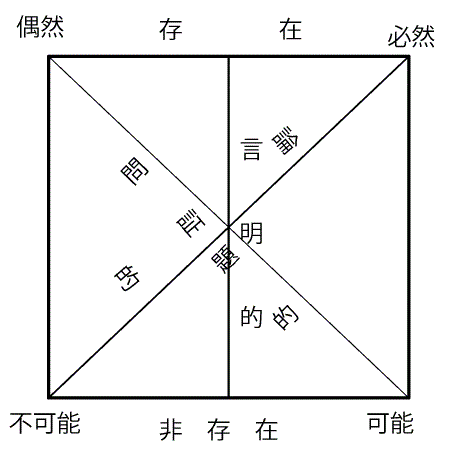
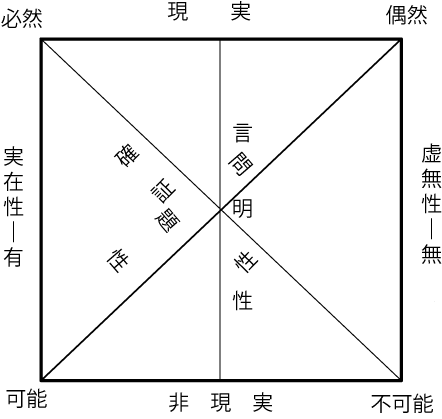 �i�Q�l�@���R���̖����j
�i�Q�l�@���R���̖����j���悤�ɋ��R�����\���ƊW�����čl���邱�Ƃ́A�^����ꂽ�����܂��͑��݂��`����I�w��ɗ��Č��邱�Ƃ��Ӗ����Ă���B��������A�����܂��͑��݂𗣐ړI���ꂩ�猩��̂ł���B�b�͉��Ȃ邩�A���Ȃ邩�A���Ȃ邩�ł���Ƃ����悤�ɁA���ړI�ȉ\���������̔w�i�Ƃ���̂ł���B�������āA���悤�ȗ��ꂩ�猩�����R�̈Ӗ��́A��X���\�̏ꍇ���A���Ȃ킿���ڎ����A�����m�Ă���Ƃ��ɖ����Ɍ�����̂ł���B��X���\�̏ꍇ�������m�Ă���Ƃ��Ƃ́A�Ⴆ��鍎q�A�����A���n�Ȃlj\���������ċ��R�̗V�Y������ꍇ�ł���B����̂ɁA�i�h���h�̓N�w���A���E���V�Y�̂��߂ɑ����Ƃ��邱�Ƃɂ��[���Ӗ������o�����Ƃ��o����B���悻鍎q�̌��킷�ʂ����R�Ƃ����̂́A�Z�̉\����w�i�Ƃ��čl���邩��ł���B���̌܂ł����蓾���ƍl���邩��ł���B���̎��A鍎q�̌��킷�ʂ́A鍎q�A�������A���Ȃǂ̕����I�����ɂ�ĕK�R�I�ɋK�肳��Ă���B�������Ȃ���A���̕K�R���̈��ʓI�n�������蓾���ƍl����_�ɁA���܌����Ƃ��ė^����ꂽ���ʌn�K��������ΐ������Ă��Ȃ��ƍl����_�ɁA���Ȃ킿�\���ƌ����Ƃ̊Ԃ��ꗂ�������ƍl����_�ɁA���R����������̂ł���B�|�A���J���̓��[���b�g�̗V�Y�Ɋւ��Ď��̂₤�ɉ]�Ă���B�u�~�Ղ�S�ӂ̐�`�ɕ����āA���݂ɐԂƍ��Ƃɐ��߂���ŁA�S�_�̎���ɐj�����]������̂ƍl���悤�B�j���Ԃ���`�̏�Ɏ~��Ώ��A�����炴��Ε��ł���B�����ɖ����͉�X���j�ɗ^����ŏ��̈ꉟ���ɂ���B�Ⴆ�A�j���\�܂��͓�\���]������̂Ƃ��āA�ŏ��ɋ������������キ���������ɏ]���āA�~����������Ȃ舽�͒x���Ȃ�B�����ŏ��̉����͂������̈�������͓�番�̈��������ŁA�j�͈����͍�����`�̏�Ɏ~��A�����͎��̐Ԃ���`�̏�Ɏ~��B����́A�؊o�ɂ�Ă͊��m�o�����A�X�ɔ����Ȃ��B�����Ă��Ă����蓾�Ȃ��͂��ȍ���̂��߂ł���B�]���āA���ܓ��������j���@���ɓ������͗\�����邱�Ƃ��o���Ȃ��B������������������Ă��ׂĂ����R�ɔC���đ҂̂ł���v(Science�@et�@Mthods,pp.70-71)�B���悻���R�̋��R���鏊�Ȃ́A�j���Ԃ̏�Ɏ~�܂��Ƃ��ɁA���̏�ɂ��~�܂蓾���ƍl���A���̏�Ɏ~�܂��Ƃ��ɁA�Ԃ̏�ɂ��~�܂蓾���ƍl����]�ɑ�����B�������A�����l���邱�Ƃ́A�|�A���J���̌����@���A�ŏ��̉����͂̋͂��ȍ��Ⴊ�����Ȃ��B�����Ă����蓾���A�]���Đj���@���ɓ�������\�������Ȃ��Ƃ������ƂɈˑ�����̂ł͂Ȃ��B�V�Y�҂̋������������R���͂ނ���ŏ��̉����͂��̂��̂Ɋւ��āA�����Ƃ��ė^����ꂽ���̋������K��������ΓI�K�R�������Ă��Ȃ��Ƃ����_�ɑ�����̂ł���B���Ȃ킿���̋����ł���ƍl���Ă������̖����������Ȃ��Ƃ����_�ɑ�����̂ł���B���̈Ӗ��ɂ����āA���̃N���[�o�[���O�t�łȂ��Ďl�t�ł��邱�Ƃ����R�ł���A��ԎR�����ʂ̎R�ԂłȂ��ĉΎR�ł��邱�Ƃ����R�ł���B�L�b�G�g�����s�ł����ł��Ȃ��܂����̑��̉����ł��Ȃ������̒����Ő��ꂽ���Ƃ����R�ł���B��X���A�����J�l�ł��Ȃ���x�l�ł��Ȃ����{�l�ł��邱�Ƃ����R�ł��邵�A�܂����ł��Ȃ����ł��Ȃ��l�Ԃł��邱�Ƃ����R�ł���B�w�G���܌o�x�͐l�Ԃɐ������R�����I�݂�栂��Ă���B��C�ɐ��ގ������ʂ̖ӂ̋T���S�N�Ɉ�x���̓����o���B�܂��B��̍E���镂���C���ɕY���ĕ��̂܂܂ɓ��������B�l�Ԃɐ���邱�Ƃ́A���̖ӂ̋T�������グ���Ƃ��A���܂��܂��̖̍E�ɋ����悤�Ȃ��̂ł���Ɖ]�Ă���B
���R���ɂ͋��ق̏�������B�u��v�u��߁v�Ȃǂ̌�̑��݂͂��̏�̕��Ր������Ă���B�������ĕK�R���ɏ[���̊�������̂ƍD���ΏƂ��Ȃ��Ă���B�܂��A�\���ɂ͊�]�������͐S�z�������A�s�\���ɂ͎��]�������͈��S�������B���鎖�ۂ��\�ł���ꍇ�ɂ́A���̎��ۂ̐����@���ɂ�āA��]�܂��͐S�z�Ƃ����ْ��I�������B�s�\�̏ꍇ�ɂ́A��]�͎��]�ɁA�S�z�͈��S�ɕς���B���Ȃ킿�o�ɓI������Y�ށB�K�R���[���Ƃ������ÓI������̂́A��肪���͓I���������ĉ�������Ă��邩��ł���B����ɔ����ċ��R�����قƂ��������I�����������͖̂�肪�������̂܂܂Ɋ�O�ɓ��o����邩��ł���B�v����ɁA�s�\����ѕK�R�͂��̌���I�Ș_�ؐ��̂��߂ɁA�o�ɂ���ђ��Â̐ÓI�Ȏア���������Ȃ����A�\����ы��R�͖�萫�̂��߂ɁA�ْ�����ы����̓��I�ȋ�����������̂ł���B�������ĉ\�ɔ�����]�A�S�z�ْ̋��I����ƁA���R�ɔ������ق̋����I����Ƃ̎�v�Ȃ鑊��́A�O�҂������Ɋւ��A��҂����݂Ɋւ��Ă��邱�Ƃł���B�\�͔݂����݂𖢗��Ɋ��҂��Ă���̂ł���B���R�͑��݂����݂�����݂���ς���̂ł���B���R�ɔ������ق́A�\�I���ڎ��̈���[�肳�ꂽ���߂ɁA�[��̐�ΓI���R�ɑ��ĉ����`����I��ł���B�v���g�����w����сx�̂����ŁA�b�����Ɂu���R�琂���(?�˃�?�ԃ�)�v�Ƃ��ɂ́u�ޓ��͉������������킭(�ƃ��҃ʃ��Ѓ�?�@?�ȃ�?�уу̓˃у���)�v(Symp.,192b)�Ɖ]�Ă���̂́A�N�w�I���قƂ��Ẵƃ��҃�?�ăÃǃ˂̌����Ȃ���ł���B
�Ȃ��A���̋��ق͔@���Ȃ闣�ڎ��̑[��ɂ��������̂��̂ł��邪�A���ɒ�����������̂́A�[�肪�ړI�I�[��ł��邪�@����������ꍇ�A���Ȃ킿�u�ړI�炵���v�̑�����ꍇ�ł���B����̂ɃA���X�g�e���X�̓�?��?�ʃ��у̓˂���у�?�ԃł́u������̂̂��߂Ɂv(?�˃Ã�?�@�у̓�)�N�鎖�ۂ͈̔͂ɑ����邱�Ƃ��A���������ꂽ���ʂ̂��߂ɋN�����̂łȂ��ꍇ�ł���Ƃ���(Phys.,�U.6.197(�@��))�B���Ȃ킿�A���R�Ƃ͂��ꎩ�g�A�ړI���Ɋւ�����̂ƍl����ꂽ�B���ҏ��H���Ắw���̖��x�̂����Ɂu���̓����Ȃ��̏��֍s�����̂͋��R�Ƃ͎v���Ȃ��C�����܂��v(��O��)�Ƃ������t������B�Ėڟ��́w������x�̂����ɂ��u���ꂪ�܂����R�Ȃ̂��A�̈ӂȂ̂��A���ɂ͉���Ȃ��v(���A�\�l)�Ƃ������t������B����������R�̂����́u�ړI�炵���v���ڌ�����Ă���B�܂����ĐV������ŁA�V�}��g�D���Ă������鐭���Ƃ��Ăт��Ƃ̐��}�A�������Ƃ��̒k�b�Ɂu���������c������Ɉ�̒Ґ肪�o���B�u�l�͐l�A�����A��Ɛe�ꂢ���v�Ƃ����̂ł��邪�A���ɖ��Ȃ��Ƃł���v�Ɖ]�Ă����B�܂��A�ނ��Əo���q�ƌĂ�ł����^��y���u�E�̂悤�Ȗ��ȒҐ�Ŗ��Ȋ����������v�Ɖ]�Ă����B�܂��u�@���v�Ƃ�����Łu�v�̎��S��A���̈�q���߂��Ė��S�l�̏�ɋN���悭�������e�̓�i������燘_���A������������ɓ����@��\�\���T�i�@�@��\�\�ŊJ���ꂽ�v�L�����V���ɍڂ���ꂽ���Ƃ�����B���̊�Ƃ����Ƃ��������Ƃ͋��R�́u�ړI�炵���v�ɑ�����قɂق��Ȃ�Ȃ��B
�Ȃ����w�����R�����D����̂��u�ړI�炵���v�ւ̋��ق̏�Ɋ�Ă���B���w���Ȃ͂��L�`�̎��́A���e�ƌ`���̓���ʂɂ����ċ��R�����d�v�Ȍ_�@�Ƃ��Ă��Ă���B���e��ɂ��ẮA�Ⴆ�w������L�x�Ȃǂ͋��R�����S�̂̍��q���Ȃ��Ă���B�������P�Ɉ�̋��R�ł͂Ȃ��B�S�̂����R��������Ƃ���ϑt�Ȃɂق��Ȃ�Ȃ��B�܂��w�ȁw��ہx�́A��ۂƔނ̎o�Ƃ�����̊ւŋ��R�Ɉ������������ŏ\���̌��I���ʂ���������w�ȂƂ��Đ�������Ă���̂ł���B�������ē��c�̏h�ŗ��̋q������V���琂���[�Ⴊ�ڂ������Ԃ��Ėӏ��ɂȂĂ��邱�Ƃ�A��ۂ��Ӑl�ł��邱�Ƃ́A���̕��̍E�ɋ����������ʂ̋T���ӂł��邱�ƂƓ����Ɂu���R�̈Í��v�u�ӖړI���R�v�Ȃǂ̌�ɕ\���Ă�����R�̈Í����A�|�ڐ����ے������Ă���ɂق��Ȃ�Ȃ��A���R�́u�ړI�炵���v�͖Ӗڂł��邪�̂ɔߌ��Ɗ쌀�Ƃނ̂ł���B����̂Ƀm���@���X���u���ׂĎ��I�̂��̂͂������I�łȂ���Ȃ�ʁB���l�͋��R���q���v(Novalis.,Fragmente)�Ɖ]�Ă���B�Ȃ��`����ɂ��ẮA���C��̋��R�̈�v�A���Ȃ킿�����ً`�̌�𗘗p���ĉC����������B�Ⴆ�u���v�Ƃ������t�̓��e�A���Ȃ킿�����Ȃ̐A���ƁA�u�҂v�Ƃ������t�̓��e�A���Ȃ킿���̐S����ԂƂ́A�Ӗ��̏�ɉ����̊W�Ȃ��ɍS�炸�����������Ă���B���͂��̋��R�������B�܂��|���̖����́A��̉����ق���̈Ӗ��ɕ������āA��̈Ӗ��̗L���鉹�C��̋��R�I�������Ϗ܂���̂ł���B�܂������͔ۂݓ��Ȃ����I���l�����Ă��邪�A���C�̋��R���Ɋ�b��L������̂ƁA�|���̋��R���Ɋ�b��L������̂Ƃ���v�̈ʒu���߂Ă���B�|�[���E���@�����[�͎����`���āu����̋��R(�^)�̏����Ȃ�̌n�v(Varit,p.159)�Ƃ����A�܂����C�̗L����u�N�w�I�̔��v(ibid.,p.67)��
�����Ă���B���R�������w�̓��e����ь`���̏�ɗL����d��Ȃ�Ӌ`�́A�u�ړI�炵���v�ɑ���`����I���قƁA����ɔ����u�N�w�I�̔��v�ɑ����Ă���B
�v����ɁA���R�ɔ������ق́A�݂𑶍݂̔w�i�Ƃ��A�݂�葶�݂ւ̐��ڂɂ��A�܂��͑��݂��݂ւ̓]���ɂ��A��X�����̗��R��₤�Ƃ��A�₻�̂��̂�����ł���B���R�͔݂̉\���Ӗ�����B�V�F�[�N�X�s�A�̂������@���u���L���Ȃ�(It�@hath�@no�@bottom)�v(Midsummer�@Night�fs�@Dream,�W.1)�B�ց[�Q���̂������@���u���R��L���Ȃ�(Es�@hat�@keinen�@Grund)�v(Wissenschaft�@der�@Logik,hrsg.v.Lasson,�U,S.174)�B���R�́u��ΓI�s��(absolute�@Unruhe)�v(ibid.)�ł���B���R�ɂ����Ă͔݂��[�����݂�N���Ă���B���̌�����R�͐Ƃ����݂ł���B���R�͒P�Ɂu���̏ꏊ�v�ɂ܂��u���̏u�ԁv�ɐ�[�I�ȋ���ȑ��݂��q���݂̂ł���B�������Đ�ΓI�K�R�͈�̋��R���S�т��߂ɒė�����u�܂��Ƃ̐[���v(�w���������ᔻ�xB.641)�ɂق��Ȃ�Ȃ��B��̋��R�͕���Ɣj�ł̉^�������{�I�Ɏ��Ȃ̂����ɑ����Ă���B�u���ҊF��A���A����L�ʗ��A������ہA��؊F�J�Łv(�w���όo�x�����)�B���݂��݂ɒ��ʂ��A�݂����݂��낭����Ƃ��A��X�͜\���Ƌ��ɍ��X�̔@�����ق��āu���́v�̖����̂ł���B�܂��A��X�͎���ɓ����邽�߂ց[�Q���̌���J�Ԃ��̂ق��͂Ȃ��B�u���Ր��ւ̔ނ̕s���������A�ނ̌����̕a�ŁA�܂��ނ̎��̐����̖G��ł���v(Encykl.,��375)�B
�܁@���_
�ȏ�ɂ����Ę_���I�A�o���I�A�`����I�̎O�n���ɂ��ċ��R����葖����v���B���̎O�̗��r�n�͂܂��q��I(��)�A�����I�A���ړI�n���Ɖ]�Ă����x�Ȃ��B�_���I���R�́A�q��I���f�ɂ����āA�T�O�Ƃ��Ă̎��ɑ��ďq�ꂪ��{���I���\���Ӗ�����Ƃ��ɐ��������B���Ȃ킿�A���錾���I���f�����Əq��Ƃ̓��ꐫ���������߂ɘ_�ؐ��A�]���ĕK�R���������Ȃ����Ƃ������ɂȂ��ꍇ�ł���B�o���I���R�́A�_���I�Ɍ��\����Ȃ�A�����I���f�̗��R�A���̊W�ȊO�ɗ����̂Ƃ��Đ��������B���Ȃ킿�A���R�ƋA���Ƃ̓��ꐫ�ɂ�ċK�肹��ꂽ��_�ؐ��A�]���ĕK�R���͈̔͊O�ɂ�����̂Ƃ��Đ��������B�`����I���R�́A�^����ꂽ�q��I���f�������͉����I���f���A���ړI���f�̈�敪���ƌ��āA���ɂ��Ȃ�����̋敪����������ƍl���邱�Ƃɂ�Đ�������Ɖ]����B���Ȃ킿�A�����I�܂��͘_�ؓI�̖���𗣐�萌W�ɗ��敪���ƌ��邱�Ƃɂ�āA��敪�T�O�̓��ꐫ�ɑ��č��ʐ����J������Ƌ��ɁA������(���ݐ�)����Ҙ_�ؐ�(�K�R��)���萫�ɖ�艻����̂ł���B
�_���I���R�̊j�S�I�Ӗ��́u���v�Ƃ������Ƃł����B�o���I���R�̊j�S�I�Ӗ��́u��̌n��Ƒ��̌n��Ƃ��琁v�Ƃ������Ƃł����B�`����I���R�̊j�S�I�Ӗ��́u�������Ƃ̉\�v�Ƃ������Ƃł����B���ł��邪�̂ɁA��ʊT�O�ɑ��ċ��R�I���\������Ă����̂ł���B�Ɨ������n��ƌn��Ƃ��琂ł��邪�̂ɁA���R�ƋA���̕K�R�I�W�̊O�ɂ����̂ł���B�������Ƃ̉\�Ȃ邪�̂ɁA��Ύ҂̐�ΓI�K�R���ɜ����̂ł���B�������āA�����̋��R�̎O�̈Ӗ��͌����Čɕ������Ă���̂ł͂Ȃ��A�ӑR�Ƃ��Ĉ�ɗZ�����Ă���B�u������ьX�̎��ہv�̊j�S�I�Ӗ��́u��̌n��Ƒ��̌n��Ƃ��琁v�Ƃ������Ƃɑ����A�琂̊j�S�I�Ӗ����琂��Ȃ����Ƃ��\�ł��邱�ƁA���Ȃ킿�u�������Ƃ̉\�v�Ƃ������Ƃɑ����Ă���B�������āA����炷�ׂĂ����{�I�ɋK�肵�Ă�����R���̖{�L�I�Ӗ��́A�ꌳ�Ƃ��Ă̕K�R���ɑ���̑[��Ƃ������Ƃł���B�K�R���Ƃ͈ꌳ���̗l���ɂق��Ȃ�Ȃ��B���R���͓��̂���Ƃ���ɏ��߂đ�����̂ł���B���̋N���͈ꌳ�ɑ���̑[��ɑk��B�琂͓��琂ɂق��Ȃ�Ȃ��B�������Ƃ̉\�͈ꌳ�ɑ��锾�t�Ɋ�b��L����B�L�̈Ӗ��ꗥ�ɂ�ċK�肵�A���ꗥ�ɔ�������̂ƊŘ��o�����j�f�X�̓N�w�́A���R�ɑ�����قɔ����ēɑ��鋺�ЂɏI���B��������X�̓o�����j�f�X�̓N�w�Ɉ���Ӗ��̐^�������F���Ȃ���ɂ䂩�Ȃ��B�����ɂ܂��l�Ԃ̊�тƔY�݂Ƃ�����ł���̂ł���B
�G�ɋ��R���̖��́A���̖�����ނ��̂ɁA�����Ɍ`����w�̖��ł���Ɖ]���B�܂��`����w�Ƃ��Ă̓N�w�ȊO�̊w��͖��̖�����O���邪�̂ɁA���R������Ƃ��Ȃ����Ƃ��]���B���R���́u���̏ꏊ�v�u���̏u�ԁv�ɂ������琂Ƃ��Đ�[�̊낫�ɗ���粍ۂȂ����ɗՂނ��̂ł���B���R���͕��ՓI�v�҂ɂ�Ė@���̕K�R���̂ݒǂ��w��ɂƂĂ͋��炭��ڂ̉��Ȃ����ɉ߂��Ȃ��B�A���X�g�e���X�����R�́u�w��(�@�@�@�@�@�@�@����?�Ƀ̓���?)�v(phys.,�U.5,197(a))�ɂ��Č���B�ց[�Q�����u���R�𗝉����邱�Ƃ��T�O�ɋ��ނ�͍̂ł��s�K�ł���v(Encykl.,��250)�Ɖ]���Ă���B�v����ɋ��R���͊w�I�F���ɑ��Č��E���`�����Ă���B�������āA�F���̌��E�Ɏv���O���A�����������𒍎����āu���فv���邱�Ƃ͓N�w�ɗ^����ꂽ���R�ł�������ł���B
�N�w�ȊO�̊w��ɂƂċ��R�������Ӗ��̂��̂ł���Ɠ��l�ɁA�͂��Ȋw�Ɏ���ϗ����ɂƂĂ����R��e���ꏊ�͂Ȃ��B�������J���g�̗ϗ������A�����@�����ė�O���������镁�ՓI���R�@�̔@���ɂ��炵�߂悤�Ƃ���̂ł���Ƃ����Ȃ�A�u�����̂����ӎu���Ȃ��ӎu�v�ɑ��郄�R�[�r�̋`���͕K�������s���Ƃ͉]���Ȃ��B���R�[�r�͉����̂����ӎu���Ȃ��ӎu�ɔ��R���āA���ɗՂ�ō������f�X�f���i�̂悤�ɍ���炤�Ɖ]���B�e�C�����I���̂悤�ɐl���E�����B�I�b�g�[�̂悤�Ɏ��E�����悤�B�_�r�f�̂悤�ɐ_�a�ɓ��ē������B�܂��Q�����邪�̂Ɉ����ڂɔ��̕��E�����Ɖ]��(Jacobi�fs�@Werke,�V,S.37)�B�����������ˋ�Ȃ��̂łȂ��A�͂Ƃ��Č����ɐ����悤�Ƃ���Ȃ�A�^����ꂽ���R�Ƃ��č���������̂łȂ��Ă͂Ȃ�ʁB���R�ɑ�����ق͒P�Ɍ��݂ɂ̂݊�b�Â����˂Ȃ�ʂ��Ƃ͂Ȃ��B��X�͋��R���̋��ق𖢗��ɂ�ē|�t�I�Ɋ�b�Â��邱�Ƃ��o����B�u�ړI�炵���v�𖢗��ɏ������琂́u�u�ԁv�ɋ��ق������Ƃ��o����B�������āA��̋��R���̋��ق𖢗��ɂ�ċ������邱�ƁA���Ȃ킿���R�������Đ^�ɋ��R�����炵�ނ邱�Ƃ��A�L���Ȃ�l�Ԃɗ^����ꂽ�ۑ�łȂ���Ȃ�ʁB�w��y�_�x�Ɂu�ϕ��{��́A������ߎҁv�Ƃ���͕̂L�킱�̂��Ƃł��炤�B���������ɑ����ĖŖS�̉^����L������R���ɉi���̈Ӗ��^����ɂ́A�����ɂ�ďu�Ԃ����ނ���ق��͂Ȃ��B�N�l���\���́u���́v�ɑ��ė��_�̌����ɂ��Ă͏\�S�Ȃ��^�����Ȃ��ł��炤�B�͂��ɖ������H�̗̈�Ɉڂ��āu�����ċ��߂���܂�v�Ƃ������Ƃ��o���邾���ł���B
��
(��)���f�̗l����̋��Problematica,assertoria,apodictica����I�A�����I�A�_�ؓI�ƖĂ͂ǂ����Ǝv�ӁB
problematica�͕��ʂɁu�W�R�I�v�Ɩ�Ă��邪�A�ɂ߂ĕs�K�ł���B�W�R�Ƃ�probabilis�̖�ł���B��������probabilis��problematica�����ϋɓI�ȈӖ����e�����Ă���Bproblematica�̓�?���ɃŃʃ����痈�����̂Ƃ��āu���I�v�Ɩ��Ƃ��K�̂悤�ɍl����Bassertoria��asserere���痈�����̂ł��邩��u�����I�v�ƖBapodictica��?��?�Ãǃ̃�?�����ƂƂ��邩��u�_�ؓI�v�ƖB�]���͎O�̂��Â�ɂ��u�R�v�̎����ē��ꂵ�ė��������̕K�v�͂ǂ��ɂ��Ȃ��Ǝv���B
(��) ���f�̊W��̋�ʂɊւ����̂����ł�categorica�̓ȃ��уŃ��̓�?�����痈�����̂Ƃ��āu�q��I�v�Ɩ��Ƃ��K�̂悤�Ɏv���Bhypothetica��?��?�ƃÃЃ�?�Ɋ�b��L������̂Ƃ��āu�����I�v�̖�����Bdisjunctive��disjungere���痈�����̂ł��邩��I���I�Ƃ�������́u���ړI�v�Ƃ�����̕������B�܂��O�̂�����ɂ��u���v�̎����Ē茾�I�A�����I�A�I���I�ȂǂƓ��ꂷ��K�v�͔F�߂邱�Ƃ��o���Ȃ��B
�_���v�|
�_���́u���R���v�Ƒ肵�A��A���ǁA��A�_���I���R�A�O�A�o���I���R�A�l�A�`����I���R�A�܁A���_�̌ܐ߂�萬��B
��A���ǂɉ��āA���R�Ƃ͔݂̉\�Ȃ鑶�݂Ȃ邪�̂ɁA���R���̖��͖��ɑ���ݖ�ƕ������邱�Ɣ\�͂��ƂȂ��A�܂����̌���A���̖��͌`����w�ɂ��Ă̂ݒ�o����ׂ������̂��̂Ȃ邱�Ƃ�����B�Ȃ����R���͕K�R���̔ے�ɂ��āA�K�R���͓��ꐫ��\�z���ƂȂ��B�܂����ꐫ�́A�_���w��̊T�O�ƁA�o���E�ɉ�������ʐ��ƁA�`����I�̐�Ύ҂Ƃɉ��čł������Ɍ����ƁA���̎O�l�̓��ꐫ�]���ĕK�R���ɑ��ĎO�l�̋��R���̑����ׂ��Ȃ�Ɛ��f���B�_���I���R�A�o���I���R�A�`����I���R���Ȃ킿����Ȃ�B
��A�_���I���R�Ƃ́A�{���I���\�̑S�̂Ƃ��Ă̊T�O�̗L���铯�ꐫ�A�]���ĕK�R���ɑΗ������{���I�������͋��R�I���\�̋��R���Ȃ�Ɖ����B�]���ĕ��͓I���f�Ƒ����I���f�Ƃ̑Η��A����ёS�̔��f�Ɠ��̔��f�Ƃ̑Η��̔@�����A�_���w�̗̈�ɉ�����K�R���Ƌ��R���Ƃ̑Η��̂�����ɊO�Ȃ炸�B�v����ɁA�_���I���R�Ƃ͌�����ʊT�O�ɑ��Ă��K��Ȃ�B�R��Ɍ��͈�ʊT�O�ɑ��Č��������ɉ��Ă̂��R����L������̂ɂ��āA�����ꎩ�g�ɉ��Ă͕K�R���ɂ�đ��݂��B�̂ɋ��R���̖����A�_���w�̒��ۓI�̈��莩�R�N�w����ѐ��_�N�w�̌o���I�̈�ֈڂ��čl�����ׂ��ƂȂ��B
�O�A�o���I���R�̈Ӗ��𖾂��ɂ��邽�߂ɐ�È��ʐ��ƖړI���Ƃ̈Ӗ���葖����B���ʐ��͓��ꐫ�ɊҌ������ׂ��A���̌���ɉ��āA�K�R����L���B�ړI���͈��ʐ��̋t����ȏ�A���ʐ��̗L����K�R������L���B���ʓI�K�R�ƖړI�I�K�R�Ƃɑ��āA���ʓI���R�ƖړI�I���R�Ƃ̓�B�o���I���R�Ƃ͗��҂��w���Ă����B�ړI�I���R�ɂ́A�ړI�݂̔����ɓI�ɖڌ�������ɓI(��ΓI)�ړI�I���R�ƁA�ړI�ȊO�̂��̂̑��݂�ϋɓI�ɖڌ�����ϋɓI(���ΓI)�ړI�I���R�Ƃ̓�킠��B�R��ɖړI�I���R�Ƃ͖ړI�ɑ��ď��߂đ�������̂ɂ��āA���̖{����A�L��A���`�̈��ʐ��̖��ɊҌ����čl�@����ׂ����̂Ȃ�B���ʓI���R�ɂ́A�������̈Ӗ��ɂČ�����������ΓI(���ɓI)���ʓI���R�ƁA��̈��ʌn��Ƒ��̈��ʌn��Ƃ̕K�R�I�Ȃ炴�鑊�ΓI�W���Ӗ����鑊�ΓI(�ϋɓI)���ʓI���R�Ƃ̓�킠��B��ΓI���ʓI���R�̊ϔO�͌��ۊE�Ɋւ������͉�����������̂��̂Ƃ��Ė��I�Ȃ�B���ΓI���ʓI���R�́A���ۊE�ɉ������̌n��Ƒ��̌n��Ƃ��琁A���Ȃ킿���ꐫ�̕K�R����ے肷��َ��I�̐ڐG�Ƃ��āA���R���̊j�S�I�Ӗ����`�����B�����Ă��Ƃ����ΓI���ʓI���R���ԐڂɕK�R���̋K����Đ���������̂Ƃ�����A�����ʌn�݊Ԃ̘A�ւ̌���Ƃ���̋N�_�ɉ��Ă͈ˑR�Ƃ��ċ��R�������F��������B䢂ɉ��āA���R���̖��͌o���I�̈���`����I�̈�ֈڂ�B
�l�A�`����I���R�Ƃ́A�`����I��Ύ҂̓��ꐫ�]���ĕK�R���ɑΗ�������̂Ȃ�B�����ʌn�ݘA�֑̌n�̋N�_�Ƃ��Ă̋��R�����ΓI����҂Ƃ��đ[�肷��Ƃ��ɁA�`����I�K�R�����A���̔ے�Ƃ��Č`����I���R�̊ϔO���B�̂Ɍ`����I���R�Ƃ͕L��A�o���I�K�R�̈��Ȃ�B�`����I�K�R���ƌ`����I���R���Ƃ̑Η��͗v����Ɏ������Ƒ������Ƃ̑Η��ɊO�Ȃ炸�B�����đ������Ȃ킿���ȈȊO�̌����ɂ�đ��݂�����̂Ƃ��āA�`����I���R�́A�݂̉\�Ȃ鑶�݂����\���B�`����I���R�͖���w�i�Ƃ��A�\�I���ڎ��̎����I�[����Ӗ����B�̂ɋ��R�́u���̏ꏊ�v����сu���̏u�ԁv�Ɍ���đ��݂��A���ɋ������Ƃ����݂Ȃ�ƒf���B
�܁A���_�ɉ��āA�_���I���R�A�o���I���R�A�`����I���R�̎O�҂̑��݊W���ڂ�Ƌ��ɁA����炷�ׂĂ����{�I�ɋK�肷����R���̖{�L�I�Ӗ����A�ꌳ�Ƃ��Ă̕K�R���ɑ���̔w���I�[��ɉ��Č���Ƃ��B�Ȃ����R���̖�肪�A�@���̕K�R��Nj�����Ȋw�ɂƂĖ����l�Ȃ�Ɠ��l�ɁA�͂��Ȋw�Ɏ�ϗ����ɂƂ��Ă����R��e������ꏊ�Ȃ��͓��R�Ȃ�B�R��ǂ������ɐ�����Ƃ��铹���ɂƂẮA���R�������Đ^�ɋ��R�����炵�ނ邱�Ƃ����Ɏ��v�̉ۑ�Ȃ�B�����ė��_�̌����ɂď\�S�Ȃ��^����������R���̖��ɐϋɓI�Ӗ��^����͎��H�̗̈�ɉ��ĂȂ�ƌ��_���B
��Ȃ�s�����̓_
��A�_���I���R�̏͂ɉ��āA�_���I���R���Ƃ͌�����ʊT�O�ɑ��Ă��K��Ȃ邱�Ƃ��]����݂̂ɂāA���Ղƌ��Ƃ̊W���̂��̂𑶍ݘ_�I���Ƃ��Ď戵�͂��肵���B
��A�o���I���R�̏͂ɉ��āA�ϋɓI(���ΓI)�ړI�I���R�ƁA���ΓI(�ϋɓI)���ʓI���R�Ƃ̓��I�W�Ɋւ��Ę_�������肵���B
�O�A���R�̎����I�[��Ɗm���_�Ƃ̊W�ɏA�āA�����ɂĈꌾ������݂̂ɂāA�`����I���R�̏͂ɉ��ďڐ������肵���B
�l�A�`����I���R�̏͂ɉ��āA�u�ړI�炵���v�̓�����L������R���̓��ِ��ɏA�Č��y���Ȃ���A�\���Ȃ�葖����Ȃ������肵���B
���a�V�N(1932�j
2012.1.10