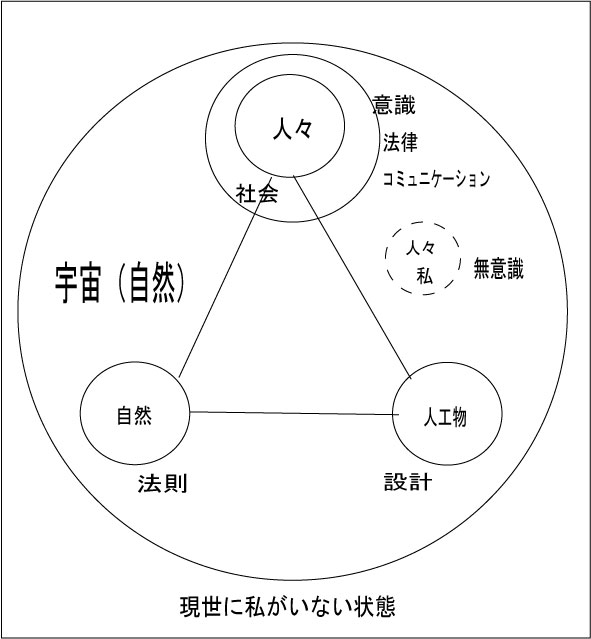�����A�����ɁA���̎���������s�v�c�B��O�����̌��������X���X�߂������Ă����B��b�O�͂����Ȃ��B�����Ď��͈������ƔE�ъ��B�����͕K������Ă���B
���ꂵ�݁E���ɂ��āB�����ꂵ�܂��Ɏ��˂���A�K�������m��Ȃ����A���ւ̎����͋������낤�B���ɗՂ�ŁA�a�Ȃǂŋꂵ���ꍇ�A���ւ̎������A�ނ��뎀�ɂ����Ǝv�����낤�B
���_�͑P�l��s�K�ɂ��A���l���K���ɂ��邱�Ƃ�����B�s�����ȉ^������X�Ɏ�����B
�����̕s�������ǂ��l���邩�B
��X�͔ߌ��E�쌀���ӏ܂����S�ɂЂ���B�_�͉�X�̐����l�������̂悤�Ɋӏ܂������������ɂЂ����Ă��邩���m��Ȃ��B�P�l���s�K�ɂȂ�����ߌ����͋������A���l���K���ɂȂ�����쌀���������Ă������낢�̂����m��Ȃ��B
����͂��ׂĂ̑��݂��z�������݁A���̑��݂��z�������݁A���݂��z�������݁B
���u��C�ɐ��ގ������ʂ̖ӂ̋T���S�N�Ɉ�x���̓��������A�܂��B��̍E���镂���C���ɕY���ĕ��̂܂܂ɓ���������A�l�Ԃɐ��܂�邱�Ƃ́A���̖ӂ̋T�������グ���Ƃ��A���܂��܂��̖̍E�ɋ����悤�Ȃ��̂ł���v�G���܌o�i����P�T�j
���́u�ӋT����栂��v�́A�������A��O�I�ȁu�ł����Ɓv�����Ƃ��Č���ꂽ�̂ł͂Ȃ��B�ނ���t�ɓT�^�I�ȁu�ł����Ɓv�̂��Ƃ��ƌ���ׂ��ł���B���Ȃ킿�A�F���i���E�j�ɐ����邱�Ƃ͂��ׂāu�ӋT����栂��v�̂悤�ɂقƂ�ǂ��肦�Ȃ��A����Ȃ��s�\�ɋ߂��u�ł����Ɓv�ł���A�F���͂��̂悤�ȁu�ł����Ɓv�ɏ[�������Ă���B�ꗱ�̍��������ɂ���A�ꖇ�̖̗t�������ɂ���B���Ȃ��������ɂ������āA�������܂����ɂ������đ��݂��邱�Ƃ��A���Ȃ��Ǝ����o���������Ƃ��A�����Ă����������̉F�����������đ��݂��邱�Ƃ����̂悤�ȁu�ł����Ɓv�ł���B���R���i�\�������̋Ɍ��j�̓T�^�I�ȗ�͂ǂ��ɂ���̂ł��Ȃ��A�܂����o������Ƃ����̂ł��Ȃ��A�܂��ɂ��܂����A�r���ɂ���ƌ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����������͂���ł��A�܂����ł��ǂ��ł����R���ɏo�����Ă���B���̉F���A�u���v�̑��ݎ��̂����R���̓T�^�I�ȗ�ł���B�u�r���ƌځv���邢�́u����ԏƁv�Ƃ����T��́A���̂��ƂɋC�Â����Ƃ̋H�Ȃ����Ɍ����Č���ꂽ���t�ł���ƎƂ߂邱�Ƃ��ł��悤�B�u��C�v�Ƃ͂��̉F���̂��ƁA�����Ɛ��m�Ɍ����A�������̉\�I�F���̂��Ƃ������̂ł���A�u�ӋT�ƕ��̏o�����i�̌��ʁj�v�Ƃ͂��̉F���Ǝ��́u���݁v���Ӗ����Ă����̂ł���B�i��S�����̓N�w�@���l�P�M�j
�����������܂߂��F���̍\���́A�l�Ԃ̂�����l����A�C���[�W�ŕ`���Ă���悤�Ȃ��̂łȂ��Ƃ���́A�Ȃɂ��Ȃ��킩��Ȃ����́A�����A�������Ȃ͖̂��������A�������Ɏ��������邱�Ƃł���B
���f�J���g���_�͒��S����~���ֈ��������������ׂē������Ƃ������Ƃ��^�łȂ��悤�ɂ����鎩�R�������Ă���ƍl�����͈̂Ӗ��̐[�����Ƃł���A������m�I���ς̑O�ɂ͘_���I������E�����\�����������邩���m��ʁA�����̗���ɂ������́A���悵�ā|�P�ƂȂ鐔�͖��Ӗ��ȕs�\�̂��̂ł���A�u�\�I���݂ɑ��閳�v�ł���A���������f���̗���ɗ��Ă�|�P�͐ϋɓI�ȈӖ����������u�L�v�ł���B
�����R���Ə@���Ƃ̊W�ɂ��čl���Č���̂ɁA�E�E�E�E�E�i�R�y�[�W�ȗ��j�@���̖{���͕L��A�s�m�ɑ���A�˂ł���B�������ĉ^���A�������R�ɑ�����فA�s�v�c�̂��ɂ��ɑ�����ق��₪�ĕs�m�ɑ����ΓI�A�˂̌`�����̂ł���B���R���̑��݂������ɉ����āA�@���͑��̑��݂̓N�w�I���R��L�Ă���B�������Ȃ��獟�̓N�w�I���R�͓����ɂ܂��@������̊T�O�I�v�ق�f�O���ĒP�ɕs�m�ɑ���A�˂̌`�ő��݂��ׂ����Ƃ�v������̂ł���B�m�N�w�͒P�ɍ����I�F���ɗ��r���ĔF���̌��E�����E�Ƃ��Ď����悢�̂ł���B�n�i��S�T�����A���R���i�u���j�A1929.10.27�A�S�W��Ap343�j
�����͈������ƔE�ъ��B�����͕K������Ă���B
���l���̌����͔ߌ��ł��鈫�l�ɂ��P�l�ɂ����������͂���Ă���B�_�͑P�l�ɂ����l�ɂ������ł���B
���l���̌����͎��ł���K���E����鎀�ʂ͎̂��E�҂݂̂ł���B
����X�͐��܂ꂽ�����玀�Y��鍐����Ă���B�����A���ʂ�������Ȃ������ł���B
�������̋�ԂƉi���̎��ԂƂ̐^�����̈ꙋ�߂��Ă���䂻���ē��B
������ł��ē���O�A�����Ă���͕̂s�v�c�ł�����R�ł���B
�����̂��d�݂͑��ΓI�ł��邪�A���̔����Ă���d�݂͐�ΓI�ł���B
�����̂��߂ɐ����Ă���̂��A�����Ђ�����ɁA���ʂ܂Ő����邽�߂ɐ����Ă���
�����̂��߂ɐ����Ă���̂��A�����Ђ�����ɁA���ʂ��߂ɐ����Ă���B�����}���Đ����Ă���B
�����̑��ݗ��R�E�E�E�E���ɍ��A�����Ɂu���̎��v�����邱�Ƃł���B
���I�v�̉F���ƍ������ɂ���u���̎����v�̊�O�����̌��������X�߂������Ă䂭�B�P�b�O�͂����Ȃ��B
�u�Ō�w���ƍl���鋳��w�v�̒��ŌÐ�Y�k�� �up181�F7�F�����Ƃ͎��ԓI���݂ł��B�����̂Ȃ��ɑ��݂���A�ڂɌ������̓I�ȑ��݂������Ȃ̂ł�����A����͎��Ԃ̂Ȃ��Ő��܂�A���ԂƂƂ��ɕω����A�₪�ď��ł��Ă������̂ł��B���Ԃ̗���ƂƂ��ɁA�₦�ԂȂ��A�����E�ω��E���ł���̂������ł��B���������āA���������Ӗ��ł̎������ɒ��ڂ���Ȃ�A���Ƃ��������ł��A����̎��ƍ����̎��Ƃł́A�u�����v���ł͂Ȃ��̂ł��B�����Ƃ́A�u���́v�u�ԁA�u���́v�ꏊ�ɁA�܂��ɓ_�̂悤�ɁA���̂ǁA���݂�����̂Ȃ̂ł��B�������Ƃ́A���݂́u���̂��́v���ł���Ɠ����ɁA�u���̂ǁv���ł���ƌ����Ă��悢�ł��傤�B�v�Ƃ����Ă���B
���X�@���O�̒����u�S��v�ɕ����ł����u��v�A�F���̑吶���̐������F���i���̉Ȋw�I�Ȃ����Đ����̐i���Ƃł��������ʂ���q�ׂ��Ă���B
�u�N��ڂ����A�������ɂ���Ƃ��������́A�����Ɛ��m�Ɍ����A�ꉭ�N�̂̐�c�̂����A�����N�ߋ��̃A���[�o�̂����Ƃ����Ɏ~�܂�Ȃ��B�A���[�o�ɂ���c�͂���̂��B����ɂ��̐�c�����ǂ��Ă䂭�ƁA���ʂɂ͐������Ȃ��Ǝv���Ă���A�Y�f�Ƃ����f�Ƃ��i�g���E���Ƃ����������̌��q�ɓ��B���A����ɐi�ނƗz�q�A�d�q�A�����q�A���Ԏq�Ƃ�����ɖڂł͌����Ȃ��f���q�ɍs�������Ă��܂��B(P13)�v�Ɖ]���Ă���B
����Ɂu���̂悤�ɘb�����߂Ă����ƁA�����������Ƃ������Ȃ��ł͂����Ȃ��Ȃ�B
�@1.�f���q�A���q�A���q�A���@���A�L�@���A�����q�i�傫�ȕ��q�j�A�P�זE�����A���זE�����A�l�ԁA�Љ�A���E�A�F�����`�Â���A�������Ă��鍪�{�̗͂��ޑR�Ǝ��݂���B�����ł͂��̗͂̂��Ƃ���ƌ����Ă���B
�@2.���̗͉͂i���̉ߋ������p�������Ă���A����ꂪ�����ɑ��݂��A�����Ă���̂��A���̗͂̍�p�ɂ���Ăł���B
�@3.�����鐶�������ɐ���������̂ł͂Ȃ��B�i�{���ɐ[�������̌��������ꂽ�Ȋw�҂ɂ��������Ă݂�ƁA�����Ɩ������̋��ڂ͉�R�Ƃ��Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ��j���@���ɂ��A���f�A�i�g���E���ɂ�����������B�܂�A�����A���͂������z�������܂߂āA��������̂������������Ă���B�v
�Ɖ]���Ă���B
�@���ɓ������A�X���O��
�u�u��܂��߁v�v�l�@�v�̒��ŁA����������������A�V�X�e���������Ƃ���܂łɂȂ��@�\���o������Ƃ����B�u�o������l����A�f���q�ł��邪�A���ꂪ�W�܂��Ď��̂��̂ɂȂ����Ƃ��ɐV�����@�\���o�A�V�������̂���������B���̊�{�ɂ��錴���͓�ȏ�̂��̂����̂���ƁA���܂܂łɂȂ������V������p�����o����Ƃ������Ƃ��B�i�Ⴆ�A���͎_�f�Ɛ��f���������Ăł��邪�A����͎_�f�ł����f�ł��Ȃ���O�̕����ł���i�s�A���j�B���������ɂ͎_�f�Ɛ��f�����ݓI�ɑ��݂��邩��A����͎_�f�ł��萅�f�ł�����i�A���j�B�j�iP102�j�v
�Ƃ������Ƃł���B
�@�u�X�@���O���A���펯�@�@�_�C�������h�Ёv�̒��ł�
�u�����͕����̈�A�Ƃ������Ƃɂ��čl���Ă݂悤�B�����Ƃ������̂��ƑΗ������錩���͑����B�������́A���̐��_��p�����܂߂Đ����Ƃ͕������G�������g�Ƃ��鋐��V�X�e���ɂ���Ĕ������ꂽ����Ȍ`�Ԃł���Ƃ����ϓ_�������Ă���B�����ɂ��Ȃ���Ă��鐫���ɂ͂��낢��Ȃ��̂�����B������p�A�����A���L���͂Ȃǂ͂��̗�ł���B�����͓���̌��q���������݂��邾���Ŕ������鐫���ł���B�َ�̌��q�������L�@�I�Ɍ�������ƁA�����q�A�E�E�E�E�v���X�`�b�N�͂��̗�ł��邪�E�E�E�E�E�Ƃ����傫�ȕ��q�ɂȂ�A�����O�ɂ͌����Ȃ�������������������B���ꂪ����ɑ��푽���V�X�e�}�e�B�b�N�Ɍ�������ƁA������������B�V�X�e���Ƃ������̂́A�G�������g��������x�ȏ�̕��G���Ōn������������������ƁA����܂łɂ͌����Ȃ������َ��̐����A�V�����@�\��������̂ł���B�����͕����V�X�e�����������Ă��鐫���̈�ł���B(p206)�v
�Ɖ]���Ă���A������v�f�Ƃ��āA���G�Ɍ���������V�X�e���ƂȂ��Đ��������������B���������Ă��̌��ł��镨���ɂ�����������Ƃ����̂ł���B
�����{�b�g�H�w�̐��҂ł���A�����ɑ��w���[���X���O�͂��̒��u�S�@�̂����߁v�̒��ŁA
�u���ӎ��̐��E�́A��Ȃ��̌̂悤�ɐ[���傫���B(P91)�v
�Ƃ����A
�u�ӎ��̂����ł͎v�������Ȃ��s�����Ȏ������A�����玟�ւƈӎ��̂����Ɏv�킸�オ���Ă���B����ȂǁA���ӎ����E�ɂ���Ĉӎ����E���R���g���[������Ă���؋��Ƃ����Ă悢�B(p92)�v
�Əq�ׂĂ���B������
�u�����̐S�̉���ɂ͖��ӎ��̐��E������B�����͎����̈ӎu�ōs�����Ă��邪�A���̈ӎu�͖��ӎ����E�ɂ���Ċ��S�ɃR���g���[������Ă���B(p119)�v
�Ƃ��]���Ă���B�F���̐��ȓ����ɂ���āA����ꂪ�����Ă���A��������Ă���؋��ł�����B
���X���O�́u�X���O�̕�������v�̂Ȃ��Ŏ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�u�ڂ�������l�тƂ�̐l�Ԃ́A�����̈ӎu�ŁA�����̗͂ŁA�l���A�s�����A�����Ă���̂��Ǝv������ł���B����ǂ��A������܂̊���Ƃ����Ă݂�ƁA���ׂĂ̑��݂��A�傫�ȑ厩�R�̈ӎu�A�F���̐����̓����ɂ���āA�c�_��������A�߂���A���A��������A�����肵�Ă���Ƃ�������̂��B�E�E�E�E �ڂ��́A���ꂪ�u��������Ă���v�Ƃ������Ƃ��ƍl����̂��B(P232)�v
�Əq�ׂĂ���B
���������͂��C�̓Łi�X�@�v�h�L�j
�������ɂ͑P�����ʂ�����悤�Ɏv���Ă��܂����A���{�b�g�H�w�̐��҂Ƃ��ėL���ȁA�X���O���ɂ��܂��Ƃނ���A�����A�����͑P�ł����ł��Ȃ����L�Ƃ������݂ł����āA�l�ԂɂƂ��ēs���̗ǂ����̂͑P�A�s���̈������͈̂��ɂȂ邾���ł���Ƃ����Ӗ��̂��Ƃ������Ă��܂��B�u�q�̂ɑP���̓�ʂ�����̂ł͂Ȃ��A���L�̈�ʂ����Ȃ��B�����P�ɂ����A���ɂ�����͎̂�̂ł���l�Ԃ��������v�Ƃ������Ƃł���A���Ƃ��ΘH��ɗ����Ă���u�v�͐l�Ɍ����ē����������ł��舫�ɂȂ�܂����A�̎��̊k������̂Ɏg���ΗL�p�ȓ���܂�P�ƂȂ�܂��B
���l�Ƃ̏o����ɂ��Ȃ����Ƃ��A�F�B���w����ɂ���������܂��傤�Ƃ��E�߂�킯�ł����A���̏o��Ƃ������̂��A�܂�����B���̏o��ɂ��lj��ƁA����������B �o����ɂƂ������āA���ꂪ�������ƁA�s�K�̎�ɂȂ�����A�w�Z�ɗ��Ȃ��Ȃ����肢�����܂��B���ׂĂ̏o����lj��ł���K��������Ă��܂��Ă悢�̂ł����A�����͂��܂������Ȃ��B�����ł������ꍇ�ɂǂ�����悢���B���ꂪ��V�Ȃ̂ł����ǂ����傤���Ȃ��B���ɓI�����@�́A�����������ĉ�������B������B�ϋɓI�l�����Ƃ��ẮA�����ɗ^����ꂽ�����Ƃ��āA�����𐬒������Ă����̌����ƍl���āA�����B�Ƃ������ƂɂȂ낤���Ǝv���܂��B ���̈����A���肪�l�Ԃ̏ꍇ�́A�����邱�Ƃ��o�������ł����A������������������Ă��܂��B
�a�A�V�A���A�]�ϒn�ςȂǂł���܂����A����͂ǂ�����悢���B
�m���ɕa���ۂ�E�C���X�ɂ���Ăނ��܂�Ă��铖�l�͂炢�ł��낤�B
�l���A����a�C�ɑ���s����S�z���Ō�܂ł��邾�낤�B�������y�����V�^ࣖ��ɐ�����ꂽ��ǂ��ȁ[�Ǝv���B�������l���Ă݂�Ɩ������y�����A�K�������ς��Ȃ�A���ʂ̂͂Ƃ��Ă�����ŁA��ɔ��������Ǝv����������Ȃ��B�����s����S�z���邢�͋ꂵ���l���Ȃ�A�����邱�Ƃɂ���قǎ������Ȃ���������Ȃ��B
�܂��A�l���̌����͎��ł���܂��B���͎��Ȃ̐��̓O��I�Ȕے�ł���܂����A�F���̐����ւ̉�A�Ƃ݂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł��낤���B���邢�͌�������̓O��I�Ȕے�ł���܂����A��������̉���E���R�Ƃ��݂Ă��悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�P �@�@�@�@�@�@�@�@���L�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�̎��̊k������ �@�@�@�� �@ �@�l�ɓ�������
�w����p�ɂȂ� �� �g���̂����
�����g���@�@�@�@�@�@ �@�@�����@�@ �@�@���K������
�ԈႢ�Ȃ�������@�@ �@�@���v�@�@�@ �@ �@�s���R
�K���ɂ��Ă����@�@�@ �@�lj��@�@�@ �@�L���V�ɂȂ�E���q�ɏ��
�����𐬒������Ă���� �@�����@�@�@�@ �@�@�s�K�ɂȂ�
��������@�@�@�@�@�@ �@���܂��@�@ �@�@���ւ̐鍐
�،h�i��j�i������j�@�@���ʁ@�@�@�@ �@���|�i����j�i������j
�F���̐����ւ̉�A ���Ȃ̐��̓O��I�ے�
��������̉���E���R�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@��������̓O��I�ے�
���̕\�͐X���O�̂��̂��Q�l�ɐX�v�h���L�q�������̂ł���B
���u�����������������z�v�i�u�k�Ёj�̒��ҁA�X���O�͂��̂Ȃ��ŁA
�u�����̔r�����͐A���̐H�Ƃł���A�A���̔r�����͓����̂��߂̎_�f�ƂȂ��Ă���B(p214)�v
�Əq�ׁA�u�u���R�͑S�����́v-------�䕗�͉Ƃ𐁂�����A�^���͐l���̂ށB�ҏb�͐l�Ԃ��P���A�a���ۂ�E�B���X�͐l�̂��ނ��ށB�͂����Ď��R�͑S�����̂��H���͔��������A�E���R�͏X���B�Ԃ͔���������A���s���̏L�C�͕@��˂��B����ł����R�͔��������H�iP217�j�v
�Ƌ^����A���̂��Ƃɂ���
�u����͉��̎�������Ȃ��߂Ă��邩��ł���B�l�Ԃ̃��x���ŁA�l�Ԓ��S�Ɍ��Ă��邩��ł���B�����ɂ͋ߊ�邱�Ƃ�����Ȃ��炢�L���E���R�ɁA�n�G�������邪�A����͂����炭�n�G�ɂƂ��Ă͂悢����ł���A�����������������Ȃ̂ł��낤�B�v
�Ƃ����Ă���B
�������ɂ͑P�����ʂ�����悤�Ɏv���Ă��܂����A���{�b�g�H�w�̐��҂Ƃ��ėL���ȁA�X���O���ɂ��܂��Ƃނ���A�����A�����͑P�ł����ł��Ȃ����L�Ƃ������݂ł����āA�l�ԂɂƂ��ēs���̗ǂ����̂͑P�A�s���̈������͈̂��ɂȂ邾���ł���Ƃ����Ӗ��̂��Ƃ������Ă���B�����āu�����������������z�v�i�u�k�Ёj�̂Ȃ��ŁA
�u���͑P�ɓ]���邱�Ƃ��o����B���ꂪ�~�ς̓��ł���B�P�͈��ɓ]����\��������B���ꂪ���̓��ł���B�v
�Ƃ����]�����
�u�����̋������̂قǑP���͋����E�P�����������̂قLj���������(P148)�v�B
����P�ɓ]����ɂ́A
�u�P�]�̗v�_�́u����v�邱�ƁB�ip155�j�v
�ł���Ɖ]���B
���ɏ����ϓ_�̂��ƂȂ�Ƃ炦���ŁA�Ⴆ�I�[�g�}�`�b�N�Ԃő��邽�߂ɂ́A���邽�߂̋@�\��������悢�悤�ɍl�������ł��邪�A�����ł��낤���B���Ȃ킿�A���̏ꍇ
[���邽�߂ɂ́A���邽�߂̃A�N�Z����������悢�̂��H]
�@�@�u���邽�߂ɂ́|�|�|�|�|�A�N�Z���y�_��
�@�@�@�~�߂邽�߂ɂ́|�|�|�|�|�u���[�L�y�_���v
�ł��邩��A�����u�u���[�L���͂����ĎԂ𑖂点�Ă݂�E�E�E�E�댯����܂�Ȃ��B�v
���ƂɂȂ�B
���S��
�u����ɂ́A�A�N�Z���ƃu���[�L�Ƃ̗������K�v���B(p124)�v
�Ƃ������ƂɂȂ�B
�܂�A���L�̂悤�ɂȂ�B
�@�@�@�u�@�@�@�@�b�|�A�N�Z��������u�X�b�L�������`�ɂ����
�@�@�@�@����|�|�b
�@�@�@�@�@�@�@�@�b�|�u���[�L�@�@�@�@�@�v
�i��̎����j�����ꁩ�i���̎����j
�@�@�@�@�@�@�@�@�b�|��[��]�͑��Ɓi���̔��́j�~�Ƃ��܂ށB
�@ �@�@[��]�|�|�b
�@�@�@�@�@�@�@�@�b�|�~
�݂��ɐ����̑��Ǝ~�Ƃ��A�������ʂ̖ړI[��]�ɑ��ċ��͂��A���ꂼ��̖�����S�@�����āA�͂��߂�[��]�邱�Ƃ��ł���B�v
�Əq�ׂĂ���B
�@����Ɏ��Ƃ������Ƃɂ��āA
�u�l�Ԃ͈�l�c�炸���ʁB�l�Ԃ̔ϔY���猩��ΐȂ����A�������݂���Ƃ������Ƃ��A���a�Ȃ̂��B�S�����ƂȂ̂��B�E�E�E�E�E�E�]���A�A���l�ԁA�Ⓚ���ȂǂȂǂ́A�����Ɋւ�����́E�E�E�E�E�����͐����m�肵�C����ے肵���̂��������Ƃ���ł��邪�A�E�E�E�E�E�E���d����Ƌ��Ɏ�����e����p�����Ȃ���Ή����Ȃ��ł͂Ȃ����B�����ł܂���̐}�����g�����B(p218)
�b�|��
�@�@[��]�|�|�|�b
�b�|��
����[��]�̈Ӗ��͐[���B����[��]�ɂ���āA�����͐������邱�Ƃ��ł���̂ł���B����[��]�������A�i���ɐ����ʂ��̖��ł���B�v�ƋL�q���Ă���B����[��]�͑厩�R�̂��̉F���̉i���̐����Ӗ����Ă���̂ł��낤�B
���X���O�́u��֎ԁv�̂Ȃ��ł�
�u�u���|�v�͎���ɑ��鎷������N����E�E�E�E���̋��|�ɂ��Ă��A��������o���A���̎���Ɏ������邩�玀�ɂ����Ȃ��Ǝv���A���|��������E�E�E�E�v(p266)
�Əq�ׂĂ���B�����āi�F���̎d�g�Ƃ��_��Ƃ��������ƂɈ،h���킢�Ă���Ɓj
�u�������낵���ł��،h�̔O�������Ȃ�A���|�̔O���Ȃ��Ȃ�B�،h�̔O���킭�Ƃ��ɂ́A�傫�Ȏ��R�̂��炭�肪�킩���Ă���̂ŁA���������̒��̈���Ǝv���ƈ��S�ł���B�i�������Ă��炩�����j(p146)�v
�Ɖ]���Ă���B�����
�u���|�S���Ȃ��Ȃ�Ƃ����Ă��A�������S��������킯�ł͂Ȃ��B�E�E�E�E���|�S���،h�ɓ]����̂ł���iP201�j�v
�Ƃ����Ă���B����������ł����Ă����ꂪ��ɂȂ�̂ł���B
���C���h�N�w�A�����N�w�҂ł����������@���́u���n����---���̎v�z�Ɛ���---�v�iNHK�u�b�N�X�A���a45�N3��20����1�����s�A���a51�N2��1����18�����s�j�̂Ȃ��ŁA�F���̌����A�\�����邢�͐�ΔF���Ƃ����悤�Ȃ��Ƃɂ���
�u�����̔F���\�͂͋ɂ߂Č���ꂽ���̂ł���A����ꂪ���퐶���ɂ����āA�펯�I�ɔc�����������Ă���̂́A�^�̎��݂̈ꑤ�ʂɂ����Ȃ��B���邢�͐^���̎����Ƃ͂�قLjقȂ������̂ł��邩������Ȃ��B�����ɂ͂���͂킩��Ȃ��B��̎��݂́A�����̔F���\�͂������̂ł���B�v
�Ƃ����A
�u�����́A�Ȃ����͒m��Ȃ�����ǂ��A�������Đ��܂�Ă����킯�ł��ˁB���܂�Ă��Đ����Ă���Ƃ������Ƃ́A�����ɁA�����ɑ����̏����A����ɓ�������āA�ڂɌ����Ȃ������̗͂ɓ�������Ă��邱�Ƃł��ˁB�iP217�j�v
�Ƃ��]���Ă���B�ڂɌ����Ȃ������̗͂Ƃ́A�F���S�̗̂͂ł���A���ׂĂ͂��̗͂ɂ���ē�������Ă���̂ł���B
���ȉ��A���l�P�M���́u��S�����̓N�w�@�Y���̍��v���A�X�v�h���C�ɓ������������������̂ł���B
�����ł���̂ŁA�����ҁA���l�P�M���̈ӂɔ�������߂����藧�\���̂��邱�Ƃ����f�肷��B
���ЁA������ǂ܂�邱�Ƃ������߂���B
�܂��A���ׂĂ̏o�����͐_�ɂ��K�R���ɂ�萬�藧���Ă���Ƃ����K�R�̓N�w�҂ł���X�s�m�U�ɂ��ċL�q���ꂽ�����ł���B
�u�X�s�m�U�Ƌ�S�v
�up28�@�l�Ԃ��A�������A���������̓V�̂ɔ����������ƁA����ɐ��������������������������̓V�̂����݂��邱�ƂɂȂ�悤�Ȃ��̉F�����J�n��������---���̂悤�ɁA�o�����E���݂̌��������߂đk���Ă������Ƃ��ł��邾�낤�B�X�s�m�U�I�ɂ݂�A���ɑ��݂�����́A���N���鎖�ۂ̂Ȃ��ɋ��R�I�Ȃ��́A�s�v�c�Ȃ��͉̂���Ȃ��A���ׂẮu�K�R�̑��̂��ƂɁv�isub�@specie�@necessitatis�j������B
�@�������A�Ȃ��͂��߂ɂ��̂悤�ȉF�����J�n���Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂��B�ʂ̉F���ł����肦���̂ɁB���ɂ��܂��̉F�����������đ��݂���Ƃ����A�܂��ɂ��̎�������艻����B���݂̕s�v�c���B�Ȃ����̉F���́A���̎��͑��݂���̂��B���̉F���́A���̎��͑��݂��Ȃ����Ƃ����肦���̂ɁB�ʂ̎d���œW�J����F���A�ʂ̐��U�����ǂ�悤�Ȏ��ł����肦���̂ł͂Ȃ��������B�������y���ɐ��܂�A�G�g���ʂ̎���ɐ����邱�Ƃ��\�ł������͂��ł͂Ȃ����B�����͓V�S�̎q�ł����肦���͂��ł���B���m���w���Ȃ������������ꂸ�A�O�����ɁA���邢�͂܂��A���w�҂ɂȂ��Ă�����������Ȃ��B���Ƃ��āA�ւƂ��āA���̖Ƃ��āA���̕��_�Ƃ��Đ��܂�邱�Ƃ��\�������͂��ł���B�l�Ԃ����݂��Ȃ��F���A�l�����ȏ�̎��������̍\���Ƃ���悤�ȉF���A���邢�͐l�Ԃ��ʼn����ȓ����Ƃ��đ��݂���悤�ȉF���E�E�E�E�E�E�B
�@�������Ɂu�_�ɐ�����N�w�ҁv�ƌ�����X�s�m�U�́A������u�_�����R�i�F���j�v�iDeus�@sive�@Natura�kMundus�l�j�Ƃ����v�z�����̂悤�Ȗ₢�ɑ����̉ł��肤�邾�낤�B�u�_�͑��݂���A����䂦���R�͑��݂���v�B�u�_�͑��݂���A����䂦���͑��݂���v�B���̂��Ƃɉ��̕s�v�c���Ȃ��B�u���z�i�_�j�v�͑��݂���A����䂦�Ɂu���M�i�F���A���j�v�͕K�R�I�ɑ��݂��邵�A�܂��u���M�v�Ƃ��Ă������݂����Ȃ��B�u���M�v�͑��݂���̂ɂ��̎n���ł���u���z�v�����݂��Ȃ��ƍl����͖̂{����]�|���Ă���B�������̂悤�ɍl����ҁA�܂�u���_�_�ҁv�Ǝ��̂���҂�����Ƃ���A����́A�X�s�m�U����݂�A�����̂Ȃ����ʂ�����Ƃ������悤�ȋY���������A���̋��C�Ƃ������ƂɂȂ낤�B�X�s�m�U�ɂ��A���̉F�����A���̎����A���܂����ɂ������đ��݂��Ă��邱�Ƃɉ��̕s�v�c���Ȃ��A�Ȃ��Ȃ�_�͑��݂���̂ł��邩��A�Ƃ����̂ł���B���ׂĂ̑��݁E���ۂ́A����ȊO�ł͂��肦�Ȃ��d���ŁA�K�R�I�ɐ��N���Ă���̂ł���B����͂���Ȃ�ɖ����ȉł���ƌ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v
�ƋL�q����Ă���B
�@�����ċ��R�̓N�w�҂ł����S�����̓N�w�ɂ��āA���̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�u��214�F�@�B���R�F���_�i�V�Y�F���_�j
�@���Ƃ��T�C�R�����U���ċ��R�Ɉ���ڂ��o��悤�ɁA�����̉\�I�F���Ƃ����u�ځv���������u�T�C�R���v���U���ċ��R�ɏo���u�ځv�����̉F���ł���ƍl������B���́u�ځv���o��\���������ɂ������B���́u�ځv���o���̂͂܂��������R�ł���B�u�T�C�R���v���U���Ȃ����Ƃ����肦���ł��낤�B�������A���ɂ��̉F���Ƃ����u�ځv�@�͏o�Ă���̂ł��邩��A����͐U���Ă��܂��Ă���̂ł��邪�A�_�͉��̂��߂ɂ����U�������Ƃ����A����́u�Y��v�ɂł���B����ȊO�ɈӐ}�E�ړI���������킯�ł͂Ȃ��B
p221�F ��2�߁@�琂Ƃ��Ă̋��R
�����Ƌ��R
�@�l�ԂƂ��������́A�����̂悤�Ɂu���݂���v(esse�j�����ł͂Ȃ��B�������̂悤�Ɂu�����Ă���v�ivivere)�����ł��Ȃ��B�l�ԂƂ��������́A���݂������Ă��邪�A�������ꂾ���ł͂Ȃ��B���炪���݂������Ă��邱�Ƃ��u�m���Ă���v(intelligere)�B�u�l�ԑ��݂ɂ����Ă͑��݂̎d�����݂Â���ɂ���Č��肳���Ƌ��ɁA���̌���ɂ��Ď��o����Ă���̂ł���B�l�ԑ��݂͑��݂��̂��̂����o�I�Ɏx�z���Ă���v�Ƃ͂����������Ƃł���B�������A�l�Ԃ����o�I�Ɏ���̂��肩�������肵����I���ݎ҂Ƃ��āA�܂�����Ƃ��đ��݂���ɂ��Ă��A���ꂪ�������đ��݂��Ă��邱�Ǝ��̂͋��R�ł���B����͑��݂��邱�Ƃ����݂��Ȃ����Ƃ��\�ł������B���̉\���̂����ꂩ��I�ԂƂ������Ƃ͂����ɂ͕s�\�ł������B�����͎��炪���݂��邱�Ǝ��̂����猈�肵�����̂ł͂Ȃ��B�C�Â����Ƃ��ɂ͂������łɑ��݂��Ă��܂��Ă����̂ł���B���̈Ӗ��Ől�ԂƂ����������݂����R�I���݂ł���B�l�ԂƂ����������݁A���Ȃ킿���������܂��܂��܂����ɂ������đ��݂���B�u���R�������ɋ��R���Ă���v�̂ł���(XI�A����`��O)�B�����ɂł��邱�Ƃ́A�����������炪�������݂��邱�Ƃ�I���̂��Ƃ��Ɉ����Ԃ��Ă�������A���̑��݂̂��肩�������肵�Ă䂭���Ƃł���B�V�Y����_�������̖ڂ��������T�C�R�����Y��ɐU�����B�����͂��̐��E�ɁA���̐��E�ƂƂ��ɁA�T�C�R���̖ڂ̂��Ƃ��ɓ����o���ꂽ�̂ł���B�������V�Y����_�͂����U��Ȃ����Ƃ����肦���B���������ɂ��̐��E�́A�u���v�͑��݂��Ă���̂ł��邩��A����͐U��ꂽ�̂ł���B�Ȃ��A���̂��߂ɐ_�͂����U�������ƌ����A����͋Y��̂��߂ɂł���B�Y�ꂪ�^�ɋY��ł���̂͋Y��ȊO�ɖړI���Ȃ��Ƃ��ł���B�_�͋��R�ɏo���ڂ����ę��������A����Ƃ��ދ��������A�����͒m��Ȃ��B
���R����
�@�u���R�v�Ƃ́u���܂��܁i��)��������i�R)�v�Ƃ����Ӗ��ł���B�Ƃ������Ƃ͗��ʂɁu�����łȂ����Ƃ����肤��v�Ƃ����Ӗ����܂�ł���B�u���v�͂��܂��܂��܂����ɂ������đ��݂��Ă���B�Ƃ������Ƃ́u���v�͑��݂��Ȃ����Ƃ����肦���Ƃ������Ƃł���B��S�͂��̂悤�ȁu���v�̑��݂̐^���T�w�G���܌o�x�ɂ���u�ӋT����栂��v�������Đ�������i�U�A��Z�Z�F�V�A��l�Z�j�B��C�����̓��Ă��Ȃ��ؕЂ��Y���B���̑�C�ɏZ�ގ������ʂ̖Ӗڂ̋T���S�N�Ɉ�x�C�ʂɎ����������B�ؕЂɂ��������ɋT�̎���B�ؕЂ̕Y���͂������̂��ƁA�T�̓������A���������ċT�̎ؕЂ̌��ɓ��邱�Ƃ��Ӑ}���ꂽ���Ƃł͂Ȃ��B���ׂĂ����܂��܂����ł������B���̂悤�ɂ��ċT�̎ؕЂ̌��ɓ������Ƃ������ƁA����͌���Ȃ��s�\�ɋ߂��u�ł����Ɓv�A�����ǂ���u�L�肪�������Ɓv�ł��낤�B���������̉\���̓[���ł͂Ȃ��B�ɏ��ƃ[���Ƃ̂������ɂ͒����������f�₪����B�\�����������s�\���ɐڋ߂������قNj��R���͑��傷��B
�@���́u�ӋT����栂��v�́A�������A��O�I�ȁu�ł����Ɓv�����Ƃ��Č���ꂽ�̂ł͂Ȃ��B�ނ���t�ɓT�^�I�ȁu�ł����Ɓv�̂��Ƃ��ƌ���ׂ��ł���B���Ȃ킿�A�F���i���E�j�ɐ����邱�Ƃ͂��ׂāu�ӋT����栂��v�̂悤�ɂقƂ�ǂ��肦�Ȃ��A����Ȃ��s�\�ɋ߂��u�ł����Ɓv�ł���A�F���͂��̂悤�ȁu�ł����Ɓv�ɏ[�������Ă���B�ꗱ�̍��������ɂ���A�ꖇ�̖̗t�������ɂ���B���Ȃ��������ɂ������āA�������܂����ɂ������đ��݂��邱�Ƃ��A���Ȃ��Ǝ����o���������Ƃ��A�����Ă����������̉F�����������đ��݂��邱�Ƃ����̂悤�ȁu�ł����Ɓv�ł���B���R���i�\�������̋Ɍ��j�̓T�^�I�ȗ�͂ǂ��ɂ���̂ł��Ȃ��A�܂����o������Ƃ����̂ł��Ȃ��A�܂��ɂ��܂����A�r���ɂ���ƌ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����������͂���ł��A�܂����ł��ǂ��ł����R���ɏo�����Ă���B���̉F���A�u���v�̑��ݎ��̂����R���̓T�^�I�ȗ�ł���B�u�r���ƌځv���邢�́u����ԏƁv�Ƃ����T��́A���̂��ƂɋC�Â����Ƃ̋H�Ȃ����Ɍ����Č���ꂽ���t�ł���ƎƂ߂邱�Ƃ��ł��悤�B�u��C�v�Ƃ͂��̉F���̂��ƁA�����Ɛ��m�Ɍ����A�������̉\�I�F���̂��Ƃ������̂ł���A�u�ӋT�ƕ��̏o�����i�̌��ʁj�v�Ƃ͂��̉F���Ǝ��́u���݁v���Ӗ����Ă����̂ł���B�K�R���i���Ȃ炸�������邱�Ɓj�������Ȃ������A�قƂ�Ǖs�\�ɋ߂��A���̈Ӗ��łقƂ�ǖ��ɒ��ʂ����̏�ɕ��V���Ă���u�ł����Ɓv�A���ꂪ���̉F���̑��݂ł��莄�̑��݂ł���B�������Ȃ�����́u���v�ł͂Ȃ��B����͂���Ή����w��Ɂu���݂��̂��́i�K�R���j�v�������Ă���̂ł���B
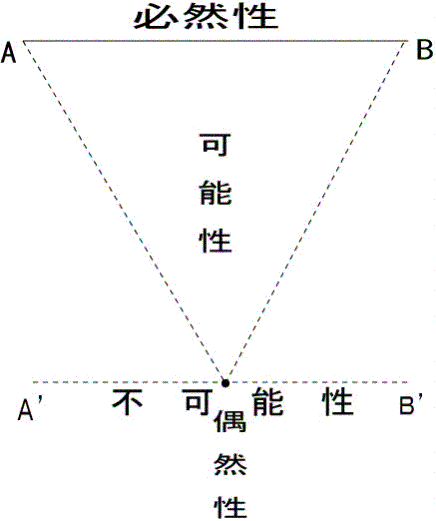 �i�t�O�p�`�́j��ӂ̎����A�Εӂ��Ȃ���{�̔j���A���_�����̐�[�ɂ����Ă܂��ɂ���ɐڂ��悤�Ƃ��Ă��閳�i�u�s�\���v�j��\���j���A�����͂��ׂĖ��������ł���A����䂦���Ă͂��Ȃ��B�܂肻��͖����ɐL�т䂭���ɂ���Č`������铮�I�\���������������t�O�p�`�Ȃ̂ł���B�u�K�R���v��\�������́A����Ί��S�ɖ��̉e��r���������݂��̂��́A�����̏[��Ƃ������悤�Ȃ��̂ŁA�_�C�i�~�b�N�Ȗ����҂܂��͐�Ύ҂������Ă���B�O���ň͂܂ꂽ�ʁi�u�\���v�j�͒��_�i�u���R���v�u�������݁v)�ւ̏Փ��Ȃ����ٓ�������u�\���v�ł����āA�u�K�R���v���̂��ٓ��ɛs�ޏՓ��ł���B�����Ē��_�́A���i�u�s�\���v�j�̔j���ɒė�����s���ɐ₦����������Ă���B�E�E�E�E�E�E
�i�t�O�p�`�́j��ӂ̎����A�Εӂ��Ȃ���{�̔j���A���_�����̐�[�ɂ����Ă܂��ɂ���ɐڂ��悤�Ƃ��Ă��閳�i�u�s�\���v�j��\���j���A�����͂��ׂĖ��������ł���A����䂦���Ă͂��Ȃ��B�܂肻��͖����ɐL�т䂭���ɂ���Č`������铮�I�\���������������t�O�p�`�Ȃ̂ł���B�u�K�R���v��\�������́A����Ί��S�ɖ��̉e��r���������݂��̂��́A�����̏[��Ƃ������悤�Ȃ��̂ŁA�_�C�i�~�b�N�Ȗ����҂܂��͐�Ύ҂������Ă���B�O���ň͂܂ꂽ�ʁi�u�\���v�j�͒��_�i�u���R���v�u�������݁v)�ւ̏Փ��Ȃ����ٓ�������u�\���v�ł����āA�u�K�R���v���̂��ٓ��ɛs�ޏՓ��ł���B�����Ē��_�́A���i�u�s�\���v�j�̔j���ɒė�����s���ɐ₦����������Ă���B�E�E�E�E�E�E�@���Ă����ŁA��S�͖����t�O�p�`��p���ĉ����������Ƃ����̂��A���߂Č��Ă݂悤�B�\���̑���ɂ��������ċ��R���͌������A�\������̋Ɍ��͕K�R���i�\���S��)�Ɏ���B�t�ɉ\���̌����ɂ��������ċ��R���͑��債�A�\�������̋Ɍ��͕s�\���Ɏ���B�\���͕K�R���i���݁E�L���邢�͂P�O�O%�j�ƕs�\���i�݁E�����邢�͂O%�j�Ƃ̊Ԃɋ���ȓ��I���ԗ̈�i�\�I���݂��邢�͂O%��P���P�O�O%)���`������B��Ɍ����悤�ɁA�t�O�p�`�̒�Ӂi�����ł��邱�Ƃɒ��Ӂj�ŕ\�������u�K�R���v�́A���̓��ۂ͕ʂƂ��ċ�S�͂��������Ă���̂ł��邪�A���m�N�w�j�̂Ȃ���.�u�s���̓��ҁv�A�u���݂��̂��́E�������̂��́v�A�u���Ȍ����v�ȂǂƌĂ�Ă������́A�v����Ɂu�_�v���邢�́u��Ύҁv���Ӗ����Ă���B��������S�͈Ӗ��]�����{���Ă�����u�V�Y����_�v�ƌ��Ă���̂ł��邪�B����͑��݁E�����̖����̉\���̏[���A�P�O�O%�̉\���ł���B�����Ă��̖����̉\���̒��̈�̉\���̌���A�قƂ�Ǖs�\���i���j�ɐڂ��悤�Ƃ���ʒu�ɁA����ΉJ���̈ꎴ�������̑�C�֒ė������@��₦���s�ނ��̂悤�ɁA�Ƃ��ʊ��Ȃ��Ǎ݂���̂����R���i�����I���݁j�A�܂肱�̐��E�A���̎��̑��݂̌���ł���B���Ɩ����̂������ɍ����������Ė��ɐڂ��Ȃ��牓�����Ȃ��ɑ��݂��̂��̂���������Ă��鑶�݁A���邢�͂���Βw偂̎��ɂ���Đh�����đ��݂��̂��̂ɂȂ���Ă��鑶�݁A���ꂪ���R�������̌������E�̑��݂Ɓu���v�Ƃ��������̌���ł���B�E�E�E�E�E�E�E
���R�������E�Ɓu���v�Ƃ��������݂̍�悤���̂��̂��s�ސ[���������̂ł���B���R�������̐��E�̑��݂Ɓu���v�Ƃ��������́A���傤�ǖ����̖ڂ��������T�C�R�����R���R���Ɠ]�����ċ��R������̖ڂ̂悤�Ȃ��̂ł���B���܂��܂��̖ڂ��o�����A���̖ڂ��o�邱�Ƃ����肦���̂ł���B���E�́A�u���v�͖������̈�̊m���ŋ��R�����̂ł���B�ǂ�����Ƃ��Ȃ�����Ă��āA�ǂ��ɂ���Ƃ��m�ꂸ�A�ǂ��ւƂ��Ȃ������Ă䂭��Ɠ��Ƃ��A�䂭��Ȃ��琂���|�|�|�|�u�ӋT�ƕ��̏o�����v�Ƃ͂����������Ƃł������B�������A���̂悤�Ȏ����Ƃ��Ẳ�Ɠ��Ƃ́A��������琂ł�������A���悢��u������ߎҁv�i�����ċ��߂���Җ����j�A����u���܋�ߎҁv�i�����ċ��߂���Җ܂�j�Ƃ������Ƃ�������̂ł͂���܂����B��S�̎����_�̍���ɂ͂��̂悤�ȋ��R-�|�|�琘_������B�����t�O�p�`�ɂ���ċ�S�����������͈̂ȏ�̂悤�Ȃ��Ƃł��낤�B
��256�F��S�́A�����̐l�ԂƂ͕ʂ̎d���ő��݂���悤�Ȑl�ԁA�����̉F���Ƃ͈قȂ����݂���ł̉F���A�����̗��j�Ƃ͕ʂ̎d���œW�J����悤�ȗ��j�I���E���\�ł������ƍl���Ă���B�u��X�����o�A���o�A�k�o�A���o�A�G�o�̎��������S�ɔ����đ��݂��Ă��鑶�݂̎d���͑����̉\���̒��̒P�Ɉ�̉\���ɉ߂��Ȃ��B���\����L���̑����̌������\�ł���v�B
�@�l�ԂȂ����͎��Ȃ͌��܊���L���Ă��邪�A����͉\�I���E�̒��̈�ɂ����Ȃ��A����䂦�܂��A���܌��Ă���Ƃ���̊��o�I�����������āA���Ă����E�͂��������A���ꂩ������邾�낤�Ǝv���̂́A���Ȃ��܂߂Đ��E��ÓI�E�Œ�I�Ɍ��邱�Ƃł���B��S�́u�\���v�Ƃ����l���̏d�v�������߂ċ������A����Ƒ��̎O�l���i�K�R���A���R���A�s�\���j�Ƃ̑����s���̊W�������Ȃ��瓯���ɂ��̓Ǝ��̗̈������B�\����w�i�ɂ��Ă��̐��E������Ƃ������Ƃ́A���̐��E�I�Ɍ���Ƃ������Ƃł���B�����炭�A�g���{��I�Ɍ����鐢�E���ƁA�����l�ԂɌ��ۂ��Ă��邻��Ƃ͂��Ȃ�قȂ������̂ł��낤�B������Ƃ����ăg���{��I�Ɍ����Ă��鐢�E�͋q�ϓI�Ȃ��̂ł͂Ȃ��s���S�Ȃ��̂ł���Ƃ͌����Ȃ��ł��낤�B�����������Ƃ���̂ł���A�����l�ԂɌ����Ă��鐢�E�����A���̓_�Ɋւ��Ă͑哯���قł��낤�B��S�́A�K�R���A���R���A�\���A�s�\���Ƃ����l�l�����A���E�̑��ݘ_���w�I�\�����ƌ���B��S�N�w�̓_�C�i�~�b�N�ȊW�\���_�Ƃł�����������̂ł��邪�A�Ƃ��ɂ��̌������E���\����w�i�ɂ��Č��邱�Ƃ����������Â��Ă���B�w���R���̖��x�̗�̖`����A�u���R���Ƃ͕K�R���̔ے�ł���v�Ƃ́A�u���R���Ƃ͕K�R���̎��Ȕے�Ԃł���v�A���邢�́u���E�͐_�̎��Ȕے�ɂ�鎩�Ȍ����ł���v�Ƃ������Ƃł������B�����Ă���������ł�����x����������A�u���E�͉\���S�́i�K�R���j�̈�̉\���̌������i���R���j�ł���v�A���邢�́u���E�͗��ڎ��S�̂̈ꎈ�̌������ł���v�Ƃ������ƂɂȂ�B�\���S�́i�K�R���j�̂Ȃ��̈�̉\�����������i���R���j�������̂Ƃ��Ă��̐��E������̂ł���B�u���܁A�����v�Ɏ����l�ԂƂ��āA�܊������������̂Ƃ��đ��݂��Ă��邱�̌����́A�����̉\���̒��̈���������������̂ł���B�����ɓW�J���Ă��邱�̗��j�́A�����̓W�J�\���̒��̈���������������̂ł���B����͎v���Εs�v�c�Ȃ��Ƃł��낤�B
�@�������A���ꂾ���ł͂Ȃ��B�u���͓����Ő��ꂽ�҂ł��邪�A���s�Ő��ꂽ���Ƃ��A���l�Ő��ꂽ���Ƃ��\�Ȃ��ƂƂ��čl������B���̗��e�͂��Â�����{�l�ł��邪�A���e�̈�����O���l�ŁA�����������Ƃ��Đ��܂ꂽ�ꍇ���e�Ղɍl������B����݂̂Ȃ炸���e�Ƃ��O���l�ŁA�A�����J�l�Ƃ��ăj���[���[�N�Ő��ꂽ�ꍇ���A�C�^���A�l�Ƃ��ă��[�}�Ő��ꂽ��܂��l������v�Ƌ�S�͌������A
��
����́A���Ƃ��Č����A�u�O�p�`�v�Ƃ����u��v�iSpecies�j�T�O�̂��ƂɁA�O�ӂ̒��Z�A�O�̊p�x�̑召�Ɋւ��Ė����̑��l�����������I�O�p�`�iindviduum�j���l������A�Ƃ����悤�Ȃ��̂ł��낤�B�������A������ɂ��Ă������͓����̎O�p�`�i�\�I���E�j�ł��邱�Ƃɕς��͂Ȃ��B���ꂾ���ł͂Ȃ��A����́A�}�`�i�\�I���E�j�Ƃ��đS���ʎ�̐}�`�A���Ƃ��u�l�p�`�v�A�u�܊p�`�v�ȂǁA�����̂�����l���Ă����ł��낤�B�����̑��p�`�́A�}�`�Ƃ�����̗ށigenus�j�ɑ����邳�܂��܂̎�Ƃ��Ă̐}�`�Ƃ��āA���ׂē����̐}�`�Ȃ̂ł���B�u���v�����݂��Ȃ����E�A����l�Ԃ����݂��Ȃ��F���A�܂�S���ʎ�̉F�������肦���Ƌ�S�͍l���Ă����ł��낤�B����́A�u��v�T�O�̂��Ƃɂ��܂��܂́u�v�����Ă��������ł͂Ȃ��A����ɂ��܂��܂́u��v���u�ށv�T�O�̂��ƂɌ��Ă����̂ł���B�v
�Ƃ���B��S�N�w�ɂ��ď��l���̋ɂ߂Đ[�����߂����݂��Ă���h�����A��l�ł������̐l�X�ɗ��z���邱�Ƃ��肤�҂ł���B
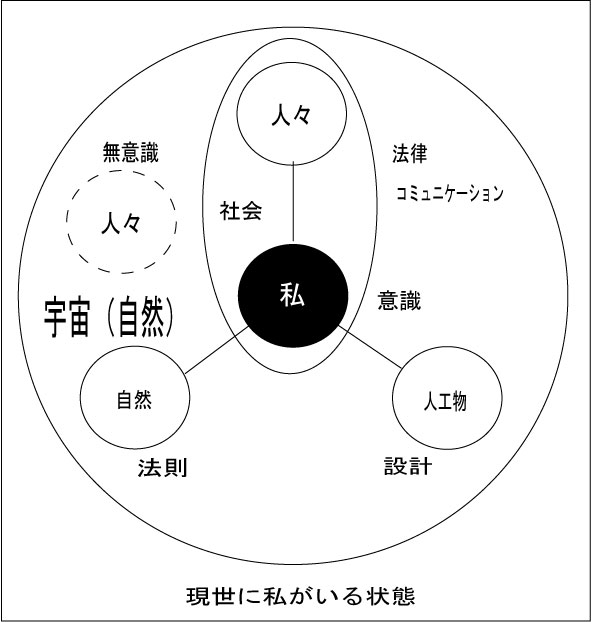 �F��(���R�j�̒��ɁA�����܂܂�Ă���B���Ȃ����������A�����������ӎ������ӎ������R�̈ꕔ�ł���B���R�̈ꕔ�ł��鎄�����Ƃ����ӎ��������A���R�ƑΛ����Ă���悤�ɁA���̖ڂ���O�E�������Ă���B���Ȃ������������ƈӎ����Ă��āA���Ȃ��̊O�E�����Ă���B�������������Ȃ����厩�R�̓��ł���B���ׂĎ��R�̈ꕔ�ł���B���R���I���ɂ��ׂĂ��`����Ă���B���ׂĂ͎��R�̚��āi��ځj�̓��ł���B���R(�F��)�̑z����₷��▭�ȓ����̌����ł���B�����Ď��R(�F���j�ɑ��Ĉ،h�̔O���ւ����Ȃ��B���̂悤�Ɋ�����������B
�F��(���R�j�̒��ɁA�����܂܂�Ă���B���Ȃ����������A�����������ӎ������ӎ������R�̈ꕔ�ł���B���R�̈ꕔ�ł��鎄�����Ƃ����ӎ��������A���R�ƑΛ����Ă���悤�ɁA���̖ڂ���O�E�������Ă���B���Ȃ������������ƈӎ����Ă��āA���Ȃ��̊O�E�����Ă���B�������������Ȃ����厩�R�̓��ł���B���ׂĎ��R�̈ꕔ�ł���B���R���I���ɂ��ׂĂ��`����Ă���B���ׂĂ͎��R�̚��āi��ځj�̓��ł���B���R(�F��)�̑z����₷��▭�ȓ����̌����ł���B�����Ď��R(�F���j�ɑ��Ĉ،h�̔O���ւ����Ȃ��B���̂悤�Ɋ�����������B