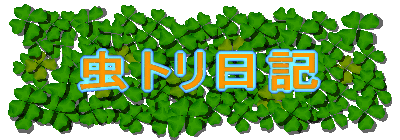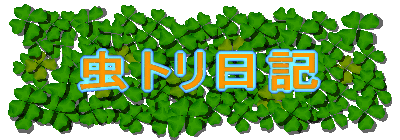�O�W�N�P���Q�Q��
���N�͌��C�ɒ��g�����n�߂����ŁA�Ђ����ɂP���̗\������ĂĂ��܂����B�܂��͖���������������Ƃ̂Ȃ��E���S�}�_���V�W�~�̗����̂�ɍs�����ł��B�Q�Ԗڂ͏���������ł����A��N�A�E���i�~�A�J�V�W�~�̗c������𑽐����������ꏊ�ŗ���T���Č��邱�Ƃł��B�P�[�Q���ŗǂ��̂Ō����ė�����̎�����������ł����B
�������A�P���S�������炵�������ׂɂ�����A���ꂩ�牽���o�������ׂȓ��𑗂��Ă��܂����B���̌�P�V���ɂ͎��a�̌��f�����Ƃ���A�܂����a���Ă���Ƃ̂��ƂŁA�����܂œ�������܂�Ȃ��ꍇ�͓��@�ƌ����Ă��܂��܂����B���@����ƒ��̃V�[�Y���ɊԂɂ���Ȃ��̂ŁA��������ł��B
����ۊǒ���匂�c���B���w�Ǖ��u�����܂܂ŋC�ɂȂ��Ă��܂��B�W���m���`���E�̗c���͍��N��匂�����ꖳ�����ƐS�z�ł��B���A�A�T�M�}�_����匂����͏������H�����āA�c���匂͈�ɂȂ�܂����B�H�����������͍��̋G�߂ɓ������Ă��d�����Ȃ��̂ŁA�S���A�Ⓚ�ۊǂ��܂����B
��N�A���炵���N���}�_���\�e�c�V�W�~��G���}�E���i�~�W���m���𖢂��������Ă��Ȃ������̂ŁA�������������āA�����A�u���E�G�L�v�ɍڂ��܂����̂ł����������B
�@
�Q���O�W�N�Q���W��
�������Q���ɂȂ�܂������A�̒��͍���ŊO�o�͍T���Ă��܂��B���a�̂ق��͂P�����̌��f�ł͖�̌��ʂ��������������X�ɂQ�T�ԗl�q�����鎖�ɂȂ�܂����B���̂悤�Ȗ�œ��L�ɍڂ��镨�͂Ȃɂ����������̂ł����A�������̂j������
�^�C�����c�o���V�W�~�̉z�~�c���𑗂��Ē����܂����̂ŁA���K��̂��q����ɐ��Ē��������Ǝv���ʐ^���ڂ��܂����B
�^�C�����c�o���V�W�~�͏H�ɐH���̃V�o�n�M�̉Ԃ��炭���ɐ������H�����A�V�o�n�M�ɎY�����ꂽ���͛z�����V�o�n�M���Q�A�Ԃⓤ��H�I��c���ɂȂ�܂����A����̏ꍇ�A�I��c���͉z�~���Ɏ���ł��܂����N�̏H�܂ŏI��c�����ɕۊǂ��A�����̎p�����鎖�͊F���ł����B���R��Ԃł��ǂ̂悤�ɉz�~���Ă���̂��͑S���������Ă��܂���ł����B
���̌�A�Q�O�O�U�N�ɉz�~�c�����X�X�L�̌͂�t�ɂ���̂�������܂����B�j���̂��b�ł̓X�X�L�̍�������Q�O�a���̌͂�t�ʼnz�~���Ă��邻���ł��B����A�����Ē������̂͂��̂悤�ȏ�ԂŃX�X�L�̌͂�t�ɂ���c���ł��B���ꂩ��H�܂ł̕ۊǕ��@�ł����A�܂��m���������@�͂���܂����ʂ��̗ǂ������A���ǂ��̂ł͂Ƃ̎��ł��̂ŁA�䂪�Ƃ̌����ŕۊǂ��鎖�Ɍ��߂܂����B���A���x�������Ɠ~�G�ł�匉�������ł��܂������ł��B
���̋@��ɂO�U�N�̗c���̎���ƍ���̉z�~�c���̎ʐ^���u���E�G�L�v�ɂ��ڂ��܂��̂ŁA�����������B
�@
�R���O�W�N�R���Q�R��
�R�������ɋ߂Â����̊J�Ԃ��Ԃ��Ȃ��悤�ł��B���悢�撱�̃V�[�Y�����n�܂�܂��̂ŁA������������G�߂ł����A���̎��a�̌��_�͌����܂Ŏ����z���ł��B����̌��ʂ�����A���̊�]�I�ϑ��ł͓��@�͔�����ꂻ���Ɋ����Ă��܂����A�����̌��f�Ō��_���ł܂��B
��N���獡�N�ɂ����ĉz�~�����ۊǒ��̒��̗c����匂͗�N�Ɣ���Ȃ��������A�����Ȃǎ��O�ɕۊǂ��Ă���w�Ǖ��u�����܂܂ł����̂ŁA���x�Ǘ������[���łȂ�����ł��܂����c����A��肭�H���ł��邩���s����匂Ȃǂ������A�t�ɂǂꂾ�������̎p�������邩�S�z�ł��B
�̒��������ǂ��Ȃ��āA�C�����g�����Ȃ��Ă��܂����̂łR�����U��ɉ��O�ɕۊǒ��̗c����匂̗l�q�����邱�Ƃɂ��܂����B�~���A���������̒��ŕۊǂ��Ă����~���}�J���X�A�Q�n�A�J���X�A�Q�n�A�i�~�A�Q�n��匂͑����A�����̂悤�ł��B���ۂ̏�ɒu���Ď��X�������Ŏ��C��^���Ă����M�t�`���E�ƃX�M�^�j�����V�W�~��匂́A���Ȃ莼�x�s������������������܂����A�Ƃ肠�������������ɓ���A�H���̏��������܂����B
��N����`�K���Ŏ��炵�Ă����C�`�����W�Z�Z���͌͂ꂽ�`�K���̗t�̑��̒��œ~�����Ă��܂����B�P�������ʂɎ��炵�Ă���
�C�`�����W�Z�Z���̗c���͂P�Q���Q�S���ɂ͂V��ł������A�z�~���Ɍ͂ꂽ�`�K���̉��ɕ��Ɠ����̒E��k�𗎂Ƃ��Ă��܂����B�~�̊Ԃ̒g�������ɒE�炵�ĂW��ɂȂ����l�ł��B�V�����ΐF�̃`�K�������܂������A���̂Ƃ���w�Ǔ����Ă��܂���B
��N�A�V�����ɂR��ŋx���ɓ������J���t�g�q���E�����̗c���͕ۊǒ��̎��x�������Ȃ�߂����悤�ŁA�S���p��������܂���B���H�A�Y���A�z�������E���M���q���E�����̗c�������l�Ɏ��x�����߂����̂��A������܂���B�ɐl�̎��ł������a�ɂ͏��Ă܂���B���ǁA���t�̎���̓C�`�����W�Z�Z���̉z�~�c�������ɂȂ肻���ł��B
�@
�@
�S���O�W�N�S���V��
�S���ɓ���g���ȓ��������A�{���Ȃ�P�|�Q�x�͖�O�ɏo�Ă��锤�ł����A�R�����̌��f�ł͓��@�͔������܂������A����͑����鎖�ɂȂ�A�̒������܂薳���͏o������������܂���B���Ƃ��S�����ɂ͉��ĊO�o�������Ǝv���Ă��܂��B
���҂��Ă����M�t�`���E�ƃX�M�^�j�����V�W�~��匂́A�������݁A�H���̋C�z�͑S������܂���B��͂�P���ȍ~�̊Ǘ����������x�s���̉e�����Ƃ������肵�Ă��܂��B
�^�C�����c�o���V�W�~�̗c���͂Q���̏�ԂƑS���ς�炸�X�X�L�̌͂�t�̒��ŐÎ~���Ă��܂��B
�s���������āA���y�Y�ɖk�C���i�ϒO�����Y�j��
�W���E�U���V�W�~��匂��܂����B�����ɉH��������A�̗��ɒ��킵�Ă݂����ł��B�������L�����\�E��}���l���O�T�̎莝���͂���܂���̂ŁA����ɂ���c�������Q���^�C�g�S�����g���Ă݂����ł��B
�O�o�͂ł��Ȃ����A�����ł����܂�̂��g�����͏o���܂���̂ŁA�X�V�L�^�ɂ͍ڂ��Ă��܂��g�o�̎ʐ^�̓��ꊷ���Ȃǂ��������s���Ă��܂��B���ɂȎ��ɐ����������B
�O�W�N�S���P�V��
�P���ȍ~�A����œ��Â����Ă��܂������A���ɂ������̂łb�s���B��܂����Ƃ���A�����ȍ����������Ă���A���a�̉e���̉\���������Ƃ̎��ŁA�����������Â���Ɠ����ɍ����Đ�����_�H���s���܂����B�S�������{���߂��R��֍s�����������������Ă��܂����A�C��������Ŗ����Ƃɕ��������Ă��܂��B
���҂��Ă����X�M�^�j�����V�W�~�ƃM�t�`���E�͑S���H�����܂���B��͂�P���ȍ~�̎��x�Ǘ��ɖ�肪�������悤�ł��B�n���n���t�߂�匉z�~�����ނ͂��Ȃ荂�߂̎��x�������Ɩ����ɉH�����܂���B�X�M�^�j�����V�W�~�����牺��Ēn���匉z�~����\�����������ł��B
�E���M���q���E�����̗c�����g�����Ȃ����S���X���ɓˑR�A�p�������܂����B��N�̏H�Ƀc�{�X�~����A�����A�ؔ��ɛz�������P��c��������Ă������̂ł����A�����璲�ׂĂ��p�������Ȃ������̂ŁA����������߂Ă��܂����B�c���͓y�̏��͂ꂽ�X�X�L�̗t�̃V���̒��ɂ����炵���A�Ȃ��Ȃ�������Ȃ������̂ł����A�g�����Ȃ��Ĉ�x�ɐ������p�������܂����B���ɂP��c���͂P�������ŁA���͂Q��ȏ�̂悤�ł����B�S���X���ɂP������c���̎ʐ^�ƁA��ԑ傫�ȗc���̎ʐ^���ڂ��܂����B
�s������O�U�N�Ɉ�������
�G�]�V���`���E�̗c���̉z�~�����܂����B�O�U�N�ɂ͂T��c���ɖ��A���������c�����Ԃ��`��������o���đS�ł��Ă��܂����̂ŁA���N�͉��Ƃ�匉��A�H���܂ň�Ă����Ǝv���Ă��܂��B������o�ĉa��H�n�߂ĂP�T�ԑ��炸�ł����A�ꕔ�̗c���͂S��ɂȂ�܂����B
���H�A���s�̎R�Ȃō̂�A���炵��
�N���Z�Z����匂ʼnz�~���ł������A�S���P�S���ɍŏ��̂P�����H���A�S���P�U���ɂQ���ڂ��H�����܂����B
�W���E�U���V�W�~�͍ŏ��̂P�����S���P�S���ɉH�����܂����B�W���E�U���V�W�~�͎��Y�̋�ʂ�����̂ŁA�������͗L��܂����A�l�H�̗��ɒ��킷�����ł��B�Ƃ肠�����Q�|�R���ڂ��̉H���҂��ł��B�z���p�ɋߏ��Ő��m�^���|�|�̉Ԃ��̂�r�}���ɂ��A�H���������Ƌ��ɗe��ɓ���܂����B
�@
�@
�T��
�O�W�N�T���P�U��
���炭���L�̍X�V���ł����\����܂���B���͓��Â̕���p�ő̖̂Ɖu�@�\���ቺ���A������w���Ƀw���y�X���ł��܂����̂ŁA����𒆎~���܂������A�x�����łĂ��č��M�������A�����o�����ɐQ�Ă��܂����B�w���y�X���x�����قڎ���܂������A���ɂ͈�����������A���g���ɏo������͓̂���̂ŁA�v���U��ɓ��L���X�V���鎖�ɂ��܂����B
���L���X�V���܂��ƌ��������̂́A�M�������ĐQ�Ă��܂����̂ŁA�𒎒B�̖ʓ|��w�nj���ꂸ�A����̎��s�L�^�̗���ɂȂ�܂��B
�E���M���q���E�����͉z�~��A���������͊��ɑ傫���Ȃ��Ă���A�P��c���͂P�������m�F�o���Ȃ������̂ő�Ɉ�ĂĂ����̂ł����A�T���R���Ɋ�����тĎ���ł��܂��܂����B�a�̃c�{�X�~����r�}���ɂ��ė^���Ă����̂ł����A�c�����X�~�����牺��Ă��܂��a�ɖ߂�Ȃ������悤�ł��B�c���͐H���̎��ȊO�͉a�̃c�{�X�~�����痣��Ă��鎖���w�ǂł����A�r�}���̃X�~���ł͗c���̓X�~���ɖ߂�Ȃ��m���������Ȃ�܂��̂ŁA�a�̃c�{�X�~���͍��̕����𐅂ŔG�炵���e�b�V���Ŋ����A���~�z�C���Ŋ������a��p�ӂ���ׂ��ł������A�Ǘ��s�[���ŗc���ɂ͉��z�Ȏ������܂����B
�P���匂܂ł̈�A�̎ʐ^���B��̂ɂ͎��s���܂������A��ԑ傫�ȗc���͂U��ɂȂ����l�ł��B���ɂ��R�������A�ؔ��̃c�{�X�~���̒��ɂ��܂����A�ʐ^���B�낤�Ƃ���Ɖ��ɗ����Ă��܂��܂��B�q���E�����ނ̒��ł͌��╨���ɕq���Ȏ�ނɓ���܂��B
�G�]�V���`���E�͑�R���܂������A�T�d�Ɏ��炵�܂����̂ŁA���N��匉��B�H�������҂��Ă��܂������A��N�Ɠ��l�T��ɂȂ��Đ����őS���A����ł��܂��܂����B�����͉����H�S��������܂��A�Ǘ��l�����C��������A���ʂ͂Ƃ������A���������C�����������炪�ł����̂ɂƎc�O�ł��B
�W���E�U���V�W�~�͂S���P�S���ƂP�T���ɉH�����܂������A�����������̂��S������̋C�z�͖����A���̌̂̉H����҂��܂������H�������̂͂T���P���ŁA��ɉH�������͎̂���ł��܂����B�H���̃L�����\�E�܂ŗp�ӂ��ăW���E�U���V�W�~�̎�����܂������A���ŏI���܂����B
��N�̏H���玔�炵�Ă����ʎ����
�C�`�����W�Z�Z���͂T���R����匂ɂȂ�܂����B�W�c�Ŏ��炵�Ă����c�����S���A匂ɂȂ�܂����B�W�c����̗c���̒��ň�ԍŏ���匉������̂͂T���P�Q���ɉH�����܂����B
��N�A���炵��
�X�M�^�j�����V�W�~���S���H�����Ȃ������̂ŁA���N�͑��߂Ɏ��炵�ĐF�X�ȏ�����匂�ۊǁA�H���̏�Ԃׂ����ł������A�Q����ł���ԂɃX�M�^�j�����V�W�~�̋G�߂͍ς�ł��܂��܂����B���Ɏc�O�Ȃ͎̂Ԃʼn��t���̃g�`�̎��ɁA�����A��R�Y������Ă��锤�i��N�̎��тł́j�ł��̂ŁA�s�����������̂ł����A���N�͌�����ł��B
�������A�������̂j������L�n�_�ō̗����ꂽ���𑗂��Ē������炷�邱�Ƃ��o���܂����B�ŏ��͌ʂɎ��炷�����ł������A�S����Z�߂ďW�c�Ŏ��炷�邱�Ƃɂ��܂����B���N�̐H���͗c���̎p�������Ղ��A�ۊǂ��y�ȃL�n�_�ɂ��܂����B��N�̓~�Y�L��H���ɑI�т܂������A�I��c���̑̐F�����ʂ���ɕω����܂������A�L�n�_�ł̎���̏ꍇ�͏I��c���̑̐F�͗ΐF�ł����B
�Q���ɒ�����
�^�C�����c�o���V�W�~�̗c���͂��̌�A�ς�薳���X�X�L�̗t�ɐÎ~���Ă��܂��B�ۊǂ͊�����Ԃ̕����ǂ��Ƃ̎��ł��̂��A���x�̒Ⴂ���Ɏ��X�A���������������ŕ������Ă��܂��B
���H�A��墂�����
�S�}�_���`���E�̗c���𐔓��̂�A�ۊǂ��Ă������A����Ă��Ȃ��c�����S���c���Ă����B�|�̐V���^���Ă��������A�����_�E�����ĉa�s���ɂȂ�A�P���̗c�����T���X���ɋɏ���匂ɂȂ�܂����B�a�s���ł���̕ۑ��ׂ̈ɂ�匂ɂȂ�̂�����悤�ł��B���݂Ɏc��̂R���͍ŋ߂͉a���[���ɗ^�Ă��܂��̂ŁA���Ȃ�傫���������܂����B
�s������k�C���Y��
�I�I�����T�L�̗c�����܂����B�k�C���̃I�I�����T�L�͗��ʂ̉��F�������A��֍s���قǗ��ʂ̐F���������Ȃ邻���ł��B�ߋE�n���̃I�I�����T�L�Ƃǂ̂悤�ɈႤ�̂��H�����ɂȂ�̂��y���݂ł��B
�O�W�N�T���Q�V��
��Ԑ����̑����ʎ����
�E���M���q���E�������T���P�X����匂ɂȂ�܂����B�������^�����A�O匂���E�炵��匂ɂȂ�Ƃ��ɗ������āA�e��̒�ɗ����Ă��܂����B���̂悤�Ȏ��̂��߂ɃI�I�����T�L��S�}�_���`���E��匂��H��������̑����ۊǂ��Ă��܂��̂ŁA�|�̌͂�t�̑���ɃE���M���q���E������匂����܂����B���������������ׁA�����A匂͕ό`���Ă��܂��̂ŁA�����ɐ����ɂȂ�邩�ǂ����͕s���ł��B
�c��͏W�c����̗c�����S���قǂ��܂��B�A�ʐ^���L�^���Ƃ��Ă��܂���̂ŁA���m�ȗ�͕s���ł����A匉��܂łɂ͖������炭�����肻���ł��B
�T���P�W���ɂs���������A��㑺�k����փ��}�L�}�_���q�J�Q���̂�ɍs���ꂽ�A��Ɋ�蓹�����āA��N�A�g�`���Q��
�X�M�^�j�����V�W�~�̗����t���Ă����g�`�̖̉ԕ�i���N�͊��Ɉꕔ�͉Ԃ��J���Ă����B�j����[�Ƃ��ė��Ē������B�T���P�X���̒��ɉԕ��ǂ����ׂ�ƂS���̂��Ȃ�傫�ȗc�������܂����B�̐F�����ΐF�Ȃ̂ʼn�������̂��H�T���̂������ւ�ł��B
�T���Q�O���ɗc��������Ɨc���̑̐F�������Ԗ���ттĂ��܂����B�̒��𑪂�ƂP�O�D�T�_�@�̕��Q�D�T�_�����x�ł��̂ŁA�I��ɂȂ����̂ł��傤���H�T���Q�P���ɂ͍X�ɑ̐F���Ԃ��Ȃ�܂������A�g�`�̉ԕ䂩�痣��鎖�͂���܂���̂ŁA匉��͖����̂悤�ł��B
�T���Q�S���A�̐F�͂T���Q�P���Ɠ������x�̐Ԃ��ł����A�c���͉a�̃g�`���痣��ĕ����܂���Ă��܂��B匉����߂����ł��B
�T���Q�U���ɂ͂P����匉��B�c��̂R���͑O匂ɂȂ�܂����B匉��O�̗c���A�O匋��ɑ̐F���ԐF�ł������A匂��Ԗ���ттĂ��܂��B
����A�������������Y�̗c���̓L�n�_�ň�ėc���̑̐F�͗ΐF�ł������A�ޗnj���㑺�Y�̗c���̓g�`�̉ԕ�ň�āA�����͉��ΐF�ł������A�I��c���͂��Ȃ�Ԗ���тт��̐F�ŁA匂����Ȃ�Ԗ���ттĂ��܂��B��㑺�Y�̗c���͂��Ȃ�傫���Ȃ��Ă���̎���ŁA�������S�������̎���ł��̂ŁA�Ď��炪�K�v�ł����A�H���̎�ނɂ��̐F�͂��Ȃ�ω�����悤�ł��B
�T���P�V���ɋL�ڂ̎ʐ^��u���E�G�L�v�ɋL�ڂ̃~�Y�L�Ŏ���̎ʐ^�ŗc���̑̐F�̕ω�������ׂĒ��������Ǝv���܂��B
�s������
�I�I�S�}�_����匂�������܂����B�e�n�̍����قŃI�I�S�}�_����匂̓W�������Ă��܂��̂ŁA�������ɂȂ��Ă�����ł��傤���A���炽�߂ċ��F��匂̎ʐ^���ڂ��Ă����܂��B
�a�s���ŏ��^��匂ɂȂ����S�}�_���`���E�͂T���Q�O���ɉH�����܂����B�J���U�O�_�@�O�����R�S�_�ł����B�莝���̕W�{�Ɣ�r����ƁA�O�Q�N�T���U���H���̕W���I�ȑ傫���̃S�}�_���`���E���J���V�R�_�@�O�����S�O�_�ł����炩�Ȃ菬�����ł��B���A�W�����ł��̂ŁA������u���E�G�L�v�ɍڂ������ł��B
�k�C���Y��
�I�I�����T�L�͖w�ǂ��E�炵�ĂS��i�R��ʼnz�~�Ɖ��肵�āj�ɂȂ�܂������A���������c�������܂��B�ߋE�n���̃I�I�����T�L��菭���������x���l�ł��B
�@�@
�U���O�W�N�U���V��
�T���P�X����匉�����
�E���M���q���E�����͂U���T���ɉH�����܂����B匂��������ď����ό`���Ă��܂������A��͂荶�E�����̑傫��������Ă��܂����B�W�c����̗c�����S���I��ɂȂ����l�ł��B�W�c����ň�Ԑ����̑����c�����e��̒�ŖZ���Ȃ������܂���Ă������A��Ō���ƃ|���e��̏㕔���ǂ�匉����Ă����B����A���܂�ʐ^���B���Ă��܂���̂ŁA�O匁A匁A�I��c���̎ʐ^���ڂ��܂��B
�E���M���q���E�����̉a�̃c�{�X�~���������Ȃ����̂ŁA�ߏ��̏����u�˂܂Ŏ��ɍs���܂����B�E�c�M�̉Ԃ��炢�Ă��܂����̂Ńg���t�V�W�~�̗c�������Ȃ����T���Ă����
���X�O���q���E�����̗Y���z���ɂ��܂����B���̕ӂŃ��X�O���q���E����������̂͏��߂Ăł��̂Ŏʐ^���B���܂����B�����܂�ɂ͑傫�ȃ����V�W�~�̗Y���������Ă��܂����B���̎�����
�����V�W�~�͉��̂���Ȃɑ傫���̂ł��傤���H��Q�����Ǝv���܂����H���͉��Ȃ̂ł��傩�H
�i�k�C���j
�I�I�����T�L�̗c���͈�ԑ傫���̂͏I��ő̒��S�S�_�i�S�X�_�j�@�̕��T�D�T�_�@�������̂��I��O�̉������ł��B�k�C���̃I�I�����T�L�̐����͂��Ȃ�x���ł��B
�������̂j���ɂ��肢����
���N�V�}�����V�W�~�̗��𑗂��Ē����܂����B�����������̓��}�����A�m�o���A�C���Q���}���A�A�J���K�V���ȂǂɎY�ݕt���Ă���܂����B�H���ɂ��Y���̕ω��ׂ�ꂽ�l�ł��B���̕��̓��}�����A�m�o���A�C���Q���}���A�E�o���K�V�ň�Ă����ł��B���A�z�����ĊԂ��Ȃ��c���͔��ɏ������̂ōs���s���ɂȂ�Ȃ��悤�ɒ��ӂ��K�v�ł��B
�O�W�N�U���P�W��
���N�V�}�����V�W�~�͖w�ǂ̗����U���W���ɛz�����܂����B�����A���}�����A�m�o���A�E�o���K�V�A�C���Q���}���Ŏ�����n�߂܂����B��P�O���Ԏ��炵�����ʂł̓��}�����̐V�肪��Ԑ����������l�ł��B����Ɏʐ^���B��₷���̂����}�����ł��B�����E�o���K�V�ł��B�E�o���K�V�̎�t�͈ӊO�ɍd���A�c���ɂƂ��ĐH�ׂɂ����̂����m��܂���B�m�o���̐V��͓�炩�����ł����A�O�̐H���̓��A��Ԑ����������ł��B����ɗc�����t�̂���̒��Ȃǂɂ���ƌ����Ďʐ^���B��̂������ւ�ł��B�C���Q���}���͈�܂P�O�O�~�̐H�p�i���i�C�t�ŊJ���ė^���Ă��܂����A�������Ղ��c�����������Ԃ͐����������悤�ł��B
�i�k�C���j��
�I�I�����T�L�͈�ԑ傫���c�����U���P�Q����匂ɂȂ�A��Ԗڂ��U���P�U����匉����܂����B
���N�قǖw�NJO���������Ȃ������̂ő��������A���܂����B���������̒ɂ݂�����܂����̗͋����ׁ̈A�܂��Ă��܂������U���P�P���ɂ͖��������֍s�����������Ă݂܂����B��N�͂U���U���ɍs���A�I�o�Z�Z���̗���c���������܂������A���N�̓A�I�o�Z�Z���͌����炸�A�P�|�R��̃X�~�i�K�V�̗c���������܂����B�U���P�U���ɂ͎U�������˂ď��Ă̎��r���n�̎ʐ^���B��ɍs���܂����������ł��X�~�i�K�V�̗�����P�|�R��c���������܂����B�����̎p�͉ߋ����N�łR�x�قnj��������ł����c���͌��\������̂ł��B
�O�W�N�U���Q�W��
���N�V�}�����V�W�~�̗c���͓����A�T�����ɕ������}�����A�E�o���K�V�A�m�o���ŌʂɎ���A�c��̗c���͑S���Z�߂ă��}�����Ŏ��炵�܂����B�������A�s���s���ɂȂ�����A�r���Ŏ��肵�āA匂ɂ܂łȂ����̂̓��}�������S���A�E�o���K�V���Q���A�m�o�����O���ƑS���U���Ȃ������B�c���̓��X�̕ω���m�肽���Ǝv���ƌʂɎ��炷��K�v���L�邪�A�ʐ^���B������A����e�킩��o�����肵�܂��̂ŁA���̏����ȗc���͐H�����痎������A�H�����痣��čs���s���ɂȂ�l�ł��B���̓_�A�W�c����̏ꍇ�͐V�N�ȐH���̋������[���ŗL��Ζw�ǂ̗c����������匂ɂȂ鎖�������ł��B��������}�����œZ�߂Ď��炵���c���͑S���A匂ɂȂ�܂����B
�R��̐H���̓����}�����ň�Ă��c���͂U���Q�O�|�Q�P���ɑS��匉����܂����B���A�U���Q�W���ɏW�c����̌̂��܂ߑS�Ă�匂��H�����܂����B
�E�o���K�V�ň�Ă��c���͂Q����匂ɂȂ�܂����B�U���Q�U����匉������P���͑O匂���匂ɂȂ鎞�̒E�炪�s���S�ł����̂ŁA���������ɂ͉H���o���Ȃ��Ǝv���܂��B�U���Q�W����匉������c���̓��}�����Ŏ��炵���c���ɔ�ז�P�T�ԁA�c�����Ԃ����������ɂ�������炸匂̑傫���͏����������B
�m�o���Ŏ��炵���c���͏I��܂łQ���̗c�����c���Ă��܂������U���Q�U���ɂ͂Q��������ł��܂��܂����B匂ɂȂ�܂Ŏ���o���Ȃ��������A�E�o���K�V�Ŏ��炵���c�����X�Ɏ�����Ԃ����������������͊m���ł��B
�U���Q�R���ɖ��������֍s���܂����B�V�C�\��ł͔~�J�̐���ԂƂ̎��ł����̂ŁA�����炵�ɕ����������̂�����ł����B�������A���n�ɓ�������Ƃ܂��Ȃ��J���~��n�߂܂����B�܊p�����̂ŁA�U���P�P���ɗ��Ĉȗ��̃X�~�i�K�V�̗c���̏����ċA�����ŃA���u�L�̐����Ă���ꏊ�֍s���܂����B�U���P�P���ȍ~�ɎY�����ꂽ�炵���X�~�i�K�V�̏����ȗc�����V���ɂ��܂����B�X�~�i�K�V�̎Y�������͂��Ȃ����l�ł��B
�J�r�������Ȃ����̂ʼnJ�h�肪�Ă�̉��ŋx�e���Ă��āA�T�̃��~�W�̗t���ӂƌ���ƁA
�~�X�W�`���E�̗c�������܂����B�������܂Ŏ��炵���͉̂z�~��̗c�����w�ǂŁA������c������̎���͂���܂���̂Ŏ����A�莔�炷�鎖�ɂ��܂����B�~�X�W�`���E�̗c���͑̒��R�D�T�_�@�̕��O�D�T�_�ł����B�ߋ��A���炵�����̂���z�V�~�X�W�̂P��R���ڂ̗c�����̒��R�_�@�̕��O�D�T�_�ł����̂ŁA���̃~�X�W�`���E�̗c���͑����A�P��I���ł���Ɛ��肵�Ă��܂��B�U���Q�U���ɂ͒E�炵�ĂQ��ɂȂ�܂����B
�s�����琶��R�ō̂�ꂽ
�E���W���~�h���V�W�~�̎����A�̗����鎖�ɂ��܂����B�[�t�C���X�̗̍��͉ߋ��E���i�~�A�J�V�W�~�A�A�J�V�W�~�A�~�Y�C���I�i�K�V�W�~���ɒ��킵�܂������A�S�����s�ł����B��������M�͖��������̂ł����A�|���e��Ƀi���K�V���̎}�����̗��ׂ̈̃Z�b�g�萬�������܂����B�S���Y�ދC�z�͂Ȃ��������A�Q�|�R����Ƀi���K�V���̎}�̕��ɂS���A�Y�ݕt�����Ă��܂����B���̌�Z�b�g�蒼���Đ��������Ă��܂����A�オ�����܂���B�����͖������C�ɂ��Ă��܂��̂ŁA�����A���҂��Ȃ���̗��Z�b�g��`���Ă��܂��B
�������̂j���������哇�̗F�l���瑗���Ă����ꂽ
�q���V���r�A�V�W�~�̗��̈ꕔ�𑗂��ĉ������܂����B�O�S�N�ɂ������Ē������炵�܂������A���c���͏������̂ŁA���Ȃ��J�����L��������܂��B�����̓V���r�A�V�W�~�i��������j�ł������A���̌㖼�̂��ς��q���V���r�A�V�W�~�ɂȂ�܂����B�����Ē��������͂U���Q�T���̒��Ɍ���Ɗ��ɑS���z�����Ă��܂����B�c���͑̒��P�_��@�̕��O�D�P�T�_���x�ŁA�V�ዾ�����ł͌������\�����L��܂��̂ŁA�V�ዾ�̏ォ��X�Ƀw�b�h���[�y�������T���܂����B�H���͂O�S�N�Ɠ��l�ɃV���c���N�T�ɂ��܂����B�c�����������Ԃ͒T���̂ɋ�J���܂����A�ʐ^����肭�ʂ�܂��A���Ƃ������ɐ����ɂ������Ǝv���Ă��܂��B
�@
�V���O�W�N�V���W��
�~�X�W�`���E�͂R��U���ڂɂȂ�܂����B�̒��͖����U�|�V�_�ł����A�̂̓ˋN���傫���Ȃ�܂����̂ŁA�g��ʐ^�Ō���Ǝ��ۂ��傫�������܂��B�~�X�W�`���E�̗c���͉z�~��E�炵�ďI��c���ɂȂ�܂����A���ɂR��U���ڂł��̂ʼnz�~���ɂ͂��Ȃ�̊��Ԃ�����܂��B�I��c�����T��Ƃ���Ήz�~�c���͂S��ł����A�͂����ĉ���ʼnz�~����̂��H������y���݂ł��B
���̂P�O���Ԃ�
�q���V���r�A�V�W�~�̗c���͂S��ɂȂ�܂����B��ς�鎞�̉����ƒE��͒E��k���m�F�o����Ίm���ł����A����̎���ł͈ꕔ�̗c���̒E��k���m�F�ł��������ł��B�������A�����ɉ������̗c�����ʂɎ��炵�܂����̂ŁA����炪��Ăɉ����ɓ��蓮���Ȃ��Ȃ�����A�E�炵�ė�ς�蓮���o���܂��̂ŁA�قڊm���ɒE�炪�m�F�ł����Ǝv���Ă��܂��B���A�������͑̒��������k�ތX��������A�E���͋}�ɑ傫���Ȃ�܂��B�̌^��̐F����������ɓ����������قڊm�F�o���܂����B
�U���Q�S���ɎR�钬��
�E���i�~�W���m���̎����̂�A�`�a�~�U�T�ō̗����܂����B�E���i�~�W���m���͉�������炵�Ă��܂����A�Q���ځi�X�����{���H���j�̎���͏��߂Ăł��B�c���͂V���Q���ɛz�����ĂV���W�����݁A�����̑����c���͂Q��ɂȂ�A���͉��������w�ǂł��B
�V���P���̌ߌォ��_��R�֍s���܂����B�ȑO����R���t�߂ɂ̓q���E�����ނ����ł��܂������A�c�}�O���q���E�������~�h���q���E�������낤�Ə���ɍl���������Ă��܂����B����������A�E�c�{���������A�炢�Ă���ꏊ������A�E���M���q���E�����ƃI�I�E���M���X�W�q���E�������z���ɗ��Ă���̂������܂����B�E���M���q���E�����͐̂͑�R���܂������A�ŋ߂͖ő��Ɍ������܂���B�ʐ^���B�����Ǝv���܂������A�������Ă�����Ԃ��o���Ă���̂����Ȃ菝��ł��܂����̂Ō�����܂����B����
�L�A�Q�n��I�I�`���o�l�Z�Z���������z���ɗ��Ă��܂����B
�V���T���Ɏ��r���n��
�I�I�����T�L�̗Y���z���ɗ��Ă���̂������ʐ^���B��܂������A�Ȃ��Ȃ���肭�ʂ�Ȃ����̂ł��ˁB�����J�����̕������Ȃ�������Ȃ��̂ł��傤���H����Ƃ��R���p�N�g�f�W�J���ł͖����Ȃ̂ł��傤���H
�O�W�N�V���P�W��
����A
�~�X�W�`���E�̒E����������Ă��܂��܂����B�V���P�T���̗c���̗l�q�������̂悤�Ȃ̂ŁA�����ɓ����E��k�ׂ�K�v���������̂ł����A���ׂ��ɕ��̑|�������Ă��܂��܂����B�������A�����O��̗c���̓ˋN�⓪���̑傫������A�S��ɂȂ����ƍl���Ă��܂��B�����A�����Ɏ��炵�Ă���Ɗm�F���₷���̂ł����A�ŏI�m�F�͍Ď���܂Ŏ����z���ł��B�������قڊԈႢ�Ȃ��Ǝv���܂��̂Ŏʐ^�̐����͂V���P�U���ɂS��ɂȂ����ƍl���L�ڂ��Ă���܂��̂ŁA�������������B
�q���V���r�A�V�W�~�͑唼�̗c�����V���P�P����匂ɂȂ�A�T����̂P�U���ɂ͉H�����܂����B�P�V���̒��A�w�Ǔ����ɂȂ荡�ɂ��H����������匂����܂����̂Ŏʐ^���B���Ă���ƁA�H�����n�܂�܂����B���̎��̎ʐ^���ڂ��܂����̂ł����������B
�E���i�~�W���m���͗\�z�ʂ菇���Ɉ���Ă��܂��B���̗c���Ɠ����Y�n�̉z�~�c���͂U��I��ł������A���Ð�Y�i�N�P���j���V��I��ł������A���̗c���͂T��I��̂悤�ȗ\�������܂��B�P�W�����݉������̗c���͑̒��P�R�D�T�_�@�̕��Q�_�ł����A�u���E�G�L�v�ɍڂ��Ă���܂������Y�n�̉z�~�c���͂S��P���ڂ̑̒����W�_�@�̕��P�D�T�_��ƈ��菬���Ȋ����ł��B�ܘ_�A�̍�������܂��̂ŁA�����ɂ͉������̗c���̕��ϒl�Ŕ�r����ׂ��Ȃ̂ł��傤���I
�����E�L���E�E���i�~�W���m���̒���c�����s������Ⴂ�܂����B�E���i�~�W���m���̗c���Ɣ�ׂ�Ƒ̐F�͏��������ł��B�H���̓`�W�~�U�T���g���܂����B
�N���{�V�Z�Z���͂P�X�V�R�N�ɐΊ_���Ŕ�������A���̌㎟��ɖk�サ�A�ŋ߂ł͓�F�ł��p��������悤�ɂȂ��������ł��B�������s�̂j������^�C�����c�o���V�W�~�̕��z�g��ׁ̈A�V�o�n�M�̕c��A���ɓ�F�֍s���̂ŃN���{�V�Z�Z���̗����̂�邩������Ȃ��Ƃ́A���b�����肢���܂����B�����ɂ����͋���肾�����Ƃ̎��ł����A����c���𑗂��Ē����܂����B�H���͞��q�ނł�����A�w�ǐH�ׂĂ���邻���ł����������ł̓A���J���V�����������ł��̂ŁA�A���J���V���g���܂����B�ŏ��A�ߏ��̉ԉ��ׂ܂������A���J���V�͖ܘ_�A�V�����`�N��J���m���`�N�������炸�ł�܂������A���̉��|�X�łR�틤�A�����Ă���̂��������S���܂����B���A����A�^�C�~���O�������ėc���̎ʐ^���B���Ă��܂��A�H���̗t���d���̂ŁA�����J���鎞�ɗc�������������Ȃ̂ŁA�c�����o�ė������ɎB�����Ǝv���Ă��܂��B
�V���P�S���ɐ_��R�֍s���܂����B�R���t�߂ɂ̓q���E�����ނ���ь����A�V�N�ȃW���m���`���E�����ނ炩���яo���܂��B���ɑ̐F�̂������W���m���`���E�̎�����яo�����̂ŁA�悭����ƃI�I�q�J�Q�ł����B�܂�������ȏꏊ�ɃI�I�q�J�Q������Ƃ͎v���Ă����Ȃ������̂ŁA�����܂����B�����A�R�[�̎��n�̃X�Q�Ŕ��������̂��R���܂Ŕ����̂��낤�Ƒz�����Ă��܂��B
�_��R��
�N���V�W�~������ƕ������̂ŁA�����̂��ĎY�������A�N���I�I�A���̑���ɂȂ��Ĉ�ĂČ������ƍl���܂����B�܂��Y�������ɂ́A�N���I�I�A�������C���̂�A�A�u�����V�t���̃X�X�L���N�k�M�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�āA�������Ă��܂������A�̐S�̃N���V�W�~�̎p��S�����鎖���o���Ȃ������B
�����̂V���P�T���ɂ����肸�ɐ_��R�֍s���܂����B���͎Ԃ��牺��Ėw�Ǖ����K�v�������ƌ��������b�g������A�ʖڂ��Ƃŏo�������̂ł��B�������A�̐S�̃N���V�W�~�̎p�͂��̓�������܂���B���߂ċA�낤�ƁA���ނ��ĕ����Ă���ƁA�n�ʂ���P�O�a�قǂ̍����̑��ɃN���V�W�~�̎����Ƃ܂��Ă��܂����B�������H�������ĂŖ�����ł����B�܊p�A���������܂������A���̖��͂��Ȃ��܂���ł����B�A���A�N���V�W�~�����鎖�͂��̖ڂŊm�F�ł��܂����B���̖������Ȃ���ɂ̓N���V�W�~�̌̐��̑������ꌧ�܂ő����̂��K�v������̂ł��傤���H
�O�W�N�V���Q�W��
�V���P�W���̓��L��
�~�X�W�`���E�̂R������E��k���������肵�āA���̑|���̎��Ɏ̂ĂĂ��܂������������܂������A���̌�A�H����V�����̂Ɏ��ւ��鎞�Ƀ��~�W�̗t�̏�ɓ����E��k���t���Ă���̂������܂����B�X���ȏ�̊m���łV���P�U���ɂS��ɂȂ����ƍl���Ă��܂������A����łP�O�O�l�ԈႢ���������m�F�ł����S���܂����B�c���́i�S��P�R���ځj�ɂȂ�܂������ڗ������ω��͂���܂���B�����Č����Α̕��������傫���Ȃ��������ł��B
�E���i�~�W���m���́i�S��P�O���ځj�ɂȂ�܂����B�z�~�c���̎���Ɣ�ׂ�ƉĊ��̎���͔�r�I�A�����������̂ŏ������ł��������̕ω����y���݂ł��B
�����E�L���E�E���i�~�W���m���͂Q���A�����Ď��璆�ł������A�P��������ɑ�����������ł��܂��܂����B�ʐ^���ڂ��Ă���c���������C���ő̕����ׂ��Ȃ����悤�ł��B���߂Ă̎���ł��̂ł悭������܂��A�c���̑̐F�����������悤�Ȋ����ł��̂ŐS�z���Ă��܂��B��p�H�̃`�a�~�U�T��H�ו������Ă��܂����A�`�a�~�U�T������Ȃ��̂ł��傤���H���݂Ƀ��G���}�E���i�~�W���m���̓`�a�~�U�T�ŗǂ��������܂����B
���N�����������ł͊���
�N���}�_���\�e�c�V�W�~���������Ă��܂��B�j�����̗����ꂽ���𑗂��Ē����܂����B��N�̏H�ɂ������Ē������炵�܂������A���̎��A�H���̃\�e�c�̐V����t�̓��肪�o�����H���������Ē����܂����B����ȗ��\�e�c�̐����Ă���ꏊ�ɋC�����Ă��܂����̂ŁA���N�͐H���̊m�ۂ͏o���������ƈ��S���Ă��܂����B�������A���ۂɌ��n�֍s���ă\�e�c������ƍd���Z�ΐF�̗t����ŁA�V������������炸�������肵�܂����B�\�e�c�̎�t������o���Ȃ����̓C���Q���}���ƃ\�e�c�̎��̒����Ŏ��炷�����ł������A���ƈꏏ�Ƀ\�e�c�̐V����t�������ĉ��������̂ŁA�c���B�ɂ͑�p�H�ł͂Ȃ��A���������̃\�e�c��^���鎖���o���܂����B
�V���P�X���ɓ����������͂��̓��̓��ɖw�ǂ��z�����܂����B��N�̏H�̎���ł͛z����P�R�����x��匂ɂȂ�A���̑����ɋ����܂������A����̎���ł͂V���Q�U�����ɖw�ǂ̗c����匉����܂����̂ŁA�z����V�����x��匂ɂȂ�܂����B���̒��q�ł͏H�܂łɂ͑唭���������ł��B�A���H���̐V�莟�悩���m��܂���B
���a�̎��o�Ǐ�͂��Ȃ�ǂ��Ȃ�܂������A�����ł�������ċC���ŊO�o�͖w�ǂ��Ă��܂���B�������A���N�A������������ŁA�����o���Ă��Ȃ��z�\�o�Z�Z����A���炵�����Ǝv���V���P�V���ɓ�R��܂ŏo�����܂����B�I�I�q�J�Q�̎Y�n�̋߂��ł��̂ŁA���C�Ŕp�c�̌l��������Č��܂����B�U�����{�Ȃ琔���͎p��������ꏊ�ł����A���ɏ����̂łP���p�����������ł��B���ĖړI�̃z�\�o�Z�Z���͂Q���A�p�����܂������Y�炵�����^�ł����B���������Y�̔��荢��ł����̂ňꉞ�̂��ċA��̗������݂܂����B�ł��A��͂�Y�������炵�����͎Y�݂܂���ł����B�Y�ɗ����Y�߂ƌ����Ă������ł��ˁB���z�Ȏ������܂����B
�@
�@
�W��
�O�W�N�W���W��
�~�X�W�`���E�͖����A�a�̃��~�W��H�ׂĂ��܂����w�Ǒ傫���͕ς��܂���B�P��c�����̏W���܂����̂łP����Ԃ͕s���ł����Q����Ԃ͂V���ԁA�R����Ԃ͂P�R���ł����B�S����Ԃ͂W���W���łQ�S���o���܂����������̋C�z�͗L��܂���B�z�~�܂ł̂S�����ԂɂT��ɂȂ�̂ł��傤���H���̂܂܂S��ʼnz�~����̂ł��傤���H
�E���i�~�W���m���͈�Ԑ����̑����̂̎ʐ^���ڂ��Ă��܂����A���̗c�����i�S��P�S���ځj�ɑO匂ɂȂ�܂����B�V�W�~�`���E�ނ͂S��I��ł����A�W���m���`���E�ނ͂T��ȏオ�I��ł��B������L�ڂ��܂������ߋ��Ɏ��炵���E���i�~�W���m���͗c���̏I��͂T�`�V��ł����B�E��̌������ƌ��������l�����܂����A�E���i�~�W���m���̒E��O�̉������Ԃ͒����A������Ԃ����m�ɕ�����܂��̂ŁA�������̉\���͒Ⴂ�ƍl���Ă��܂��B����ɉ����Ė����A�c���̎ʐ^���B���Ă��܂��̂ōĊm�F�ׁ̈A�ʐ^�����Ă݂܂����������̉\���͗L��܂���ł����B
����A���̗c���ȊO�ɂT���̗c�����ʂɎ��炵�Ă��܂��̂ŁA���̂T���ׂČ��܂����B�P���͍���i�W���V���j�Ɂi�S��P�V���ځj��匂ɂȂ�܂����B���̂S���͂W���W�����݁A�P�����i�S��P�T���ځj�A�Q�����i�T��U���ځj�A�c��̂P���́i�S��X���ځj�ʼn������ł��B���̓��L�L�ړ��ɂ͌��ʂ��o�Ă��܂����A�ʂɎ��炵���U���̓��R���͂S��I��̗l�ł��B�R�����̒E������������͂���܂���̂ŁA�E���i�~�W���m���̑�Q���̗c���ɂ͂S��I��̗c��������悤�ł��B
�����������̂ŐS�z���Ă���
�����E�L���E�E���i�~�W���m���͂W���Q���ɒE�炵�ė�ς��܂����B�䂪�Ƃ֗��Ă���Q�x�ڂ̒E��ł��B�W���W�����݂͑̒��P�P�D�T�_�@�̕��P�D�T�_�Ə����傫���Ȃ�܂����̂ŁA�������S�ł��B
�������̂j������V���ɑ����Ē�����
�N���{�V�Z�Z����匂͂W���Q���ɉH�����܂����B���̗��ʂɍ����_������̂����O�̗R���ł����A�ߋE�ł͗��ʂɍ����_�̂���Z�Z���͂��܂���̂ŁA���͂������܂��B
�W���T���ɂ͗��Ǝ��c�����ēx�A�����Ē����܂����B���c�����ԐF�ł���̂͐}�ӂȂǂŒm���Ă��܂����̂ŁA���قNj����܂���ł������A���ɂ͋����������܂����B���a�P�_�ȏ�ō��Ɣ��̎Ȗ͗l�ŁA�����A�����̂��闑�ł��B���͐���g�債�Ă����������B
�ŋ߂̏����ɂ͂�������ċC���Ŗ�O�ɂ͖w�Ǎs���Ă��܂��A�w�Ǖ����Ȃ��čςސ_��R�ւ͂V���R�O���ɍēx�s���܂����B����ƃN���V�W�~�̎����̂莝���A���āA����̃E�o���K�V�̐V��ɃA���}�L�̕t�����̂�T���A�N���I�I�A���𐔕C�̂�A�e��̒��ɓ���Ă����܂������A�Y���͂��܂���ł����B��͂茻�n�̃L�W���~�Ȃǂ̕t�����X�X�L��G��T���Ď����A��Ȃ���ΑʖڂȂ̂����m��܂���B����茻�n�Ŏ����Y�����Ă���̂�������̂���ԗǂ������ł��B
�O�W�N�W���P�W��
�~�X�W�`���E�͉a��H�ו������Ă��܂����w�Ǒ傫���Ȃ炸�S��R�O���ڂ��z���܂����B���̂܂܂S��ʼnz�~����̂��ƍl���Ă��܂����B�������A�����i�W���P�W���j�ɗc��������ƂS��R�S���ڂɉ����ɓ����Ă��܂����B���̗ʂ������Ă��܂��̂ŁA�����ɊԈႢ����܂���B�����ɂ͂T��ɂȂ��Ă��锤�ł��B
��ԑ���匉��i�W���Q���j����
�E���i�~�W���m����匂��W���P�O���ɉH�����܂����B���������W�c�Ŏ��炵�Ă���匂��W���P�S���[�P�W���̊Ԃɐ����A�H�����܂����B���炵���c���͂قړ������Y������z�������c���ł����A�����I��c�������܂��̂ŁA�H���̎����͂��Ȃ�̂�����ł܂����B�ʏ�A���s�R�钬�̃E���i�~�W���m���̂Q���̔����͂W��������X�����{�ƌ����Ă��܂����A���̎���Ɠ��������ɉH�������Ƃ���A���Ɍ��n�ł͔������Ă��锤�ł��B�ʐ^�̐����͏W�c�Ŏ��炵�Ă���匂��W���P�W���ɉH���������̂ł��B
����A���Ɏc�O�Ȏ����Q���L��܂����B����̓����E�L���E�E���i�~�W���m���̗c���������ƃN���{�V�Z�Z���̗c���ɓ�����ꂽ���ł��B
�܂�
�����E�L���E�E���i�~�W���m���͑召�A�Q���̗c�����V���X���ɒ����H���̓`�a�~�U�T�ň�Ă܂������A�傫�ȗc���͂���̒����k�݂V���Q�T���Ɏ��S���܂����B
�c��̏����ȗc����������L�ɍڂ��Ă��܂����B�����ȗc�����ʐ^�Ō��Ē����Ă���܂��悤�ɖw�Ǒ傫���Ȃ�܂��V���P�S���ƂW���Q���̂Q��̒E������Ă��܂��̂ʼn��Ƃ�匂܂Ŏ��炵�����Ǝv���Ă��܂����B�������A���̗c�������������Ɋ�����тĎ���ł��܂��܂����B�ꉞ�W���P�R���܂ł̎ʐ^���ڂ��ďI�������Ē����܂��B
�N���{�V�Z�Z���̓A���J���V��H���C�ɐ������Ă��܂����B�W���P�O���ɂ͒E�炵�ė�ς��܂����B�W���P�P���ɂ͏����傫���Ȃ�̐F�̐Ԗ������������Ȃ�A���悢�悱�ꂩ�炪�y���݂ł������P�Q���̒�����Ǝp�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�H���̕r�}���Ɨc����e��ɓ���X�g�b�L���O�ŊW�����Ă��܂������A�X�g�b�L���O�̌��Ԃ��瓦���o�����l�ł��B�������A���ɂƂ��Ă͗�����̎��炪�{���ł��̂ŗ��̛z����҂��Ă��܂����������̂������A�����̕s�����P�R���o���Ă��z�����Ă���܂���B����͉������̗c���ƒE���̎ʐ^���ڂ��܂����B
����̒�ɂQ�b�قǂ̃A���J�V�̖�����
�����T�L�V�W�~���Z�ݒ����Ă��܂��B�����b�������̎p��ǂ����܂��̂ŁA�A���J�V�̐V��ׂ�Ɛ����̗c���Ɨ���������܂����B�����T�L�V�W�~�̌ʎ���͖������Ă��Ȃ��̂��v���o�������̂��Ă鎖�ɂ��܂����B�R���̂����̂ł����z�������̂͂P�������ł����B�z����Q���Ԃقǂ͏������ď�肭�ʂ��Ă��܂��A�������������B
���Ԃ͑��ς�炸�����ł����A���͋v���U��ɗ������H�̋C�z���������܂����B�����ɕ����ĂQ�T�ԂقNJO�o���Ȃ��������A�W���P�W���ߌォ�玺�r���n�֍s���Č��܂����B�������Ȃ�̏����ł����A��N�H���[�܂��Ă���p����������A�T�M�}�_�����Q�����܂����B�A�T�M�}�_���͂����H�������Ă���̂ł��傤���H
���������r�֍s���ƃX�~�i�K�V��A�I�o�Z�Z���c�������Ȃ����ׂČ���A���u�L�̖ɂ̓X�~�i�K�V�̂Q��c�����Q���������܂����B�������A������܂ŗc���������悤�ȐV������̑�����R����܂����B�I�ɂł��P��ꂽ�̂ł��傤�B
�O�W�N�W���Q�W��
�S����ԂR�S���Ԃ�
�~�X�W�`���E�͂W���P�X���ɂ���ƂT��ɂȂ�܂����B�W���Q�W���łT��P�O���ڂ̗c���͕��s���̑̒��ł����P�P�D�T�_�ɂȂ�܂����B�z�~�܂łɂ�����x�E�炷�邩�ǂ������y���݂ł��B
�����T�L�V�W�~�̗c���͂Q��̒E����m�F�ł��܂������A�����P��̒E����m�F�o���Ȃ������B���̋@��ɂ͂T���قǎ��炵�āA����A�E��̊m�F�����������̂ł��B
�c���͂W���Q�S���i�z����P�U���ځj�ɂ͎���e��̒�ŁA�̂̑O�ƌ�Ɏ���O匂ɂȂ�܂����̂ŁA�H������菜���A�e��̏㕔���i�C�����X�g�b�L���O�ŕ����Ă��������A�c���͓����������Ԃ��瓦�������܂����B����͂����ւƒT���܂�����A����e��̒�ɕ~�����h��Ȑ܂荞�ݍL���̗��ʂőO匂ɂȂ��Ă��܂����B匂��L�����ڗ����܂����������������B
�E���i�~�W���m���̌ʎ���������U���̗c���͍Ō�̂P�����W���Q�T���ɑO匂ɂȂ�܂����B�U���̓��A�P����匉��o�����Ɏ��ɂ܂������A���̗c���́i�S��P�X���ځj�ő̐F���������ɂȂ�A�i�S��Q�O���ځj���畳�����Ȃ��Ȃ�܂����̂ŁA匉�����̂��Ǝv���Ă�����i�S��Q�X���ځj�Ɏ��S���܂����B�������A�c���͐���ł���i�S��Q�O���ځj����匂ɂȂ����Ɛ��肵�Ă��܂��B���̗c���̏I����S��Ƃ���U���̓��R�����S���匂ɂȂ�A���̂R�����T��I��ł����B�E���i�~�W���m���͎Y�n�⎞���ɂ��I��ω����Ղ���ނ̂悤�ł��B
�W���Q�Q���ɎR�钬�̃E���i�~�W���m���̎Y�n�֍s���Č��܂����B�������͏��Ȃ����Q�������p�����܂����B����Ŏ��炵���̂́i�W���P�O���j�P���A�i�W���P�S���j�P���A�i�W���P�T���j�Q���A�i�W���P�V���j�R���A�i�W���P�W���j�Q���A�i�W���Q�P���j�P���A�i�W���Q�R���`�W���Q�W���j�W���A���H�����A�c���匂͂Q���قǂł��̂ŁA���R��Ԃ�菭���H���������悤�ł��B���̎��猋�ʂ́u���E�G�L�v�̃E���i�~�W���m���̃y�[�W�ɏڍׂ��L�ڂ������ł��B
�܊p�ł��̂œ�R��܂ő����̂��I�I�q�J�Q�����ɍs���܂����B���Ȃ�������Ȃ�܂����������p�͏��Ȃ��P���A���������ł��B���ɂ̓I�I�`���o�l�Z�Z���A�L�}�_���Z�Z���̐V�N�ȑ�Q���̎p���������܂����B
�W���Q�T���̓V�C�\��ł͌ߌォ��܂ʼn�J������Ƃ̎��ł����̂ŁA�ߏ��
�����������琶��R�֏o�����鎖�ɂ��܂����B�Q�����Ԃ�ɃA���u�L�̃X�~�i�K�V��A�I�o�Z�Z����T���Ă݂܂����B�X�~�i�K�V�̑��͂��Ȃ肠��܂������A�S���A�Ƃł����B�H���߂Â��I�̐��������Ă���̂��A�A���u�L�̎���ɂ��I�������A�X�~�i�K�V�̗c�����I�̉a�ɂȂ����\������ł��B�A�I�o�Z�Z���͉������̂Q��c�����P���������܂����B
���̗t�ɂ̓R�`���o�l�Z�Z���̗c�����ޕ������ɑ����Ă��܂����B���������̗t�����Ă���ƃI�I�`���o�l�Z�Z����匂��t�̗��ʂɂ��Ă��܂����B�I�I�`���o�l�Z�Z���͂��̕t�߂ł��܂茩���������͂���܂���̂ŁA�����A��H����҂��ɂ��܂����B�i�W���Q�V���ɉH�����܂����B�j�V�N�ȃ_�C�~���E�Z�Z�����Q���ڌ��A���}�C���̗t�ɑ���ꂽ���c���̑�������܂����B���ɖڌ��������̓A�T�M�}�_���A�N���q�J�Q�A�����L�A�Q�n�A�N���A�Q�n�Ȃǂł����B
�@
�X���O�W�N�X���W��
�~�X�W�`���E�̗c���͐Î~���͋����t�߂��R�̂悤�ɏ�ɂ����Ă��܂��B�Î~��Ԃł�.�̒��͒Z���Ȃ���s���͑̒��������Ȃ�܂��̂ŁA���ɂ�葪��l���P�_�`�Q�_���x����l�ł��B�ʐ^���B�鎞�͖��邢�ꏊ�֗c����u���܂��̂ŁA�w�ǂ̏ꍇ���������̒��͒��߂ɂȂ�܂��B������肵���������ł����A�ʐ^���B������̒��̑���ɂ͑S������܂��B
�X���P���̓V�C�\��ł͌ߌォ��܂łɂ킩�J�Ƃ̎��ł����̂ŁA�ߑO���A���r���n�֍s���܂����B�P�T���Ԃ�ɃA���u�L�ׂ�ƃX�~�i�K�V�̂Q��c�����V�`�W���A�S��A�T��c�����P���������܂����B
�T���X�x���̗t�������
�����^�e�n�̗����Q�����Ă����B�v���U��Ɏ��炵�Ă݂悤�Ǝv�����������A�鎖�ɂ��܂����B���͂X���R���ɛz�����A���݂R��ɂȂ�܂����B�����^�e�n�̗c���͐����ɂ�̐F���ω����܂��̂�匉��܂Ŗ����A�ڂ������܂���B
���r���n�ł͒�����
�S�C�V�V�W�~�������܂����B���r���n�͎����߂��̂ŗǂ��s���܂����R�N�O�i�Q�O�O�U�N�j�ɂP�������������ł����B�����R�N�O�ɐ���R�̊z�c�W�]��t�߂ŁA���ݏZ�̃x�e�����̕�������ŏ��߂ăS�C�V�V�W�~���P�������A�̏W���ꂽ�Ƃ̘b���܂������A����R�n�ł͒������l�ł��B�S�C�V�V�W�~�̔��Ă����Ă���ƂƂĂ��������̈ړ��͕s�\�Ɏv���܂����A������ˑR����A�܂��p�������Ȃ��Ȃ�̂͑S���s�v�c�ł��B����͖����H�������Ă炵���V�N�Ȍ̂ł������ʐ^���B���Ă���Ԃɓ����Ă��܂��܂����B�t�߂̍��̗t���ׂ�ƁA�T�T�R�i�t�L�c�m�A�u�����V�̂����Ղ炵�����������t���Ă��܂��������A�u�����V���a�̎p��������܂���ł����B�������S�C�V�V�W�~��匂��P�����܂����B����匂͂X���R���ɖ����ɉH�����܂����B
����̒��
�N���A�Q�n�̎������A�Y���ړI�̒���s�Ń~�J���̖�J���^�`��T���Ă����̂ŁA�߂܂��ă~�J���ō̗�������\�����Y�݂܂����B�P���݂̂��ʂɎ���A���͂܂Ƃ߂ďW�c�Ŏ��炵�܂����B���͂W���Q�O���ɛz�������̂ł����A�����ɂ͍ڂ��Ă��܂���ł����B�������X���T���ɂT��ɂȂ����c���͗ΐF�̏I��ł͂Ȃ��A���̕���̗c���ł����B��ɂ�����鎄�Ƃ��Ă͐������������Ǝv���W���Q�O���ɑk���Ďʐ^���ڂ��܂����B�ʐ^�ɂ͊e��̓����E��k�Ɖ������̎ʐ^���ڂ��Ă��܂��B��N�̏H�ɂ̓i�~�A�Q�n�̏I��V��ƌ����P�[�X������u���E�G�L�v�ɏ悹�܂������A���̃N���A�Q�n�̏ꍇ�͂ǂ��Ȃ��ł��傤���H����A�ʎ���͂��̂P�������ł������A�������ʂɎ��炵�Ă�����ǂ��Ȃ����̂��Ǝv���Ə����c�O�ł��B
�O�W�N�X���P�W��
�~�X�W�`���E�́i�T��R�P���ځj�ɂȂ�܂������A�a��H�ׂ�ʂ͏��Ȃ��A�傫�����w�Ǖς��܂���B�T��̂܂܉z�~����̂ł��傤���H
�N���A�Q�n�͂U��ŗΐF�̏I��c���ɂȂ�A�X���P�W���ɂ͑O匂ɂȂ�܂����B����͂P�������̌ʎ���ł������������炵�A�������t�A�āA�H�ƕς��ĉ���I����m�F����Ɩʔ����Ǝv���܂��B�ӊO�ɏI��T��ȊO�̃P�[�X���x�X�L�邩������܂���B
��O�ŃT���g���C�o���̗��ʂɂ���
�����^�e�n�̗c����������Ɖ��F�A�ԐF�A�����ۂ��̐F�ȂǐF�X�̗c�������܂��B�ŏ��͌̕ω����Ǝv���Ă��܂������A�ʂɎ��炵�Ă݂�Ɨ�ɂ���đ̐F���ω�����悤�ł��B�̂ɂ�葽���̕ω��͂���܂����P��c���͍��F�A�Q��c���͍��F�̕������w�ǂňꕔ�ɉ��F�̕������ł��܂��B�R��c���͏��X�ɉ��F�̕����������Ă��܂��B�S��͉��F�̕��������X�ɐԂ��Ȃ��Ğ�F�ɂȂ�܂��B�T��͐ԍ����̐F�ɂȂ�܂��B�W���̓��L���獡���̓��L�Ɋe��̎ʐ^���ڂ��Ă��܂��̂ł����������B
�X���P�O���ɐ_��R�֍s���܂����B�ړI�̓E���M���q���E�����ƃI�I�E���M���X�W�q���E�����̎����̗��p�ɍ̂鎖�ƃz�\�o�Z�Z�����X���ɂ��������Ă��Ȃ���������ׂł��B���̕ӂ̃z�\�o�Z�Z���͂X���ɂ��������锤�ł����p�͑S�������Ȃ������B�t�߂̃X�X�L�����ׂĂ݂����z�\�o�Z�Z���̑��炵�����̂�������Ȃ������B�q���E�����ނ̓c�}�O���q���E�����A�~�h���q���E�����A�E���M���q���E�����̗Y�A�I�I�E���M���X�W�q���E�����̗Y�̎p���������܂������ړI�̎��͂��Ȃ������B�R���t�߂ɂ̓W���m���`���E�̎��������A���ł��܂����B�W���m���`���E�͒��N���炵�Ă��܂����A�����z�����Ȃ������莄�̑̒������������肵�āA���܂���匂�������������܂���̂ŁA�����̂��č̗����鎖�ɂ��܂����B
�A��ɉ��������Ė������֊��܂����B�ޗǕt�߂ł͔����s�⋞�s�{�R�钬�ȂǂɃE���i�~�W���m���̎Y�n������܂����ޗnj����ł̓E���i�~�W���m���̎Y�n��S�����������͂Ȃ������B�������Q�O�O�U�N���s�̂r�o�h�m�c�`�i���咱�����s�j�ɂ��Ɩ������ɎY����Ƃ̕�����A�܂��ŋ߁A�ޗǂ̂s������E���i�~�W���m���𖾓����ō̂����Ƃ̘A������������ł��B�s�����畷�����ꏊ�֍s���ƃq���E���i�~�W���m���ɍ������āA�E���i�~�W���m�������ł��܂����B���ɐ����͂���Ă��܂������A���͑S�����炵���ȒP�Ɍ�����܂����B
�X���P�P���ɂ͋����R�֍s���܂����B�ړI�̓T�J�n�`�`���E�̎����̂�̗����鎖�ł��B���N�O�Ɏ��炵�āu���E�G�L�v�ɍڂ��Ă��܂����A�ʂɎ��炵�����͖��������̂ŁA����A�ʎ�����������ł��B�O�炵���o���ł̓T�J�n�`�`���E�̗c���̑̐F�͍��F�ł������F�ɂȂ鎞��������A�܂����F�ɂȂ�匉����܂��B�ʂɎ��炵�ĉ���Ŕ��F�ɂȂ�̂��m�F�������Ǝv���Ă��܂��B
����t�߂ɂ�
�q���L�}�_���q�J�Q���������Ă��܂����A�������x���̂łR���قnj������������ł��B���������̗t�ׂ�ƁA���c���Ɨ���������܂����B���͈ȑO�ɍ̗����܂��������܂��z�������A�P�O�����{�ɍ̏W�����c�������炵�A�u���E�G�L�v�ɍڂ��Ă��܂��B����͐���A���܂��z�����ė~�����Ɗ���Ă��܂��B
�O�W�N�X���Q�W��
�~�X�W�`���E�́i�T��S�P���ځj�ɂȂ�܂������傫���͖w�Ǖς�炸�A�E��̋C�z������܂���B���Ȃ�������Ȃ��Ă��܂����̂ŁA�T��ʼnz�~�������ł��B�z�~�c�����̏W���Ď��炵���o���ł͉z�~�シ���Ɉ��A�E�炵�A���~�W�̐V�t��H�ׂđ傫���Ȃ�匉����܂��̂ŁA���̗c���͂U��I��̉\�����������ł��B
�U��I�����
�N���A�Q�n�ƌʎ�������ė�Ƃ̑̐F�̕ω����ʐ^�ɎB����
�����^�e�n�́A�����Ƃ�匂ɂȂ�܂����B�������āu���E�G�L�v�ɍڂ��܂����̂ł����������B
�O�Q�N�ƂO�S�N��
�R�~�X�W�����炵�ʐ^���u���E�G�L�v�ɍڂ��Ă��܂����A�O�Q�N�̎���͂X������O�R�N�̂S���܂ł̉z�~����ł������W�c����ł����̂ŁA���m�ȒE��͕s���ł����B�������A���̌�O�S�N�W���Ɍʎ��炵���S���̗c���͑S�ĂT��I��ł����B����A�W���Q�R���ɛz�������c�����ʂɎ��炵�Ă݂܂�����Q���̏I��U��ł����B�����̗c���͊���匉����܂����̂Ŏb���҂Ăΐ������H������Ǝv���܂��B�H�ɐ��炷��c���͂U������̂ł��傤���H�z�~����c�����U��I��Ȃ̂ł��傩�H����̎ʐ^�͊���匂ɂȂ芮�����Ă��܂��̂ŁA������������āu���E�G�L�v�ɍڂ��܂����B
�ޗnj��������Y��
�E���i�~�W���m���̎����Y�����܂����̂Ŏ��炷�鎖�ɂ��܂����B���N�̏t�܂ŕς��f���̂��Ȃ��ΐF�̗c���̎ʐ^���ڂ��܂����������������B�����g�͉���ʼnz�~���I�����ɋ������L��܂��B
�T�J�n�`�`���E�͂U�N�Ԃ�̎���ł����A���ɖʔ������ł��B�܂��Y���ł����H���̗t�ɎY���̏�Ɏ��̗����Y�݁A�܂����̏�ɏd�˂ĉ������Y�����܂��̂ŁA�܂�ŗt�̏�ɏ����Ȓ��������Ă���悤�Ɍ����܂��B�z�������c���͏�ɑ̂��Ȃ��t�����i���̌`�����ĐÎ~���Ă��܂��̂ŁA�̒��̑���͐��m�ɂ͏o������ɐ���l�ł��B�܂����c���͐H���̃R�A�J�\��h�炷�Ǝ��������ėt���痎���܂��B���R��Ԃł͗c���̓R�A�J�\�̉��}�̗t�̏�ɖ����ɗ�������̂ł��傤���A����̏ꍇ�͉��ɗ�����Ɖ쎀�̊댯������܂��̂ŁA������͋C�z�肪�K�v�ł��B
�q���L�}�_���q�J�Q�̗��͎c�O�Ȏ��ɛz�������ɍ����Ȃ��Ēׂ�Ă��܂����B��Q�Ăœ����ɍ̏W�����c�����P���ʂɎ��炵�悤�Ǝv�����̂ł����A�W�c����̗c���̐����ɂ��������A��̊m�F�Ɏ��M���Ȃ��̂ŁA���N�͒��߂鎖�ɂ��܂����B
�X���P�O���ɐ_��R�ō̂���
�T�g�L�}�_���q�J�Q�̎��������Y�݂܂����B�ȑO�ɉ����炵�Ă��܂����A����z�������c���͎��̊Ԃ͌Q������܂��̂ŁA�P���������������Ɛ����Ɏx�Ⴊ���肻���Ɋ����P�������̎�������������Ȃ������̂ŁA����͌ʂɎ��炷�鎖�ɂ��܂����B���̗c���Ɋւ��Ă͌Q��������Ă������Ɉ���Ă��܂��B
�@
�P�O���O�W�N�P�O���W��
�O��̓��L�łT��ʼnz�~���H�Ə���ȗ\�z�����Ă�
�~�X�W�`���E�́A�P�O���U�����牼���ɓ���P�O���W���ɒE�炵�U��ɂȂ�܂����B�T����Ԃ͂T�O���Ԃł����B
�E���i�~�W���m���i�������Y�j�͂P�O���V�����牼���ɓ���W�����݉������ł��B
�T�J�n�`�`���E�͂S�����ʂɎ��炵�Ă��܂����S���T��ɂȂ�܂����B���̒��̂P���̎ʐ^���ڂ��Ă��܂����A���̗c���̏ꍇ�A�E�炵���Ắi�S��P���ځj�̑̐F�͖w�Ǎ��F�ł����̂̈ꕔ�ɊD�F�̕���������Ă��܂��B�����o�ɏ]���̐F�͔����Ȃ�A�T��ɂȂ�O�̉������͑̐F�͖w�ǔ��F�ł��B�E�炵�ĂT��ɂȂ�Ƒ̐F�͈�]���Đ^�����ɂȂ�܂��B�̂ɂ�葽���̕ω��͂���܂����A���̗c�����قړ��l�łS��c���͔����ۂ��̐F�ł��B�A���S���̂����P���͂T��c���̑̐F�����F�ł��B���������̗c���͂P�O���W�����݉������ł��̂łU��ɂȂ�l�ł��B�����Ɍ����Ƒ̐F�������Ȃ�̂͏I��̑O�̗�̎��ł��B
�T�g�L�}�_���q�J�Q�͏����Ɉ炿�i�S��S���ځj�ő̂��傫���Ȃ�܂����B�������ʎ�������Ă�������P���̗c���͖����i�R��U���ځj�ő̒��W�D�T�_�@�̕��P�D�T�_���Ə������ʐ^�̗c���̔������x�����L��܂���B�����ɂ��Ȃ������L��悤�ł��B
�P�O���P���Ɏ��r���n�֍s���B���n���ł̓~�h���q���E�����𑽐����������̃q���E�����ނ̎p�͂Ȃ������B�ڌ��������̓C�V�K�P�`���E�A�E���M���V�W�~�A�C�`�����W�Z�Z���ȂǂŎ�ނ͏��Ȃ������B
�X���P���ɃS�C�V�V�W�~��ڌ���匂��̂����ꏊ�֍s���A���炭�҂��Ă���Ɛ������Q���A���ł��܂����B���͂̍��̗t�̗��ʂ��ׂ�ƃT�T�R�i�t�L�c�m�A�u�����V�炵�������A�u�����V�̌Q�����܂����B�������c�O�Ȏ��ɃS�C�V�V�W�~�̗c���◑�͕t���Ă����a�̖K����Ȃ������B�P�T�Ԃقnj�ɂ�����x�s���č��̗t�̗��ʂׂ����ł����B
�P�O���W���̌ߌ�Ɏ��r���n��
�S�C�V�V�W�~�ƃA�u�����V�����ɍs���܂����B�A�u�����V�̏�Ԃ͂P�O���P���Ɩw�Ǖς�炸�S�C�V�V�W�~�̗c���͂��������Y������Ă��Ȃ��l�ł��B�Ƃ肠�����A�u�����V�̕t�������̗t�����������A��܂����B�S�C�V�V�W�~�͑S���łR���������A���̓��P�͌�����ł����B
�P�O���R���ɂ͈ɒO��
�V���r�r�A�V�W�~���̂�ɏo�����܂����B�ߑO�P�O���ɂi�q�ɒO�w�ɒ����A�P�O���قǕ����ƒ�����̒�h�ɒ����܂����B�ߋ��A����������V���r�A�V�W�~�̗��𑗂��Ē������炵�����͂���܂����ߋE�n���̃V���r�A�V�W�~�̎�������Ă��Ȃ��̂ŁA�����̂�̗�����̂��ړI�ł��B�ߑO���͗Y�𐔓��݂����܂����������Ȃ��Ȃ�������܂���B�͌��Ŏ��Q�ٓ̕���H�ׁA�������x�e���Ăю���T���܂����B�ߌ�͎����p�������ړI���ʂ����܂����B���������Y���ɔ�r�I�V�N�Ȍ̂������A���Ɍߌ�ɂȂ��Ď����p�������܂����̂ŁA������̎�������̂łȂ����ƁA����ʐS�z�����Ă��܂��B������̂����������ʐ^���B���܂������A�z���C�g�o�����X�̒����̎��s���H�ςȐF���ɂȂ��Ă��܂��܂����B
�O�W�N�P�O���P�W��
���Ԃ͏�����������܂������[�͔������Ȃ��ė��܂����B�������~�W�̗t�͌͂�Ă͂��܂��A���璆��
�~�X�W�`���E�͕��ʂ�����A�̂������k�l�ł��B�������O�T�N�̏H�ɍ̏W�A���炵���c���̋L�^������ƂP�P���Q�S���ł��a��H�ב̒��P�V�_�A�̕��S�_�ł��̂ŁA�z�~�܂łɂ͂܂��܂���������̂�������܂���B
�E���i�~�W���m���i�������Y�j�͒E�炵�ĂR��ɂȂ�܂����B�E���i�~�W���m���̗c���͏��H�Ń`�a�~�U�T�̗t���ꖇ����Ƃ��Ȃ�̓������ł��̂ŁA�w�Ǔ����������t�̏�ɂ��鎖�������l�ł��B
���L�ɍڂ��Ă���
�T�J�n�`�`���E�̗c���͂T��I��Ŗ�����匂ɂȂ�܂����B�������ʂɎ��炵���S���̂����P������O���������Ƃ�O��̓��L�ɍڂ��܂������A���̗�O�̗c���͏I��U��ł����������łȂ��A�I��̑̐F�����̗c���̂悤�ɐ^�����ł͖��������F�ł����B�c���̑̐F�̕ω��������̑̐F�ɉe������Ȃ�ʔ����̂ł����A���̎�ނł̌o���ł͕ω��͊��ҏo���܂���B
�T�g�L�}�_���q�J�Q�̗c���͂P�O���P�V�����牼���ɓ���P�W���������������ł��B�W���m���`���E�ނ̉����͔�r�I�����A�����S�����Ȃ��Ȃ�A�̌^���ۂ������ɂȂ�̂ŁA�����Ƃ����͖ő��ɂ���܂���B
�i�ɒO�Y�j
�V���r�A�V�W�~�̗̍��p�ɍ̂����������Ȃ��Ƃ��Q�O�`�R�O���قǂ͎Y������\��ł������A���V��ȂǂŎY�����������������炵���A�Y�����Ă��ꂽ�̂͂P�O���قǂł����B�������A�S�z�����������͖����S���z�����܂����̂ŁA�ʂɂT�������炷�鎖�ɂ��܂����B�z�������Ă̗c���͔��ɏ������̂ŒT���̂ɋ�J�������ł����A�c���͐H���̃V���c���N�T�ɖڗ������H�����c���܂��̂ŁA��r�I�y�Ɍ����鎖���o���܂��B
��N�A
�N���}�_���\�e�c�V�W�~�����߂Ď������֏㗤�A�ߋE�n���ł��ꕔ�̒n��Ŕ������b��ɂȂ�܂����B�z�N�o���Ȃ����낤�Ƃ̗\�z�ɔ����āA���N�͋ߋE�n���ōL�͈͂ɔ������Ă��܂��B���̂t����蕷���Ƃ���ɂ��Ɛ��̕��͍����A���A���ł͒��V���A���{�����A�Ԕ��̂������ߌ��Βn�A����ł͊ݘa�c�A��A���ȂǑ����ʂŔ������m�F����Ă��܂��B�����ł��X�H���̃\�e�c�ɃN���}�_���\�e�c�V�W�~���������Ă���Ƃs�����A�����A�����s���Č��܂����B�����͖ܘ_�A�c�����\�e�c�̎�t�ɕt���Ă��܂����B�ߏ��̔��A���̉Ԃł��z�����Ă���A���̔ɐB�͂��ĔF�����܂����B
�O�W�N�P�O���Q�W��
�O��A�~�X�W�`���E�̐H���ׂ蕳�ʂ������Ă���Ə����܂������A�P�O���Q�O���Ɏ���ł��܂����B�܊p�A�P���U��܂Ŏ��炪�ł��A���ƈꑧ�ʼnz�~�ɓ��鎞���������̂Ŏc�O�ł��B���N�͉��Ƃ������̏W�A�̗����Ė�P�N�̎���ɍĒ��킵�����Ǝv���܂��B
�E���i�~�W���m���͂P�O���Q�T���ɉ����ɓ���A�S���ڂ̂P�O���Q�W���ɂ������������ł��B���A�O��A�c���͏��H�Ŗw�Ǔ����������t�̏�ɂ���Ə����܂������A�悭����ƐH���̃`�a�~�U�T�̗t�͒[�̕��ɐH���̎c���Ă�����̂��w�ǂł��̂ŁA���\�A�c���͓����Ă���悤�ł��B�����������ꏊ�ɖ߂��Ă��鎖�������悤�ł��B
�T�g�L�}�_���q�J�Q�̗c���͂P�O���P�X���ɒE�炵�ĂT��ɂȂ�܂����B�ʐ^�ɎB���Č���Ɩw�Ǖω����L��܂��A�̂͐����傫���Ȃ�܂����B
�V���r�A�V�W�~�̗c���͂T���������Ɉ���Ă��܂����A����ɂ͂��Ȃ���������܂��B�P���͂P�O���Q�W�����݁A�O匂ɂȂ�A�R���͂S��c���ŁA�c��̂P���͂R��ł��B
�P�O���P�R���ɔ�����
�N���}�_���\�e�c�V�W�~�����ɍs�������Ɏ����ꓪ�A�����A��A�\�e�c�̎�t����ꂽ�e��ɕ����Ă����܂����B�R���قnjo���Ē��ׂĂ݂�Ƒ����̗����Y�ݕt���Ă��܂����B���ɔɐB�͂̋��������������āA�̗��͔��ɊȒP�ł��B
��N�A�������̂j���ɂ��肢���ė�����������炵�܂����̂Ŏʐ^�͑�R����܂����A��̕ς�鎞�̉�����E��͏[���A�m�F�o���Ă��܂���B�V�W�~�`���E�ނ̒E��k�͋�X�m�F�o���鎖���L��܂����m�����͗L��܂���B�����������͂��Ȃ�m�F�ł��܂��̂ŁA����͂S���̗c�����ʂɎ��炵�A�قڊԈႢ���������̊m�F���o�����c���̎ʐ^���ڂ��܂����B
�̗��̓\�e�c�̎�t���g���܂������A�����ɐH�אs�����܂����̂ŁA�㔼�̐H���ɂ̓C���Q���}�����g���܂����B�ʎ���̂S���̓C���Q���}���ɐ�ւ��Ă��A�̐F�ɑ傫�ȕω��͂���܂��A�W�c�Ŏ��炵�Ă��鑽���̗c���͐^���ԂɂȂ�܂����B���܂ŃC���Q���}���Ŏ��炷��Ɨc���̓C���Q���}���̒��ɂ����荞���̉e���Ő^���ԂɂȂ�Ǝv���Ă��܂������A�C���Q�}���Ŏ��炵�����ɏo�鐅���̉e�������m��Ȃ��Ɛ��肵�Ă��܂��B���C���Q���}����H�ׂĐ^���ԂɂȂ����c���́u���E�G�L�v�̃N���}�_���\�e�c�V�W�~�̒��ɍڂ��Ă��܂��B
�P�O���Q�O���ɂ܂��S�C�V�V�W�~�����ɍs���܂����B���r���n�̃|�C���g�ɒ����ƃS�C�V�V�W�~�����ł��܂����B���̂悤�ł����̂Ő������܂܍̂�A�a�̃T�T�R�i�t�L�c�m�A�u�����V��T���Ă��܂��ƁA�X�ɂP���A���ł��܂����B������͗Y�̂悤�ł���������̂�A�T�T�R�i�t�L�c�m�A�u�����V�̕t�������̗t����莝���A��܂����B�����ƃA�u�����V�̕t�������̗t��e��̒��ɓ���Ă����܂������Y���͂��Ă���܂���ł����B���H�̒������炵�����Ƃ��˂��ˎv���Ă��܂����A�S�C�V�V�W�~����ԂƂ肭�݈Ղ����ł��̂ŁA���N�������炵�����Ǝv���Ă��܂��B
�@
�P�P���O�W�N�P�P���W��
��������
�E���i�~�W���m���́i�S��P�P���ځj�ɂȂ�܂����B���ɂQ�����ʂɎ��炵�Ă��܂����A���ꂼ��i�S��R���ځj�Ɓi�S��U���ځj�ł��̂ŁA�_���q�̃E���i�~�W���m���Ɠ��l�ɂS��ʼnz�~����\�����������ł��B����������܂������A�N�P���̉��Ð�Y�͂U��ŁA�������Y�͂R��ʼnz�~���܂����B
�T�g�L�}�_���q�J�Q�͂T��Q�P���ڂɂȂ蓪�������Ȃ�Ԃ��Ȃ�܂����B�W�c�Ŏ��璆�̗c���̖�������匂ɂȂ�܂����̂ŁA���̗c�������낻��匉��������ł��B
�V���r�A�V�W�~�͋C���̉e�����H�A���Ȃ萬���ɍ������܂����B�قړ����ɛz�������T���̗c���̂�����Ԑ����̑����̂͂P�O���R�P����匉����܂����B�ʐ^���ڂ��Ă���c�����߁X匂ɂȂ肻���ł����A���̂R���͖����̒��T�|�U�_�ő̕����Q�_��ł��B
�P�O���Q�X���ɈɒO�s�̒������h�֍Ăэs���܂����B���̓��͒�h�̑�����ŃV���r�A�V�W�~�̔����ꏊ�̋߂��ŁA������̋@�B�����萔�l�ő������Ƃ̍Œ��ł����B�K���Ȏ��ɃV���c���N�T�̐����Ă��镔���ɂ͎�͓��炸�c���Ă��܂����B�������A�P�O���R���ɗ������Ɣ�ׂ�ƋC�����Ⴍ�A�����������̂ŃV���r�A�V�W�~�͂��܂����A�V���c���N�T�̉Ԃŋz������t�ɂƂ܂��Ă��鐬�������������A�Y���p�ɍ̂�܂����B�������������܂o���邾�����C�ȏ�ԂŎO�p���ɓ����͈̂��J�ŁA�A��㒲�ׂČ�����Y��}�g�V�W�~���������Ă��܂����B����̗̍����ʂ͑O����X�Ɉ����T���قǂł����B�~�G�̎��������ɂ͂���ŏ[���ł����A���܂Ń��}�g�V�W�~��c�o���V�W�~�̗̍��ł͗]���č�����ł����̂ŁA�S���̊��҂͂���ł����B���N�A�g���Ȏ����ɍ̗��ɍăg���C���Ă݂����ł��B
�������h�֍s��������
�q���A�J�^�e�n�����������ł��܂����̂Ŏ����P���̂胈���M�ō̗����܂����B�����ł�����o����Ǝv���ʂɂ͎��炵���������������̂ŁA�����Ȃ肩���Ă���̎���ɂȂ�܂��B����t�߂ł͂P�Q���ł������M�ɑ��������c�������܂��̂ŁA��������Ȃ�Ȃ�Ƃ������ɂȂ�̂ł͂Ɗ��҂��Ă��܂��B
������
�N���}�_���\�e�c�V�W�~�͂P�O���P�R���Ɍ��������͐����傫�������܂����̂ŁA���璆�̗c��������傫�Ȍ̂��H������Ǝv�������A�r������H�����\�e�c����C���Q���}���ɐ�ւ����ׂ�匂͈ȑO�Ɠ��l���Ȃ菬�����悤�ł��B���N�A�N���}�_���\�e�c�V�W�~���ߋE�ɂ��邩�ǂ����͕�����܂��A�C���Q���}����A���ĎႢ����^����ǂ��Ȃ邩���Č������Ǝv���܂��B
�������̂j�����疶���Y�̃E���M���q���E�����Ƌ{�茧���юs�Y��
�N���K�^�q���E�����̗��𑗂��Ē����܂����B�N���K�^�q���E�����̗̍��ł͂Q�T�O�����Y�����������ł��B�����������͖����S�����ł������P�P���V���ɃN���K�^�q���E�����̍ŏ��̗c�����z�����܂����B����Ƃ��ޗnj��암�Ⓦ���ɂ͂��܂����A�H�Ɋm���Ɏ����̏W�o����ꏊ�͎��̒m��Ƃ���ł͗L��܂���B���t�̊y���݂�������܂����B
�O�W�N�P�P���P�W��
�E���i�~�W���m���͖����a���H�ו������Ă��܂��̂ŁA�z�~�ɓ���͖̂�����̂悤�ł��B�ʐ^�̗c���́i�S��Q�P���j�ɂȂ�܂������A���ɕω��͗L��܂���B
�T�g�L�}�_���q�J�Q�͂P�P���P�R��������H���̍��𗣂�āA����e��̒�ɂ��܂����B�̒��������k��ł��܂����̂�匉����߂������Ǝv���Ă��܂������P�T���ɂ���ƑO匂ɂȂ�܂����B�P�U�����O匂̂܂܂łP�V����匂ɂȂ�܂����B匂͐�匂ł����ȒP�ɗ������A���R��Ԃł͖w�ǂ��������n��ʼnz�~���܂��B�䂪�Ƃł�匂͎��������ۂ̏�œ~���z���܂��B���������̒���匂�ۊǂ���Ət�ɂȂ��Ă��w�ljH�����܂���B�M�E�`���E�Ǝ��Ă��܂��B
�ʐ^���ڂ��Ă���
�V���r�A�V�W�~�͂P�P���P�T����匂ɂȂ�܂����B��Ԑ��匉������c�����P�O���R�P���ł����̂łP�T���x���匉��ł��B���P�O���R�P����匂ɂȂ����̂͂P�P���P�U���ɉH�����܂����B�����ɛz�������c��̂R���͖����a��H�ו������Ă��܂����S���傫���Ȃ炸�A���̂܂܉z�~����̂��ȂƐ��肵�Ă��܂��B
�P�O���Q�X���ɂQ��ڂ̒�����֍s�������̗��͂S�����z�����܂������A�����̒����Q�_�ȉ��̏����ȗc���ł��̂ŁA������͗c���ʼnz�~����̂͊m�����Ǝv���܂��B
�q���A�J�^�e�n�͂P�P���P�R���ɛz�����܂����B�c���͑�������܂������A�傫�ȗt�̏�̗c���͗t���[���ɋȂ��鎖���o���Ȃ��̂ŁA�c���̏�Ɏ��̖Ԃ��Ă��܂��B�c���̎p�͊ی����ł��B�t�̐V��̏o�鍠�͐g���B������邩���m��܂���B
�W���Q�R���ɛz������
�R�~�X�W�̗c�������炵����U��I��ł����̂ŁA�u���E�G�L�v�ɂQ���̗c�����ڂ��Ă��܂����A���͓����ɛz�������c���R�����ʂɎ��炵�Ă����̂ł����A�R���Ƃ������ĒE�炵�A�T��ɖ��Ȃ�A�Q���͂U��ɂȂ�܂������A�c��̂P���͉����A�E�炪�m�F�o���܂���ł����̂ŁA��̕ς�����̂����������̂����Ǝv���Ώۂ���O���Ă��܂������A�U��̂Q���̗c�����X���Q�T���ƂX���Q�W����匉����Ă��A���̌㉽���܂ł�匂ɂȂ炸�P�O���T���ɒE�炵�܂����B��������������U��ɂȂ�����ł��B���̌�A�����܂Ŗw�Ǖς�炸�i�U��S�T���ځj�ɂȂ�܂����B�ǂ������̂܂܉z�~����悤�ł��B�قړ������ɛz�����āA�������Ŏ��炵���c�����A�N���H���Ɖz�~�g�ɕ������͕̂s�v�c�ł��B�������A�ߋ��̎���L�^������ƃC�`�����W�`���E�A�S�}�_���`���E�A�I�I�����T�L���ł������܂��̂ŁA�ǂ����鎖�����m��܂���B
�O�W�N�P�P���Q�W��
�ŋ߂͂��Ȃ�C���̒Ⴂ��������A�P�P���Q�O���ɂ͓ޗnj��ł����X���͂�P�Q�����{�̋C���������̂ŁA
�I�I�����T�L��S�}�_���`���E���|�̖��牺�肾�����̂ł͂Ȃ����ƋC�ɂȂ��Ă��܂����B���N�̉Ă̐����͔��ɐ������Ȃ������̂ŁA�悯���ɋC�ɂȂ�A���������͑����ł����P�P���Q�V���Ɏl��떘�A���ɍs���܂����B�|�̍����ׂ�Ɩ����̐F���ΐF�̃I�I�����T�L��S�}�_���`���E�̗c�������܂����B���������͑��������悤�ł����A��N�ʂ�̐��̗c�������������S�ł��B
�E���i�~�W���m���͍������݁i�S��R�P���ځj�ɂȂ�܂������w�ǐ��������̒���̕��͕ω�������܂���B�H�ׂ�a�̗ʂ�����A���ʂ������ė����悤�ł����A�����z�~�ׂ̈̉����ɓ���C�z�͂���܂���B�������A�����Q���łP�Q���ł�����A���̂܂܂S��ʼnz�~�������ł��B
�R�~�X�W�́i�U��T�T���ځj�ɂȂ�܂����B�w�Ǖ������Ȃ��Ȃ�A�P�P���Q�S���ȍ~�͑S���������Ă��܂���B�Î~�ꏊ���S�������ꏊ�ł��B�z�~�̋x���ɓ������l�ł��B�O�R�N�ɃR�~�X�W�̉z�~�c�������炵�܂������A�t�ɂȂ��ċx������o�߂��c���͉a��H�ׂ��ɂ����ɑO匂ɂȂ�܂����̂ŁA���̗c���͂U��I��̂悤�ł��B
�q���L�}�_���q�J�Q�͗����z�����Ȃ������̂ŁA�}篁A�W�c�Ŏ���̂P��c�����ʂɎ��炷�����ł������A�W�c����̗c���̐���ɂ�����������̂ŁA���L�ɂ͍ڂ��܂���ł����B�������A�܊p���炷��̂łQ��c���Ǝv����c�����ʂɎ��炵�Ă��܂����B
���璆�̉���ނ��̗c�����z�~�̈x���ɓ�������A�w�ǐ������~�܂����肷�钆�Ńq���L�}�_���q�J�Q�������a��H�ׁA���������P�O���ȏ㗎�Ƃ��Ă��܂��̂ŁA�ŋ߂̎ʐ^���ڂ��Ă����܂��B���̗c���͋����R�Y�ł��̂ŁA�R�̏�͂��Ȃ芦���A�ǂ̂悤�ȏ�Ԃ��͕s���ł����A�䂪�Ƃ̗c���͎�������ł��̂Ō��C�Ɉ���Ă��܂��B
�q���A�J�^�e�n�́i�Q��V���ځj�ɂȂ菭���傫���Ȃ�܂����B�������A�C�����Ⴂ�ׁA����͈������̒��q�ł͔N����匂ɂȂ邩�H�N�����ɂȂ邩�H��������Ɨc���͓V���s�������m��܂���B�c���͖����̒��U�_���ł��̂ŁA�����M�̗t���ۂ߂đ������ꂸ�A�c���̏㑤�Ɏ��葃���Ă��܂��B�ʐ^�͎�����菜���ĎB���Ă��܂��B
�V���r�A�V�W�~�̗c���͖��������͕������Ă��܂����S���傫���Ȃ�܂���B���݁A�̒��U�_�قǂ̗c���R���ƂP�D�T�_�`�R�_���x�̗c���R�������܂����A���̂܂܉z�~����̂��ȁH�Ǝv���Ă��܂��B
�N���}�_���\�e�c�V�W�~�͂P�P�����{�ɖw�ǂ�匉����܂������A�Ȃ��Ȃ��H�����Ȃ��̂Ŋ����̈��̂��Ǝv���܂������P�P���Q�O���ȍ~�w�ǂ�匂��H�����܂����B�����Ŏ���A�ۊǂ��܂������C�������Ȃ�Ⴂ�̂ʼnH�����������͖w�ǔ���Î~���Ă��܂��B���A�ቷ���^�����Ȃ�̊����ō������Ă��܂��B
�@
�P�Q���O�W�N�P�Q���W��
�����A�\�Ȃ�W�����ɗc���B�̎ʐ^���B�鎖�ɂ��Ă��܂����A���̎��Ԃ̎����͂P�Q���ɓ����Ă��獡���܂łɂS���`�P�O���Ƃ��Ȃ�̕ω�������܂��B�O�C���Ƃ̍��͂T�`�U���قǍ����l�ł��B�P�Q���U���`�V���͔��ɗ₦���݊O�C���͕X�_���ł����B
�E���i�~�W���m�������ʂ������ė��đS����̓�������܂��B����̎ʐ^���ς����̂��Ȃ��ʐ^�ł����A�c���̐Î~�ꏊ�͖w�Ǖς�炸�P�P���Q�X������P�Q���Q���܂ł͖w�Ǔ����ꏊ�ɐÎ~���A�P�Q���R������P�Q���U���܂ł͂P�a�قǏ�̌s�Ɉړ����܂����B�P�Q���V���̓`�a�~�U�T�̗t�Ɉړ����č����������ꏊ�ɐÎ~���Ă��܂��B���悢��~���̎����̂悤�ł����`�a�~�U�T�������ΐF�ł��̂ŁA�c���������͈ړ����a��H�ׂĂ���̂��P�`�Q���̕��������Ă����������܂��B
�q���L�}�_���q�J�Q�͖����a��H�ׁA�������傫���Ȃ��Ă��܂��B�P�P���R�O�����牼���ɓ���P�Q���R���ɂ͒E�炵�ĂU��ɂȂ�܂����B�Y�n�̋����R�̋C���͕X�_���ł��̂ŁA�䂪�Ƃ̎�������̗c���Ƃ̔�r�͈Ӗ������������m��܂��A���̐�̐����ɋ������킢�Ă��܂��B
�q���A�J�^�e�n�͂P�P���R�O�����牼���ɓ���P�Q���Q���ɒE�炵�ĂR��ɂȂ�܂����B�c���̓����M�̗t���Ȃ߂�悤�ɐH�חt�����c���Ă��܂��B����܂ł��̂悤�ȐH�ו�������̂ł��傤���H
�O��̓��L�Ɏʐ^���ڂ����P�O���P�O���ɛz������
�V���r�A�V�W�~�͖w�Ǔ����Ȃ��Ȃ�A�V���c���N�T�̗t�̓����ꏊ�ɐÎ~���Ă��܂����̂œ~���ɓ������̂��Ǝv���܂������P�Q���S���ɒE�炵�ĂT��ɂȂ�܂����B�V�W�~�`���E�ނ̏I��͂S��ł���ƌ����Ă��܂����A�C���̒Ⴂ�����ɐ������z�~����c���͒E���������̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B�Q�O�O�S�N�`�T�N�ɂ����Ď��炵�����}�g�V�W�~�̏I��T��ł���A�E��k���m�F���A�ʐ^���B���Ă��܂��̂ŊԈႢ����܂���B���������������̕��́u���E�G�L�v�̃��}�g�V�W�~�������������B
�Q��ڂɎ��炵���P�P���P�P���ɛz�������c���̓��A�O��̓��L�ɍڂ����̂͂P�Q���P���̓V���c���N�T��H�ׂĂ������P�Q���Q�����牼���ɓ���A�S���ڂ̂P�Q���T���ɒE�炵�ĂR��ɂȂ�܂����B���̗c���͂P�Q���V������V���c���N�T�ɐH����t���n�߂܂����B�P�P���P�P���z���̗c���͑��ɂQ�����܂��������a�̃V���c���N�T��H�ׂĂ��܂��B����ɑ��P�O���P�O���z���̑傫�ȗc���͑S���łR�����܂����w�Ǔ������A�a�̐H���������w�ǂ���܂���B
�s������
�L�~�X�W�̗c�����Q�������܂����B���N�͐Ί_����^�ߍ����Ŗ����̃L�~�X�W���������������ł��B�H���̓J�����V�Ŏ��c���͌Q���A�傫���Ȃ�ɂ�ʂɍs������悤�ɂȂ邻���ł��B�������c���͑����A�I��Ǝv���܂����A�Q���͒��ǂ��P���̗t�ɕt���Ă��܂����B�P�Q���̓ޗǂł̓J�����V���w�ǂ��͂�Ă��܂����A�����ΐF�̃J�����V���c���Ă��܂��̂ŁA�Ȃ�Ƃ��T����匂܂ň�Ă����Ǝv���Ă��܂��B
�O�W�N�P�Q���P�W��
�O��̓��L�ł��w�Ǔ����Ă��Ȃ�����
�E���i�~�W���m���͂��̂P�O���Ԃ��w�Ǔ������Î~���Ă���A�������Ă���܂���B�S�������Ă��Ȃ��ƌ��������̂ł����A�R���̗c���̒��ɂ͏����Î~�ʒu�̕ς���Ă���̂����܂��̂ŁA�z�~�����g�������ɂ͏����͓����Ă���悤�ł��B������ɂ���A���悢��z�~�ɓ������l�ł��B���t�܂Ŏʐ^�����x�݂ɂ��܂��B
�q���L�}�_���q�J�Q�͖w�Ǒ傫���Ȃ�܂��A���������A�a��H�ו����P�O���ȏ㗎�Ƃ��Ă��܂��B�����ɋ����c���ł��������܂ʼna��H�ׂ�̂ł��傤���H�~���͂��Ȃ��̂ł��傤���H
�q���A�J�^�e�n�͂P�Q���P�P�����牼���ɓ���P�Q���P�R���ɒE�炵�ĂS��ɂȂ�܂����B�������̗c���͕\�炪�������������ɂȂ茩�h�������Ȃ��Ȃ�܂��B�������A�c���͉������ł��ǂ������A�̒��𑪂낤�Ǝv���Ɠ���U���Č�����܂��B
���Ȃ�C�����Ⴍ�Ȃ�A
�L�~�X�W�̐��炪�S�z�ł������A�\�z��葁���Q���Ƃ��P�Q���P�Q���`�P�R���ɂ�匉����܂����B���x�͐����̉H���҂��ł����A�ƒ��ň�Ԓg���������ŕۊǂ��Ă��܂��������H������ł��傤���H
�i�ɒO�Y�j
�V���r�A�V�W�~�Ɋւ��Đ������Ă݂܂��ƁA�P��ڂ̎��炪�P�O���X�`�P�O���ɛz�������c���ŁA�S���łT�����܂������A�P���ڂ͂P�O���R�P����匂ɂȂ�P�P���P�U���ɉH���A�Q���ڂ͂P�P���P�T����匂ɂȂ�A�P�Q���P�R���ɉH�����܂����B�c��̂R���͂Q�����T��ɂȂ�A�P���͂S��ł����A�S�����������A�Î~�ꏊ���S���ς�炸�A�̒����k�����Ă����悤�ł��̂ŁA���̂܂܉z�~����悤�ł��B
�Q��ڂ̎���͂P�P���P�P���ɛz���̗c���P���ƂP�P���P�T���z���̂Q�������炵�Ă��܂����A���݁A�S���R��Ŗ����a��H�ו������Ă��܂��B�����ɂȂ�Ήz�~�x���ɓ���̂ł��傤���H
�O�W�N�P�Q���Q�W��
�P�Q���Q�V���͎����̌ߑO�W���R�O���̋C�����S�D�T���ƍŒ�ł����B������
�q���L�}�_���q�J�Q�̗c���͓��ɕω��͖����A�H�����c���������Ă��܂����B�����ƋC����������x���ɓ���̂ł��傤���H�x���ɓ��炸�ɏ������a��H�t���}����̂ł��傤���H���̐悪�y���݂ł��B
�q���A�J�^�e�n�̗c���͂P�Q���Q�Q�����牼���ɓ���܂����B�C�����Ⴂ�ׂ��H�������Ԃ͂P�Q���Q�U���܂ł̂S���Ԃł����B�P�Q���Q�V���ɂ���ƒE�炵�T��ɂȂ�܂����B�ʐ^�̗c���ȊO�ɂ����P�������炵�Ă��܂����A���̗c���͂P�Q���Q�R�����牼���ɓ���A�������S���Ԃ̉�����P�Q���Q�W���ɂT��ɂȂ�܂����B
�C���ቺ�̉e�����H�O��ʐ^���ڂ����P�P���P�P���z����
�V���r�A�V�W�~�̗c���͂P�Q���Q�V���ƂQ�W���͕����P�������Ă��������ł����B�������P�P���P�T���ɛz�������Q���̗c���͖����������Ă��܂��B�ǂ̂悤�ɂȂ�̂����������̊��ԗl�q���������ł��B
�L�~�X�W��匉����Ă���A���Ȃ�C����������܂����̂ŁA�d�C���z�c���g���ĂQ�S���ԁA�ۉ����J�n���܂����B�ŋ߁A�d�C���z�c�̔����e���r�Ȃǂŕ���Ă��܂��̂ŁA��������ɒu���ĕۉ������b�オ����A�P�����P�Q���Q�W���ɉH�����܂����B���ʂ̎ʐ^�ł����ڂ��Ă����܂��B