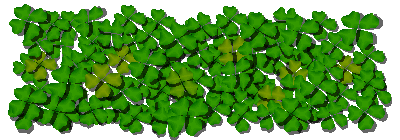
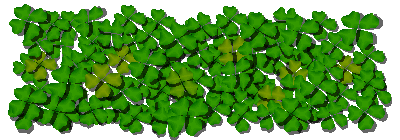
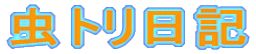
5月
7月
10月
8月
12月
|
「虫トリ日記」は虫撮りと虫採りを兼ねて付けた名前です。今年こそはもう少し野山に出て、蝶の写真を撮るつもりでしたが、持病の再発の可能性が高まり、がっかりしています。3月頃までに近場でミズイロオナガシジミの卵でも探すつもりでしたが、入院にでもなれば幼虫の飼育も出来なくなるので、当面は自宅でおとなしく過ごす予定です。(05年1月15日) |
05年1月16日(日)曇
12月の暖かい日には動いていた保管中のイモムシ達も、今は越冬状態で一ヶ所に静止して殆ど動きません。今日は現在、我が家で越冬中のイモムシ、卵や蛹の写真を載せました。
ヤマトシジミ(標準)は小さな鉢植のカタバミをいくら探しても、この数日、見つからなかったので、何処に行ったのだろうかと思っていたが、脱皮殻があったので、最近までカタバミの葉裏で仮眠していたようです。脱皮後もあまり動いていないらしく、何時までも脱皮殻のあるカタバミの葉に静止しています。新しい食痕も見つかりませんので、餌も殆ど食べていないようです。
ウラナミジャノメも殆ど静止場所を変えずにいます。寒そうに体を縮めて体長が短く、横幅が広くなり、ずんぐりむっくりの体型です。
その他の保管中の幼虫はオオウラギンヒョウモン、ウラギンスジヒョウモン、ジャノメチョウ、オオヒカゲ、ヒメキマダラヒカゲ、クロヒカゲ、オオムラサキ、ゴマダラチョウ、ミスジチョウなど9種類です。
ヒカゲチョウ、ヒメジャノメは12月中はそれぞれ庭の鉢植えの笹とスゲに数頭がいましたが、1月になって探しても一頭も見つかりません。多分、小鳥の餌になったのだと思います。
卵はミドリシジミだけです。今までは吹き流しの中で保管していましたが、半数の卵を冷蔵庫に入れました。
蛹はコツバメ、ギフチョウ、キマダラヒカゲ、ホソオチョウ、コチャバネセセリ(終齢幼虫)の5種類です。
コツバメの蛹は始めての保管で5月から春までの長い期間を過ごすのですが、どのような保管法が良いのか分からなかったので、(1)雨の吹き込む軒下に吊した吹き流しの中、(2)植木鉢の底に水はけが良いように小さな砂利を敷きその上に水苔を敷き雨のかかる軒下に保管。(3)ギフチョウの保管と同じように常時、湿った水苔の上で保管。の三通りを試みました。どの方法がベストかが分かる春のコツバメの羽化が楽しみです。
普通種ばかりで、しかも何度も飼育している種類が多いですが、結構、イモムシ達の行動にあらたな発見があります。(大袈裟かな?)中でも3-4種類は始めて飼育した種類もあり、イモムシ達の動き出す春が待ち遠しいです。
2月
05年2月9日(水)晴
今日は久しぶりに暖かく3月上旬の天候でした。本来ならウオーキングを兼ねて外出するところですが、体調が今ひとつですので、庭で保管中のイモムシ達を調べてみました。ヒョウモン類は小さくて良く分かりませんが、他の幼虫は殆どが無事に越冬しているようです。オオヒカゲのいるスゲを見ているとセセリチョウの幼虫が巣を造り中で越冬していました。スゲを取って来たときに既に付いていたのか、庭に放置中に産卵されたのかは不明ですが、今のところは巣の中でゆっくり冬眠してもらい、春になればセセリの種類を確認したいと思います。
多数飼育のウラナミジャノメは、植木鉢の中に小さな砂利を敷きその上に水苔を敷いたところへ殆どの幼虫を入れ保管しているが、2頭だけ枯れたチヂミザサに静止していたので、そのまま保管していたが、2頭共、飼育箱(プラスチック容器)の底に落ちていた。1頭は既に死んでおり、一頭は体が縮み極端に小さくなっていました。
室内で飼育中のウラナミジャノメも調べて見ると、先に記した幼虫ほどではないがかなり縮んでいました。室内の幼虫は水分を殆ど与えていませんので、霧吹きで少し水分を与えました。
ヤマトシジミも室内で飼育していますが、この幼虫は真冬でも、少しはカタバミの葉を食べているらしく、カタバミの葉に食痕を残していました。越冬中と思っていたので、幼虫の姿を見るのは久しぶりですが、幼虫は少し大きくなったようです。
3月
05年3月9日(水)晴
この3日程、最高気温は14-15℃に上がり保管中のイモムシ達の中には動き出したのもいるようです。常時湿った水苔の中や植木鉢の水苔の中に保管していたギフチョウ、コツバメ、サトキマダラヒカゲ、等の蛹を取り出して吹き流しの中に入れて、羽化に備えました。
ヒメキマダラヒカゲの幼虫は金剛山の標高1000㍍程の場所に生息するからか、7℃ほどは気温の高い我が家では既に動き出した個体もいます。大きなポリ容器の中に瓶を入れ、笹の葉を挿し、笹の葉が枯れないようにポリ容器の上をビニールシートで覆い湿度が逃げないようにして保管していたが、去年に入れた笹の葉はすっかり枯れて褐色になっていました。2月28日にポリ容器の底を清掃して、新しい緑色の笹の葉を瓶に挿し、幼虫の静止している古い褐色の笹の葉も一緒に挿しておいた。3月8日に様子を見ると、幼虫の多数が緑色の笹の葉に移行して、しかも葉に食痕を残していた。ポリ容器の底には幼虫の糞もかなり落ちていました。
ヒメキマダラヒカゲの幼虫は多数いますので、その中から数頭を選び体長や体幅を測定していますが、(1)ヒメキマダラヒカゲは体長12㍉ 体幅1.5㍉で去年の秋よりかなり縮み12月10日と比べても小さくなっていました。 (2)ヒメキマダラヒカゲ体長21㍉ 体幅3㍉弱は仮眠中で、去年の秋と比べると体は縮んでいましたが12月10日とは殆ど変化はなかった。何よりもこの時期に仮眠中だったのには驚きました。
ヤマトシジミは殆ど目立ちませんが少しずつ大きくなっているようです。体長7㍉ 体幅2㍉強を筆頭に体長5㍉ 体幅1.5㍉程の幼虫が2頭います。
ウラナミジャノメの幼虫も室内で飼育の(標準)がかなり動いて場所を変えていました。しかし、未だ、チヂミザサは全く生えていませんので、もう少しゆっくり眠っていて欲しいです。
ジャノメチョウの幼虫は鉢植えのスゲやメヒシバごとポリ容器に入れ保管していますが、今日、見ると数頭の幼虫が植木鉢の食草から落ちてプラ容器の底に落ちていました
。全部元気で、秋よりは少し大きくなっている感じでしたので、落ちたのでは無く、降りたのかも知れません。
ところで、私事ですが、2年前に3ヶ月入院した悪性リンパ腫が再発してしまいました。今年に入って徴候が現れていましたので、新しいイモムシ達や卵の採集は控えていましたが、それでも普通種ばかりですが、かなりの数の卵、幼虫、蛹がいますので、今後の幼虫達の処遇を考える必要があります。2年前は5月からの入院でしたので、越冬した蛹は既に羽化済みでしたので、飼育中の幼虫はすべて纏めて大阪の蝶好きの方に引き取って貰いました。今回は一部の種類は残し、日曜日に外出許可を頂き戻って来て何とか飼育出来ないかと考えています。しかし大部分は採った場所で放すか、飼育して下さる方が有れば貰い子に出すかを選ばなくてはならず迷っています。いずれにしてもイモムシ達の写真は滅多に撮れなくなりますので、折角のシーズンインですが虫トリ日記は暫くお休みを頂きます。無事退院できれば6-7月頃から再開の予定ですので宜しくお願いします。
05年3月21日(月)晴
入院の準備が完了。イモムシ達も鉢植えの食草に移し、鉢植の食草が無い種類は幸い飼って頂ける方がおられ、貰い子に出す等の適当な処遇をしましたが、私の方は空きベッド待ちで、未だ入れてもらえませんので、先週から、通院で治療を始めました。中途半端で落ち着きませんが、残した幼虫の一部が動き出しましたので、少し写真を撮りました。
ウラナミジャノメは2頭だけ室内で保管。(暖房はしていません。)他は室外で保管していますが、室内保管の(A)幼虫はこの数日間歩きまわるので、(A)(B)の2頭にスゲの餌を与える事に決め、鉢植えのスゲの根元に置きました。(A)幼虫は翌日にはスゲに上り、葉に食痕を残していました。(B)は翌日は未だ、下にいましたが3日目にはスゲに上り葉を食べていました。
室外保管の幼虫は未だ殆ど動いていないようですが、蛹化までは未だ1ヶ月以上かかると思いますので、そろそろスゲを用意する必要があると思います。昨年の秋迄与えていたチヂミザサは未だ、全く生えていません。姫路の産地でも餌は冬にも枯れないスゲ類の可能性が大きいと思われます。
ヤマトシジミは越冬出来たのは3頭だけで、他の幼虫は姿が見えません。此処暫く、暖かい日が続いていましたが、3月17日の夕方、幼虫を見ると、大小はありますが3頭共、脱皮していました。脱皮後1-2日程は脱皮殻の傍で静止していましたが、3月21日にはかなりカタバミの中を移動して、葉を食べていました。体長も少し大きくなったようです。
ヒメキマダラヒカゲは笹の葉に食痕を残し、糞もしており、既に春を迎えたようです。特にこの10日間に、仮眠、脱皮する幼虫が増えました。3月8日に最初に仮眠していた(2)の幼虫は2-3日後には脱皮しました。幼虫には大小の差はありますが、殆どの幼虫が脱皮したか仮眠中です。ヒメキマダラヒカゲの中に混じっていたクロヒカゲも仮眠中のようです。
05年3月31日(木)晴
通院での治療が予想以上に効果が有り、暫く通院で治療する事になり、昨日2回目の治療をしました。2週間後に結果を見て、入院するかどうかを決めるとの事です。家に居ますと、何かと自由ですし、イモムシ達の状態を見ることもできますので、非常に有り難い事ですが、通院治療だけで治るのか少し不安です。
ウラナミジャノメは順調にスゲを食べ、糞もかなりしています。越冬中は体がかなり縮み小さくなっていましたが、05年3月28日には体の大きさも、去年の秋の最高値より大きくなりました。室外飼育の幼虫もスゲの鉢の根元に水苔と一緒に置きましたが、まだ一頭もスゲに上ってはいません。
春になって気温が高くなると共にヤマトシジミの食欲は高まりカタバミを食べ、少しずつですが確実に大きくなってきました。
ヒメキマダラヒカゲは10日程前には半数以上が仮眠中でしたが、今日現在では(1)の幼虫以外は全部脱皮しました。自宅では比較的日の当たらない寒い場所で保管していますが、金剛山の1000㍍付近の幼虫の状態はどうなっているのか興味あります。
クロヒカゲも長い仮眠に終止符を打ち脱皮しました。5齢になりました。
3月21日にコツバメの第一号が羽化しました。その後3月26日と27日に各1頭ずつ羽化しました。コツバメの蛹の保管は(1)吹き流しで保管。(2)植木鉢の水苔で保管。時々湿らす。(3)ギフチョウの保管と同様湿った水苔の中で保管。の3通りに分け、約30頭の蛹を越夏・越冬させましたが、今のところ羽化したのは全部(3)の湿らした水苔の中の蛹だけです。
去年の秋に植えたスミレの小さな芽が出ていました。その中に去年の秋にいれたウラギンスジヒョウモンの幼虫が1頭無事にいるのが見つかりました。スミレの新芽の隙間に隠れていました。オオウラギンヒョウモンは木の葉の隙間で越冬した幼虫は5頭程が元気な様子です。木の葉ごとスミレの新芽の下に置くことにしました。
4月
05年4月10日(日)曇
今年の春は気温が低く、桜の開花や蝶の出現も遅れていましたが、この3-4日急に暖かくなり、桜も一度に開花し、我が家のギフチョウも4月8日に3頭が一度に羽化しました。今年程遅いのは珍しいです。毎年、少しだけギフチョウを飼っていると、その年の発生時期が推定できて便利です。
我が家のギフチョウが羽化し、蝶のシーズンが来ましたので、本来なら遠出をしたいところですが、治療の副作用で、手足がしびれますので、近場へ行くことに決め、昨日、交野山付近を歩いてみました。休日で花見の時期ですので、山の中でも結構人出が多く、人のいない場所を探して歩くのに苦労しました。こんな時期にこの辺に来るのは初めてですが、春の蝶、ミヤマセセリは約10頭程、コツバメ5-6頭、ツマキチョウ1頭、を見かけました。ルリシジミ、ヤマトシジミ、ルリタテハ、キチョウ、ナミアゲハ等も見かけました。未だ飼育経験の無いミヤマセセリとツマキチョウの雌を欲しかったのですが、今回は見送りました。
前回に載せました通り、コツバメの羽化第一号が3月21日でしたが、4月8日迄の間に7頭が羽化しました。羽化したのは全部、ギフチョウと同じように常時湿った水苔の中で保管した蛹ばかりでした。、吹き流しの中や、水苔の中に保管し、時々湿らす方法では全く羽化しませんでした。
私の病気の件ですが、4月13日に今後の治療の方針が決まりますので、入院と言う事態も考え、飼育中の幼虫の食草の鉢植えをかなり用意しました。タチツボスミレは従来から鉢植えを沢山持っていますが、スミレは少ししか有りませんので、新たに探して鉢植えを造っています。3月末にはまだ新芽だったスミレは4月8日には既に花が咲いていて簡単に見つかりました。これで何とかオオウラギンヒョウモンの飼育は蛹化迄、完了できそうです。ウラギンスジヒョウモンの幼虫は1頭は急速に大きくなっていますが、オオウラギンヒョウモンの幼虫は未だ体長2㍉強 体幅0.2㍉程度でスミレの根元の茎に静止している事が多く、探すのに苦労します。
ウラナミジャノメ(室内飼育)は毎日かなりの糞をしていますので、もっと大きくなっても良さそうですが、大きさは殆ど変わりません。但し暖かくなって、餌も充分食べた為か体色は非常に良くなりました。室外で多数飼育の幼虫もスゲの葉に上り、葉を食べ始めました。糞もしております。
ヤマトシジミの一番おおきな幼虫がやっと前蛹になりました。既に野外で成虫を目撃していますので、かなり成長は遅れているようです。他に2頭の幼虫を飼育していますが、春になって2回目の脱皮を済ませ終齢になりました。
ヒメキマダラヒカゲは3月中に今春、一回目の仮眠・脱皮が一段落しましたが、最近、今春、二回目の仮眠・脱皮が増えています。毎日、見ていると全く変化が無いようですが、全部かなり大きくなりました。
クロヒカゲも5齢になって14日経ち大きくなりました。
ミドリシジミの卵は(1)吹き流しで保管と(2)冷蔵庫で保管の二通りの方法で保管しましたが、入院の予定だった為、(2)は貰い子にだしましたが、(1)は忘れていました。3月31日に気が付き、冷蔵庫から取り出しました。以前の孵化日を調べて見ると、02年に吹き流しで保管した卵が3月30日に孵化していましたので、慌ててハンノキの芽を取ってきました。冷蔵庫から取り出したミドリシジミの卵は4月3日に精孔が黒くなって、幼虫の頭部が見え始めました。最初の孵化が4月4日で、その後2-3日の間に殆どが孵化しました。幼虫は3頭だけ個別に飼育し、他は纏めて飼育する事にしました。しかし、ハンノキの新芽に小さな巣があるだけで、幼虫がどうなっているのかさっぱり分かりません。0
05年4月19日(火)晴
4月14日に近所の「子供の森」まで散歩がてらに、蝶や花を見にいきました。桜は既に色あせていましたが、ミツバツツジが美しく咲き、スミレも何種類かが咲いていました。只、ホンスミレは全く見つかりませんでした。
蝶はルリタテハ、アカタテハ、テングチョウ等の越冬組以外にアゲハチョウの姿も見かけました。コツバメ、ミヤマセセリも「子供の森」では初めて見ましたので、目録に追加しました。何故か「子供の森」にはアセビが有りませんので、ここのコツバメはツツジを食べているのかもしれません。
4月18日に自宅の庭へトラフシジミが飛んで来ました。カメラにしようか、ネットにしようかと思っている間に遠くへ逃げて行きました。自宅付近では初めて見ました。
急に暖かくなり、飼育中の幼虫にはかなり変化がありました。去年の6月から飼育しているウラナミジャノメの6齢幼虫が更に脱皮して、7齢になったのには驚きました。脱皮後幼虫は急に大きくなり、体長20㍉を越えました。
残念な事もありました。個別に飼育していたウラナミジャノメの5齢幼虫(5齢189日目)も仮眠状態になりましたが、脱皮に失敗して死んでしまいました。しかし、頭部及び体の脱皮殻を確認出来ましたので、6齢になった事は間違い有りません。ジャノメチョウ科は5齢以上になる事は結構有るようですが、1年かかって成長する加古川のウラナミジャノメは何回も脱皮するようです。
ヤマトシジミの幼虫の2頭が蛹になりました。最初の個体が4月12日に、2番目が4月18日に蛹化、残りの1頭も前蛹になりました。
ヒメキマダラヒカゲの幼虫の内、3頭が蛹になりました。平地での飼育の為、高地より少し蛹化が早いのかもしれません。金剛山の1000㍍付近では、今頃はどんな状態なのでしょうか?
蛹化する個体もいますが、未だ体長20㍉程の幼虫もいます。成長にはかなりバラツキがあります。
ヒメキマダラヒカゲに混じって連れてこられたクロヒカゲの幼虫もほぼ同時期に蛹になりました。
成り行きで飼育したミドリシジミですが、結構、巣から出ている事が多く、幼虫の写真が撮せて、ラッキーです。未だ巣を造っている新芽が小さいので、餌を巣の外に食べに行くので、幼虫の姿が良く見られるのかもしれません。
ウラギンスジヒョウモンは成長が早く、大きな幼虫は4齢になったが、オオウラギンヒョウモンの幼虫は未だ2齢で、何処にいるのか探すのに苦労します。
今年はゴマダラチョウの飼育をする気は全くなかったのですが、寄生蠅を羽化させようと思い、ゴマダラチョウの幼虫を5-6頭、用意していました。予定通り寄生率は高く、ゴマダラチョウの幼虫は死んで寄生蠅の蛹が下に落ちていました。早速、土の中へ入れ保管しました。しかし2頭の幼虫だけは、寄生されておらず、その内の1頭が、脱皮して終齢になりました。
ゴマダラチョウから少し遅れて、少しだけ残してあったオオムラサキの幼虫も榎の枝に上り、葉を食べ始めました。毎年の事ですが、順調に榎の葉を食べ始めると一安心です。
05年4月29日(金)晴
急な事ですが、病院から連絡があり、明日から入院するように指示がありました。少し油断していたので大慌てです。今度こそ、この日記はお休みを頂く事になりそうです。
ウラナミジャノメは7齢になってから、かなり大きくなりました。しかし写真では殆ど変化は有りませんので、取りあえず2枚だけ写真を載せます。私にとっては一年がかりで飼育してきましたので、蛹まで確認したいと思っているのですが、外出許可がもらえるかどうかにかかっています。
ウラギンスジヒョウモンの一番大きな幼虫が5齢で仮眠に入りました。と言う事は6齢になるはずですが、越冬後の写真を全部見直しましたが、5回、仮眠をしていますので、心ならずも6齢と言う数字を入れる事になりそうです。
ミドリシジミは最初から同じ幼虫を載せていますが、かなり、大きくなりました。ハンノキの葉の巣も目立つようになりましたので、幼虫の採集に良い時期に入ったようです。
今回はこれでうち切ります。次回の更新が少しでも、早くできる事を願いながら!0
6月
05年6月26日(日)晴
入院中の病院から5月には数回、6月には6月19日と6月26日に一時帰宅しました。飼育中の幼虫には餌を充分与えて蛹化までは放置しておいても大丈夫と思っていましたが、鉢植えの餌が水不足で枯れたり、予想以上に餌を食べ、餌不足になったりで、ジャノメチョウ等は全滅してしまいました。
オオウラギンヒョウモンは特に気を付けて、家族(蝶には全く興味を持っていない)に餌の水やりと、羽化した時の取り入れを頼みました。蛹になった時は病院にいましたので、正確な日は分かりませんが、羽化日(6月9日、12日、14日)は家族に確認して貰い、羽化した蝶を冷蔵庫で保管するように頼みました。
6月19日に一時帰宅して、冷蔵庫に保管中の羽化した蝶を見て驚きました。オオウラギンヒョウモンではなくウラギンスジヒョウモンでした。ウラギンスジヒョウモンは昨秋、採卵したのですが、秋に孵化した幼虫がタチツボスミレを食べ始めたり、(その後死亡)、越冬した僅かの幼虫も死亡して、全滅状態でしたが、餌のスミレで越冬した幼虫が残っていたようです。その後、今春になってオオウラギンヒョウモンをそのスミレで飼育した為、ウラギンスジヒョウモンとオオウラギンヒョウモンが混ざってしまったようです。最初に大きくなった幼虫の3頭はウラギンスジヒョウモンで他の成長の遅い小さな幼虫がオオウラギンヒョウモンでした。ウラギンスジヒョウモンの幼虫は過去に飼育経験が有るオオウラギンスジヒョウモンの幼虫とよく似ており、図鑑で見たオオウラギンヒョウモンの幼虫は体色がかなり黒いので、飼育途中で少しおかしいとは思っていましたが、大失敗です。餌の管理の重要性をあらためて感じています。
言い訳が長くなりましたが、ここでお詫びと訂正をさせて頂きますので、ご了承下さい。3月31日以降オオウラギンヒョウモンとして「虫トリ日記」に載せております写真はウラギンスジヒョウモンですので、3月31日にさかのぼって、種名を変更し、一部、文章も変更しますので、宜しくご了承をお願いします。
肝心のオオウラギンヒョウモンはウラギンスジヒョウモンと比較すると、少し成長の時期がずれて入院時の4月29日には未だ(体長11.5㍉ 体幅2㍉)(体長5㍉ 体幅1㍉)で3齢程度でした。一時帰宅をした時には写真を撮っていますが、たまにしか見ることができず雑な記録になりましたが、4月29日以降、蛹までの写真を載せました。殆ど放置したような状態だったので、無事に蛹になったのは2頭だけで、今日(6月26日)に1頭が羽化。もう1頭は明日か明後日に羽化しそうです。
ウラギンスジヒョウモンはオオウラギンヒョウモンより早く成長し、蛹になり、6月9日と12日に雄が、6月14日に雌が羽化しました。
ウラナミジャノメの個別飼育した7齢幼虫は5月3日に蛹になりましたが、多数飼育の幼虫はかなり遅れて5月29日に帰宅した時に蛹になっていました。蛹は6月初旬から中旬に羽化しました。
ミドリシジミは5月初旬に殆どが蛹になり、5月29日に帰宅した時は既に羽化して、乾燥し硬くなっていました。正確な羽化日は分かりませんが、例年より早いような気がします。
例年なら、数種類の幼虫の飼育をしている時期ですが、今年は餌不足で成長の遅れたオオムラサキの蛹が少し残っているだけです。
病気の方はまだ治療中で、退院の時期は今のところ、予測出来ませんので、「虫トリ日記」の再開は未だ先になりそうです。
9月
05年9月1日
約4ヶ月振りに退院できました。只、私の病気は完治が困難な病気ですので、これからも通院は必要ですし、急に再発すると困るので、長期の旅行などは無理です。とりあえずは体力を付ける事と、入院中にたまっていた事を処理するのが一番です。
入院中に蛹になり羽化した成虫は、蝶には全く興味の無い息子に頼んで、三角紙に入れて、冷凍庫に保管して貰いました。吹き流しから蝶を取り出す時に、かなり鱗粉が落ちたようですが、帰宅後、大切に展翅しました。特にオオウラギンヒョウモン、ウラギンスジヒョウモン、加古川のウラナミジャノメ等は半年以上かけて飼育した結果ですし、標本として大切に保存するつもりです。
今は全く手持ちの幼虫はいませんが、今後の飼育に備えて、庭の食草類の点検をしました。鹿児島のK氏から送って貰ったカワラケツメイやシバハギの種を植木鉢にまいておきましたが、入院した当時は全く生えていなかったが、今はかなり大きくなっていました。ツメレンゲも子供が沢山できて数が増えていました。その他の食草類も殆どが順調に育っていますが、只、春に奈良県のT氏から貰ったクロウメモドキとアオダモの葉が変色して、枯れかけのような感じになっています。留守中も水を充分、やるように家族に頼んでいましたので、水不足と言う事は無いと思っていますが、むしろ日当たりが良すぎるのではないかと思い、日陰に移しました。
ササクサと笹の葉に幼虫の食べたような食痕が有りましたので、よく調べると、ササクサにはヒメジャノメの蛹が1頭、笹の葉にはヒカゲチョウの蛹が2頭付いていました。我が家に産卵に来るジャノメチョウ科は今までヒメジャノメだけでしたが、ヒカゲチョウまで来ていたのには驚きました。
8月29日には足慣らしの為に室池園地まで行き、ゆっくりとウオーキングをしました。8月末とは言え未だ気温が高いためか、蝶の姿は少なく、ナミアゲハ、コミスジ、ヒカゲチョウ、クロヒカゲ、スジグロチョウ、ヤマトシジミ、ルリタテハ、等を見かけただけでしたが、スミナガシ、アオバセセリ、ルリタテハ、コチャバネセセリ等の卵や幼虫を見つける事ができました。スミナガシは03年の8月末頃に多数の卵を見つけていたので、卵を期待していたのですが、この日は1卵、見つけただけでした。しかし、卵の代わりに1齢と3齢幼虫をみつけました。珍しくアオバセセリの1齢らしい幼虫も見つけました。未だ、縞模様が入っていませんが、アワブキの葉に造った巣はアオバセセリの巣の形でした。
ルリタテハはちょうど産卵の季節らしく、サルトリイバラの葉を調べると、かなりの確率で、卵が見つかりました。孵化済みの卵殻もかなりありましたが、2齢幼虫を1頭見つけただけです。多分、殆どの幼虫が天敵に襲われるのだと思います。
9月1日に枚岡公園へ行きました。8月末から9月上旬にスミナガシやアオバセセリの卵や幼虫をよく見かけるので、室池園地よりスミナガシやアオバセセリの数が多いと思われる枚岡公園のアワブキを調べて見たくなったからです。以前にスミナガシの幼虫を多数見つけた道路脇のアワブキが切り取られて無くなっていました。背の高い木や、斜面に生えた木が多く、スミナガシの食痕のあるアワブキの葉を見つけても、とても届かず。結局、スミナガシの3齢幼虫とアオバセセリの2齢幼虫をそれぞれ1頭ずつ採っただけです。
この辺りにはイヌビワも生えていますので、イシガケチョウの幼虫を探しましたが、時期が合っていないのか1齢幼虫を1頭見つけただけでした。この辺りでは成虫の姿をよく見かけますので、時期が合えば幼虫ももっと多そうな気がします。
05年9月10日(土)曇
鹿児島のK氏からタテハモドキ、ウスキシロチョウ、シルビアシジミ(奄美亜種)の3種類の卵を送って貰いました。タテハモドキは9月3日に孵化。シルビアシジミは卵は未孵化でしたが、かなり大きな幼虫、1頭が混じっており、それを飼育しています。ウスキシロチョウは食草のナンバンサイカチまで、一緒に送って頂いたのですが、残念なことに未孵化でした。
タテハモドキは9月3日に孵化後、オギノツメで飼育を初めましたが、終齢の頃には不足しそうですので、オオバコを採ってきて、オオバコ飼育とオギノツメ飼育の2グループに分けました。真っ黒の幼虫は元気に育ち、今は3齢です。
シルビアシジミ(奄美亜種)の食草はシロツメクサとの事です。送ってもらったシロツメクサにいた幼虫を現在、飼育中です。9月10日には前蛹になりました。小さな幼虫ですから、もっと大きくなると思っていたので意外でした。
退院後飼育中の幼虫が殆どいませんので、室池園地で採ったスミナガシとアオバセセリは大切に飼育しています。特にアオバセセリは孵化して間もないと思われる1齢幼虫でしたので、今回の飼育では、毎朝、巣を開いて、幼虫の写真を撮る事にしました。幼虫は2齢までは無事に育ち、アオバセセリの幼虫の特徴である縞模様も出来ましたが、幼虫は巣を造らなくなり、衰弱して死んでしまいました。毎日、巣を開いたのが悪かったのか?食草のアワブキの葉が硬すぎたのか?原因は不明です。来年には雌の成虫を採り、採卵して、多数の幼虫を飼育して、原因を調べて見たいと思っています。
スミナガシの幼虫は過去、卵からの飼育もしましたが、今回、卵と1齢幼虫を個別に飼育しています。8月29日に1齢だった幼虫が9月10日には5齢になりました。3齢だった幼虫は5齢ですが緑色の大きな幼虫に育っています。
枚岡公園で採ったイシガケチョウの幼虫は1齢幼虫でしたが、9月10日には5齢になりました。イシガケチョウの幼虫の成長の早さには驚きます。
モンシロチョウ、イチモンジセセリ等の普通種の飼育写真が有りませんので、9月8日に「子供の森」へ採りに行きました。スジグロシロチョウは10頭以上見かけましたが、モンシロチョウは全く見かけ無かった。まさか目的のモンシロチョウが採れないとは思ってもいませんでした。
一番多く目につくのはツマグロヒョウモンです。地面を這うようにゆっくりと飛んでいます。少し威勢良く飛ぶヒョウモンがいるので、良く見るとミドリヒョウモンでした。ツマグロヒョウモンは自宅の庭のスミレで、発生するほどですので、つい無関心に成り勝ちですが、今回、卵から蛹まで、2-3頭を個別に飼育してみようと思い、採卵用に雌を採りました。自宅で採卵の結果、すぐに産みましたので、親蝶は放しました。
この4ー5年ジャノメチョウの飼育をしていますが、最初の2年ほどは孵化してくれず、最近は卵の湿度管理が必要なのがわかり、毎年、幼虫を越冬さしますが、春から初夏にかけて、長期入院などの為、ジャノメチョウの蛹を見た事が有りません。そこで今年もジャノメチョウの雌が欲しいと思い、いつも何頭かいる草地を歩きましたが、全く姿を見せませんでした。別の場所で、かろうじて1頭、見つけ持ち帰る事が出来ました。
05年9月20日(水)
タテハモドキの飼育では食草で失敗をしました。食草のオギノツメが大型の植木鉢に繁茂していたのと、種が飛んで付近にあった植木鉢や地面に生えていましたので、量の点では安心していました。しかし、万が一の場合を考え、15頭の内4頭の幼虫を一齢の初期に食草をオギノツメからオオバコに切り替えました。幼虫は無事にオオバコを食べて成長しましたので、安心していました。
幼虫が終齢になった時点で、オギノツメが不足しそうでしたので、オギノツメで飼育していた個別飼育の4頭の内2頭と、多数飼育をしていた7頭の幼虫の餌をオオバコに切り替えました。ところが幼虫は餌のオオバコを全く食べてくれません。オオバコの葉を手でちぎって与えたり、1齢からオオバコで育っている幼虫と同じ容器に入れる等、工夫してみましたが、結果的には7頭の幼虫は蛹になれずに、干からびて死んでしまいました。
個別飼育の残りの2頭も2-3日絶食状態でしたが、他の個別飼育の幼虫が蛹化した後、余ったオギノツメを与え、何とか蛹になりました。
他の蝶の飼育の場合、餌が不足して途中で他の種類の食草を与える事は良くあり、通常は他の種類の食草でも良く食べ育ちますが、タテハモドキの幼虫にとってオオバコは代用食であって、オギノツメで育った幼虫の口には合わないようです。
枚岡公園で採ったイシガケチョウの幼虫は早い成長で、9月10日には5齢になっていたが、5齢になって間もない朝に、容器の底で死んでいました。全く原因は分からない。1齢の初期からの飼育でしたので、蛹まで育てたかったのですが残念です。
スミナガシも最後の1頭が昨日、蛹になりました。スミナガシの幼虫は孵化後の1齢幼虫から、蛹までずっと変化があり、何回飼育しても、面白い幼虫です。特に終齢幼虫の形と色相には魅力があります。ここに5齢1日目から前蛹までの8枚の写真をのせますので、ご覧下さい。
05年9月12日の午後から南山城、上狛、神童子の三ヶ所を足早に廻った。南山城でオオヒカゲの雌を1頭、上狛、神童子でウラナミジャノメを各1頭採った。早速持ち帰り、ビニール掛けしておいたら、ウラナミジャノメが産卵し、9月19日に孵化しました。年1回発生の加古川のウラナミジャノメの飼育はしたが、年2回発生のウラナミジャノメの飼育は初めてですので、早速、チヂミザサで飼育する事にしました。
シルビアシジミ(奄美亜種)は9月12日に蛹になり、9月16日には羽化しました。蛹から羽化迄の期間が短いので驚きました。
11月
05年11月5日(土)
9月30日に「虫トリ日記」をプロバイダーに転送中にバソコンが故障しました。早速、修理に出しましたがHDDが壊れているとの事で、今年、撮した写真や飼育の記録が失われました。今年は入院期間が長かったので、去年と比べると保存していた写真や記録は少なかったのですが、(加古川産)ウラナミジャノメ等、去年から引き続き飼育していた幼虫の写真は完結するまで、コピーを取っていなかったので、それらが失われたのは非常に残念です。
ホームページもプロバイダーに転送されたのは残っていましたが、手元の記録が全部無くなりましたので、更新が出来なくなり、しばらくお休みを頂きました。
パソコンも新しいのに入れ替え、ホームページもプロバイダーから引き戻し、やっと更新が出来るようになりました。しかし、蝶のシーズンが終わりに近づき、しかも9月迄の記録が無くなりましたので、ホームページに載せられる写真は限られていますが、これからもボチボチ載せていきますので、是非、ご覧ください。
ここに載せる写真は10月1日以降に撮したもので、9月30日以前の写真はありませんので、飼育写真も途中からになりますのでご了承ください。
神童子のウラナミジャノメは9月20日に1齢2日目の写真を載せていますが、今回は10月1日2齢4日目の写真から載せました。幼虫は2齢の期間が16日、3齢期間が24日で11月5日に4齢になりました。この調子では5齢になるのは12月頃になりそうですが、4齢のまま越冬するのか?、5齢で越冬するのか?どちらでしょうか?
台湾からの迷蝶、コモンマダラの卵を鹿児島のK氏より、食草付きで送って頂きました。食草はガガイモ科のブラウンカズラで鹿児島でも珍しい植物との事です。入手が困難なので、幼虫の飼育には制限があり、1頭あたり5-6枚のブラウンカズラを何回かに分けて送ってもらいました。
実は今回載せた幼虫の少し前にもコモンマダラの幼虫を送って頂き、その幼虫が5齢4日目に前蛹になったので、今回もその計算で食草のブラウンカズラを送って頂きましたが、今回の幼虫はだらだらと餌を食べ5齢5日目にはブラウンカズラが無くなってしまいました。鹿児島まで連絡しても間に合わないので、とりあえず葉の感じが似たキジョランと自宅付近に生えているガガイモを瓶に挿して、入れておきましたら、幼虫はガガイモを食べていました。卵から蛹まで、ガガイモで育つかどうかは不明ですが、ブラウンカズラの代用食にガガイモが使える可能性はありそうです。
退院後約2ヶ月が過ぎましたが、最近は自分で野外で手に入れた幼虫より、鹿児島から送って頂いた幼虫の飼育の方が多くなっています。ウスキシロチョウやツマグロキチョウも鹿児島産です。ウスキシロチョウは食草のナンバンサイカチ付きで送ってもらいましたが、飼育写真のほとんどが失われ、蛹と羽化時の写真だけが残っていました。ツマグロキチョウは以前に夏の飼育はしていますが、秋型の羽化を見たかったので、幼虫を送ってもらい蛹と羽化した成虫の写真を撮りました。
オオヒカゲは今年も多数の幼虫が孵化しましたが、1頭だけ個別に飼育している個体がいます。この幼虫は11月1日頃から仮眠中でしたが、今朝見ると脱皮して3齢になっていました
05年11月15日
年2化の神童子のウラナミジャノメは11月15日現在、4齢10日目で体長が10.5㍉ 体幅1.5㍉ですが、去年、飼育した年1化の加古川のウラナミジャノメは06年11月15日に6齢36日目で体長14.㍉ 体幅2㍉強でした。加古川の幼虫は06年12月19日まで、僅かですが糞をしていましたが、12月20日以降は完全に冬眠に入りました。神童子の幼虫は何時まで餌を食べるのか、4齢のまま越冬か?終齢で越冬するのか?興味があります。
今年、1頭だけ個別に飼育しているオオヒカゲの幼虫は11月5日に3齢になりましたが、以前に飼育した時は年が明けてから3齢になっています。越冬時の齢はばらつきがあるようです。今まで何回かオオヒカゲの飼育をしていますが、孵化後蛹化までの個別飼育は出来ていないので、今回は何とか最後まで、個別飼育を続けたいと思っています。
オオヒカゲの幼虫の飼育は冬の間殆ど放置しておいても良いので楽ですが、個別に飼育して、毎日、写真を撮ろうと思うとたいへんです。幼虫はスゲの葉の裏にいる事が多いうえに、寒くなると根元付近の茎の間に入ったりするので、ピントが合わず、全く写真の撮れない日もあります。それにスゲの葉に似た色ですので、写真が撮れてもピンボケが多いです。
鹿児島産の大型ヒョウモン類の卵を6種類送って貰いました。過去に飼育して「蝶・雑記」に載せている種類もありますが、6種類を一度に飼育するのは初めてですので、来年の春、一斉に飼育して、種類間の成長の違い等を比較出来るので楽しみにしています。
中でも、今年の春、入院の為、中途半端に終わったオオウラギンヒョウモンや奈良では滅多に見られないクモガタヒョウモンの飼育を完結したいと思っています。これから4-5ヶ月の越冬が重要です。
ヒョウモン類の卵は二つに分けて保管しました。一つはスミレを植えた容器の中へ卵を入れ、ナイロンストッキングで蓋をして、室外に置いてあります。残りの一つは容器の中に木の葉を入れ、孵化した幼虫が木の葉の裏に静止出来るようにして、室内で保管しています。これは時々、霧吹きで湿気を与えるようにします。幼虫の観察には室内保管の幼虫を見るようにします。
11月15日現在、オオウラギンスジヒョウモンとウラギンヒョウモン以外の4種類は幼虫が孵化しました。ミドリヒョウモンは10月24日に最初の幼虫が孵化、2-3日の間に全部孵化しました。メスグロヒョウモンは10月29日から2-3日の間に孵化。クモガタヒョウモンは10月30日から2-3日で全部孵化。オオウラギンヒョウモンは11月3日に最初の1頭が孵化。その後だらだらと孵化し、11月15日現在、約半数が孵化しました。
桜井のT氏が和歌山南端付近で採られたヤクシマルリシジミとサツマシジミの雌、それに九州から貰われたルリウラナミシジミの幼虫を届けてくださった。
ヤクシマルリシジミはウバメガシの新芽に数卵、産卵して、早くも幼虫が孵化し始めました。産卵日は2-3日の間に限定されますが、孵化にはかなりばらつきがあるようです。
サツマシジミも人工採卵に挑戦していますが、一向に産んでくれません。晩秋に花のある食草はヤツデ、ビワ等で、モチノキの花芽にも産卵するとのことです。モチノキの花芽がよく分かりませんが、とりあえず前記の三つを食草として選びましたが、全く産卵の気配はありません。
ルリウラナミシジミはインゲン豆で飼育出来るとのことで、スーパーで買ったインゲン豆を与えました。最初はインゲン豆に穴を開け中に入って豆を食べていましたが、この2-3日は豆から離れて歩きまわっています。多分、蛹化が近いのだと思います。、
2
200