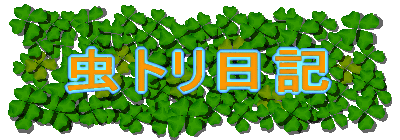
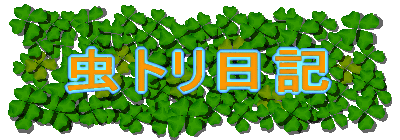
2006年
06年1月3日(火)
05年11月26日の午後から再入院がきまりました。急な事でしたので、05年11月15日以降の「虫トリ日記」を更新していなかったので、去年の写真が殆どですが、今年の始めの日記に載せさせて頂きます。
まず、急な入院のため餌を補給出来ず、行方不明になったオオヒカゲ(個別飼育)とヤクシマルリシジミの幼虫の最後の写真(11月26日)を載せます。
オオヒカゲは3齢22日でしたが餌のスゲがすっかり枯れて幼虫の姿は見つからなかった。
ヤクシマルリシジミの2齢10日目の幼虫は仮眠中でしたが、1週間先には帰宅して、餌のウバメガシを新しのに替えるつもりでしたが、外泊許可が出ず、帰宅した時はウバメガシはすっかり枯れ、幼虫は糞だけを残して行方不明になっていました。両種共、個別飼育は今迄していなかったので、残念です。
ルリウラナミシジミはインゲン豆のサヤから出て歩きまわっていましたが5頭の内2頭は蓋のナイロンストッキングの隙間から逃げ出し行方不明になりました。残った幼虫の内、一番早いのが11月17日に漸く前蛹になり、更に3日程して、11月20日に蛹になりました。この蛹は黒くなっていますが、まだ羽化していません。
しかし、最初に逃げ出して、部屋の何処かで蛹化していた個体の内1頭は12月末頃、に羽化して、既に硬くなっていました。2頭目はラッキイな事に1月1日に羽化して、部屋の壁にとまっていました。
ウラナミジャノメは入院の日の午前中に食草をスゲに切り替えました。チヂミザサは春の芽生えが遅いですがスゲは冬でも新芽が生えて来ていますので、入院が多少、長引いても大丈夫です。個別飼育の3頭と集団飼育の数頭はスゲの根元で寒そうに体を縮めて静止しています。多分、越冬は4齢だと推定しています。(幼虫のそばに脱皮殻は落ちていません。)
オオウラギンスジヒョウモンの幼虫が1頭だけ孵化して、枯れ葉の上に静止していました。他の卵はすっかり白っぽくなっていますが、幼虫は未だ中にいるようです。
今年はジャノメチョウの孵化が遅く、11月26日に初めて2頭が孵化しました。スゲの葉にとまらせて置いたらスゲの葉をかじって、少し大きくなったようです。
2月
06年2月12日(日)
このところ毎日曜日に一時帰宅の許可を得て入院先の病院から自宅へ帰っていますが、寒い日が続き、幼虫達も越冬中ですので、写真を撮る事もすっかり減っていますが、1月3日以降に撮った写真を少し載せておきます。
10月1日に紀和町まで、行った時にモミジの葉にいたミスジチョウの幼虫を見つけ持ち帰り、鉢植えのモミジにとまらせておいたら、枯れ葉の上で越冬していました。10月1日にはモミジは青葉でしたが、幼虫はモミジの枯れ葉に静止していました。当時と比べると少し大きくなったようです。庭に放置した鉢植えのモミジの葉で4ヶ月無事に過ごしていますが、春になると天敵の餌になる可能性もあるので、春には早く退院して、室内飼育に切り替えるつもりです。
餌のスゲが水不足ですっかり枯れてしまい行方不明になったと思ったオオヒカゲの幼虫(個別飼育)が枯れたスゲの茎に静止して越冬しているのが見つかった。11月26日に3齢22日目で未だ餌のスゲを食べていたが、今は全く食べずに静止していました。体色も悪くなり、大きさも少し縮んだようです。計算してみると今日で3齢100日目でした。
今年の春にはヒョウモン類の飼育に力を入れるつもりで、幼虫や卵を種類毎に二つに分け、一部は室内で保管して時々霧吹きで湿度を与えていますが、大部分は食草のスミレを植えた容器の中で保管していましたが、スミレにアリマキが大発生して、ヒョウモン類の幼虫の姿が全く見つからないのには大ショックです。今更、慌てても仕方がないので、春までこのまま様子を見るつもりです。室内保管の幼虫は干からびて死ぬ幼虫が増えていますので、春までに少しでも多く生き延びて欲しいと願っています。
ウスバシロチョウの卵の孵化の時期が近づいてきたので、調べてみると全部で15卵の内3卵の上部に穴が開いていました。今日は最高気温が5℃で随分、寒い日ですが、昨日は10℃と暖かい日でしたので、幼虫が孵化の準備を始めたようです。卵はムラサキケマンの根元においてありますので、孵化した幼虫は餌に困る事は有りません。しかし、私が幼虫の姿を見られるのは最短で来週です。
06年2月25日(土 )
実は先週末に急に退院しました。治療が一段落したので、今後暫く外来で様子を見る事になりました。ちょうど良い季節に退院出来てラッキーです。未だ治療の副作用が残っているのと、入院による体力低下で、人並みのことは出来ませんが、とりあえず、あまり世話の出来なかった芋虫達を調べてみました。
ウスバシロチョウの卵は2月12日に既に3卵程が孵化直前の状態でしたが、2月22日には大部分が孵化しました。天気予報では奈良地区の最高気温は15℃程度で非常に暖かい日でした。
幼虫は4頭を個別に飼育、ムラサキケマンの鉢植に一頭ずつ入れ、その鉢をプラスチック容器に入れ、上部をナイロンストッキングでカバーしました。2月23日に芋虫の様子を見ると孵化後2日目の幼虫は、ムラサキケマンの鉢から降りてプラスチック容器の底に降りていました。02年に飼育した時も幼虫は同じような行動をしたのですが、その時は餌のムラサキケマンとオヤブジラミを間違えたので、餌不足の幼虫が餌を求めて歩き回ったのだと思っていたのですが、餌を離れるのはウスバシロチョウの幼虫の習性なのでしょうか?今年の餌はムラサキケマンに間違いは有りませんが少し心配です。
その後、2月24日ー25日と様子を見ましたが、ムラサキケマンの葉の上に幼虫を置いても、時間が経つとプラスチック容器の底に幼虫は移動するようです。自然の状態でも幼虫はムラサキケマンの根元から離れているのでしょうが、ムラサキケマンの葉に戻るのは簡単だと思いますが、植木鉢を上ってムラサキケマンの葉に戻るのは大変かもしれません。ムラサキケマンの直植えの容器に入れる方法(集団飼育で行っている方法)に変える必要がありそうです。
集団飼育の幼虫は深めの植木鉢に半分ほど土を入れムラサキケマンを植え、その中へ幼虫を入れ、ナイロンストッキングで蓋をしていますが、昨日、様子を見たところ一頭はナイロンストッキングの上にいましたが残りの7-8頭の幼虫は何処にいるのか、全く分かりません。
ウラナミジャノメはスゲの根元付近で全く動かず、冬眠中です。昨年、ウラナミジャノメと同じ頃に飼育し始めたヒメウラナミジャノメは4頭が健在ですが、既に終齢幼虫で、暖かい日には餌のスゲを食べています。
ジャノメチョウの幼虫は全部で3頭いるようです。これも暖かい日はスゲを囓り、少しずつ大きくなっています。オオヒカゲ(個別飼育)は2月12日の状態と全く変わらず、冬眠状態です。
2月24日に久しぶりに外歩きに出かけ、ついでにオオムラサキとゴマダラチョウの幼虫を探しました。数頭ずついましたので、今年も少し飼って見るつもりで持って帰りました。例年、必ずいる木には今年は3頭いただけでしたので、そばに生えている榎も探しましたが、2頭いただけでした。オオムラサキの産卵は一度にかなりの数を産みますので、2-3頭しかいないのは秋までにかなり外敵に襲われ、減ったようですね。ゴマダラチョウもほぼ同数いますが、殆どが寄生されていると思いますので、寄生バエを羽化させて見るつもりです。
3月
06年3月6日(月)
3月3日午前9時30分に冬眠中のオオヒカゲ(個別飼育)を見ると少し動いていました。少なくとも2ヶ月以上は枯れたスゲの葉の同じ場所に静止していましたが、この朝は静止場所が少し変わっていました。3月4日と6日の写真も載せましたが、幼虫は新しいスゲの葉に移動してスゲの葉を食べ始めました。幼虫の体色も少し良くなりました。
ジャノメチョウは毎日少しずつスゲを囓り、少しずつ大きくなっています。写真では随分大きく見えますが未だ体長5㍉ 体幅1㍉強の小さな幼虫です。
ウラナミジャノメは個別飼育、集団飼育の幼虫ともに、2月の写真と全く変わりなく、スゲの根元で冬眠しています。今日は未だ気温が低いが、明日、明後日は暖かそうですから、そろそろ動き出しそうです。
ウスバシロチョウは孵化後、10日以上が過ぎましたが、相変わらず鉢植のムラサキケマンから離れてプラスチック容器の底へ下りています。集団飼育の幼虫は大きな植木鉢にムラサキケマンを植え、その中に7-8頭の幼虫を入れてありますが、何時見てもムラサキケマンの葉の上にいることは無く、多くて2-3頭の幼虫がムラサキケマンの根元に近い茎にいる程度で、日によっては全く姿が見られません。多分、土の部分にいるのでしょうが、土が黒いので、姿が見つけにくいのだと推定しています。自然の状態でも幼虫は餌を食べる時だけ食草に上がり、それ以外は食草から下り、枯れ葉の下などに隠れているそうです。
昨秋に鹿児島から送って頂いた大型ヒョウモン類6種類の幼虫の越冬方法は05年11月15日に述べましたが(1)ポリ容器の中に浅めに土を入れスミレを植え、木の葉を入れ、その中へ幼虫を入れ、ナイロンストッキングで蓋をする。(2)ポリ容器の中に木の葉を入れ、幼虫を入れて保管。時々霧吹きで適当な湿度を与える。の2方法で保管しました。
11月末から2月中旬まで入院していましたので、出来るだけ手のかからない(1)の方法がベターだと思ったのですが、冬の間、幼虫の姿の見やすい(2)の方法も併用しました。出来るだけ日曜日には家に帰り、幼虫の世話をするつもりでしたが、(2)の方法では霧吹きの回数が減り干からびて死んだ幼虫が増えました。6種類の内、何とか今まで生き残ったのはミドリヒョウモンとメスグロヒョウモンの一部だけでした。クモガタヒョウモンとオオウラギンヒョウモンは去年の11月の時点では多数の幼虫がいましたが、干からびて死んでいました。
(1)の方法は自然の状態に近く、良い方法だと思うが、今回は入院中に乾燥しすぎてスミレが枯れ、春になっても芽が出ない様な状態は避けたいと思い水分の補給が多すぎ、加湿になったのではないかと思います。庭の鉢植えのスミレは1月には全部枯れていましたが、(1)の方法でポリ容器の中に植えたスミレは枯れずに残り、多数のアリマキが発生していた。2月に容器の中を見た時はどの容器にも幼虫の姿は全く見つからなかったので、今年のヒョウモンは全滅したと思い諦めていました。3月に入りヒョウモンの幼虫が動き出す時期が近づいたので、すべての容器を調べました。結論としては、生存率は低かったがウラギンヒョウモンを除いて他の5種類のヒョウモン類は少しずつ生き延びていました。特に未だ飼育経験の無いクモガタヒョウモンの幼虫の姿を見つけた時は驚き感激しました。意外な事にスミレが枯れて、餌らしいものは無いのに幼虫は体長4㍉程度と、かなり大きくなっていました。オオウラギンヒョウモンの幼虫は卵の産まれていたススキの葉にいましたが体長1.5㍉程度と孵化したままの状態で未だ、冬眠状態でした。
尚、今冬のヒョウモン類の生存率が悪かったので、再度、越冬後の幼虫を鹿児島から送って頂きました。到着した幼虫を見て驚きました。オオウラギンヒョウモン、オオウラギンスジヒョウモン、メスグロヒョウモンなどの幼虫は奈良で越冬した個体は未だ体長1.5㍉程度ですが、鹿児島の幼虫は大きな個体は体長2.5㍉と既にかなり大きくなっていた事です。鹿児島と奈良の気温差をつくづく感じました。
06年3月16日(木)
前回に記載しましたヒョウモン類の越冬方法(1)で、アリマキが多数発生し、ヒョウモン類の食草のスミレやタチツボスミレの茎や葉裏にびっしりとアリマキが付き、湿気が高か過ぎ、環境が悪いので、ヒョウモン類の幼虫は全滅したと思っていましたが、中に入れた木の葉やススキの葉等を一つずつ調べ、少ないながらウラギンヒョウモン以外の種類は生きているのを確認出来た事を記載しましたが、確認出来た幼虫は食草を植え込んだ別の容器に入れ飼育を開始しました。
幼虫を越冬さしたポリ容器は更に幼虫が残っている可能性があるので、念の為そのまま保存していましたが、暖かい日に容器を覗いて驚いた。容器の中のスミレやタチツボスミレは新芽を出し始め、新芽にはアリマキの大群が殆ど隙間が無いぐらい付いていましたが、そのアリマキの群の隙間にヒョウモン類の幼虫がいました。見た目であまりにも環境が悪すぎるので、悲観し過ぎたようですが、良く考えてみれば、アリマキ自体はゴイシシジミの幼虫の餌であり、クロシジミの産卵はアリマキのいるような場所に行われるようですし、ヒョウモンの幼虫にとって、アリマキは殆ど無視出来る存在なのかも知れません。メスグロヒョウモンなどは全くいないと思っていたのに気温が上がり暖かい日には湧き出るように多数の幼虫が姿を現し驚きました。
ヒョウモン類の幼虫の越冬には(1)法を少し改良し、湿度管理に気を付ければ、かなり生存率は上がりそうです。これ以外に冷蔵庫を使用する方法もかなり有力なのでないかと推定しています。昨年、ミドリシジミの卵を冷蔵庫で保管した場合、吹き流しで室外保管するより、かなり孵化率が高かったので、卵と幼虫の差は有りますが次の機会には是非試して見たいと思っています。
今冬は予想外に気温が低く寒い日が続きましたが、3月には日替わりで気温の高い日と低い日があります。ヒョウモン類の種類にもよりますが、気温の高い日は幼虫は元気に動きますが、気温の低い日は幼虫は全く動かず仮眠状態です。
越冬したヒョウモン類の幼虫の中ではクモガタヒョウモンの成育が一番早いようです。クモガタヒョウモンが越冬したポリ容器の中を調べると、タチツボスミレの新芽が出ており、かなり食べられ跡がありました。3頭のクモガタヒョウモンの幼虫が生き残っていましたが、3頭とも既に2齢になり、その内の1頭は仮眠に入っています。この2-3日はかなり寒い日が続きますが、気温の高い日がくれば、脱皮して3齢になりそうです。
オオウラギンヒョウモンは他のヒョウモン類と比べ、成育速度は遅いようです。奈良で越冬した幼虫の一部は体長2㍉強程度まで大きくなった個体もいますが、未だ枯れたスミレの茎などの隙間で静止している個体もあります。特に小さな個体は気温の低い日は何処に行ったのか全く姿の見えない事があり、心配していると気温の高い日にはひょっこり姿を見せたり、一喜一憂の日々です。
尚、3月5日に鹿児島から再度、送って頂いたオオウラギンヒョウン、オオウラギンスジヒョウモン、メスグロヒョウモンの幼虫は2齢幼虫が増えてきました。奈良で越冬した幼虫とかなりの差がありますので、個別に飼育するのは奈良で越冬の個体でおこなう事にします。
メスグロヒョウモンはクモガタヒョウモンについで、春の成長は早いように感じます。鹿児島から3月5日に送って貰った幼虫のかなりの数が2齢になりました。奈良で越冬した幼虫も1頭が2齢になり、仮眠中の幼虫もいます。しかし、未だ小さな幼虫も少しはいますので、例外はありそうです。
オオウラギンスジヒョウモンはメスグロヒョウモンとほぼ同じように成長していますが、強いて言うならメスグロヒョウモンより少し遅い感じです。未だ飼育の初期段階ですので、飼育が完了しないと成長の速度をうんぬんするのは少し早そうですが、クモガタヒョウモンが早くて、オオウラギンヒョウモンが遅いのは間違いなさそうです。
只、クモガタヒョウモン以外は過去に飼育経験がありますので、過去の記録を見てみますと、4月初旬に1齢幼虫の飼育を始め、4月中旬に2齢になっていますので、奈良で越冬した小さな幼虫はまだまだゆっくりと大きくなりそうです。食草のスミレも我が家では室内に入れていますので、かなり大きくなっていますが、戸外では、昨年、多数のスミレが生えていた場所でも、未だ見つかりません。但し、タチツボスミレは見つける事が出来ます。
ウラナミジャノメはスゲの根元で全く動かず静止しています。それに比べてヒメウラナミジャノメは暖かい日はスゲの葉を食べ、糞もかなりしています。
ジャノメチョウは毎日、スゲを少しずつ囓っていますが、なかなか大きくなりません。変わりばえしませんが1枚写真を載せます。
室内で飼育のオオヒカゲは個別飼育の幼虫が動き出し、スゲを食べて少し大きくなりましたが、室外で飼育の多数の幼虫は未だ動き出していない様です。大きさは体長10㍉程度の小さいのもいますが、平均13㍉ー14.5㍉程度です。
4月
06年4月15日(金)
また急に入院して、虫トリ日記をしばらく休んでしまいました。3月中頃から腹具合が悪いと思っていたのですが、3月24日に我慢が出来ないので、病院へ行ったら、そのまま入院となり、10日あまりを病院のベッドの上で過ごしました。持病の治療薬の副作用による腸閉塞ではないかとの説明でした。
残念だったのは、その間飼育中の幼虫達の面倒を見る事が出来ず食草が枯れ、一部の幼虫が死亡したり、行方不明になった事です。それに写真も全く撮れなかったので、その間の幼虫の成長記録が抜けてしまいました。日記は約一ヶ月抜けてしまいましたが、シーズンインの為、結構、沢山ありますので、比較的、最近の状況を載せる事にします。
個別飼育のウラナミジャノメの幼虫が3頭いますが、越冬した場所で静止していましたが、やっと動きだしました。(A)体長8㍉ 体幅1.5㍉強 4月12日に動き出し4月13日から餌を食べ始めました。(B)体長13㍉ 体幅1.5㍉ 他の幼虫に先駆けて、4月5日から動き出し、食事も食べ始めましたので、他の2頭に差を付けて随分大きくなりました。(C)体長7㍉弱 体幅1.5㍉はやっと4月13日から動きだしました。
昨年の10月中旬のウラナミジャノメの孵化日とほぼ同じ時期に孵化し、終齢幼虫で越冬したヒメウラナミジャノメは2月中旬の暖かい日には動きだし、スゲを食べていましたが、4頭の内1頭は4月9日に前蛹になり、4月15日には蛹化していました。引き続き2頭目が前蛹になりました。発生時期が1ヶ月以上差がありますが、ウラナミジャノメの成長はゆっくりしています。
個別飼育のオオヒカゲはスゲを食べて、かなり大きくなりました。4月8日には5回目の仮眠に入り、4月9日には脱皮して5齢になりました。過去の飼育経験では終齢幼虫の体色は背部が少し白っぽくなり、青と白の線模様ができましたが、今回の5齢幼虫は4齢までと殆ど変わらないので、更に脱皮して6齢になりそうな予感がします。去年からの写真を見直しましたが、間違いなく5回脱皮をしています。
今年も蝶の季節になりましたが、入院続きで体力が充分でないので、未だ一回も本格的な外歩きはしていません。春だけしか発生しない蝶も多いし、未だ飼育をした事のない蝶も多いので、多少、焦りを感じています。
ツマキチョウは今からが雌の多い季節ですが、この2-3年タネツケバナでの採卵を失敗していましたので、今年こそはと思っていました。ところが鹿児島のK氏からツマキチョウの採卵をしたので、飼育の希望があれば送るとのメールを頂き、発送して貰いました。さすがに暖かい鹿児島では4月初旬に既にツマキチョウの産卵が終わっているのには感心しました。鹿児島での採卵はスカシタゴボウでされ、卵はスカシタゴボウに産み付けられていました。私もスカシタゴボウで飼育をしたいと思い近所を探しましたが見つからないので、沢山生えているタネツケバナで飼育する事にしました。タネツケバナも今の時期は未だ花が咲き種も小さいので扱い易いのですが、すぐに大きくなり種がはじけるので苦手です。鹿児島のツマキチョウは順調に大きくなり、今は2齢幼虫です。
サツマシジミの卵も餌のサンゴジュの蕾付きで鹿児島から送って頂きました。但し、こちらへ付いたときは幼虫は既に孵化しており、すぐにサンゴジュの蕾が役立ちました。幼虫は体長1㍉ 体幅0.2-0.3㍉程度の大きさで、老眼の私には幼虫の確認に時間がかかります。4月12日に幼虫は孵化しましたが、4月14日にサンゴジュの蕾にいる幼虫を天眼鏡を片手に探していましたら、偶然、サンゴジュの蕾に産卵されたサツマシジミの卵を2卵見つけました。ちょうどその日に2卵は孵化し、幼虫が2頭増えました。
昨年から飼育のヒョウモン類は10日あまりの入院で、タチツボスミレが枯れて、幼虫が死んだり行方不明になったり、無事に育った幼虫も成長記録が途切れたりですが、とりあえず最近の写真を載せることにしました。
一番大切にしているオオウラギンヒョウモンは未だ1齢か2齢幼虫で、なかなか大きくなりません。毎日、幼虫の写真を撮ろうと思うのですが、幼虫はスミレの根元や土の上の枯れ草の陰にいることが多く、なかなか見つかりません。たまにスミレの上の方にいていて、明かりで照らすとポロリと下に落ち、容器の外に出てしまう事があり、気づかずにいると幼虫を1頭失う事になりますので、毎日、幼虫の姿を探すのも善し悪しなのですが、たまに幼虫を見るのでは脱皮などの成長過程を見逃してしまいますので、幼虫を見るのにも神経をつかいます。早く3齢以上になるのを楽しみにしています。
他のヒョモン類はかなり大きくなっていますし飼育も比較的らくです。特にメスグロヒョウモンは成長が早く、個別に飼育している個体は体は黒色で棘は橙色ですので5齢のようですが、大きさが未だ体長16㍉程度です。以前飼育した時には蛹化前には体長40㍉ほどになりましたので、今後どうなるのかと思っています。
ミドリヒョウモンはメスグロヒョウモンについで成長が早く、大きな幼虫は15㍉程度になっています。
クモガタヒョウモンは最初の成長は随分早く、トップを走っていましたが、ここしばらくは殆ど大きくなっていません。タチツボスミレから下へおりて、飼育容器の底にいたり、タチツボスミレの葉の裏面で静止している姿ばかりで、食草を食べる姿を見ていません。無事に蛹まで育つか少し心配です。
オオウラギンスジヒョウモンは入院のため最も被害を受け、個別に飼育していた幼虫の食草が水不足で枯れて、幼虫は行方不明になりました。やむを得ず集団飼育をしていた幼虫の中から、一番小さな幼虫を選んで、個別に飼育することにしました。
桜井のT氏がエゾシロチョウの越冬巣を10巣貰ったが、小さな巣でも20頭以上の幼虫が入っているので、沢山いるのでと、私にも1巣持参して下さった。早速、桜の若葉を用意して枝の上に巣を置くと、今まで冷蔵庫で保管されていた多数の幼虫が巣から出て葉を食べ始めました。越冬幼虫は3齢で褐色、体長6-7㍉ 体幅1㍉程度ですが、4月15日には一部の幼虫が4齢になったらしく、白い長い毛の生えた幼虫が混じっていました。
エゾシロチョウの幼虫と共にキリシマミドリシジミの卵も持参されたが、すっかりカビが生えてしまったので、孵化せぬ場合は「ごめんね」との事でした。、私としては一頭でも孵化して、蛹までの写真を撮るのが目的ですので、カビを筆で軽く落とし、湿らせたテッシュを敷いたプラスチック容器に卵を入れ、暖かい場所に置き孵化を待ちました。4月12日には幼虫が孵化しましたので、早速、庭のアラカシの新芽を少し開いて、幼虫を中へ入れました。幼虫は中へもぐり込み4月15日現在全く消息は分かりませんが、大きくなって姿を現す事を期待しています。しばらく写真は撮れませんが我慢して待つつもりです。
06年4月25日(火)
個別飼育のウラナミジャノメの幼虫は3頭の内2頭は未だあまり餌を食べず、大きさも越冬時と殆ど変わらないが、1頭だけは餌をよく食べ成育が早く、4月24日には5齢になりました。
オオヒカゲは5齢になってから17日が経ち、体も随分、大きくなりました。最近になって、胴体に沿って白線がでてきたので、このまま蛹になるのかな?と思っていましたが、4月25日には仮眠に入りました。この幼虫は6齢になる訳ですが、集団で飼育中の幼虫達が何齢で蛹化するかは確認出来ません。
鹿児島から送って貰ったツマキチョウの卵は既に5齢になりました。簡単に手に入る食草はタネツケバナですので、タネツケバナで飼育していますが、幼虫が孵化した頃は花がかなり咲いていましたが、今は種子が実り弾けています。タネツケバナの最盛期は過ぎ去ったようです。例年、ツマキチョウの採卵をタネツケバナで行い失敗していますが、最近、イヌガラシの生えている場所を見つけましたので、今年も採卵に挑戦するつもりでツマキチョウの♀を採りに行きましたが、見かけた4-5頭は全部、♂でした。日を改めて行くつもりです。
メスグロヒョウモンとミドリヒョウモンの4月15日の記載で、齢表示に誤りがありましたので、来訪者の皆様にお詫び致します。今日、気が付き訂正いたしました。メスグロヒョウモンは既に4-5頭が5齢になりました。それに続いてミドリヒョウモンも5齢になり始めました。飼育容器が足りないので、室内で鉢植えの食草にオープンで飼育している幼虫もいますが、5齢になると食草のスミレ類から離れる個体が増えますので、容器のやりくりがたいへんです。
オオウラギンスジヒョウモンは未だ4齢幼虫が殆どで、やっと1頭が5齢前の仮眠に入っています。
オオウラギンヒョウモンは相変わらず小さなままで、幼虫はスミレの根元付近にいる事が多く、スミレの茎や小さな蕾を囓っている事が多く、スミレの葉も小さな根元付近のものを囓るようです。他の種類と比べると、かなり神経質で、すぐに落下します。現在、一番大きな幼虫は3齢幼虫ですが未だ5㍉程度で、すぐに落下しますので、紛失せぬように気を使います。
サツマシジミの幼虫はサンゴジュの実を食べてかなり大きくなりましたが、それでも私の老眼で探すのには苦労ですし、正確な体長の測定などは不可能です。
3月24日の朝、餌のサンゴジュが萎れているのに気が付きました。幼虫を調べると一頭の幼虫がサンゴジュから下りて瓶の外側にいました。写真を撮って、パソコンで拡大すると、意外にごつごつした幼虫でした。
アラカシの新芽で飼育中のキリシマミドリシジミの幼虫は孵化後一週間経った4月20日にはアラカシの新芽の中側を食べ尽くしたのか、新芽が枯れて来た為かは不明ですが、芽から出て外を歩いていました。早速、新しいアラカシの新芽に移し替えました。その前にいつもはなかなか撮れない写真を撮しました。
5月
06年5月5日(金)
4月15日に個別飼育のウラナミジャノメの写真を3頭(A.B.C.で表示)載せましたがその後、(B)は早くから餌のスゲを食べ大きくなりましたが(A)(C)は餌を食べるのが遅れ、未だ小さく、4齢です。特に(C)はスゲの硬い部分に静止しており、硬い葉を少し囓るだけで、体が成長する事無く、死んでしまいました。(A)は餌を食べ始めましたが、未だ(B)の半分以下の体長しかありません。今日、載せた4枚の写真は全部(B)のものですが、驚いた事に脱皮して6齢になりました。以前に飼育した(加古川)の年一回発生の幼虫が7齢になったのにも驚きましたがこの幼虫が6齢になるとは思っていませんでした。(C)幼虫が今後、どのような成長を示すのかが楽しみです。
オオヒカゲは6齢になりました。背面が白っぽくなり、白線と緑色の線模様が体に沿って表れた。大きさも体長51㍉と随分、大きくなりました。
エゾシロチョウの幼虫の大部分は4齢幼虫ですが、一部の幼虫が5齢になりました。5齢幼虫は背部が橙食で白い毛が生えています。3齢から4齢になった時も白い長い毛が目立ちましたが、今は殆ど目立ちません。群でいる事が好きですので、こすれて毛がねてしまうのかも知れません。
鹿児島のツマキチョウは5月初旬に全部、蛹化しました。未だタネツケバナを時々見かけますが、タネツケバナは非常に少なくなりました。種子は少ないようですがオオタネツケバナの花が少し遅れて咲いています。奈良では産卵用のツマキチョウの雌を採るには今頃が良い時期のようですが、自然状態でツマキチョウの雌は何に多く産卵するのでしょうか?この3年ほどツマキチョウの採卵に失敗していますので、5月1日にツマキチョウの雌を採りイヌガラシで採卵を行いましたが不成功でした。未だツマキチョウはいますので、今年もう一度トライのつもりです。
ヒョウモン類ではメスグロヒョウモンが予想以上に残っていました。数も多いですが、成長も早く既に3頭ほどが蛹化しました。(写真の幼虫は同じ個体を載せていますので、未だ終齢幼虫です。)終齢になると餌のタチツボスミレから離れ飼育容器の隅や天井に静止している事が多いです。写真が撮りにくいので餌の上に戻してやると非常に早く動き廻り、なかなか写真を撮らしてくれません。しばらくしてから見ると盛んに餌を食べている事が多いです。
メスグロヒョウモンに少し遅れてミドリヒョウモンも1頭が前蛹になりました。メスグロヒョウモンと同様に終齢幼虫は餌のタチツボスミレから離れて、飼育容器の底や天井にいる事が多くなります。
オオウラギンスジヒョウモンも殆どの個体が5齢になりましたが、大きさは随分小さいので、もう一度脱皮する可能性が大です。写真の幼虫は実際に6齢になりました。軽々しく発言できませんが、ヒョウモン類は終齢が6齢のものが結構、あるのかもしれません。昨年の秋にツマグロヒョウモンを4頭飼育しましたが、全部、終齢は6齢でした。残念な事にパソコンのHDDが壊れ写真が残っていませんので、暇な時にもう一度飼育して確かめ、、今度は写真を保管するつもりです。
オオウラギンスジヒョウモンの幼虫はタチツボスミレの葉の裏面にいたり、葉の表や茎にいる場合も写真を撮そうと思い明かりを照らすと頭部を曲げ、体も曲げて静止してしまい、なかなか良い写真が撮れません。
オオウラギンヒョウモンは3月頃から毎日、眺めていましたが、いっこうに大きくならず、それだけで無く姿まで隠してしまうので、やきもきしていましたが、ようやく成長を始めました。オオウラギンヒョウモンの奈良での観察は4月に入ってからでも良さそうです。個別飼育の幼虫は何頭か紛失してしまいましたが、集団飼育の幼虫は無事に成長しているようです。写真の幼虫は仮眠に入りました。相変わらず写真を撮ろうと明かりを照らすと落下したり、大急ぎで逃げたりしますので、仮眠中の撮影は気が落ち着きます。
キリシマミドリシジミが孵化した4月12日には我が家のアラカシの新芽が開く直前でしたが、今ではすっかり大きな葉になってしまいました。幼虫には少しでも柔らかい葉をと思い近所に生えるアラカシの芽を与えています。幼虫は大きくなり、若齢では体色は緑色でしたが、だんだん赤味が増してきました。
サツマシジミの食草のサンゴジュの蕾もサツマシジミの卵と一緒に鹿児島から送って貰ったので、サンゴジュの蕾が無くなりかけて大慌てで、心当たりのサンゴジュの生えている場所へ行ったが、意外な事に殆どのサンゴジュには蕾が無かった。刈り込みの具合で蕾が付き難いのでしょうか?生け垣で赤い実を見かける事が多いので全く安心していたのですが!とりあえずガマズミの花が咲いていましたので餌をガマズミに切り替えました。幼虫はガマズミの蕾や茎を食べていましたので安心していたのですがガマズミの蕾が少なかったのか、今回の写真が最後になってしまいました。面白い形の幼虫ですので、大きな幼虫や蛹を見たかったのですが残念です。
06年5月16日(火)
ウラナミジャノメは個別飼育の内、1頭が急に大きくなりましたが、2頭目もスゲの柔らかな新芽を食べて、成長が早くなってきました。冬眠から早く目覚め、餌のスゲの柔らかな部分を食べるかが、成長に大きく影響するようです。集団飼育のウラナミジャノメも小さな方の個体と同じ程度の成育状況です。
オオヒカゲは体長、体幅共に大きくなり、5月16日には体が半透明になり体長も少し縮んだようです。蛹化が近いようです。
5月5日迄、載せていたサツマシジミは残念な事に死んでしまったのですが、また新たにサツマシジミの卵とサンゴジュの蕾を送って頂き再飼育することになりました。卵は5月14日ー15日に一斉に孵化しました。幼虫は非常に小さいので、私の老眼ではたいへん見にくいのですが、写真でもかなりぼけています。卵から孵化するところを20枚ほど撮ったのですが、載せるのを躊躇する様なぼけ写真です。取りあえず3枚だけ載せる事をお許し下さい。
キリシマミドリシジミは孵化後27日で前蛹に、28日目に蛹化しました。餌にした庭のアラカシの葉はすっかり大きくなり、今では幼虫を飼える新芽は全く有りません。ミドリシジミ類の孵化は食草の芽生える僅かな期間が勝負なのですね。幼虫がその僅かな期間を知り、孵化するのが不思議です。
鹿児島県照国町産のミカドアゲハの卵とオガタマノキの新芽、新葉を送って貰いました。オガタマノキの新芽や新葉はかなり厚みが有り、硬い感じですが、卵はかなり大きな新葉にも産卵してあり、孵化した幼虫はその大きな葉を食べます。オガタマノキの新芽でもかなり硬い感じで、アオスジアゲハの食草の楠の新芽と比較すると随分硬さが違う様です。
九州のミヤマカラスアゲハの卵を送って頂きました。近畿地方のミヤマカラスアゲハより九州産の飼育の方が先になってしまいました。
ミドリヒョウモンは前回、前蛹になりましたが、今日は蛹を載せました。
日記に載せたメスグロヒョウモンは意外に蛹化までに日数がかかり、今日現在、吹き流しの中で前蛹の状態です。吹き流しの中の前蛹の写真は撮りにくいので、先に蛹化した個体の写真を載せておきました。
オオウラギンスジヒョウモンは6齢になって10日余りが経ちましたが、未だ蛹化の気配はありません。毎朝、写真を撮ろうと思い様子を見ると、スミレの鉢から下りて、飼育箱の底にいますので、スミレの葉に上げると、丸くなって静止していますが、しばらく放置すると盛んに餌を食べています。この作業をしないと幼虫は何時までもお腹を空かせているのか、自分で餌を探して植木鉢の上に戻るかは不明ですが、自然の状態ではスミレから離れていても必ず戻る筈です。しかし、集団で飼育していた幼虫の一頭が飼育箱の底で仮眠していたので放置して数日後に見ると、脱皮していましたがスミレに戻るのを忘れたのかどうか理由は定かではありませんが死んでいました。それ以来、なるべく飼育箱の底にいる幼虫は食草に戻す様にしています。
オオウラギンヒョウモンは相変わらず成育が遅く、ここに載せている幼虫は成育の早い方ですが漸く5齢になりました。オオウラギンヒョウモンはオオウラギンスジヒョウモンと同様に飼育箱の底で静止している事が多く、スミレの上にいる事は少ないです。むしろオオウラギンヒョウモンの方が地上にいるのが好きなようです。特に若齢の時は土の上の物陰に潜む事が多く、姿を探すのがたいへんですが、写真の幼虫はかなり大きくなったので、見つけ易くなり、何時も飼育箱の底をまず探す事にしています。
エゾシロチョウは写真のように5齢になり、蛹化も近そうだと思っていたのですが、最近になって幼虫が赤い汁を出して死に始め、今日現在弱った幼虫が1-2頭いますが、時間の問題です。原因は不明ですが、可能性の高いのは病気だと思います。他に沢山飼育していますので伝染が心配です。他に考えられるのは餌の詰め過ぎですが、残った1-2頭は餌を減らし大きな容器に入れてありますが、回復は不可能のようです。
06年5月26日(金)
オオヒカゲは5月16日に載せた写真が既に半透明で、蛹化が近い様子でしたが、5月19日に前蛹になり、5月20日に蛹になりました。集団飼育の幼虫は終齢幼虫が殆どですが、未だ、蛹にはなっていません。
ウラナミジャノメは個別飼育のとびきり成育の早い幼虫が蛹になりました。個別飼育のもう1頭の幼虫は6齢になりましたが、未だ6齢4日目ですので、蛹化にはもう少し日にちがかかりそうです。集団飼育の幼虫も随分大きくなりましたが、未だ蛹化の気配は有りません。以前に飼育した加古川のウラナミジャノメは5月初旬には蛹になっていました。産地により発生時期が変わるのでしょうか?それとも今年の天候不順で全体が遅れて居るのでしょうか?
新しく飼育をしなおしたサツマシジミの幼虫の写真を載せます。孵化したての幼虫は非常に小さいので、孵化後3日目からの写真です。幼虫は急速に大きくなり、孵化時の数倍になりましたが、それでも孵化後12日目で体長5㍉ 体幅2㍉強です。成長の途中で幼虫は脱皮をしている筈ですが、完全に確認出来ていませんので、幼虫の大きさは孵化後の日数を書きました。孵化後12日目の幼虫は姿がかなり変わり、脱皮殻がありましたので、脱皮して齢が変わった事は確かですが何齢になったのかは不明です。(3齢ぐらいかと推定していますが?)
ミカドアゲハは毎日、少しずつ大きくなり、5月24日には5齢になりました。4齢までは黒い幼虫で、写真では何齢か分かり難いですが、5齢になると体色が黄褐色になります。始めて見ると一瞬、病気かと思います。体色は26日にはかなり黄色っぽくなってきました。
ミヤマカラスアゲハの食草は最初、キハダを使いましたが、キハダの入手が難しいので、途中からカラスザンショウに切り替えました。少し心配しましたが、全く問題無く食べてくれました。自然に生えているカラスザンショウで車で行けると言う条件を満たすにはかなり遠くまで行く必要があり、何回も行かなければならないかと心配していましたが、冷蔵保存で蛹までの期間、充分新鮮でした。
三輪神社から天理の方へ「山辺の道」を歩いていると、ウツギの蕾にトラフシジミが飛んできてとまりました。産卵している様子でしたので、調べると卵が見つかりました。緑色の小さな卵です。5月15日の夕方に孵化しました。幼虫は黒褐色で非常に小さいです。成長は早く5月26日(孵化後7日目)には体長は3㍉程になり、探し易くなりました。
オオウラギンスジヒョウモンはメスグロヒョウモンやミドリヒョウモンと比べかなり遅れましたがようやく蛹化しました。飼育頭数や飼育方法により、多少の変化が有るかも知れませんが、4種類のヒョウモン類の中ではメスグロヒョウモンの成育が早く、ほぼ同じであるが、心持ち遅れてミドリヒョウモンが続きます。既にこの2種は成虫が羽化を始めました。オオウラギンスジヒョウモンはかなり遅れて蛹化しました。
オオウラギンヒョウモンは更に遅れて、未だ3齢らしい幼虫がいます。今回の個別飼育は植木鉢に食草を植え、その植木鉢の入る大きなプラ容器に植木鉢を入れ幼虫を飼育したが、幼虫は殆ど植木鉢を下りてプラ容器の底にいました。毎日、写真を撮る時は幼虫を植木鉢の上へ戻しているが、戻すと幼虫はスミレを盛んに食べ始めます。自然状態では幼虫はスミレを離れても、フラットな場所で有ればスミレに戻り易いが、高低差が有ると戻り難いのでは等と考えてしまいます。但し、多数飼育の場合は大きな植木鉢の底に少しだけ土を入れスミレを植え、幼虫をその植木鉢の中で飼育していますが成長は遅く未だ3齢程度の幼虫もいます。多分、飼育方法の影響は少なく、オオウラギンヒョウモンの成育が特に遅いのだと思います。
6月
06年6月6日(火)
かねてから蒜山高原へ行って見たいと思っていたが、長距離の車の運転は無理なので諦めていたのですが近所の知人が日帰りバスツアーが有るので、一緒に行かないかとのお誘いを頂き、5月28日(日)のバスツアーに参加することにしました。格安ツアーでしたので、その日だけで35台のバスが近畿から出ているとの話でしたが、行って見ると大勢の人が指定コースのサイクリング用道路を歩いていました。人の多いのが難点でしたが、上蒜山、中蒜山、下蒜山の山麓に広がる草原の美しさを堪能できました。あいにく曇がちの天候でしたが、時折、日が照ると多数のウスバシロチョウが飛び、新鮮なギンイチモンジセセリも姿を見せました。ウスバシロチョウは奈良県には棲息せぬ蝶ですので、多数のウスバシロチョウを見ただけで満足でした。ウスバシロチョウとギンイチモンジセセリの写真を撮って来ましたので載せておきます。
サツマシジミの食草のサンゴジュですが、個人住宅では生け垣に、公園では生け垣やまるく刈り込んだりしていますが、刈り込んだ木や小さな木には殆ど蕾は有りません。それに比べて、手入れのしてないサンゴジュの木や大きな木には多数の蕾がついています。サツマシジミの飼育には自然生えのサンゴジュの大きな木を探しておく必要が有ります。今回の飼育では卵とサンゴジュの蕾を鹿児島から送って頂いたので、冷蔵保存で蛹まで無事に飼育できました。サンゴジュの蕾は20日程度は冷蔵庫で保存可能です。蝶の飼育全般に言える事ですが、サツマシジミの幼虫も蛹化少し前の終齢では沢山食べますので要注意です。花や蕾を食べる幼虫の成長は早いですが、サツマシジミも孵化後15日で蛹になりました。
ミヤマカラスアゲハが終齢の末期に入り驚く程大きくなりました。特に頭部付近の横幅は大型アゲハ類の中でも特に大きい部類に入ると思います。最近、小さな種類の飼育が多いので、逃げない様に気を使いますが、ミヤマカラスアゲハの幼虫は殆ど動かず、見失う事もないので、安心して飼育できます。
ミカドアゲハは4齢までは体色が黒色でしたが、5齢になり黄褐色になり、黄味が強くなり、次に緑色に変化します。やがて半透明になった幼虫は蛹化します。食草のオガタマノキは鹿児島から送って頂き、冷蔵保存で蛹化まで充分保存可能でした。
トラフシジミの食草のウツギは産卵された時は緑色の小さな蕾でしたが、やがて大きく膨らみ白い花を咲かせます。幼虫は花の花粉も食べますので、糞が黄色くなります。幼虫は成長するにつれ、沢山食べるようになり、食草の確保の為ウツギの木を探す事になります。以前にウツギの木を見た場所へ行くために山の中まで入りウツギの蕾を採っていましたが、白い花が咲き目立ちだすと自宅のすぐ近くに沢山有るのに気が付きました。しかし山の中までウツギを採りに行ったおかげで、ウツギの蕾にはトラフシジミの幼虫がついており、幼虫の数が随分増えました。但し気を付けないと最初からいる幼虫との区別が付かなくなりますので、ウツギの蕾のチエックが必要です。最後の幼虫が蛹になる頃にはウツギの花も満開から散り始めになります。花の時期は短いので、幼虫の成長もそれにあわせているようです。
トラフシジミの春型の産んだ幼虫は蛹になり、夏型として羽化する個体と越年して次の年の春に羽化する個体に分かれるそうですが、ちょうど良い機会ですので、見てみたいと思っています。
オオウラギンヒョウモンは個別飼育をしている2頭の内1頭がやっと蛹になり、集団飼育の幼虫も2頭が蛹になりました。写真の蛹は随分黒いですが、集団飼育の蛹は淡褐色でかなり明るい感じです。殆どの幼虫が終齢で、蛹化の時期が近そうですが、まだ3齢か4齢程度の幼虫もいます。
ギンイチモンジセセリの採卵を行い飼育をすることにしました。幼虫は出来るだけ個別に飼育して、成長の過程を見てみたいと思い、ススキに比べて背丈の低いチガヤを小さな鉢に少し植え、一鉢で1頭ずつ飼育する予定をたて、最初に孵化した幼虫をチガヤにのせました。幼虫はチガヤの葉の先端付近を綴って巣を造って中にいるのや、巣を造らずに行方不明になるのもいましたので、ススキの葉の上部を切り瓶ざしにした状態で幼虫をススキの上におきました。幼虫は葉の先端付近に巣を造り中にいます。巣の付近のススキも食痕を残していますので、これで何とかいけないかと思っています。
今回でミカドアゲハの飼育は終了しましたが、アオスジアゲハとの比較を改めて見てみたいと思い、たまたまアオスジアゲハの卵がありましたので、飼育することにしました。アオスジアゲハもミカドアゲハも共に1齢幼虫は頭部付近に枝分かれした稲妻の様な(厳密には稲妻模様ではありませんが)棘を持っていますが、2齢になると太い黒い棘に変わりました。厳密には黒い太い棘も小さな枝を持っていますが、一見して1齢と2齢の区別は付きます。
06年6月16日(金)
6月8日に久し振りに枚岡公園へ行く。目的はアオバセセリの幼虫です。去年、1齢幼虫を見つけ、毎日巣を開いて写真を撮していたら途中で死んでしまいました。セセリの中でもダイミョウセセリは毎日、巣を開いても平気でしたが、アオバセセリの場合、どうなのか、もう一度試して見たいと思ったからです。
例年なら必ずスミナガシかアオバセセリの幼虫がいる時期ですが、目的のアワブキの木の下へ行って驚きました。アワブキの葉が殆ど無いと言って良いほど虫(多分、蛾の幼虫)に食われていました。アワブキの葉は例年でも、虫に食われている事がよく有りますが、これほど丸裸になったのは初めてです。目的のアワブキだけで無く他のアワブキも虫に食われて殆ど葉のない木が多い様です。これも今年の天候異変の影響なのでしょうか?アオバセセリが駄目ならイシガケチョウの幼虫でもいないかとイヌビワを見ながら歩きましたが、イシガケチョウの幼虫も全くいません。その代わりに下草にとまっているウラジロミドリシジミ(雌)とミズイロオナガシジミを見つけました。両方とも未だ新鮮でした。例年より発生が遅れている様です。
生駒山の蝶にお詳しい地元のU氏にお目にかかり、色々、お話をお聞かせ頂きました。先日、枚岡公園でゴイシシジミを見つけられたそうです。この辺ではゴイシシジミが確認できたのは、今回が初めてとの事でした。
トラフシジミは6月6日に最初の幼虫が蛹化しましたが、他の幼虫は未だ前蛹や終齢幼虫の状態でした。餌のウツギについてきた幼虫も前蛹になりましたが、なかなか蛹になりませんので、どうなっているのかなと思っていると、ある朝、前蛹の傍にルリシジミの幼虫のようなものがいるので、よく見るとトラフシジミの前蛹から出てきた寄生蠅の幼虫のようです。軟らかい土の上に置くと土の中へもぐっていきました。土の中で蛹になったのだと思います。容器の中に放置しておくと蛹にならず、幼虫のまま死んでしまいます。寄生率は非常に高く、8割以上の可能性が有ります。
ギンイチモンジセセリの飼育には参りました。ススキやチガヤを2-3本小さな鉢植えにして幼虫をとまらすと最初は葉の先端付近に巣を造り中にいますので、安心しているとやがていなくなります。次にススキの葉の先端部分を20㌢ほど切り、瓶挿にして幼虫をとまらせる方法をとりましたが、これも結果は同じでした。幼虫はススキの葉の先端に造った巣のまわりの葉を食べて、巣が小さくなると次第にススキの葉の下の方に巣を造りますが、巣から出た幼虫はススキの根元の方まで移動する性質がある様です。下へ降りた幼虫はススキが少ないとススキの葉に戻れないのかも知れません。全部、行方不明になります。そのような訳で個別に飼育していた幼虫は全滅です。只、大きめの植木鉢に植えた一株のススキには、未だ2-3個、巣が残っていて、たまに幼虫が巣から出て歩いているのを見かけますので、ススキが多いと幼虫は行方不明にならないのかもしれません。なにしろ怖くて巣を開いていませんので、幼虫の姿は滅多に見ることが出来ません。
尚、母蝶の採れた現地でギンイチモンジセセリの巣造りを見れば、飼育の参考になると思って、今日、(6月16日)に現地へ行ってみましたが、ススキやチガヤが沢山生えていましたが、ギンイチモンジセセリの巣は見つかりませんでした。
鹿児島のK氏からウスコモンマダラの2齢幼虫と食草のタイワンタシロカズラの葉を送って頂きました。鹿児島県では昨年、ウスコモンマダラが多数採れたそうですが、今年は鹿児島県で未だ2頭しか採れていないそうです。食草のタイワンタシロカズラは台湾に生えていますが、寒さには弱く鹿児島県では冬を越し難く、今は僅かな葉しか有りませんので、幼虫、1頭が成育出来る量の葉を送って頂ける事になりました。タイワンタシロカズラの成長は早いので、ウスコモンマダラが終齢になり、多量に食べる頃に、食草を再度送って頂けるそうです。
アオスジアゲハの飼育は久し振りですが、1齢以外は緑色の幼虫だとの記憶しか無かったのですが、改めてよく見ると頭部付近に有る棘などが成長するにつれ少しずつ変化しています。更によく見ると胴体の部分には細かい地味な模様があります。
最近、クロセセリは近畿地方でも京都などで発生しているそうですが、私は未だ飼育した事が無く、一度飼育してみたいと思っていました。ところが鹿児島のK氏宅で、庭のミョウガに自然発生したクロセセリの巣が有るとのお話を聞き、送って頂きました。幼虫は4頭いますが、一番小さな幼虫の成育状況の写真を撮りたいと思い、この幼虫を1頭だけ別に飼育する事にしました。
昨年から飼育していた種類や今年の春から飼育した種類を含む殆どが、前回の日記で蛹になりましたが、最近は羽化ラッシュです。サツマシジミは6月12日ー14日の間に多数が集中的に羽化。ミヤマカラスも6月10日ー15日に6頭全部が羽化しました。鹿児島県産のミヤマカラスアゲハは前翅だけに白線の入った成虫でした。日誌には載せていませんが、毎年、少しずつ飼育しているオオムラサキも6月14日に雌が羽化。ミドリシジミも例年より遅れ気味ですが6月9日から今も羽化が続いています。個別飼育をしたオオヒカゲは6月5日に羽化しました。これは少し早めです。ヒョウモン類ではオオウラギンスジヒョウモンが6月9日に雄、6月15日に雌が羽化。6月16日にオオウラギンヒョウモンの雄が羽化し始めました。
06年6月26日(月)
クロセセリは餌のミョウガ付きで頂いたので、当初は餌の心配は無かったが、これが切れる迄に食草の確保をすればよいと安易に考えていました。ところが大きな幼虫は終齢になったらしく、ミョウガの葉が急速に減り始めました。急遽、以前に自然生えのミョウガがあった場所へミョウガを取りに行ったが、記憶していた場所にはミョウガは無く、結局は近所の家の庭に生えているミョウガの葉を貰い急場をしのぎました。大きな幼虫は6月18日には2頭が前蛹になり、19日には蛹になりました。残りの大きな幼虫はミョウガの葉を1枚使って巣を造っていましたが、これも続いて蛹になりました。一番小さな幼虫は残念な事ですが、逃げ出したらしく行方不明になりました。
ウスコモンマダラは4齢になりましたが4齢2日目には食草のタイワンタシロカズラの1枚目が無くなり、幼虫が食草から離れて飼育容器の中を歩きまわり始めました。そこで2枚目の葉を用意するために冷蔵庫を調べると、なんたる事でしょうか、食草の葉は冷凍庫の方に入り、カチカチに凍っていました。早速、解凍して幼虫に与えましたが、幼虫は葉の上を忙しげに歩くだけで、一向に食べる気配は有りません。以前にギフチョウの食草のカンアオイを冷凍してしまい解凍して与えた事が有りますが、その時は食べてくれましたので、新しいカンアオイの入手まで冷凍食で我慢して貰いましたが今回は全く食べません。コモンマダラがガガイモを食べたのを思い出しガガイモやキジョラン等を与えましたが食べてくれません。万策尽きてそのまま全ての餌を入れたまま外出しました。すっかり諦めて外出から帰ると幼虫は解凍して変質したタイワンタシロカズラの葉の上にのぼり葉を食べていました。幸いな事にその後幼虫は仮眠に入りました。鹿児島から食草の葉を送って頂いてもとても間にあわないと思っていたのですが、予想より1日早く食草を送って頂き、ちょうど仮眠から覚めて5齢になった幼虫は新しい食草をもりもり食べ始めました。鹿児島のK氏のご尽力と幼虫の仮眠が私の不注意をカバーして、殆ど影響無く飼育が継続できました。
6月16日に5齢1日目だったアオスジアゲハの幼虫は意外に早く5齢期間3日で6月19日に前蛹になりました。5月8日に孵化したミカドアゲハが26日かかって蛹になったのと比較するとアオスジアゲハは孵化から蛹化まで19日でした。気温や個体差などにより、成育の速度は異なってきますので単純に比較はできませんが、南方系の種類が一般的に早い様な気がしていましたので全く意外でした。
トラフシジミは保管していた蛹が全部羽化しました。来年まで蛹のまま越冬する個体が有るかもと期待していましたが、全部羽化して夏型でした。
ギンイチモンジセセリのいるススキの鉢には幼虫の巣の空き家が増えてきました。幼虫は巣の付近を食べて巣が小さくなると引っ越しをしますので、今後も巣の数は増えると思います。巣を調べて見ると3頭だけは無事に育っているようです。鉢植えのススキは非常に貧弱で、草丈は50㌢以下、葉の幅も5-6㍉しかありません。葉の幅が狭いので3頭の幼虫の内2頭は巣の外から幼虫の姿が見えます。幼虫にとっては不満かもしれませんが私にとってはラッキーです。巣の外から幼虫の写真を撮る事ができました。
6月19日の午後に室池園地へ行きました。今年は今までアオバセセリやスミナガシの幼虫の姿を全く見ていませんので、アワブキの木の葉を調べながら歩きました。例年必ずいる木にも今年は未だ姿を見ていません。ウオーキングを兼ねて、少し距離はありますが今年初めてのコースを歩きました。30分程歩いた所で初めて見つけたアワブキを見るとスミナガシの2-3齢幼虫が数頭いました。久し振りですので持ち帰り飼育することにしました。6月24日現在、幼虫は3-4齢です。
7月
06年7月6日
6月26日の日記にウスコモンマダラの幼虫がそろそろ5齢になると記しましたが、6月27日には前蛹になりました。鹿児島から送って頂いた時体長が4㍉程度でしたが、昨年飼育したコモンマダラが1齢時の最高体長が約6㍉でしたので、なんの根拠も無く1齢幼虫であると判断したのが間違いだったようです。各齢の期間を調べましたが1齢期間が長すぎますので、発送途中で2齢になったと思われます。先月の日記の中で記した幼虫の齢を1齢ずつ繰り上げました。誤った齢を載せた事を皆様にお詫び致します。その後6月27日に蛹化しました。蛹はは他のマダラチョウ類と同様に宝石の様に美しい淡黄緑色です。9日後の7月5日には無事に羽化しました。
6月19日に室池園地で採ったスミナガシの2-3齢幼虫は全部5齢になり、体色も5齢初期の赤褐色から5齢後半の緑色に変化しました。6月29日に5齢になりたての頭でっかちで、体の小さな幼虫が、動きまわって面白い恰好をしていましたので、写真を載せておきます。6月30日にまた室池園地へ行って見ましたがアワブキの葉には2齢幼虫が3頭程いただけで、期待のアオバセセリは全く見つかりませんでした。
園地の道を歩いているとオオムラサキやナガサキアゲハより大きな幼虫がのろのろと歩いているのを見つけました。ヤママユの幼虫のようです。ナマケモノと言う猿がいますが、それに似た動きで非常に剽軽な恰好ですので、気にいってつれて帰る事にしました。蛾の幼虫ですので本来は持って帰らないのですが、梅雨で雨降りが多いので、飼育中の幼虫が少なく、手空き気味ですので飼う気になったのです。鉢植えのアベマキの枝が伸び過ぎていましたので、枝を切ってアベマキの葉を与えました。幼虫は大型アゲハ類の幼虫に似て殆ど動かず同じ場所にいます。アベマキの葉を沢山食べ、5㍉以上もある大きな糞を沢山します。
6月の日記に枚岡公園や室池園地でアオバセセリの幼虫を探しに行ったが今年は全くいなかったと記したのを、ご覧頂いた和歌山のI氏から、那智山へ行ったらアオバセセリの幼虫がいたので必要なら送るとのメールをもらい、送って頂いたら餌のヤマビワ付きで到着しました。こちらではアワブキしか見たことが有りませんので私にとっては非常に珍しく、アオバセセリの幼虫がヤマビワの葉で造った巣の写真を撮りました。幼虫の1頭は5齢でしたが発送中に前蛹になり、翌日、蛹になりました。
7月4日は梅雨の中休みで久し振りに枚岡公園へ行きました。6月に行った時にU氏から枚岡公園にもウラナミジャノメがいると教えて頂いたので、少し時期は遅そうですが、雌を1-2頭欲しいと思って行ったのですが、全く姿を見かける事は出来なかった。
枚岡公園は今ちょうどオオムラサキのシーズンで、平日ですが何人もの人がオオムラサキ狙いで来ていました。オオムラサキがテリトリーをはる場所には長網を持った人がテリをはっていました。
6月8日に来た時はアワブキの葉が虫(蛾の幼虫?)に食われて丸裸状態でしたが、今日はかなり回復して葉が増えていました。スミナガシの幼虫は1頭見かけただけですが、アワブキの新芽が出たのでアオバセセリの幼虫が巣を造っていました。今年は諦めていた「アオバセセリの幼虫の巣を毎日開いて写真を撮る事」を那智山のアオバセセリで行うつもりでしたが、枚岡公園の一番小さなアオバセセリで行います。去年はノイローゼになった?幼虫が途中で死んでしまいましたが、今年は蛹まで写真を撮れるでしょうか?幼虫には迷惑な事ですね。那智山産の幼虫はヤマビワの食草で自然の状態で育て、羽化したら標本にするつもりです。
ギンイチモンジセセリの幼虫は3頭だけ残っていたのですが、全部行方不明になりました。今回の失敗を参考に夏型の雌で再挑戦してみます。
最近、羽化したのはクロセセリとヒョウモン類では最後のオオウラギンヒョウモンの雌です。
今年のオオムラサキは私の僅かな飼育の結果では少し遅れ気味の様です。今年最後の幼虫は6月29日に前蛹になりました。今日現在、未だ2頭の蛹がいます。
川上村産のコジャノメで採卵をしましたら20卵ほど産卵しました。以前に飼育した時は殆ど孵化せず、卵からの飼育は未経験ですので今回飼育することにしました。7月2日に2卵産卵しているのに気づきましたが、7月5日には卵が黒くなってきましたので慌てて写真を撮しました。ヒメジャノメと成虫は似ていますが、幼虫はかなり違うので飼育が楽しみです。
06年7月16日(日)
那智山のアオバセセリの一頭はは7月2日に蛹化し7月13日に羽化しました。残りの2頭は送って頂いた食草のヤマビワが無くなり、アワブキに切り替えましたが、無事にアワブキの葉で巣を造り食欲旺盛です。多分、2-3日後には蛹化するでしょう。
今回、枚岡公園で採ってきた幼虫には気の毒ですが、毎日、巣を開けて写真を撮り体長を測っています。昨年の秋に1齢幼虫から毎日、巣を開けて写真を撮っていたら、幼虫がノイローゼになったのか?死んでしまいましたので今回は予備を見て3頭の幼虫の巣を開く事にしました。幼虫の中でも、のんびり屋と神経張り詰め型がいて、巣を開けると上半身と頭部を猛烈に振って威嚇する幼虫と余り動かずにじっと静止する幼虫がいます。
写真を撮っているアオバセセリの幼虫は3頭いますがその内の1頭の写真を載せます。
ヤママユは緑色の美しい繭を造りました。以前に自宅のウバメガシに造られたヤママユの繭を保管しておいたら、立派な寄生蜂が羽化しました。今回は大きなヤママユが羽化するか、大きな寄生蜂が羽化するか楽しみです。(蜂の写真は「蝶・雑記ー2」の「蝶の幼虫の天敵」にありますので、ご興味の有る方はご覧下さい。)
コジャノメは04年に採卵し飼育したが、殆どの卵が孵化せず、かろうじて1頭だけ孵化したが若齢幼虫の段階で死んでしまい、卵から蛹までの個別飼育はできていなかったので、孵化までは心配していました。しかし、未孵化の卵は全く無く幼虫も無事に育っています。
7月10日に南山城付近へ行き、オオヒカゲのいる廃田跡や林道へ行ったが、オオヒカゲの姿は全く見られ無かった。暑くなるとキマダラモドキやクロヒカゲモドキ等と同様に仮眠中なのだと思います。林道にいたオオチャバネセセリとキマダラセセリを産卵用に採りました。ホソバセセリも姿を見ましたが逃げられました。帰りに神童子へ寄りウラナミジャノメの雌を探しましたが、さすがに1ヶ月遅れではヒメウラナミばかりでした。
その時採ったオオチャバネセセリとキマダラセセリが卵を産みましたので飼育するつもりです。キマダラセセリはチヂミザサを食草として以前にも飼育していますが、今回は個別に毎日、姿を見たいと思っています。オオチャバネセセリは笹で飼育しますが、笹は鉢植えでないとすぐに萎れますが鉢植えの数は少ないので、個別飼育は笹の瓶挿しで行います。しかし、非常に早く葉が萎れますので全く自信はありません。以前にコチャバネセセリを飼育した時、鉢植えの笹に沢山卵を産み、孵化も順調でしたが、小さな巣を造っただけで笹の葉を食べずに全部干からびて死んでしまった経験があります。オオチャバネセセリの場合も鉢植えの笹を使ってもうまく育ってくれるか心配です。
7月13日に四条畷へオオムラサキの雌を採卵用に採りたいと思い出かけました。以前からよさそうだと思っていた場所でクヌギの樹液に来ている雄と飛んで来た雄の2頭がネットに入りました。(リリース)。他に飛翔中の2頭の姿を見ましたが雄のようでした。以前に新鮮な雌を採り、1ヶ月程飼育、採卵をしましたが不成功でしたので、今回は時期を遅らしましたが目的の雌は採れませんでした。オオムラサキの卵からの飼育は今年も見送りのようです。
06年7月26日(水)
7月22日(土)久し振りの梅雨の晴れ間に室池園地へ行きました。網を持った子供連れが多く、子供達は今も虫好きが多いのだと思い安心しました。子供達はクワガタやカナブンが好きなので、クヌギの樹液を特に熱心に見ていますので、余り期待はしていなかったのですが、2㍍ほどの高さの場所にオオムラサキの雌が吸密にきていました。リックからネットを取り出しオオムラサキの雌を採りました。オオムラサキは3齢幼虫からの飼育しか経験がありませんので、採卵して卵からの飼育をしてみたいと思います。しかし、かなり古いので、うまく産んでくれるでしょうか?
ユキヤナギの垣根にはホシミスジが産卵に来ていました。ホシミスジはデジカメを買う以前に飼育をした事がありますが、飼育の写真がありませんので、卵を一つ持ち帰り飼育する事にしました。
コジャノメは5齢5日目になりました。齢を重ねる度に体色がくすんできましたが、5齢になって褐色が強くなりました。食欲も旺盛で、若齢ではチヂミザサの葉が1枚有れば数日の食料になりましたが。最近は数枚を1日で食べる様になりました。尚、この写真の幼虫は成長が一番早く、一番遅い幼虫は4齢3日目で未だ白っぽい体色の幼虫です。
アオバセセリは5齢になり、縞模様の黒色の部分にある青色の斑紋が濃く鮮明になりました。4齢時も青色の斑紋はありましたが、淡くぼんやりしていました。尾部も4齢までは黒かったのがボルドー色になりました。人によっては毒々しい幼虫だと言う方もおられるが、私から見れば非常に美しい幼虫です。
この幼虫は3齢から飼育しましたが、2齢から飼育した別の幼虫は3齢期間5日、4齢期間5日で5齢になって、10日目です。5齢期間はかなり長いようです。
オオチャバネセセリは7月17日から18日に孵化しました。その内3頭を個別に飼育するつもりで、瓶挿しの笹へ1頭ずつ移しました。最初、幼虫は元気に巣を造り始めていましたが、笹が枯れ易いので3頭の内2頭は行方不明になってしまいました。やむを得ずポリ容器の中でビニールシートで覆って飼育することにしました。新しく個別飼育用の18日生まれの幼虫を追加しました。
他の幼虫は集団で鉢植えの笹で飼育していますが、順調に生育して中には既に2齢になった幼虫もいます。巣の大きさも次第に大きくなってきました。
キマダラセセリは以前に飼育した写真がありますが、個別に巣まで開けて飼育したことはないので、今回、2頭の幼虫を出来れば1日1回巣を開いて、写真を撮り、幼虫の状態を見たいと思います。巣を開くと幼虫は驚いて上半身を振る事もありますが、今までは翌日には巣を造りなおしています。幼虫は早くも2齢から3齢への仮眠に入りました。
コチャバネセセリは7月14日に金剛山で採ったので、自宅付近とは成育状態が少し異なると思います。しかも卵からではなく、途中からですが、とにかく個別飼育をしてみようと思い、これも毎日、巣を開いて写真を撮っています。幼虫は大小の2頭がいますが齢は全く分からないですが、次回に飼育するときの参考にしたいと考え気楽な気持ちで飼育しています。写真は小さい方の幼虫です。多分、26日現在、3齢だと思うんですが?
8月
06年8月6日
ホシミスジは7月28日の午後に気が付いたら既に孵化して、ユキヤナギの葉に食痕を残していました。1齢の間は最初に食べたユキヤナギの葉が枯れても、その葉にに戻っていましたが、7月31日から枯れ葉の上で仮眠に入りました。枯れ葉は丸く曲がった巣になっていて、幼虫はその中にいますので、写真が撮り難くて困ります。巣のある葉は葉柄の付け根を糸で綴っていますので、葉が枯れても落ちる心配は有りません。脱皮して2齢になった幼虫は新しい葉に移りました。
コジャノメは赤褐色の5齢幼虫が緑色がかってきたと思ったら前蛹になり、次の日には蛹になりました。多数飼育の幼虫も一斉に蛹になりました。残りの幼虫は1-2頭です。
今回、アオバセセリの幼虫の巣を毎日、開いて写真を撮りました。以前に1齢幼虫から毎日、写真を撮ろうと思ったが幼虫が死んでしまったので、今回は3頭の2-3齢幼虫の巣を開いて写真を撮る事にしました。幼虫には気の毒でしたが3頭とも無事に蛹になりました。幼虫はアワブキの適当な大きさの葉が有れば毎日巣を開いても翌日には巣を補修していました。仮眠中の写真や各齢の期間など私の興味を充分に満たしてくれました。
前回の日記で5齢後期の幼虫と前蛹の写真を載せましたが、今回は3頭とも蛹になりました。3頭とも前蛹になる前に今迄入っていた一枚の葉で造った巣を出て、2-3枚の葉を綴った広いけれどもラフな巣に入り前蛹になりました。多分、蛹化時の脱皮がし易い様に広い空間の有る巣に移るのだと推定しています。今回は2-3齢幼虫からでしたが、次回は卵から蛹までの写真を撮りたいと思っています。
オオチャバネセセリは約20頭ほどの幼虫が鉢植えの笹で育っています。笹の鉢を蜂や鳥から防ぐ為にネットがかぶせてある以外は放置したままですが幼虫は順調に育っています。それに比べて笹の葉の瓶挿しで育てている個別飼育の幼虫の生育状態は最悪です。一応3齢にはなりましたが、全く大きくなりません。何とか蛹までなって欲しいと願っています。
キマダラセセリは食草はチヂミザサですから飼育は楽です。チヂミザサを瓶挿しする時は適当な長さに切り、細い根を2本ほど残して水の中へ入れておけば、かなりの期間枯れることは有りません。しかし、チヂミザサの葉は小さいので、巣を開ける時は幼虫に傷を付けない様に注意が必要です。毎朝、巣を開いて幼虫の姿をながめていますが、翌日には必ず巣は補修してあります。
コチャバネセセリは2頭の内、小さな方の幼虫の写真を載せていますが、大きな方の幼虫は蛹化して、蛹が黒くなってきていますので、羽化寸前だと思います。小さな幼虫は家へ来てから2回目の脱皮をしました。コチャバネセセリも食草は瓶挿しの笹を使っていますが、何とか無事に成長しています。
鹿児島のN氏からタテハモドキの卵を送って貰いました。昨年の秋に飼育した時の写真はHDDの破損で殆ど失いましたので、新しくオギノツメとオオバコで各3頭ずつ個別に飼育するつもりでした。しかしオオバコの葉においた幼虫は3頭とも行方不明になりましたので、個別飼育はオギノツメが食草の3頭だけになりました。代用食のオオバコは最初の食いつきが悪い様です。特に孵化したての幼虫には葉が硬いのかも知れません。1齢後半の幼虫を数頭一緒にオオバコの葉の上においた場合は無事にオオバコを食べてくれました。昨年飼育した時も1齢後半から2齢幼虫でオオバコを食草にした場合、オオバコで飼育可能でしたが、オギノツメで4-5齢まで飼育した幼虫はオオバコへの食草の切り替えはできませんでした。
私の2回だけの飼育経験ですが、孵化直後からオオバコを与えるとオオバコを食べる確率は低いが、少し大きくなった幼虫を(特に数頭一緒に)オオバコの食草に切り替えれば、食べてくれる確率は高い様です。しかしオギノツメで終齢近くまで育てた幼虫のオオバコへの切り替えは困難でした。
近所の方から「キアゲハが庭へ来て卵を産んでいるので、いりませんか?」との電話を頂きました。早速、キアゲハの卵を数個頂いてきました。卵からの飼育は久し振りですので、1頭だけは個別飼育をして、残りは数頭一緒に飼育することにしました。個別飼育の幼虫の写真を蛹まで載せるつもりです。
06年8月16日(水)
オオムラサキは毎年、冬に3齢幼虫を数頭採り飼育していますが、今年は是非、卵から飼育したいと思いオオムラサキの雌を採り、採卵を試みましたが、なかなか産んでくれず苦労しました。榎の鉢植えの上から捕虫網をかぶせオオムラサキの雌を入れておきましたが、夜中に小動物(ネズミ?)が来て捕虫網に穴を開けオオムラサキは食べられてしまいました。またオオムラサキの雌を採りに出かけ、再びセットしましたが、2度目も網に穴を開けられました。失敗の度にオオムラサキの雌を採りに行き、採卵にトライしましたが遂に産んでくれました。次は卵が無事に孵化するのを待っていましたが8月13日に孵化が始まりました。未受精卵もあり、孵化率は悪かったが、それでも幼虫はかなりの数です。取りあえず4頭を個別に飼育、他はまとめて飼育の予定です。餌の榎は瓶挿しですので、3日に1度は替える必要が有ります。数は多いですが、越冬までは食べる量は少ないのでなんとか飼育してみるつもりです。
キアゲハはきわめて短期間で蛹になりました。今回、食草のミツバを鉢植えにして鉢ごとプラスチック容器に入れ、1頭だけを飼育しましたが、若齢の時に脱皮を見逃した様です。取りあえず毎朝、撮っている写真を再度見て、脱皮の再確認をしましたが、頭部脱皮殻を確認していませんので、100%の自信はありません。食草を鉢植えにする利点は幼虫に自然に近い状態の餌を与えられる事ですが、鉢の中に落ちた頭部脱皮殻や糞の量が分かり難い欠点があります。通常は瓶挿しの食草で、白い紙箱の上に瓶を置き、糞の処理と脱皮殻の確認をしています。仮眠の状態や期間は種類や時期により異なりますが仮眠中は糞をしませんので、糞量の変化でも仮眠の確認の参考にはなります。それに個別に飼育する幼虫を3頭程度にすると、見逃しが分かり易いので、なるべく3頭程度を同時に飼育するように心掛けていますが、普通種のキアゲハは何時でも飼育できると軽く考え1頭だけしか飼育しませんでした。油断は禁物です。近々、再飼育して確認するつもりです。いいわけが長くなりましたが今回は5齢幼虫からさかのぼって齢を入れ直しました。
ホシミスジは8月4日に新しい葉に移ってから8月13日頃までは同じ葉の上に静止していました。食事の時は移動して他の葉を食べますが、必ず元の葉に戻っています。しかし、最近は幼虫が大きくなった為か8月16日は巣にしている葉の傍の枝で仮眠していました。
食草のユキヤナギは瓶挿しでも長持ちしますし、ホシミスジはユキヤナギを離れる事はありませんので、飼育は楽です。今、4回目の仮眠中ですから次回は5齢幼虫の写真を載せる事になります。
タテハモドキは3頭をオギノツメで育て残りはオオバコで育てていますが、オギノツメで飼育中の幼虫の成育が早いのには驚きます。8月7日に3齢1日目の幼虫は8月15日には蛹になりました。齢の変わるごとに写真を載せたら、殆ど毎日の写真になりました。
オオバコで飼育中の幼虫は数は数えていませんが十数頭はいるようですが成育にはかなりばらつきがあります。1頭は蛹になり終齢幼虫も5頭程いますがまだ2齢程度の大きさの幼虫もいます。全部、元気ですので餌は食べているようです。
オオチャバネセセリの飼育では瓶挿しの笹の葉をよほどこまめに替えないと、笹の葉が干からびて幼虫の成育が悪くなります。今回、飼育の2頭目も4齢にはなりましたが成育が悪く4齢になった次の日に死んでしまいました。個別飼育の幼虫が上手く育たないので、幼虫が減る度に集団飼育の幼虫を個別飼育に切り替え、現在2頭の幼虫を個別に飼育していますが、参考までに4齢1日目の写真を載せました。次回に飼育するときは笹の鉢植えをあらかじめ用意して育てたいと思います。
現在、飼育中の集団飼育の幼虫は鉢植えの笹で飼育していますが、殆どの幼虫が5齢になったようです。既に2鉢の笹をたいらげ最後の3鉢目を食べていますが不足しそうなので心配しています。
キマダラセセリの飼育も既に1ヶ月ほどが過ぎ8月16日には(5齢7日目)になりました。幼虫が大きくなり、チジミザサの葉が小さいので、毎日、巣を開くのが苦労です。おまけにチジミザサの葉が完全に開かず指で葉を押さえながら写真を撮りますので、写真に見難い指が写りますがお許し下さい。
コチャバネセセリは(5齢9日目)に入りました。7月14日に金剛山で採った幼虫の内、2頭を飼育しましたが、大きい方の幼虫は7月29日に(5齢8日目)で蛹化用の密閉した巣を造りましたので、写真の幼虫もそろそろ蛹化の時期だと思います。尚、7月29日に蛹化した幼虫は8月7日に既に羽化しました。
自宅の庭にはヒョウモン類の飼育用にスミレやタチツボスミレの小さな鉢植えを沢山置いてありますが、今年はツマグロヒョウモンの雌が毎日と言って良いほど飛来して卵を産み、孵化した幼虫が鉢植えのスミレ類を全て食べ尽くし、食べる餌の無くなった幼虫が餌を求めて庭を歩きまわるといった状態でした。それでも雌が飛来して、食べ尽くされたスミレの鉢にはえた雑草に卵を産んでいきました。
昨年の秋に4頭のツマグロヒョウモンを飼育して、4頭共、終齢幼虫が6齢になった事を思い出しこの卵を飼育する事に決めました。昨年の飼育写真はHDDの破損で残っていませんので、今回は頭部脱皮殻も必ず写真に撮すつもりです。8月16日現在では(3齢1日目)ですが、はたして終齢は5齢か6齢かどちらでしょうか?尚、脱皮の見落としや、脱皮殻が見つからない場合もありますので、同時に3頭の幼虫を個別に飼育します。
06年8月26日(土)
オオムラサキの幼虫は前回の写真の幼虫が死亡しました。榎の枝から離れて歩いていましたので、もとえ戻したのですが干からびて死にました。個別飼育4頭の内、1頭が早くも減り前途多難です。
特に集団飼育の幼虫は榎から離れ容器の側壁や蓋をしているナイロンストッキングに静止していますので、榎に戻すべきか?否か?迷います。一応、仮眠以外の幼虫は餌の榎に戻す事にしています。
集団飼育の幼虫の一部が3齢になりました。個別飼育の3頭は未だ2齢です。
ホシミスジは脱皮して5齢になりました。終齢になりホシミスジの幼虫の特徴である尾部付近の淡緑色の部分が大きく鮮明になり、背部の棘状突起も大きく立派になった。8月25日には無事に蛹になりました。これでホシミスジの幼虫の飼育は完了し、後は羽化を待つのみです。しかし、幼虫が蛹になっても未だ毎日小さな糞が多数落ちています。よく見るとユキヤナギにホシミスジの幼虫の巣がありました。ユキヤナギは庭の鉢植の枝の一部を切り取り、瓶挿しにしているのですが、その鉢植えにホシミスジが産卵していたようです。
個別飼育のオオチャバネセセリの幼虫は餌の笹が瓶挿しの為、鮮度が悪く、随分成長が遅れていましたが3齢から脱皮して4齢になった日に死亡しました。餌を充分食べ、糞量の多い幼虫は成育が早く安心ですが、いつまでも齢が変わらず大きくならない幼虫は死ぬ確率が高いです。
孵化直後から鉢植えの笹を食べて育った集団飼育の幼虫は成育が良く、4齢直前に集団飼育から個別飼育に切り替えた幼虫は8月2日に4齢になりました。この幼虫の4齢以降の写真を載せます。しかし、この幼虫も蛹化出来ず、蛹の写真は別の集団飼育の個体のものです。
キマダラセセリの幼虫は滅多に餌を離れて逃げないだろうと思い、チジミザサの瓶挿しで容器に入れずにオープンで飼育していました。しかし、いよいよ蛹化が近い(5齢15日目)に巣から出ているのに気が付きましたが、蛹化用の巣を造るのに適当な葉を探しているのだと軽く考えていましたら、翌日には幼虫の姿が見えませんでした。チジミザサの葉の無い室内のどこかで、巣無しで蛹化したのでしょうか?完成しない飼育日記ばかりですが、個別飼育した別の1頭が先に蛹化していますので、その蛹の写真を載せておきます。
コチャバネセセリの幼虫は蛹になる時期が近づき体が少し透明な感じになり、笹の葉で蛹用の巣を造りました。幼虫時代の巣は笹の葉の両端を綴りトンネル状の巣を造り、葉柄に近い部分の巣を支脈を残し食べますのでコチャバネセセリの幼虫の巣は特徴があります。しかし蛹用の巣は幼虫時代の巣と全く異なります。幼虫は笹の葉の縦の真ん中付近から折り曲げ出入り口の無い巣を造り、中で蛹になります。何頭もの巣を開くのも気の毒ですので、中の蛹の写真は別の個体になりました。写真の蛹の幼虫は8月7日に既に羽化しましたが今回蛹化の個体は羽化するのか?越冬するのか?どちらでしょうか?
ツマグロヒョウモンの幼虫は6齢になりました。ヒョウモン類は5齢が終齢だと思っていましたが、昨年の秋の飼育で6齢になりましたので、今回の飼育は再確認が目的でした。今回は3頭の幼虫をそれぞれ個別に飼育しましたが全部、足並みを揃えて同時に6齢になりました。
昨年の秋に鹿児島のK氏から頂いた大型ヒョウモン類は越冬期間があり、1-2齢時の脱皮殻確認が充分できていませんが、幼虫の変化(仮眠等)を見ていますと6齢になった種類が殆どです。大型ヒョウモン類は終齢が6齢だと思っています。1齢で越冬する幼虫が春先に脱皮するときの頭部脱皮殻を確認するには鉢植えのスミレでの飼育では無理ですので、瓶挿しのスミレで飼育する必要があります。ちょっと面倒な飼育になりそうです。
9月
06年9月6日
個別飼育のオオムラサキの幼虫は(3齢8-9日目)になりました。未だ冬眠までには2ヶ月弱程の期間があるので幼虫の状態に興味がありましたが、意外にも8月31日に集団飼育の3齢幼虫の中の1頭が仮眠中でした。オオムラサキの飼育は今までは越冬後の幼虫の飼育経験だけでしたが、脱皮を2回して蛹になりましたので越冬幼虫は3齢であると考えていました。オオムラサキの幼虫の越冬は3-4齢であると書かれた本を見たことがありますが、私の経験ではゴマダラチョウは1回の脱皮で蛹化しますが、オオムラサキの越冬幼虫は必ず2回脱皮をしますので、4齢は間違いだと思っていました。この4齢幼虫は4齢のまま越冬し、越冬後1回の脱皮で蛹化するのでしょうか?それとも2回脱皮して6齢で蛹になるのでしょうか?興味津々です。いずれにしても来年まで上手く育てる事が重要です。
セセリチョウ3種は前回で蛹までの写真を載せましたが、3種類とも今日までに羽化しました。
コチャバネセセリの羽化するのを見ましたので写真を載せました。コチャバネセセリの蛹用の密閉した笹の葉の巣を保管していましたら、中から黒いものが素早く出てきました。よく見るとコチャバネセセリの羽化でした。(コチャバネセセリで当然ですが、一瞬、何が?と思ったほど素早い動きでした。)翅を伸ばす為には狭い笹の葉の巣を大急ぎで出る必要があったのでしょう。翅が上手く伸びる様に這い上がる場所を提供、誘導しましたが、無用の心配でした。アゲハチョウ等は胴体に比べて翅が大きいので翅が伸びる為の空間の確保が必要ですが胴体の割に翅の小さなコチャバネセセリは笹の葉の巣から脱出すれば後は地面を歩いていても、翅は地面に垂れる事は無く順調に伸びるようです。
オオチャバネセセリは未だ終齢幼虫も沢山いますが、最初に蛹化した個体が羽化しました。現在、半数が蛹になりましたが、コチャバネセセリの蛹用の巣は密閉された立派な巣ですが、オオチャバネセセリの蛹は写真のように実に簡単な巣です。巣を開く事無く蛹の姿は充分に見る事が出来ます。
ツマグロヒョモンは8月27日と28日に3頭共、蛹になり、9月5日には3頭揃って羽化しました。ツマグロヒョモンは6齢で蛹になるのが確定しました。
知りあいのT氏からホリイコシジミの幼虫を頂きました。既に中齢から終齢幼虫でかなり大きくなっていましたがそれでも小さな幼虫です。食草はランタナの花ですが、全く用意をしていなかったので、花屋のはしごをしましたが、ランタナの苗はあるのですが花の咲いたランタナはなかなか見つかりません。最後にかなりデラックスなランタナの寄せ植えを見つけました。花の盛りは過ぎ花は20個ほどでしたが黄色、白、ピンクと青紫と4種類の寄せ植えを購入しました。本当は七変化と言う最も普通の種類で良かったのですが、幼虫のいのちに関わる事ですのでやむを得ません。おかげさまで幼虫は無事に全部、蛹化、羽化しました。只、問題は余りにも小さなチョウですので、上手く展翅出来ず、頂いた方とホリイコ君に申し訳無く思っています。ランタナの花さえ充分あれば累代に挑戦したと思うんですが残念でした。
9月4日に枚岡公園から生駒山麓付近に行ってみました。この時期には特に目標は無かったがイシガケチョウの幼虫やスミナガシの幼虫はいるかも知れないので、アワブキやイヌビワには注意をはらっていたが、スミナガシの食痕を見つけただけでした。諦めて帰る道でアワブキのヒコバエにアオバセセリの巣を見つけたので、傍へ行って良く見ると卵がありました。卵は白色で縦に線があり、スミナガシの卵に似ています。しかしスミナガシは硬い葉に産卵しますが、この卵は軟らかい若葉に産卵してありますし、付近にアオバセセリの幼虫もいますので、間違いありません。アオバセセリの卵からの飼育は初めてですので、是非、卵から蛹までの写真を撮りたいと思います。
鹿児島からウスキシロチョウの卵と食草のナンバンサイカチの葉を送って頂いたが、道中で孵化して小さな幼虫がいました。以前にも頂いたのですが、その時はかなり大きくなった幼虫でしたが、今回は孵化したてですので蛹までの全ての過程を撮せそうです。
06年9月16日(土)
オオムラサキの幼虫は3齢で越冬すると思っていたのに幼虫の1頭が4齢になったので、4齢で越冬する幼虫もいるのかも知れないと言う事を前回の「虫トリ日記」に載せましたが、今回はもっと驚きました。4齢になった幼虫はどんどん成長して5齢になり、今日現在、(5齢6日目)で体長も31㍉と大きくなりました。しかも他の幼虫でも4齢、5齢になる幼虫が続出しています。今朝、調べた結果では5齢幼虫が4頭、4齢で仮眠中が1頭、4齢幼虫6頭、3齢幼虫9頭と、4齢以上の幼虫が半数以上となりました。今後どうなるか全く分かりませんが4齢以上の幼虫は蛹になりそうです。何が原因でこのような事になったのでしょうか?以前、ゴマダラチョウの飼育でも年内羽化の幼虫と越冬幼虫に分かれた事があります。(「蝶・雑記」に載せていますので、ご興味がおありの方はご覧下さい。)
今回載せた写真は(A)従来、日記に載せていた個別飼育の幼虫。(B)は個別飼育の内4齢になった幼虫。(C)は集団飼育で一番最初に4齢になり、現在、5齢の幼虫です。
ウスキシロチョウは9月5日に(1齢1日目)でしたが、驚く程早く成長して毎日、脱皮をした時期もあり、9月13日には蛹になりました。その間に3回の脱皮を確認しましたが、1齢から2齢になった最初の脱皮殻には気がつかず見落とした様です。9月5日に体長2㍉の幼虫が9月6日に体長4㍉と倍になりましたが写真の写りも悪く非常に分かり難いです。しかし4頭の幼虫の写真を見ると仮眠中の様な感じの幼虫もいます。それに9月7日には体長6㍉弱と大きくなり、体幅も9月6日の0.2㍉程度から倍以上の0.5㍉程度になったのに胴体と比較して頭部が大きくなっており、脱皮直後の体型ですので、9月7日に2齢になった事は間違い無さそうです。実はシロチョウ科の幼虫の頭部脱皮殻は淡い褐色で半透明なので良く気を付けていないと老眼で探すのはたいへんです。
9月4日に枚岡公園で採った卵から孵化したアオバセセリの幼虫は毎日、巣を開いて中を覗き写真を撮っています。幼虫が最初に造った巣はアワブキの葉を扇子状に切り、基部(扇の要の部分)を糸で綴り内側に曲げた様な形です。
巣は天井はありますが横側はかなり隙間があります。幼虫は天井の部分にいますので、写真を撮るには巣の天井を開く必要が有ります。しかし、天井を開いても天井は自然に閉じる傾向があり、無理に小さな巣の天井を開くと幼虫を傷つける可能性があり、写真がなかなか上手く撮れません。
幼虫は意外にも既に3回の脱皮をして4齢になりました。過去、4齢と思い飼育した幼虫と比べるとかなり体長が小さいので、この幼虫は6齢になりそうです。
8月に鹿児島から送って頂いたタテハモドキは8月中旬に蛹化して、すべて羽化しましたが、沢山いましたので数頭を網の中に入れ、中にオギノツメを入れておきましたら、自然に交尾して産卵しました。孵化後餌をオオバコに切り替え飼育中です。順調であれば秋型が羽化する筈です。
9月15日に南山城へ行きました。かなり涼しくなり何頭かのオオヒカゲの姿を見かけました。既に数年続けているオオヒカゲの飼育ですが、今年も採卵するつもりで雌をとりました。
オオウラギンスジヒョウモンを何回か見かけた場所へ行ってみましたが姿は見えず、代わりにメスグロヒョウモンとミドリヒョウモンの雌がいましたので、これも産卵用に持ち帰りました。
本来の目的はホソバセセリの幼虫探しです。6月下旬から7月初旬には成虫の姿を見かけますが、今年のシーズンに産卵用の母蝶の採集が出来ませんでした。そこで幼虫でも見つからないかと思いススキを調べましたら巣があり、中に幼虫がいました。しかし、私はホソバセセリの幼虫を全く見たこと無く、どのような幼虫か知りませんので、本当にホソバセセリかどうか全く自信がありません。キマダラセセリの幼虫と似ていますが、少し体色がくすんでいるように感じます。ススキはの巣は10㌢以上の長さがあり、十数カ所を糸で綴っています。キマダラセセリの飼育時はチヂミザサを食草として使いましたので、巣は全く違いました。何はともあれ持ち帰り飼育して成虫の羽化を待ちます。実に気の長い話だと我ながら呆れます。
時間が早かったので、ウラナミジャノメの時期には遅すぎですが神童子へ寄りました。現地へ着いてすぐにイヌビワがあったので葉を見ると若葉にイシガケチョウの若齢幼虫がいました。飼育するつもりでイヌビワの若葉も採ってしまったので、枯れないうちに帰る事にしました。折角のウラナミジャノメは姿を見ずに帰宅しました。
06年9月26日(火)
3齢で越冬すると思っていたオオムラサキの幼虫の一部が5齢になり驚きましたが、一番最初に5齢になった幼虫が今日、前蛹になり、この幼虫より1日遅れで5齢になった幼虫が今朝、蛹になりました。この2頭を除いて個別に飼育している幼虫6頭の内、5齢幼虫は3頭、4齢幼虫は2頭、3齢幼虫は1頭です。5齢幼虫と4齢幼虫の成育の良い個体は全部蛹になりそうですが、3齢幼虫と4齢幼虫で成長の遅い幼虫が今後、どうなるのかが興味深いです。
今回の幼虫の写真は全部、9月26日現在の5頭の幼虫です。(A)(B)(C)は前回の日記に載せた幼虫です。(D)(E)は個別飼育の2頭の幼虫を追加しました。写真の右に簡単に説明してありますが、ほぼ同じ日に孵化した幼虫にこんなに差が出来てしまいました。以前にゴマダラチョウの飼育で年内羽化の第三化と越冬幼虫に分かれた様に、オオムラサキも第二化と越冬幼虫に分かれるのでしょうか?
アオバセセリは5齢になりましたが体長17㍉ 体幅3㍉とかなり小さいく、4齢時の頭部脱皮殻も2.3㍉×2.2㍉程度と小さいので、6齢になりそうです。卵からの飼育は初めてですが、頭部脱皮殻の写真は脱皮ごとに有りますので間違いは無さそうです。
イシガケチョウの幼虫の成長は非常に早く、採集した時2齢だった幼虫は24日には蛹になりました。各齢の写真を載せます。各齢ごとに背部や尾部の鎌のような突起が大きくなりますので、各齢の見分けは比較的楽です。
タテハモドキはオオバコの葉を与え、集団で飼育していますが、涼しくなった為か成長の速度が鈍っているようです。8月に飼育した時は2週間で蛹になりましたが、今回は少し長くなりそうです。
南山城で採ったオオヒカゲ、メスグロヒョウモンとミドリヒョウモンはそれぞれ採卵を行いましたが、3種類とも産卵し、オオヒカゲの卵は早いのが黒くなってきました。ヒョウモン類は早くも孵化して幼虫が出てきました。
10月
06年10月6日(金)
現在、個別飼育をしているオオムラサキの幼虫は6頭いますが、その内の3頭の写真をのせました。前回も写真を載せた(A)(B)(D)の3頭です。(A)は殆ど大きくならず(3齢36日目)で4齢になりました。(B)は4齢で殆ど大きくならないので、4齢で越冬するのだと思っていましたら、今朝見ると仮眠中でした。(D)は(5齢7日目)で体長30.5㍉ 体幅6㍉強ですので、この幼虫は蛹になり、羽化しそうです。他の個別飼育の3頭は1頭が今朝、蛹になり、2頭が5齢幼虫です。
集団飼育の幼虫は個々に脱皮を確認していませんので、正確には分かり難いのですが、殆どの幼虫が4齢以上になったようです。5齢幼虫は今月中に蛹になり、体長15-16㍉程度の4齢幼虫は4齢で越冬するのではないかと推測していますが、今まで予想が外れていますので、先になって結果が出ないと結論は出せません。
アオバセセリは今朝見ると仮眠に入っていました。予想通り6齢になるようです。今回、卵から飼育している幼虫はこの幼虫以外にも1頭いますが、同じような成育過程ですし、頭部脱皮殻も確認していますから6齢になることは間違い有りません。卵からの飼育は初めてですので、他の季節に飼育するとどうなるのかは不明ですが今回飼育の幼虫は6齢になりそうです。
鹿児島県からウラナミジャノメの卵を送って頂きました。年2化のウラナミジャノメですから、神童子や八尾産と同じだと思いますが、ひょっとすると変化が見られるかも知れないと少しばかり期待して飼育を始めました。卵の一部が今日、孵化しました。今日の2頭と明日孵化する2頭の合計4頭を個別に飼育の予定です。
南山城で採ったホソバセセリの幼虫のうち1頭(A)は翌日に巣を開けてゆっくり見ると体色が黄褐色の幼虫がいて枯れた葉の巣の中で静止して全く出てきません。その後もそのままの状態ですので、9月17日と言えば未だ暖かい日が続きましたが幼虫は越冬に入った様です。
その後10月3日に緑色で餌を沢山食べ、糞も多量にしていた幼虫(B)が10月5日には糞をしていないので巣を開けて見ると体色が黄色く変わっていました。10月6日に見ると体色は更に黄色くなり、巣も枯れてきているのに古い巣を使い続けています。糞も全くしていません。この幼虫も冬眠に入った様です。
最後に写真を載せた(C)幼虫は未だ体色も緑色で新しい緑色の巣に入り、餌を充分食べ、多量の糞をしています。冬眠に入る時期はかなり個体差があるようです。良く考えてみると、コチャバネセセリも成長の度合いに応じて9月頃から順次冬眠に入っていますので、ホソバセセリも9月頃から10月にかけて順次冬眠に入っても不思議では無さそうです。
桜井のT氏からリュウキュウムラサキの卵と若齢幼虫をを頂いた。T氏の話では今の時期のリュウキュウムラサキの飼育は期間がかかり蛹になるのは11月中旬だそうです。食草はサツマイモの葉が良いそうですが11月中旬までにはかなりの量が必要です。とりあえず放置されたサツマイモの葉を確保しましたが長期に渡り確保出来るかが心配です。イノコズチも食べるそうですので、もうすこし大きくなったらイノコズチも食べさせて見ようと思います。
タイワンツバメシジミは不思議な蝶です。食草のシバハギの咲く時期は短期間ですので、その時期に終齢幼虫になり、越冬して翌年の秋に成虫が羽化するのですが、その生活史は不明な部分が未だ多いようです。この卵を送って頂いた鹿児島のK氏自身が飼育された幼虫を冬の間保管されたが、途中で死に秋に羽化させる事は出来なかったそうです。
卵は10月1日に孵化し、シバハギの蕾に食痕と糞を残していますが姿はなかなか見つかりません。写真を撮して拡大して初めて幼虫の姿を見つけました。10月4日までは幼虫の姿が見られましたが、それ以降は全く見ていませんので、早くも失敗したのかな?と思っています。取りあえず今回は4枚の写真を載せました。
秋になり気温が下がったので飼育中のタテハモドキは成育に日数がかかっています。今日、1頭が漸く前蛹になりました。8月の飼育時に約2週間で蛹になったのと比べ格段の差です。未だ4齢程度の幼虫もいますので全部が蛹になるにはまだまだ日数がかかりそうです。
9月24日に蛹になったイシガケチョウは10月2日に羽化しました。
写真は撮していませんがオオヒカゲは全部孵化しました。
06年10月16日(月)晴
10月6日以降のオオムラサキの成育状況を記します。前回の日記で(A)(B)(C)の個体の写真を載せましたが引き続き10月16日現在の写真を載せます。(A)は(4齢13日目)になりました。(B)は脱皮して5齢になり(5齢9日目)です。5齢にしては体が小さく(体長16㍉ 体幅3㍉強)殆ど大きくなりませんので、このまま越冬するのかなと考えていますが、どうなるのでしょうか?(D)は(5齢17日目)に入りました。この幼虫は近々蛹になりそうです。
集団飼育中の1頭(F)が体長(24㍉弱)は長いのですが、体幅(3.5㍉)は他の4齢幼虫と余り変わらない細長い幼虫です。多数の幼虫を同じ容器で飼育していますので何齢かは確認していませんが5齢幼虫かなと推定しています。今後どうなるのか興味があります。(E)は9月26日に蛹になった個体が羽化しましたので写真を載せました。羽化第一号です。
アオバセセリは予想通り6齢になりました。6齢になり幼虫の尾部付近が赤くなりました。過去飼育した幼虫も終齢になると尾部が赤くなりましたので、近々、蛹になる筈です。
リュウキュウムラサキの幼虫の成育状況は予想より早いようです。写真の幼虫は4齢4日目で仮眠に入った様子です。集団飼育の幼虫の中には5齢になった個体もいます。しかし、未だ2齢の幼虫もいて成育にはばらつきが出ています。甘藷以外の食草もテストの為、イノコズチを2頭の幼虫に与えましたが順調に食べ、大きく育っています。
悪い予感の通りタイワンツバメシジミの幼虫は行方不明になってしまいましたが、今度は幼虫を送って頂きました。写真の様に小さい方の幼虫は背部中央に白い斑点がありますが、大きい方の幼虫は赤い線模様が有ります。大きくなれば赤い模様ができるのかも知れませんが、10月12日に到着した時から4日間では変化は有りません。来年の秋までの飼育は無理でも、何とか少しでも長く飼育して幼虫の成長を見てみたいと思います。
ウラナミジャノメは孵化後11日目に仮眠に入りました。個別に飼育中の他の3頭も相前後して仮眠に入っています。
06年10月29日(月)晴
オオムラサキは前回と同じ幼虫の写真をのせました。(A)(B)の幼虫は毎日少しずつ餌を食べています。しかし、前回から13日経ちましたがほんの少し大きくなっただけで体長、体幅共に殆ど変わりません。この2頭はそれぞれ4齢と5齢で越冬しそうです。(D)の幼虫は(5齢30日目)で前蛹状態になりました。多分2日ほどで蛹になり11月中には羽化の予定です。(F)の幼虫は中途半端な大きさですがこれも越冬組に入りそうです。しかし、無事に越冬出来るかどうかは不明です。
この他には集団飼育の幼虫が7頭、越冬しそうです。1頭だけ5齢と思われる幼虫がいますが成長が遅れているので、榎の葉が緑色のうちに蛹になれるかが心配です。
アオバセセリは終齢になって23日目になりますが未だ蛹化の気配は有りません。7月に飼育した3頭は終齢期間が12-14日でしたので、今の季節は幼虫の期間がかなり長くなるようです。毎日、巣を開いて写真を撮っていますが、何時までも同じ巣にいますので、巣の葉が枯れたり、破れたりして写真が汚くなってきました。
写真を載せているリュウキュウムラサキは9月30日に孵化して、1ヶ月後の10月29日に6齢8日目ですが、一番早いのは蛹になり始めました。しかし未だ4齢幼虫もいますので、全ての幼虫が蛹になるのは11月中頃になりそうです。長期に渡り食草の確保が必要ですが、リュウキュウムラサキの食草は甘藷を主に使っています。甘藷の葉が確保出来たら長期保存が必要です。甘藷の葉の保存方法は葉が水に浸からない様に注意して、茎を水の中へ浸けておきます。葉の付いた茎が枝分かれしている付近から根が出て水を良く吸い上げますので長持ちします。葉が水の中へ浸かっていると腐ってどろどろに溶けて、悪臭を放ちますのでご注意下さい。冷蔵庫の野菜室での保存もすぐに葉が茶色になり腐りますので不適です。
今回飼育の幼虫のうち2頭だけは若齢で食草をイノコズチに切り替えましたが、良く食べ成育状態も甘藷と変わらなかった。しかし終齢近くの大きな幼虫の食草を甘藷からイノコズチに切り替えようと思ったがウロウロ歩きまわり、イノコズチを食べてくれなかった。但し2頭の幼虫で短時間、試みただけですので、結論を出すにはもう少し多数の幼虫を使い長時間のチエックが必要です。
タイワンツバメシジミの幼虫は殆ど変化が無いようですが少しずつ大きくなっているようです。鹿児島のK氏が飼育されている幼虫の一部は終齢になり餌を離れて、鉢やネットに静止しているそうです。幼虫は地中に潜ると言われていますが、そんなことは無く、石の間などで越冬するのではないかと推測されています。
ウラナミジャノメは2齢になりました。これから来年の5月迄余り変化の無い写真を載せますが、私の一番興味があるのは幼虫が何齢で越冬し、何齢が終齢になるかです。過去に飼育した年1化の加古川の幼虫は6齢で越冬、終齢は7齢でした。年2化の神童子の幼虫は4齢で越冬、翌年の春に2度脱皮して終齢は6齢でした。
カバマダラの卵を鹿児島から送って頂きました。04年の秋にも送って頂き飼育しましたが、その時は1齢幼虫からの飼育でしたが今回は卵からの飼育になります。鹿児島では今の時期には例年カバマダラが増えるそうですが、今年は非常に数が少ないそうです。
11月
06年11月9日(木)晴
オオムラサキの幼虫は未だ榎の葉を食べ糞もしていますが、体の大きさは殆ど変化がありません。今、飼育中の幼虫は殆ど全部、このまま越冬する様です。集団飼育の1-2頭の幼虫は榎の枯れた葉に静止していますが、体色が黒くなってきました。未だ緑色ですが、少しくすんできた個体もいます。前回の日記に載せた(A)(B)(F)の3幼虫と少し黒くなってきた幼虫の写真を載せておきます。
アオバセセリは9月5日に孵化して2ヶ月以上経ちましたが、ようやく11月8日に蛹になりました。特に6齢になってからが長く、10月7日に6齢になり6齢32日目に前蛹になりました。7月に飼育した個体の終齢期間が13日でしたので、今回の飼育は長く感じました。写真を載せた個体以外に今回、更に一頭を飼育していますが、これも前蛹寸前の状況です。
毎回写真を載せているリュウキュウムラサキの幼虫が蛹になりました。今日までに殆どの幼虫が蛹化しましたが、特に成長の遅い5齢幼虫が2頭残っています。未だ6齢が全期間残っていますので、食草の甘藷が枯れないように確保しなければなりません。
イノコズチで飼育していた幼虫の1頭は既に蛹になっていますが、残りの1頭にイノコズチとヤブマオを与えておきましたら、ヤブマオにも食痕を残し、最後にはヤブマオの茎で蛹化していました。次に飼育の機会がありましたら、色々な食草を与えてみたいと思っています。
タイワンツバメシジミは一時、餌から離れ歩きまわっていましたが、新しい餌を与えるとまたシバハギに戻りました。シバハギの豆が枯れて来ましたので、今後どうなるのかが心配です。
ウラナミジャノメは3齢5日目になりました。食草のチジミザサも元気が無くなってきましたので、3齢で仮眠するのか4齢になるのか興味があります。
カバマダラは同じ南方系のリュウキュウムラサキと比べると成長が早く、孵化後半月で(5齢4日目)になりました。集団飼育の幼虫では発送途中で孵化していた個体は既に蛹になったのもいます。成長が早いので齢が変わった時の写真ばかりになりました。
T氏からコノハチョウの卵と(石垣島産)クロアゲハの卵を貰いました。
コノハチョウの食草はオキナワスズムシソウやセイタカスズムシチソウですがこちらでは手に入りませんので、最初はオギノツメを使うつもりでしたが、9月にタテハモドキの飼育に使い殆ど残っていなかったので、T氏からスズムシバナを頂き飼育する事になりました。幼虫はサカハチチョウの幼虫のように常に体を丸めて静止しており、体を真っ直ぐにしている時は餌を食べている時ぐらいです。従って体長を測るのは難しいので、尾部から体の屈折部までの長さを測り、写真を見て全体の体長を推察して頂く事に、勝手に決めました。
(石垣産)クロアゲハは成虫の雌は赤色紋が二重になり、非常に美しいですが、幼虫は少し見たところでは違いが有るのかどうか分かりません。今、幼虫は5齢になりたてと4齢幼虫ですが、蛹になったら奈良では年内に羽化するのか?蛹のまま越冬するのでしょうか?
06年11月19日(日)
かなり寒くなりオオムラサキの食草の榎の葉も元気が無くなってきました。飼育中のオオムラサキの幼虫は比較的気温の高い日には未だ榎の葉を少し食べ糞もしていますが、気温の低い日は糞の量は少なくなってきました。体長や体幅も殆ど変わらずほぼ横ばいです。今回も(A)(B)(F)の3幼虫の写真を載せました。
タイワンツバメシジミの幼虫(B)は11月10日にシバハギから離れてポリ瓶の上に静止していました。幼虫は11月14日にポリ瓶の下の紙の上に落ちて体を丸めて横向きになっていましたので、死んだのかと思っていたら翌日には写真の様な状態に戻っていました。その後5日間は全く動いていませんので、生きているのか死んだのか分かりませんが、この状態で暫く様子を見たいと思います。
幼虫(A)は昨日(11月18日)にシバハギを離れてポリ瓶の上にいます。タイワンツバメシジミは幼虫で越冬するそうですが、今後どうなるのでしょうか?
ウラナミジャノメは過去の飼育記録を見ると冬眠には未だ少し間があります。未だ餌も食べ糞もしています。
カバマダラの幼虫は蛹化しました。今回、卵を沢山頂いたので、3頭を個別に飼育して、他は大きな容器で集団で飼育しましたが、食草のガガイモの茎で蛹化したのは少なく殆どが容器のカバーの布で蛹になり、次に多かったのが飼育容器の側壁でした。
日毎に寒くなってきましたがコノハチョウは順調に成育し、3齢から4齢への仮眠に入りました。ただ心配なのは食草のスズムシバナです。背丈が40㌢程有りますが鉢植えにしたところ無事に根付いて下の方に小さな葉が芽吹いていますが、肝心の上の方の大きな葉が枯れて餌不足になりそうです。T氏が新たなスズムシバナを届けて下さったので、葉が枯れない様にビニールの袋に入れるなど、試行錯誤の工夫をしていますが、どうなる事でしょうか?3齢期間が10日ほどありますので4-5齢では20日以上かかりそうです。蛹になるのは多分12月の中旬ですので、気温の低下も心配です。
(石垣産)クロアゲハは一番大きな幼虫が5齢11日目になりました。体をおもいきり伸ばして餌を食べている写真を載せておきます。
06年11月29日
オオムラサキの幼虫は1頭の例外を除き年内に蛹化した個体はすべて羽化し、残りの幼虫は越冬組だけになりました。越冬組の幼虫は餌を食べなくなり、あまり動かず同じ場所に静止しています。個体により差がありますが体色は黒くなり越冬幼虫の色相になって来ました。この前の日記に載せた幼虫(A)(B)(F)の写真を今回も引き続き載せておきます。
1頭の例外は集団飼育の5齢らしい幼虫です。この幼虫が怪我をして回復不可能と判断し、飼育記録から外し1頭だけ別に飼育していたら予想が外れ、じょじょに回復して大きくなってきました。年内蛹化組がすべて羽化してかなり日が経ちましたが未だ5齢のこの幼虫は毎日榎の葉を食べ大粒の糞をしています。榎の葉も散り始めましたので今後は餌の確保に苦労しそうです。
飼育中の幼虫が越冬体制に入りましたので、野外の幼虫もそろそろ榎から下りている頃だと思い四条畷の産地まで出かけました。今年はかなり気温の高い日が多いので少し心配でしたが、例年、幼虫の見つかる木にはオオムラサキやゴマダラチョウの幼虫が下りていました。現在、飼育中で越冬に入った幼虫と自然状態の越冬幼虫の大きさを比較してみたいと思っています。
タイワンツバメシジミの幼虫(B)は残念ですが、黒くなって死んでしまいました。幼虫(A)はシバハギの豆から離れていましたが、その後またシバハギの豆に戻っていました。少し体が小さくなったようですが今日現在は豆にしがみついています。
ウラナミジャノメの幼虫は未だ食草のチヂミザサを食べ、かなり多量の糞をしています。冬眠は未だ少し先のようです。
コノハチョウは4齢9日目に入りましたので、近日中に仮眠に入り5齢になると思うのですが、それにしても5齢期間は10日以上有るはずですので、寒さと食草不足が心配です。今年の秋は暖かい日が続きましたが今週末の最低気温が0℃の予想ですので気がかりです。
(石垣産)クロアゲハは蛹になりました。奈良県ではクロアゲハの羽化は来年の春ですが、石垣産のクロアゲハはいつ羽化するのでしょうか?取りあえず蛹の保管は室内でする事にしました。2重紋の雌が羽化するのを期待しています。
9月に採卵したメスグロヒョウモンの幼虫が孵化したので、来春の事を考えタチツボスミレを中央に少し植え周りにススキの葉を細かく切ったのを入れた大きめの植木鉢を幼虫の越冬用に準備しました。その植木鉢のススキの葉に幼虫を放しました。
暫く放置していましたので、水分の補給のため鉢をカバーしていた布を外して中を見ると数頭の成長したメスグロヒョウモンの幼虫を見つけました。
ヒョウモン類の産卵は食草のスミレには産卵せず、時には高い木に産卵する事もありますが、これは孵化した幼虫がスミレを食べて年内に成長するのを防ぐ為なのかと勝手に考えてしまいます。年内に成長した幼虫が蛹にまでなるのは餌不足で大変ですし、仮に蛹になり羽化出来たとしても寒さの為母蝶は卵を産むことなく死んでしまいそうです。そのような事態を避ける為に母蝶は木や石に産卵するのでしょうか?何はともあれ私の飼育している幼虫は餌を確保して母蝶まで育てるつもりです。
12月
06年12月9日
最初におことわりを入れておきます。
最近、迷惑メールが多く、フイルターで迷惑メールボックスに入っているメールは見ずに全部削除しています。たまにフイルターを通り抜けた迷惑メールが正常なメールボックスに入っている事がありますので、その反対もあり得ると思っています。初めてメールを頂く方は件名を具体的にご記入下さるようお願い致します。
ここから本来の日記に戻ります。オオムラサキの幼虫は大きな5齢幼虫を除いて他は榎の同じ葉上に静止したまま動かず、糞もしていないので12月4日に小さな容器に入れ庭の片隅に置きました。集団飼育の幼虫が7頭、個別飼育の幼虫が(A)(B)(F)の3頭です。集団飼育の幼虫と、野外で採った越冬幼虫の大きさを比較してみましたが、大きな差はありませんでした。個別飼育の幼虫(A)(B)はこころもち大きな感じですが、大きな差は有りません。幼虫(F)だけはかなり体長が縮みましたが、それでも比較するとかなり大きいです。1頭だけ未だ餌を食べて緑色の大きな幼虫がいますが、寒さのせいか食べる量は少なく、糞も4粒程度しかしていませんので、蛹にはなりそうも無い状態です。
幼虫(A)(B)(F)は12月4日の写真を、大きな5齢幼虫は12月9日の写真を載せました。
チヂミザサの葉は幾分色が悪くなって来ましたがウラナミジャノメの幼虫は未だ葉を食べ糞もかなりしています。集団飼育の幼虫はチヂミザサからスゲに餌を切り替え、庭に飼育容器を置いてあります。
コノハチョウは4齢19日目になりました。3齢期間が10日でしたので倍程の期間になりました。この2-3日は最低気温が0℃前後になりましたので、寒さの影響もあるのかもしれません。飼育期間が長引くと食草の不足が心配ですが鹿児島からオキナワスズシロソウを送って頂いたので少し安心です。写真の幼虫にはオキナワスズシロソウを与え、最近、追加で貰った幼虫にスズムシバナを与えています。
寒くなってきましたがメスグロヒョウモンはタチツボスミレを良く食べ順調に大きくなっています。12月2-3日には写真の幼虫が脱皮しました。春に飼育した写真と比べると5齢の様ですがどうなるのでしょうか?12月9日には脱皮後7-8日になりましたので、もし終齢でしたら4-5日で蛹になるはずです。
タイワンツバメシジミはシバハギの豆にしがみついたまま死んだらしく、褐色になりました。念の為、暫く保管はするつもりですが、奈良の寒さを耐えられるとは思いませんので、写真はこれが最終です。
これから益々、気温が下がりますが暖地産のリュウキュウムラサキは奈良の寒さに耐えきれず最後に残った幼虫は死亡し、前蛹になった個体は脱皮が出来ず蛹になれませんでした。蛹から羽化した成虫も翅が充分に伸び無い等、散々です。未だコノハチョウは飼育中ですし、(石垣産)クロアゲハの蛹もいますので、寒さ対策を考える必要がありそうです。
06年12月20日
12月16日にT氏の車に便乗させて頂き滋賀県の永源寺から更に上流の方にキリシマミドリシジミとヒサマツミドリシジミの採卵に行きました。キリシマミドリシジミはアカガシの手が届く範囲に産卵していますので私でも採卵は可能ですが、ヒサマツミドリシジミはウラジロガシの頂上付近の花芽に産卵しますので木登りが必要です。道路の下の方に川が流れ、道路と川の間は急な斜面で、その部分にウラジロガシが生えていますので、もし木から落ちると大変な事になります。私にはヒサマツミドリシジミの採卵は夢のまた夢でしたが、木登り名人のT氏のおかげで、来年の春にはヒサマツミドリシジミの飼育が出来そうです。
ウラナミジャノメは未だ餌を食べ糞をしているが体は全く大きくなりません。測定誤差はありますが12月12日は体長9㍉ 体幅1.5㍉でしたので、12月20日の体長8㍉強 体幅1.5㍉は少し体長が縮みぎみです。そろそろ越冬の仮眠に入っても良さそうな時期です。因みに04年に飼育した加古川の幼虫は12月4日には糞をしなくなり一ヶ所に静止して(6齢52日目)頃に仮眠に入りました。
コノハチョウは仮眠期間を入れ4齢では24日かかりました。暖かい場所では齢の期間は数日と聞いていますので気温が低すぎる為だと思います。この調子では食草が枯れて不足し、蛹までの飼育が危ういと考え、電気座布団を購入し、上に飼育容器を置くことにしました。しかし暑すぎてもいけないと考え、電気座布団と飼育容器の間を少し離しました。今度は少しぬるそうですが徐々に改良するつもりです。
コノハチョウの幼虫は4齢では棘状突起の基部に橙色の部分がありましたが5齢になると真っ黒になりました。
今年の春に飼育したメスグロヒョウモンの幼虫は体長40㍉ 体幅6-6.5㍉程度、5齢10-11日目程度、で蛹化しました。今回の飼育では20日現在、体長、体幅はほぼ同じ大きさになりましたので、蛹化が近そうですが既に終齢18-19日目と日数は倍程かかっています。気温が低いと日数がかかる様です。
06年12月30日
最近、寒くて動かないので体が重く感じられ(実際に体重も増えている)、少し歩いた方がよさそうなので、枚岡公園まで出かけました。昨年の今頃は入院中でしたので、冬季にこの辺にくるのは久し振りです。モミジの木に残った枯れ葉を調べると、ミスジチョウの幼虫がいました。
榎の根元も何本か調べて見ましたがオオムラサキの幼虫は1頭いただけです。夏に成虫の姿をよく見るわりに幼虫は少ないです。どこかに沢山いる榎の木があるのかもしれません。
2化目のメスグロヒョウモン(幼虫1)は終齢24日目で前蛹になり、前蛹2日間を経過26日目に蛹になりました。前蛹までは室温で飼育しましたが、前蛹以降は気温が低いと脱皮や羽化がうまくいかない場合があるので、少し暖めています。現在、蛹が4頭と幼虫が5頭いますが、前蛹以降、羽化するまでは電気座布団を使って室温より少し暖める予定です。
ウラナミジャノメの幼虫も殆ど糞をせぬようになりました。静止位置もあまり変わりません。体も少し縮み気味ですので、いよいよ越冬体勢に入ったようです。今年は暖かかった為か、それとも幼虫が鹿児島産だからかは分かりませんが、過去飼育した加古川産の幼虫と比べ越冬に入るのが遅いようです。このまま越冬に入るとすればこの幼虫は3齢で越冬する事になります。
コノハチョウは5齢期間14日で前蛹になりました。4齢期間24日に比べ大幅短縮でした。4齢期間より5齢期間が長いのが普通ですが電気座布団の効果抜群でした。
(石垣島)のクロアゲハの蛹も電気座布団で暖めましたら、雄が2頭羽化しました。残念ながら近畿地方の個体と比べ大きな違いはありませんでした。蛹の一つは寄生されていました。気が付いたら蛹から脱出したらしい大きな蠅らしい蛹が下に落ちていました。残りの蛹は一つですが雌が羽化することを期待して暖めています。